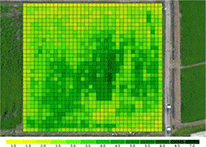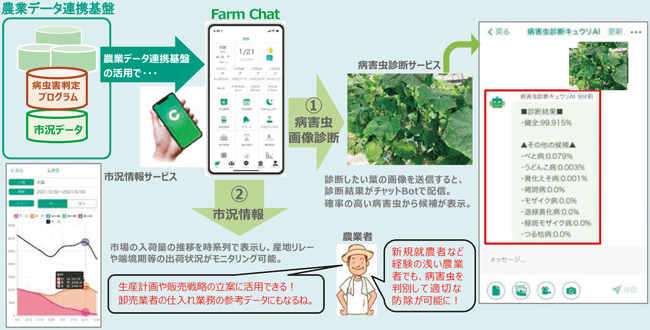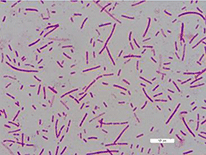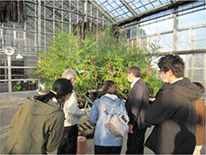第8節 情報通信技術等の活用による農業生産・流通現場のイノベーションの促進

農業生産・流通現場でのイノベーションの進展、農業施策に関する各種手続や情報入手の利便性の向上は、高齢化や労働力不足等に直面している我が国の農業において、経営の最適化や効率化に向けた新たな動きとして期待されています。
本節では、ロボット、AI(*1)、IoT(*2)等先端技術を活用したスマート農業の導入状況、農業・食関連産業におけるデジタル変革に向けた取組、産学官連携による研究開発の動向等について紹介します。
1、2 用語の解説3(2)を参照
(1)スマート農業の推進
(スマート農業導入の広がり)
農業の現場では、人手の確保とともに、農作業の省力化や負担の軽減が重要な課題となっています。このような中で、ロボット、AI、IoT等先端技術を活用したスマート農業による課題の解決や、農業経営の最適化・効率化に向けた取組が進んでいます。
スマート農業の導入状況については、株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)が令和3(2021)年7月に実施した調査によると、農業のデジタル化、スマート農業について「導入している」との回答が30.2%、「導入していないが、導入意向がある」との回答が32.8%となっており、農業現場での需要が高いことがうかがわれます(図表2-8-1)。
また、スマート農業の導入で期待する効果については、「農作業の省力化」が最も高く約8割、次いで「農作業の軽労化」、「品質・収量の向上」の順となっています(図表2-8-2)。
(令和元(2019)年度スマート農業実証プロジェクトの成果を公表)
農林水産省は、スマート農業の技術体系を実際の生産現場に導入して、課題の解決や経営改善の効果を明らかにするため、令和元(2019)年度から全国182地区でスマート農業実証プロジェクトを展開しています(図表2-8-3)。

このうち、令和元(2019)年度実証地区について、実証期間中の技術導入効果を分析して成果を取りまとめ、公表しました。水田作では、ロボットトラクタや自動運転田植機の導入により総労働時間が短縮された地区が多く確認されました。また、最も効果が上がった地区では、収量コンバインで取得したデータを基に、圃場(ほじょう)ごとの品種・作型配置の最適化や、収量が少ない圃場に対し重点的に施肥を行うことで収量が向上し、スマート農業で省力化されたことによる人件費削減との相乗効果により、農機の導入コストを差し引いても経営収支が改善したといった成果が確認されました(図表2-8-4、図表2-8-5)。
このほか、自動操舵(そうだ)機能により新規就農者(*1)等の農業者においても、熟練者と同等の精度・速度で作業が可能となり、受託する農地を増やすことができた地区も見られました(図表2-8-6)。また、導入機械の共同利用を行うことで稼働率を向上し、機械費を低減できた地区も見られました(図表2-8-7)。
このように、スマート農業の導入は新規就農者等の参入を容易にするほか、生産性の向上に有効であることが確認される一方、先端技術の導入により利益を増大させるには、導入機械の稼働率を向上させ、機械費を低減する必要があることが明らかとなりました。さらに、手間の掛かる野菜・果樹の収穫作業においては機械化が不十分であること等の課題も明らかになりました。
このため農林水産省は、令和3(2021)年2月に改訂した「スマート農業推進総合パッケージ」で示す、今後5年間で展開する施策の方向性に基づき、シェアリング等新たな農業支援サービスの育成と普及を行うほか、農業データの活用、農地インフラの整備等による実践環境の整備、農業大学校・農業高校等での学習機会の提供等、スマート農業の社会実装の加速化に取り組んでいます。




1 用語の解説2(6)を参照
(事例)スマート農業に挑戦し自社生産米を収穫(埼玉県)
持ち帰り弁当店・定食店を運営する株式会社プレナスは、農業従事者(*1)の減少による日本の農業への危機感と、自社生産米を海外の消費者に届けたいという思いから、スマート農業による米づくりを始めました。
令和3(2021)年2月、自社の精米工場に近い埼玉県加須市(かぞし)に2.5haの耕作放棄地を借り入れ、トラクターの免許を取得した自社の従業員が圃場の整備を行うとともに、ドローンの操縦に必要な講習も受講しました。
同年5月には、ドローンを活用した湛水直播(たんすいちょくはん)(*2)と高密度播種育苗(*3)の栽培方法を検証しました。湛水直播では、30aの圃場を15分で作業することができ、田植機による作業と比較して作業時間を半分以下に短縮できました。同年7月にはドローンによる空撮を行い、圃場内の稲の葉色診断により、必要な量の肥料を散布しました。
水管理システムも活用し、スマートフォンからの遠隔操作で圃場に行かずに水量の調整を行うことで作業時間を低減しました。
同年10月、9tの米を収穫することができました。収穫米は自社工場で精米後、令和4(2022)年7月頃に、豪州の自社店舗向けに輸出する予定です。令和4(2022)年度は、加須市での農地面積を約2倍に拡大するとともに、新たに山形県内でも米づくりに取り組んでいきます。
1 用語の解説1、2(5)を参照
2 用語の解説3(1)を参照
3 高密度に播種した稚苗の移植により苗箱数を大幅に削減する技術
(農業関連データの連携・活用を促進)
様々なデータの連携・共有が可能となるデータプラットフォーム「農業データ連携基盤(WAGRI(わぐり)(*1))」を活用した農業者向けのICT(*2)サービスが民間企業等により開発され、農業者への提供が始まっています。運営主体である農研機構ではデータの充実や利用しやすい環境の整備に取り組んでいます。

WAGRI
URL:https://wagri.naro.go.jp(外部リンク)
また、農林水産省は、農業者が利用する農業用機械等から得られるデータについて、メーカーの垣根を越えてデータを利用できる仕組み(オープンAPI(*3))の整備を推進するため、令和3(2021)年度から、協調するデータ項目の特定やルールの整備等、農業データを連携・共有するための取組への支援を行っています。
このほか、スマート農業の海外展開に向けて、農林水産省は、農研機構、民間企業と連携し、国際標準の形成に向けた調査・検討を行っています。
1 農業データプラットフォームが、様々なデータやサービスを連環させる「輪」となり、様々なコミュニティの更なる調和を促す「和」となることで、農業分野にイノベーションを引き起こすことへの期待から生まれた言葉(WA+AGRI)
2 用語の解説3(2)を参照
3 Application Programming Interface の略。複数のアプリ等を接続(連携)するために必要なプログラムを定めた規約のこと
(事例)農業データ連携基盤と農業者向けスマートフォン用アプリの連携
農業者向けのスマートフォン用アプリ「FarmChat(ファームチャット)」を提供する株式会社ファーム・アライアンス・マネジメントは、令和3(2021)年5月から、農業データ連携基盤(WAGRI)とのAPI連携を開始し、農業データ連携基盤が提供する病虫害画像判定プログラムの利用や青果物市況データの閲覧がアプリ上で可能になりました。このうち、病虫害画像判定プログラムを活用した病害虫診断サービス(*)では、農業者がスマートフォンで撮影した葉の画像を送信すると、病害虫診断結果を受信でき、新規就農者など経験の浅い農業者でも病害虫を判別して適切な防除を行うことが可能になります。
令和3(2021)年12月時点で、トマト・きゅうり・いちご・なすに対応
(2)農業施策の展開におけるデジタル化の推進
(データを活用した農業経営の動向)
農業分野でも、デジタル技術の活用による変革、DX(*1)に向けた取組が進みつつあります。
2020年農林業センサスによると、農業経営体(*2)全体ではデータを活用した農業を実施している割合は2割未満ですが、農業経営主の年齢階層別に見ると、15~39歳では5割以上がデータを活用した農業を実施しています(図表2-8-8)。
また、法人経営体では、5割以上がデータを活用しており、特に、センサー、ドローン等を用いて、圃場環境情報や作物の生育状況等のデータを分析し、農業経営に活用している経営体も約1割あります。
1 用語の解説3(2)を参照
2 用語の解説1、2(1)を参照
(農業DXの実現に向けた取組)
農林水産省では、農業者の高齢化や労働力不足が進む中、デジタル技術を活用して効率の高い営農を実行しつつ、消費者ニーズをデータで捉え、消費者が価値を実感できる形で農産物・食品を提供していく農業を「FaaS(ファース)(Farming as a Service)」と位置付け、令和3(2021)年3月に公表した「農業DX構想」に基づき、農業DXの実現に向けて多様なプロジェクトを進めることとしています。
具体的には、農業・食関連産業の「現場」系、農林水産省の「行政実務」系、現場と農林水産省をつなぐ「基盤」の整備に向けたプロジェクトが挙げられ、三つの区分の下で39の多様なプロジェクトを掲げています。スマート農業の現場実装は「現場」系プロジェクト、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)は「基盤」の整備に向けたプロジェクトです。
このほかにも、「現場」系プロジェクトでは、農山漁村発イノベーション全国展開プロジェクト(INACOME(イナカム))、デジタル技術を活用した飼養衛生管理高度化プロジェクト、農産物流通効率化プロジェクト等を、「行政実務」系プロジェクトでは、業務の抜本見直しプロジェクトやデータ活用人材育成推進プロジェクト等を推進しています。
(eMAFF地図の開発を開始)
「基盤」の整備に向けたプロジェクトについては、eMAFFの利用を進めながら、現場の農地情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化を図るための「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)」プロジェクトを進めています。
農地に関する情報については、現在は、農業委員会が整備する農地台帳や地域農業再生協議会が整備する水田台帳等、施策の実施機関ごとに個別に収集・管理されています。このため、農業者は、実施機関ごとに繰り返し同じ内容を申請する必要があるとともに、実施機関は、手書きの申請情報をそれぞれのシステムに手入力し、それぞれが作成した手書きの地図により現地調査を行っています。
eMAFF地図は、こうした農地に関係する作業を抜本的に改善するために開発を進めているものです。eMAFF地図により複数の台帳が一元管理されることで、最新の農地情報が一目で分かり、申請手続において画面上の地図から農地を選択することで農地情報を入力する手間が省ける、手続に伴う農地等の現地確認もタブレットの活用で手書きの地図の作成や確認結果のデータ入力が不要となる等の効果が期待できます。
令和3(2021)年度はeMAFF地図のシステム開発を進め、これに掲載するデータの「紐付(ひもづ)け」手法の開発・実証を行いました。また、関係府省と合意し、不動産登記簿の「地番」情報と農地台帳等との紐付けに当たって、個人情報保護法令に基づく整理をした上で、必要な「地番」情報のデータ提供が可能となりました。
引き続き、令和4(2022)年度中に一部地域で運用を開始できるように精力的に取り組んでいきます。
(3)イノベーションの創出・技術開発の推進
(「知」の集積と活用の場によるオープンイノベーションを創出)
農林水産・食品分野のオープンイノベーションを担う「知」の集積と活用の場の産学官連携協議会(*1)には、IT系、工学系、医学系など様々な分野から、4千以上の法人・個人が参加しており、新たな技術や商品を続々と創出しています。同協議会は、主催するセミナーのほか、アグリビジネス創出フェアや商談会等のイベントを通じて技術や商品の情報を発信するとともに、会員間での交流・意見交換を行っており、令和3(2021)年度から、「知」の集積と活用の場から生まれた商品・技術を海外展開することを目的として、新たに海外会員の募集を開始しました。

「知」の集積と活用の場産学官連携協議会
URL:https://www.knowledge.maff.go.jp/(外部リンク)
1 平成28(2016)年4月に設立
(ムーンショット型農林水産研究開発事業を推進)
内閣府のCSTI(システィ)(*1)(総合科学技術・イノベーション会議)では、人々を魅了する野心的な目標を掲げて困難な社会課題の解決を目指し、挑戦的な研究開発を進めるため、「ムーンショット型研究開発」として九つの目標を掲げています。このうち、農林水産・食品分野における目標、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」の達成に向け、農研機構生物系特定産業技術研究支援センターでは、令和2(2020)年度から、牛からのメタン削減と生産性向上の両立を始めとする10のプロジェクト研究に取り組んでいます。
1 Council for Science, Technology and Innovationの略
(事例)牛の胃からメタンの発生抑制が期待される新たな細菌を発見
農研機構は、平成29(2017)年からメタン産生の少ない牛の胃の中に存在する微生物の働きを利用した研究に取り組み、令和3(2021)年11月に、牛の第一胃からメタンの発生抑制が期待できる新たな細菌(*)を発見しました。
新たに発見された細菌は、牛の第一胃の微生物の働きで飼料が分解・発酵される過程で、プロピオン酸の元となる物質をより多く作ります。プロピオン酸は、牛のエネルギー源として利用される物質で、生成される際にメタンの材料となる水素を消費するため、第一胃においてプロピオン酸が多く作られると、メタンは生成されにくくなり、牛のエネルギー効率が上がります。
新たに発見された細菌は、プロピオン酸の元となる物質を今までに知られていた細菌よりも多く作るため、プロピオン酸の増加とメタンの発生抑制を両立する技術につながる可能性があります。今後、研究が更に進むことで、牛を始めとした反すう動物のメタン排出量の削減や、生産性向上への貢献が期待されます。
細菌の名称は、Prevotella lacticifex (プレボテラ・ラクティシフェクス)
(新たな品種改良技術の進展と国民理解の向上に向けた取組を実施)
農林水産省では平成30(2018)年から、農作物のゲノム情報や生育特性等の育種に関するビッグデータ(*1)を整備し、これにAIや新たな育種技術等を組み合わせて活用する「スマート育種システム」の開発と、そのためのデータ基盤の構築に取り組んでいます。
この取組を進めることにより、イネ、コムギ、オオムギ、ダイズ、リンゴ、タマネギ等について、気候変動等への適応力、収量、おいしさといった多数の遺伝子が関わる形質を改良する品種の開発を、従来よりも効率的かつ迅速に行うことができるようになります。
また、近年では天然毒素を低減したジャガイモや無花粉スギの開発等、ゲノム編集(*2)技術を活用した様々な研究が進んでいます。令和3(2021)年9月には、ゲノム編集技術によって開発された農作物として、我が国で初めて届出されたGABA(*3)高蓄積トマトが、続いて同年12月には、肉厚のマダイと成長の早いトラフグがそれぞれインターネットで販売開始されました。
一方で、ゲノム編集技術は新しい技術であるため、農林水産省は、平成28(2016)年度から大学や高校に専門家を派遣して出前授業等を行うとともに、消費者に研究内容を分かりやすい言葉で伝えるなどのアウトリーチ活動を実施しており、令和3(2021)年11月には、無花粉スギについての研究施設見学会を行いました。
今後も、健康的な食生活に貢献できる農作物や、農薬の使用を抑え環境負荷を低減できる病害虫抵抗性農作物等、国民が利益を享受できるような農作物の開発を推進していきます。
1、2 用語の解説3(1)を参照
3 γアミノ酪酸(Gamma Amino Butyric Acid)のことで、食品に含まれる健康機能性成分として、ストレス緩和や血圧降下作用等が注目されている。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883