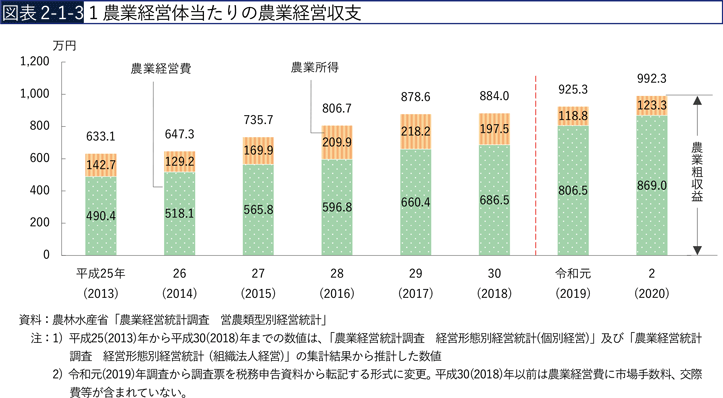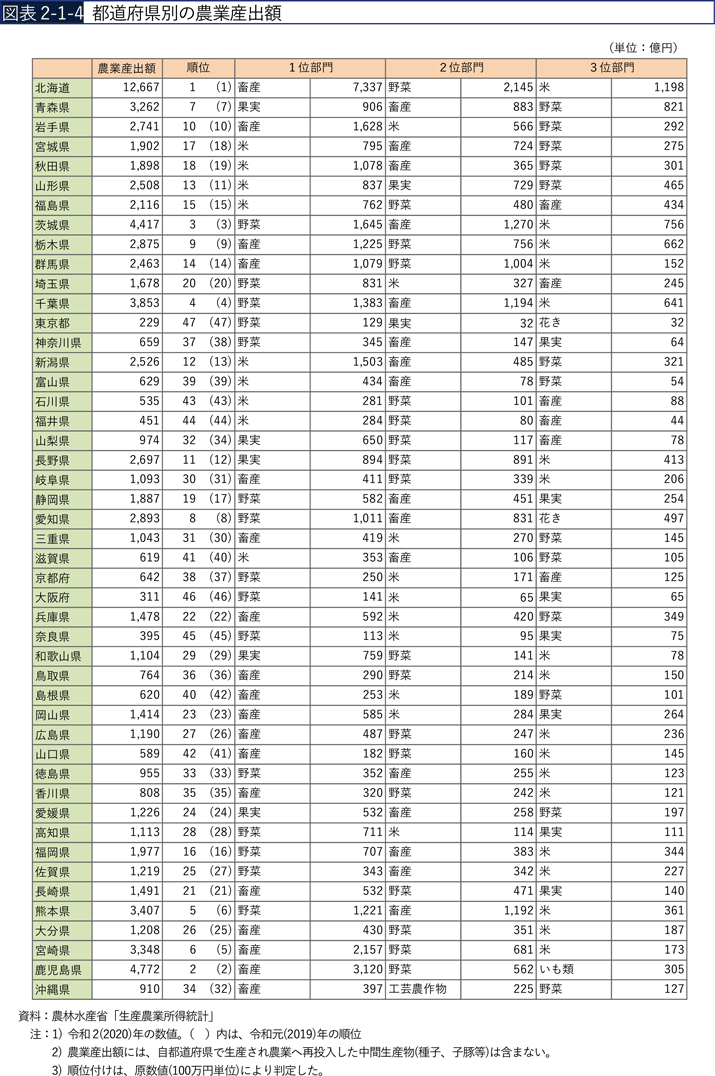第1節 農業総産出額と生産農業所得等の動向
我が国の農業総産出額(*1)と生産農業所得(*2)は長期的に減少し、近年はおおむね横ばいで推移していますが、令和2(2020)年には新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響も見られます。本節では、農業総産出額や生産農業所得、都道府県別の農業産出額等の動向について紹介します。
*1、2 用語の解説1を参照
(農業総産出額は432億円増加の8.9兆円)
令和2(2020)年の農業総産出額は、米において主食用米の需要減少に見合った作付面積の削減が進まなかったことや、肉用牛において新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により外食需要やインバウンド需要が減退したことから、それぞれの価格が低下した一方、野菜や豚において天候不順や巣ごもり需要により価格が上昇したこと等により、前年に比べ432億円増加の8兆9,370億円となりました(図表2-1-1)。
令和2(2020)年の部門別の産出額を見ると、米の産出額は、前年に比べ5.7%減少の1兆6,431億円となりました。全国の生産量は前年並となったものの、主食用米の需要減少に見合った作付面積の削減が進まなかったことや、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により中食(*1)・外食向けの需要が減少したこと等から民間在庫量が増加し、主食用米の取引価格が前年に比べ低下したこと等によるものと考えられます。
野菜の産出額は、前年に比べ4.7%増加の2兆2,520億円となりました。春先の低温や夏季の長雨・日照不足等の影響によりトマト、ねぎ、ごぼう等の多くの品目において生産量が減少したことに加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により家庭用需要が増加し、保存性の高い冷凍野菜や簡便志向によるカット野菜等の需要が増加したことを受け、多くの品目で価格が上昇したこと等が寄与したものと考えられます。
果実の産出額は、前年に比べ4.1%増加の8,741億円となりました。みかん、りんごにおいて好天により生産量が増加し価格が低下した一方、日本なし、ぶどう、ももにおいて天候不順により生産量が減少し価格が上昇したこと等が寄与したものと考えられます。
畜産の産出額は、前年に比べ0.8%増加の3兆2,372億円となりました。その主な内訳を見ると、肉用牛については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により家庭用需要が増加したものの、外食需要やインバウンド需要の減少から価格が低下し、産出額が減少したものと考えられます。一方、生乳については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により業務用需要が減少したものの、家庭用需要等から牛乳・乳製品の消費が堅調に推移する中、生乳生産量が増加したこと等により、産出額が増加したものと考えられます。豚については、大規模化の進展により生産頭数が増加したこと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により家庭用需要が旺盛となったこと等から価格が高く推移し、産出額が増加したものと考えられます。
*1 用語の解説3(1)を参照
(生産農業所得は218億円増加し3.3兆円)
生産農業所得は、農業総産出額の減少や資材価格の上昇により、長期的に減少傾向が続いてきましたが、米、野菜、肉用牛等において需要に応じた生産の取組が進められてきたこと等から、平成27(2015)年以降は、農業総産出額の増加等により増加に転じ、3兆円台で推移してきました(図表2-1-2)。
令和2(2020)年は、農業総産出額が増加したこと等により、前年に比べ218億円増加の3兆3,433億円となりました。
(1農業経営体当たりの農業所得は123万円)
令和2(2020)年の1農業経営体(*1)当たりの農業粗収益は、野菜作等の作物収入が増加したこと等から前年に比べ7.2%増加の992万3千円となりました(図表2-1-3)。一方、農業経営費は荷造運賃手数料、雇人費等が増加したことから前年に比べ7.7%増加の869万円となり、農業所得(*2)は前年に比べ3.8%増加の123万3千円となりました。
*1 用語の解説1、2(1)を参照
*2 用語の解説2(4)を参照
(都道府県別の農業産出額が上位の道県の主力部門は、畜産と野菜)
都道府県別の農業産出額を見ると、北海道が1兆2,667億円で1位となっており、2位は鹿児島県で4,772億円、3位は茨城県で4,417億円、4位は千葉県で3,853億円、5位は熊本県で3,407億円となっています(図表2-1-4)。
農業産出額上位5位の道県で、産出額が1位の部門を見ると、北海道、鹿児島県では畜産、茨城県、千葉県、熊本県では野菜となっています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883