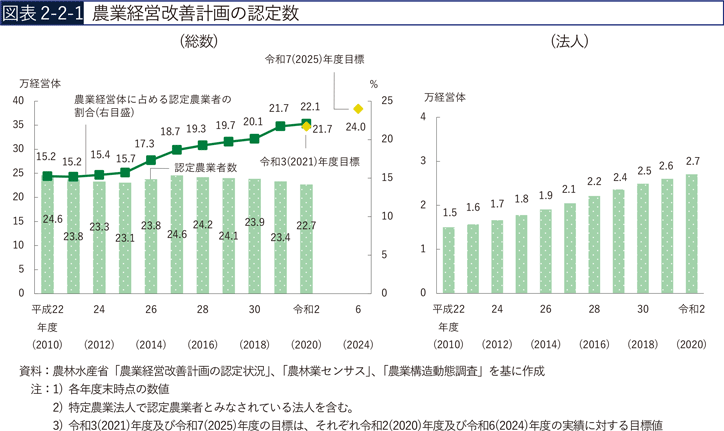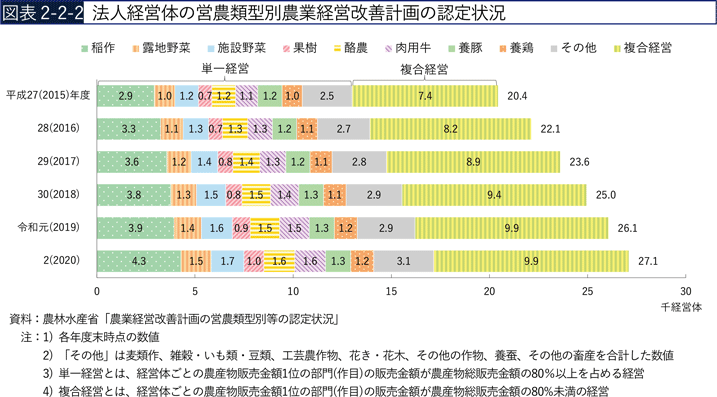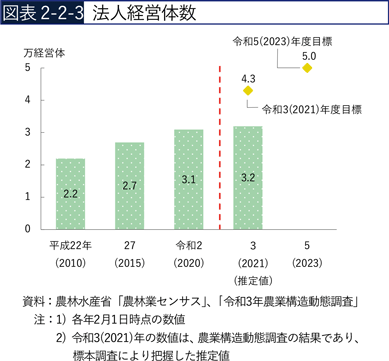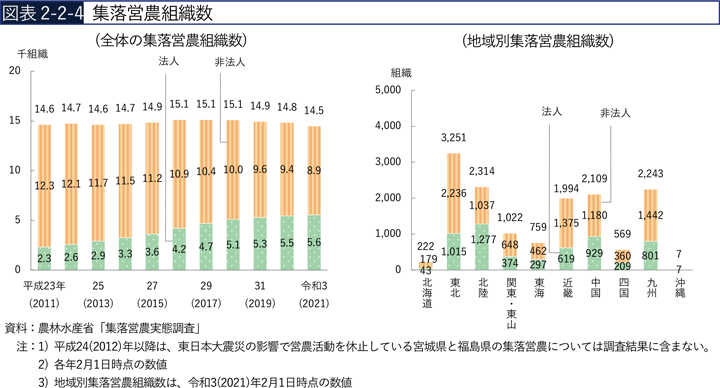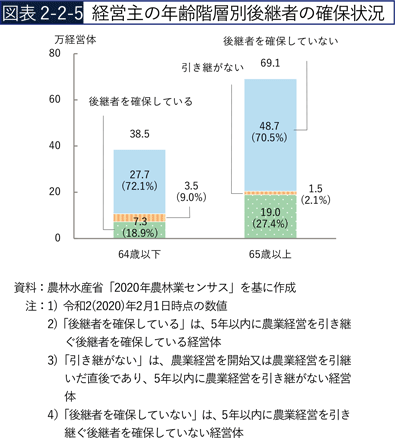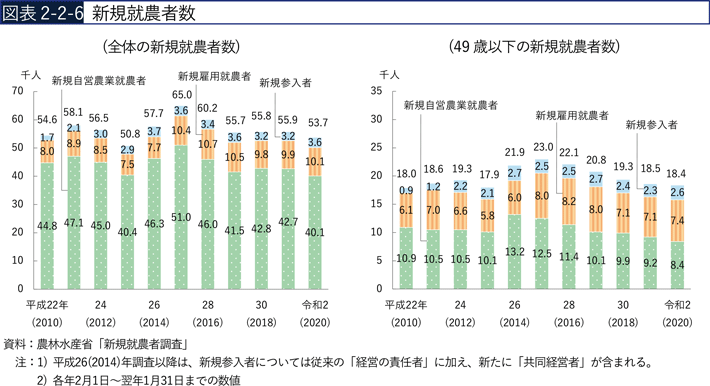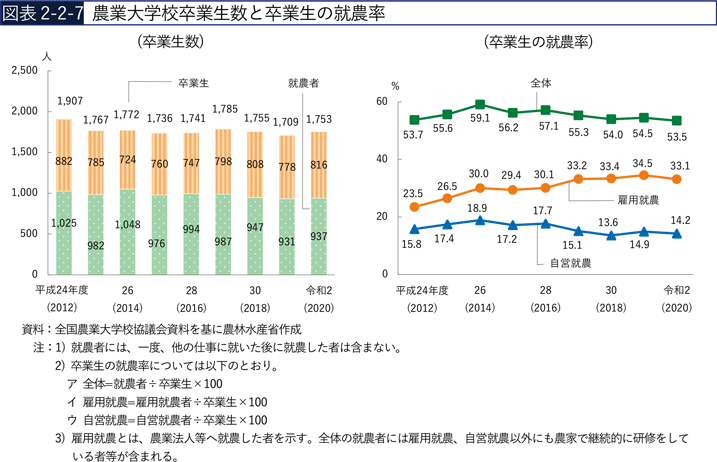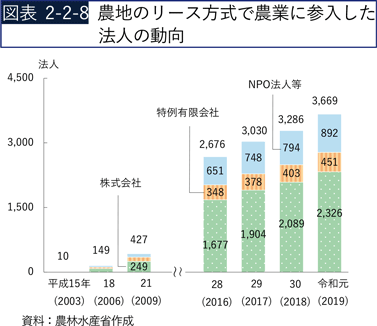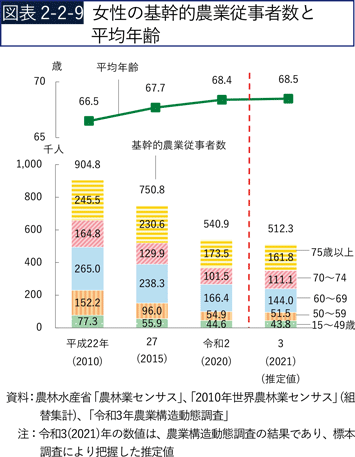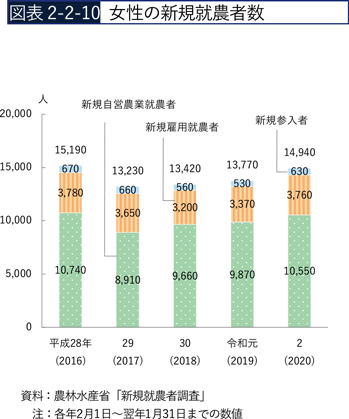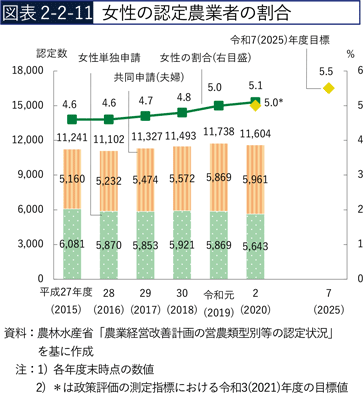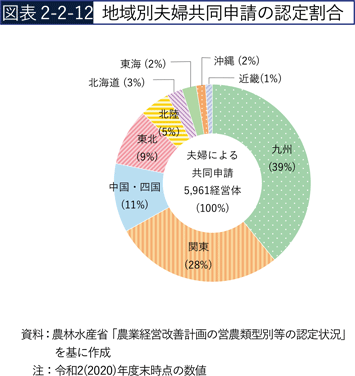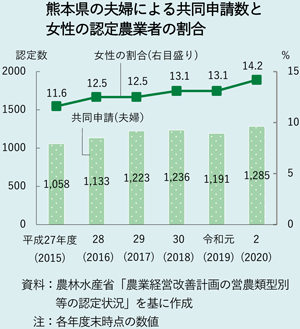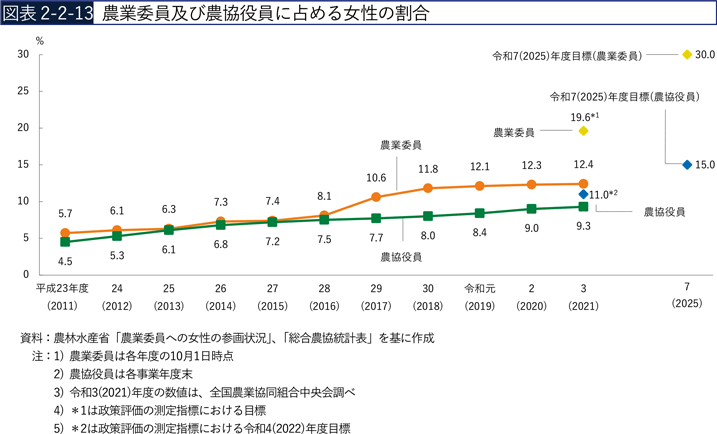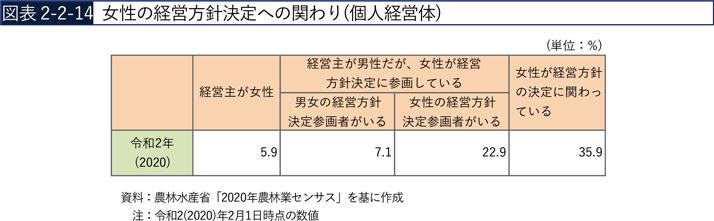第2節 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保

我が国農業が成長産業として持続的に発展していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を目指す経営体等の担い手の育成・確保が重要です。本節では、認定農業者(*1)制度、法人化、新規就農者(*2)、女性農業者等の動向について紹介します。
1 用語の解説3(1)を参照
2 用語の解説2(6)を参照
(1)認定農業者制度や法人化等を通じた経営発展の後押し
(農業経営体に占める認定農業者の割合は増加、法人経営体の認定数は一貫して増加)
農業者が作成した経営発展に向けた計画(農業経営改善計画)の認定数(認定農業者数)は、令和2(2020)年度末時点で5年前に比べ7.6%減少し22万7千経営体となりました。農業経営体(*1)に占める認定農業者の割合は増加傾向で推移しており、令和2(2020)年度末時点で21.7%の目標に対し、22.1%となっています(図表2-2-1)。
このうち法人経営体の認定数は一貫して増加しており、令和2(2020)年度末時点で5年前と比べ32.1%増加の2万7千経営体となりました。また、法人経営体に占める認定農業者の割合は85.8%となっています。法人経営体の認定状況を営農類型別で見ると、全ての営農類型で年々増加しており、特に、複合経営(*2)の認定数が多く、5年前と比べ33.5%増加し、9,942経営体となっています(図表2-2-2)。
農業経営改善計画の実現に向け、農林水産省は、認定農業者に対し、農地の集積・集約化(*3)や経営所得安定対策等の支援措置を講じており、農業経営体に占める認定農業者の割合を令和7(2025)年度までに24.0%にすることを目標としています。
さらに、令和2(2020)年度からは、認定農業者による市町村の区域を越えた経営展開に対応し、複数の市町村で農業を営む農業者について、農林水産省や都道府県において認定ができるようになりました。同年度には、農林水産省で138経営体、都道府県で1,979経営体の認定を行っています。
1 用語の解説1、2(1)を参照
2 経営体ごとの農産物販売金額1位の部門(作目)の販売金額が農産物総販売金額の80%未満の経営をいう。
3 用語の解説3(1)を参照
(法人経営体は3.2万経営体に増加)
農業経営の法人化については、経営管理の高度化や安定的な雇用、円滑な経営継承、雇用による就農機会の拡大等の利点があります。農林水産省では、農業経営の法人化を進めるため、農業経営相談所が関係機関と連携して行う経営相談、経営診断等の取組を支援しています。法人経営体数は、令和5(2023)年までに5万法人にすることを目標としており、令和3(2021)年は4万2,920法人の目標に対して、3万2千経営体となり、前年から2.9%増加しました(図表2-2-3)。
(集落営農組織の法人は増加)
集落営農(*1)組織は、地域の担い手として農地の利用、農業生産基盤の維持に貢献していますが、近年では、米、麦、大豆以外の高収益作物等の生産・販売や農産加工品の製造・販売等により収益の向上に取り組む組織が増えています。令和3(2021)年2月時点での集落営農組織数は1万4,490組織となりました(図表2-2-4)。
また、集落営農のうち法人経営体の組織数は年々増加しており、令和3(2021)年は前年に比べ106組織(1.9%)増加の5,564組織となりました。地域別に見ると、稲作が盛んな北陸、中山間地域(*2)が多い中国で法人化率が高くなっています。
農林水産省では、集落営農組織において法人化に加えて、機械の共同利用や人材の確保につながる広域化、高収益作物の導入等、それぞれの状況に応じた取組を促進し、人材の確保や、収益力向上、組織体制の強化、効率的な生産体制の確立を図っていくこととしています。
1 用語の解説3(1)を参照
2 用語の解説2(7)を参照
(2)経営継承や新規就農、人材育成・確保等
(経営主が65歳以上の経営体で後継者を確保している割合は27%、新規就農者数は5.4万人)
農業経営を引き継ぐ後継者の確保状況を見ると、令和2(2020)年2月時点において、5年以内に農業経営を引き継ぐ後継者を確保している農業経営体数は26万2千経営体で、このうち、経営主が65歳以上の階層では、後継者を確保している経営体数は19万経営体、65歳以上の経営体に占める割合は27.4%となっています(図表2-2-5)。一方、後継者を確保していない経営体数は48万7千経営体で70.5%となっています。また、64歳以下の階層では後継者を確保していない経営体数は27万7千経営体と64歳以下の経営体数の約7割を占めています。
新規就農者数は、平成26(2014)年から2年連続で増加したものの、近年は横ばいで推移しています。令和2(2020)年の新規就農者数は、前年に比べ3.8%減少の5万3,740人となっています (図表2-2-6)。この内訳を見ると、全体の約7割を占める4万100人が新規自営農業就農者(*1)となっています。新規雇用就農者(*2)は、平成26(2014)年までは8千人前後で推移していましたが、平成27(2015)年以降は1万人前後で推移し、令和2(2020)年は1万50人になっています。
このうち、将来の担い手として期待される49歳以下の新規就農者は、近年2万人前後で推移しています。令和2(2020)年は前年に比べ0.9%減少の1万8,380人となっており、5割強を新規雇用就農者と新規参入者(*3)で占めています。
1~3 用語の解説2(6)を参照
(経営継承、新規就農を支援)
農業従事者(*1)の高齢化と減少が進む中、地域農業を持続的に発展させていくためには、農地はもとより、農地以外の施設等の経営資源や、技術・ノウハウ等を次世代の経営者に引き継ぐ、計画的な経営継承を促進する必要があります。
このため、農林水産省は、農業者が話合いに基づき、地域における農業の在り方等を明確化する「人・農地プラン」(*2)の取組を進めるとともに、都道府県段階に設置した農業経営相談所において税理士や中小企業診断士等の専門家による相談対応を行うなど、円滑な経営継承を進めています。
また、世代間のバランスのとれた農業労働力の構造を実現していくことにより地域農業を維持していくことが必要です。
新規就農者は、農地の確保、資金の確保、営農技術の習得等が、経営開始時の大きな課題となっており、就農しても経営不振等の理由から定着できない就農者もいます。

就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」
URL:https://www.be-farmer.jp/(外部リンク)
このため、農林水産省では、就農準備段階や、就農直後の経営確立を支援する資金を交付するとともに、雇用就農を促進するため、農業法人等による新規雇用就農者への実践研修、新たな法人の設立に向けた研修の実施を支援しています。さらに、新規就農者の経営発展や地域への定着のため、市町村や農協、農地中間管理機構等地域の関係機関が連携して、就農後の農業技術向上や販路確保等に対しての支援を行うほか、就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」による情報発信、新規就農者の定着に向けた無利子資金等の支援を行っています。
1 用語の解説1、2(5)を参照
2 第2章第4節を参照
(若者の就農意欲を向上させる活動等を支援)
農業に関する学科を有する高等学校は全ての都道府県に設置されています。農業高校では、植物、動物、食品、地域環境等の基礎的な知識や技術を学ぶとともに、農業実習等の実践的・体験的な学習や解決方法を模索するプロジェクト学習等に取り組んでおり、近年では国際協力やGAP(*1)に取り組む高校が増えています。
農林水産省では、若い人が農業の魅力を感じ、将来的に農業を職業として選択し、経営感覚や国際感覚を持つ農業経営者として活躍できるよう、スマート農業、経営管理等の教育カリキュラムの強化や、地域の先進的な農業経営者による高校等への出前授業を行うなど、若者の就農意欲を向上させるための活動等を支援しています。
1 用語の解説3(2)を参照
(農業大学校卒業生の就農割合はほぼ横ばいで推移)
農業経営の担い手を養成する機関として道府県立農業大学校が42道府県に設置されています。卒業生は平成25(2013)年度以降はほぼ横ばいで推移しており、令和2(2020)年度の卒業生数は1,753人、卒業後に就農した者は937人と卒業生全体の53.5%となっています(図表2-2-7)。
卒業生の就農率を見ると、自営就農率は15%前後で推移しています。雇用就農率は年々増加傾向にあり、令和2(2020)年度は33.1%となりました。
(リース法人による農業への参入が増加傾向)
農地のリース方式により農業に参入し、農業経営を行う法人の数は令和元(2019)年12月末時点で3,669法人となっています。平成21(2009)年の農地法改正によりリース方式による参入が全面解禁されたことから参入する法人数は年々増加しています(図表2-2-8)。参入した法人格別の割合を見ると、令和元(2019)年は、株式会社が63%、NPO法人(*1)等が24%、特例有限会社が12%となっています。
1 用語の解説3(2)を参照
(3)女性が活躍できる環境整備
(女性の基幹的農業従事者数は5%減少、新規就農者数は8.5%増加)
令和3(2021)年の女性の基幹的農業従事者(*1)数は、前年に比べ5.3%減少し、51万2千人となっています。年齢階層別では、特に60~69歳の階層で減少しています。一方で、70~74歳の階層ではやや増加しています。平均年齢は68.5歳と前年に比べ0.1歳高くなっています(図表2-2-9)。
令和2(2020)年における女性の新規就農者数は1万4,940人で、前年に比べ8.5%増加し、そのうち49歳以下は5,430人となっています。女性の新規就農者数の内訳は、新規自営農業就農者は1万550人、新規雇用就農者は3,760人、新規参入者は630人となっています(図表2-2-10)。
新規就農者に占める女性の割合は27.8%、各就農形態における女性の割合では新規雇用就農者に占める女性の割合が一番高く、37.4%となっています。
1 用語の解説1、2(5)を参照
(女性の認定農業者の割合は増加傾向)
令和2(2020)年度末時点の女性の認定農業者数は前年度から134人減少し、1万1,604人となりましたが、全体の認定農業者数に占める女性の割合は増加傾向で推移しており、令和2(2020)年度は5.0%の目標に対し、前年度に比べ0.1ポイント増加し5.1%となりました(図表2-2-11)。
また、認定農業者制度には、家族経営協定(*1)等が締結されている夫婦による共同申請が認められており、その認定数は5,961経営体となっています。地域別で見ると、関東(*2)、中国・四国、九州の3地域で全国の約8割を占めています(図表2-2-12)。
農林水産省は、女性の農業経営への主体的な関与をより一層推進するため、認定農業者に占める女性の割合を平成30(2018)年度末時点より0.7ポイント増加させ、令和7(2025)年度までに5.5%(*3)にすることを目標としています。目標の達成に向け、女性が働きやすい環境の整備や地域を牽引(けんいん)する女性リーダーの育成等の取組を支援しています。
1 用語の解説3(1)を参照
2 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
3 内閣府「第5次男女共同参画基本計画」(令和2(2020)年12月閣議決定)における成果目標
(事例)夫婦による認定農業者制度への共同申請は全国で最多(熊本県)
熊本県の認定農業者数は、令和2(2020)年度末時点で1万334経営体となっています。そのうち、夫婦による共同申請数は1,285経営体と全国で最も多くなっています。また、同年度の認定農業者数に占める女性の割合は、14.2%と5年前に比べて2.6ポイント増加しています。
熊本県では、平成12(2000)年に認定農業者連絡会議を設立し、平成19(2007)年には、全国認定農業者協議会に加入している県組織の中で初めて女性部を設立しました。同会議の女性部では、農業の振興や地域活性化に向けて、研修会やセミナー等の活動が行われています。
(農業委員、農協役員に占める女性の割合は増加)
農業委員や農協役員に占める女性の割合は、農業委員会等に関する法律及び農業協同組合法における、農業委員や農協理事等の年齢や性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない旨の規定を踏まえ、女性の参画拡大に向けた取組が促進されたことによって、増加傾向にあります。令和3(2021)年度はそれぞれ前年度に比べ0.1ポイント、0.3ポイント増加し、12.4%と9.3%になりました(図表2-2-13)。
また、農業委員については、全国1,702農業委員会のうち、女性が委員となっている農業委員会は令和3(2021)年度において1,448委員会となりました。このうち、女性の割合が30%に達している農業委員会は65委員会(全体の3.8%)となっています。
農業委員や農協役員に占める女性の割合については、農業委員は平成30(2018)年度から約18ポイント増加させ令和7(2025)年度までに30%(*1)、農協役員は平成30(2018)年度から7ポイント増加させ令和7(2025)年度までに15%(*1)にすることを目標としています。
土地改良区(*2)についても、土地改良区等(土地改良区連合を含む。)の理事に占める女性の割合を、平成28(2016)年度から約9ポイント増加させ、令和7(2025)年度までに10%(*3)にすることを目標としています。令和2(2020)年度の割合は0.6%ですが、土地改良区等における女性参画拡大に向け、令和元(2019)年12月に「全国水土里(みどり)ネット女性の会」が発足し、女性の役職員の知見・ノウハウの共有やスキルの向上を図るなど、女性が土地改良事業の中核的役割を担える環境づくりに向けた取組を推進しているところです。
1 内閣府「第5次男女共同参画基本計画」(令和2(2020)年12月閣議決定)における成果目標
2 農地の整備や農業水路の維持管理を行うほか、住民と連携した地域づくりや地域農業の振興のための活動を行う農業者の組織。土地改良区地区数は4,325地区(令和3(2021)年3月末時点)
3 内閣府「第5次男女共同参画基本計画」(令和2(2020)年12月閣議決定)における成果目標
(「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」を策定)
令和3(2021)年6月、政府は、第5次男女共同参画基本計画で決定した目標の達成に向けて、政府全体として今後重点的に取り組むべき事項を定めた「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」を策定しました。
重点方針では、市町村や農協に対して、女性の農業委員、農協役員の参画割合の目標や、女性参画のための具体的な取組を定めるように促すとともに、これらの策定状況、参画実績について毎年調査し、公表することとしています。また、女性委員がいない農業委員会や、女性の役員がいない農協に対し働き掛けを重点的に行うなど、女性の参画を推進しています。
さらに、土地改良区等について、土地改良長期計画(令和3(2021)年3月閣議決定)に基づき、国、都道府県、都道府県土地改良事業団体連合会等で構成される協議会を都道府県ごとに設置の上、当該協議会を通じ員外理事制度を活用した女性理事の参画を促しています。
(女性が経営方針の決定に参画している割合は36%)
令和2(2020)年の女性の経営への参画状況を見ると、経営主が女性の個人経営体(*1)は、農業経営体全体の5.9%、経営主が男性だが、女性が経営方針の決定に参画している割合は30.0%となっており、女性が経営に関与する個人経営体は全体の35.9%を占めています(図表2-2-14)。

農業における女性をめぐる事情
URL:https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/gaiyo.html
1 用語の解説1、2(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883