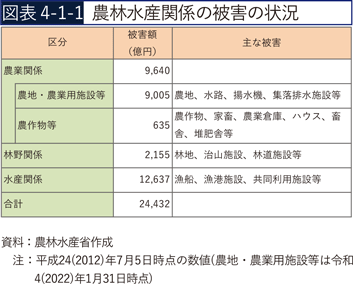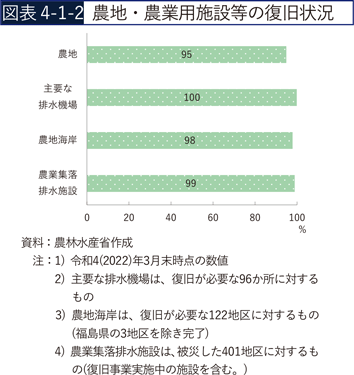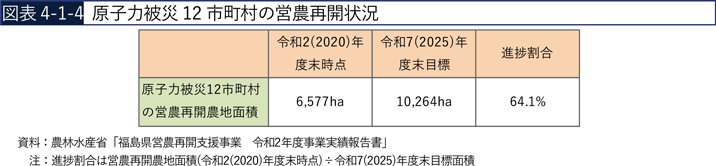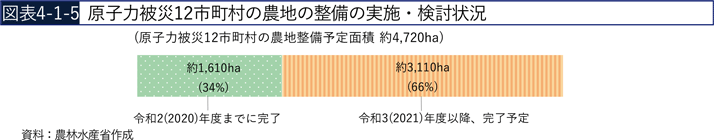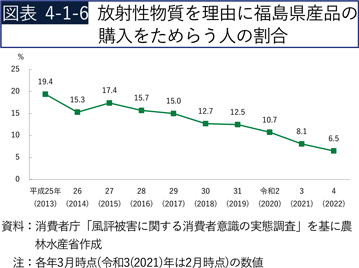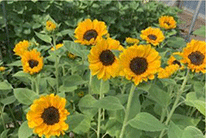第1節 東日本大震災からの復旧・復興
平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県の3県を中心とした東日本の広い地域に東京電力福島第一(とうきょうでんりょくふくしまだいいち)原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の事故の影響を含む甚大な被害が生じました。
政府は同年7月から令和2(2020)年までの10年間の復興期間に引き続き、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間を「第2期復興・創生期間」と位置付け、被災地の復興に向けて取り組んでいます。
本節では、東日本大震災の地震・津波や原子力災害からの農業分野の復旧・復興の状況について紹介します。
(1)地震・津波災害からの復旧・復興の状況
(営農再開が可能な農地は95%に)
東日本大震災による農業関係の被害額は、平成24(2012)年7月5日時点(農地・農業用施設等は令和4(2022)年1月31日時点)で9,640億円、農林水産関係の合計では2兆4,432億円となっています(図表4-1-1)。津波により被災した農地2万1,480haから公共用地等への転用が見込まれるものを除いた復旧対象農地1万9,660haのうち、令和3(2021)年度時点の目標面積1万8,650haに対して、令和4(2022)年3月末時点で1万8,630ha(95%(*1))の農地で営農が可能となりました(図表4-1-2)。
農林水産省は、除塩、畦畔(けいはん)の修復等の復旧に取り組んでおり、市町村からの聞き取り結果を踏まえ、令和6(2024)年度までに1万9,020haの農地面積、復旧対象農地の97%の水準まで復旧することを目標としています。
*1 公共用地等への転用が行われたもの(見込みを含む。)を除いた津波被災農地1万9,660haに対するもの(福島県の1,030haを除き完了)
(地震・津波からの農地の復旧に併せた圃場の大区画化の取組が拡大)
岩手県、宮城県、福島県の3県では、地域の意向を踏まえ、地震・津波からの復旧に併せた農地の大区画化に取り組んでいます。整備計画面積が前年度から280ha増加し、令和3(2021)年度末時点で8,510haとなる中、大区画化への完了見込面積は、同時点で8,240ha、96.8%となっており、地域農業の復興基盤の整備が進展しています。
宮城県と福島県では、高台への集団移転と併せて、移転跡地を含めた農地整備を10市町、合計17地区で進め、同年度末時点で14地区の整備が完了しました。
(先端的農業技術の現地実証研究と研究成果の情報発信等を実施)
農林水産省は被災地域を新たな食料生産基地として再生するため、産学官連携の下、農業・農村分野に関わる先端的で大規模な実証研究を行っています。
令和3(2021)年度からは、福島県において、農業用水利施設管理省力化ロボットの開発や土壌肥沃度のばらつき改善技術の開発など新たに6課題の農業分野に関わる研究開発・現地実証研究を行っています。また、栽培中断園地における果樹の早期復旧に向けた実証研究で得られた成果を活用して、ぶどうの根圏制御栽培やジョイントV字樹形の導入による果樹の早期成園化と省力化に取り組むなど、これまでの実証研究で得られた成果を現場に定着させるため、令和3(2021)年4月、実装拠点を県内5か所に設置しました(図表4-1-3)。各拠点では、県内の農業者や普及指導員等に対して、実証圃(じっしょうほ)での成果等を機関誌や報道機関を通じて情報提供・周知するとともに、技術導入を希望する農業者へ向けた実証圃での研修や技術移転セミナーの開催による技術指導等を行うなど、得られた研究成果の普及に取り組んでいます。
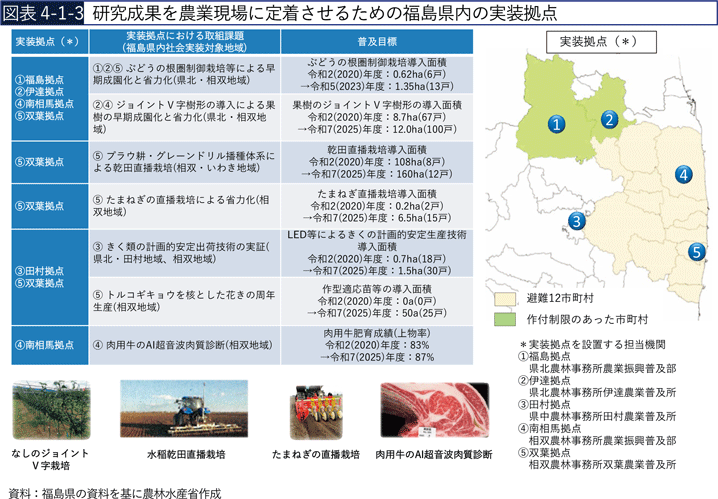
(2)原子力災害からの復旧・復興
ア 農畜産物の安全確保の取組
(安全性確保のための取組が進展)
生産現場では、市場に放射性物質の基準値を上回る農畜産物が流通することのないように、放射性物質の吸収抑制対策、暫定許容値以下の飼料の使用等、それぞれの品目に合わせた取組が行われています。このような生産現場における努力の結果、基準値超過が検出された割合は、全ての品目で平成23(2011)年以降低下し、平成30(2018)年度以降は、全ての農畜産物において基準値超過はありません。
イ 原子力被災12市町村の復興
(原子力被災12市町村の営農再開農地面積が増加)
原子力被災12市町村(*1)における営農再開農地面積は、令和2(2020)年度末時点で、前年度から1,009ha増加しているものの、特に帰還困難区域がある町村の営農再開が遅れており、6,577haとなっています。これは、令和7(2025)年度までに営農再開農地面積を1万264haとする目標の64.1%に当たります(図表4-1-4)。農林水産省は、除染後の農地の保全管理から作付実証、農業用機械・施設の導入支援等に取り組んでおり、12市町村における農業者の営農再開に向けた支援事業の進捗や避難指示解除の時期、帰還状況を踏まえ、平成23(2011)年12月末時点で営農が休止されていた農地1万7,298haの約6割を営農再開することを目標としています。
*1 福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
(原子力被災12市町村の農地整備の実施済面積は約1,610ha)
原子力被災12市町村の農地については、営農休止面積1万7,298haのうち、営農再開のための農地整備の実施・検討がされている面積は約4,720haとなっています。このうち、令和2(2020)年度末時点で、約1,610haの農地整備が完了しました(図表4-1-5)。
(農地の大区画化、利用集積の加速化に向けた取組を強化)
農地の大区画化や利用集積を加速化するため、改正福島復興再生特別措置法(*1)が令和3(2021)年4月に施行されました。これにより、市町村に代わって福島県が農地集積の計画を作成・公告できるようにするとともに、農地中間管理機構を活用して、農地の共有者の過半が判明していない農地も含め、担い手への権利設定等を行うことができるようになりました。同年11月時点で、3市町村で11件の計画が作成・公告され、約229haの農地が集積されています。あわせて、原子力被災12市町村に農地中間管理機構の現地コーディネーターを計12人配置し、農地の集積・集約化(*2)の取組強化を図りました。
*1 正式名称は、「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」
*2 用語の解説3(1)を参照
(営農再開支援のため原子力被災12市町村へ農林水産省職員を派遣)
営農再開を加速するため、農林水産省は、令和2(2020)年4月から原子力被災12市町村に対し、職員を1人ずつ派遣し、営農再開のビジョンづくりから具体化までを支援しています。このほか、地域の実情を踏まえ、福島県の双葉町(ふたばまち)と飯舘村(いいたてむら)に農業土木職員を出向させ、基盤整備に係る支援をしています。
また、福島県のいわき市(し)と富岡町(とみおかまち)に設置していた技術系職員を含むサポートチームを、令和3(2021)年4月に富岡町に集約し、一元的に支援する体制を整備しました。
(生産と加工等が一体となった高付加価値生産を展開する産地の創出)
農林水産省は、令和3(2021)年から、国産需要の高い加工・業務用野菜等を、市町村を越えて広域的に生産・加工等が一体となって付加価値を高めていく産地の創出に向けて、産地の拠点となる施設整備等の支援を行っています。
また、当該支援の実施に当たり、農業者団体、原子力被災12市町村等で構成する「福島県高付加価値産地協議会(ふくしまけんこうふかかちさんちきょうぎかい)」を同年8月に設立し、関係機関が連携して産地の創出を推進することにより、営農再開や新規参入を後押しすることとしています。
(事例)浪江町で休耕地を使った長ねぎの生産を開始(福島県)
有限会社青高(せいこう)ファームと株式会社群馬電機工業(ぐんまでんきこうぎょう)の2社は、群馬県で長ねぎの生産に取り組んでいます。
2社は、長ねぎの新たな生産拠点を求めていたところ、JAグループから福島県浪江町(なみえまち)の紹介を受け、1年間の実証栽培を行った結果、圃場(ほじょう)条件も良く、気候も長ねぎの栽培に適していたことから進出を決めました。
公益社団法人福島相双復興推進機構(ふくしまそうそうふっこうすいしんきこう)の支援により同町内の農地の仲介を受け、令和3(2021)年4月から5.3haで長ねぎの生産を開始しました。
2社は「将来的に規模を拡大して町内で100haまで広げ、地元住民の新規雇用にもつなげたい。」と話しています。
(「特定復興再生拠点区域」の復興・再生への取組を実施)
福島復興再生特別措置法においては、5年をめどに避難指示を解除し、住民の帰還を目指す「特定復興再生拠点区域」の復興・再生を推進しており、帰還困難区域が存在する全6町村(*1)が同法に基づき復興再生計画を策定し、農業の再生を目指した区域を設定しています。
福島県の双葉町、葛尾村(かつらおむら)の特定復興再生拠点区域においては、将来的な営農再開に向け、令和3(2021)年産から町村の管理の下で水稲の試験栽培が開始されました。令和7(2025)年度をめどに本格的な営農再開を目指すこととしています。
*1 福島県の双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村
ウ 風評払拭に向けた取組等
(「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組のフォローアップを実施)
消費者庁が令和4(2022)年3月に公表した消費者の意識調査(*1)によると、放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合は6.5%となり、調査開始以来最低の水準となりました(図表4-1-6)。
風評等が今なお残っていることを踏まえ、復興庁やその他関係府省は、平成29(2017)年12月に策定した「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組のフォローアップとして、「知ってもらう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の三つを柱とする情報発信を実施し、風評の払拭に取り組んでいます。
また、福島県の農林水産業再生に向けた取組の一つとして、令和3(2021)年度は、福島県産の新ブランド米「福、笑い」のイベント等の実施により認知度を高めつつ消費者や販売店への販売を展開しました。福島牛については、展示会等での小売業者等への売り込み、消費者向けの農場見学等を実施することでブランド力の再生を図るなど、積極的なマーケティング展開を行いました。
さらに、「食べて応援しよう!」のキャッチフレーズの下、消費者、生産者等の団体や食品事業者等、多様な関係者の協力を得て被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組を進めることで、被災地産食品の利用・販売を引き続き進めています。

(海外向け動画)
Just how delicious is Fukushima Food? Yeah, you’ll see
URL:https://www.youtube.com/
watch?v=fs8U2cj3aMs(外部リンク)
資料:福島県
このほか、被災地産の農林水産物の風評払拭に向けた取組として、国内外のメディア向けに被災地の姿や魅力の発信を動画や東京2020大会(*2)のメインプレスセンター復興ブースで行うとともに、この復興ブースを活用して、ビクトリーブーケの紹介や、GAP(*3)による安全・安心な農産物生産、日本産食品の放射性物質に関する安全性について、オンラインでブリーフィングを実施しました。
*1 消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査(第15回)」(令和4(2022)年3月公表)
*2 大会は令和3(2021)年に開催
*3 用語の解説3(2)を参照
(コラム)復興への願いが込められたビクトリーブーケの花
東京2020大会では、メダリストに副賞としてビクトリーブーケが授与されました。ブーケに使われた花には、主に東日本大震災で被災した地域で栽培されたトルコギキョウ、ヒマワリ、リンドウなどが選ばれました。
選ばれた花にはそれぞれエピソードがあります。トルコギキョウは福島県が県ぐるみで生産に取り組んでおり、震災による影響で農作物の出荷が減った際に、特定非営利活動法人(NPO(*))が花を栽培することで復興への希望を見いだしたものです。ヒマワリは、宮城県の震災で子供を亡くした親たちが、子供たちが避難するために目指した丘にヒマワリを植え、その丘にはヒマワリが毎年咲くようになったそうです。リンドウは岩手県を代表する花で、東京2020大会のエンブレムと同色の藍色の美しい花を咲かせることから選ばれました。
三つの花にはこうした意味合いが込められており、世界最大のスポーツイベントである東京2020大会を通じて、復興の進展のシンボルとして、世界にアピールするものとなりました。
* 用語の解説3(2)を参照
(東京電力による農林水産関係者への損害賠償支払)
原子力損害の賠償に関する法律の規定により、東電福島第一原発の事故の損害賠償責任は東京電力(とうきょうでんりょく)ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が負っています。
東京電力によるこれまでの農林漁業者等への損害賠償支払累計額は、令和4(2022)年3月末時点で9,749億円(*1)となっています。
*1 農林漁業者等の請求・支払状況について、関係団体等からの聞き取りから把握できたもの
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883