用語の解説
用語の解説
(1)五十音順
あ
アフリカ豚熱
ASFウイルスによって引き起こされる豚やイノシシの伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病。有効なワクチン及び治療法はない。本病はアフリカでは常在しており、ロシア及びその周辺諸国でも発生が確認されている。平成30(2018)年8月に、中国においてアジアでは初となる発生が確認されて以降、アジアで発生が拡大した。我が国では、これまで本病の発生は確認されていない。なお、豚、イノシシの病気であり、ヒトに感染することはない。
温室効果ガス
地面から放射された赤外線の一部を吸収・放射することにより地表を暖める働きがあるとされるもの。京都議定書では、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4、水田や廃棄物最終処分場等から発生)、一酸化二窒素(N2O、一部の化学製品原料製造の過程や家畜排せつ物等から発生)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs、空調機器の冷媒等に使用)等を温室効果ガスとして削減の対象としている。
か
家族経営協定
家族で営農を行っている農業経営において、家族間の話合いを基に経営計画、各世帯員の役割、就業条件等を文書にして取り決めたものをいう。この協定により、女性や後継者等の農業に従事する世帯員の役割が明確化され、農業者年金の保険料の優遇措置の対象となるほか、認定農業者制度の共同申請等が可能となる。
供給熱量(摂取熱量)
食料における供給熱量とは、国民に対して供給される総熱量をいい、摂取熱量とは、国民に実際に摂取された総熱量をいう。一般には、前者は農林水産省「食料需給表」、後者は厚生労働省「国民健康・栄養調査」の数値が用いられる。両者の算出方法は全く異なり、供給熱量には、食品産業において加工工程でやむを得ず発生する食品残さや家庭での食べ残し等が含まれていることに留意が必要
荒廃農地
現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地
高病原性鳥インフルエンザ
鳥インフルエンザのうち、家きんを高い確率で致死させるもの。家きんがこのウイルスに感染すると、神経症状、呼吸器症状、消化器症状等全身症状を起こし、大量に死ぬ。なお、我が国ではこれまで、鶏卵、鶏肉を食べることによりヒトが感染した例は報告されていない。
さ
集落営農
集落等地縁的にまとまりのある一定の地域内の農業者が農業生産を共同して行う営農活動をいう。転作田の団地化、共同購入した機械の共同利用、担い手が中心となって取り組む生産から販売までの共同化等、地域の実情に応じてその形態や取組内容は多様である。
食料安全保障
我が国における食料安全保障については、食料・農業・農村基本法において、「国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しく逼迫(ひっぱく)し、又は逼迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。」とされている。他方、世界における食料安全保障(Food Security)については、FAO(国際連合食糧農業機関)で、全ての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好(しこう)を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的にも社会的にも経済的にも入手可能であるときに達成されるとされている。また、食料安全保障には以下の四つの要素があるとされている。<1>適切な品質の食料が十分に供給されているか(供給面)、<2>栄養ある食料を入手するための合法的、政治的、経済的、社会的な権利を持ち得るか(アクセス面)、<3>安全で栄養価の高い食料を摂取できるか(利用面)、<4>いつ何時でも適切な食料を入手できる安定性があるか(安定面)
食料国産率
国内に供給される食料に対する国内生産の割合であり、飼料が国産か輸入かにかかわらず、畜産業の活動を反映し、国内生産の状況を評価する指標。輸入した飼料を使って国内で生産した分も国産に算入して計算
食料自給率
我が国の食料全体の供給に対する国内生産の割合を示す指標
○品目別自給率:以下の算定式により、各品目における自給率を重量ベースで算出
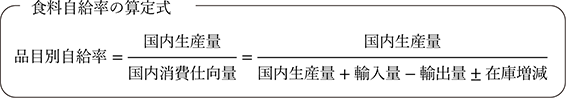
○総合食料自給率:食料全体における自給率を示す指標として、供給熱量(カロリー)ベース、生産額ベースの2通りの方法で算出。畜産物については、輸入した飼料を使って国内で生産した分は、国産には算入していない。
なお、平成30(2018)年度以降の食料自給率は、イン(アウト)バウンドによる食料消費増減分を補正した数値としている。
供給熱量(カロリー)ベースの総合食料自給率:分子を1人・1日当たり国産供給熱量、分母を1人・1日当たり供給熱量として計算。供給熱量の算出に当たっては、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づき、品目ごとに重量を供給熱量に換算した上で、各品目の供給熱量を合計
生産額ベースの総合食料自給率:分子を食料の国内生産額、分母を食料の国内消費仕向額として計算。金額の算出に当たっては、生産農業所得統計の農家庭先価格等に基づき、重量を金額に換算した上で、各品目の金額を合計
○飼料自給率:畜産物を生産する際に家畜に給与される飼料のうち、国産(輸入原料を利用して生産された分は除く。)でどの程度賄われているかを示す指標。「日本標準飼料成分表(2009年版)」等に基づき、TDN(可消化養分総量)に換算し算出
食料自給力
国内農林水産業生産による食料の潜在生産能力を示す概念。その構成要素は、農産物は農地・農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者、水産物は潜在的生産量と漁業就業者
○食料自給力指標
我が国の農地等の農業資源、農業者、農業技術といった潜在生産能力をフル活用することにより得られる食料の供給熱量を示す指標
生産を以下の2パターンに分け、それぞれの熱量効率が最大化された場合の国内農林水産業生産による1人・1日当たりの供給可能熱量により示す。くわえて、各パターンの生産に必要な労働時間に対する現有労働力の延べ労働時間の充足率(労働充足率)を反映した供給可能熱量も示す。
<1>栄養バランスを考慮しつつ、米・小麦を中心に熱量効率を最大化して作付け
<2>栄養バランスを考慮しつつ、いも類を中心に熱量効率を最大化して作付け
水田の汎用化
通常の肥培管理で麦・大豆等の畑作物や野菜を栽培できるよう、水田に排水路や暗渠(あんきょ)を整備して水はけを良くすること
スマート農業
ロボット、AI、IoT等の先端技術を活用する農業のこと。ドローンやロボット農機の活用による作業の省力化・自動化や、データの活用による、農産物の品質や生産性の向上が期待される。
生態系サービス
人々が生態系から得ることのできる便益のことで、食料、水、木材、繊維、燃料等の「供給サービス」、気候の安定や水質の浄化等の「調整サービス」、レクリエーションや精神的な恩恵を与える「文化的サービス」、栄養塩の循環や土壌形成、光合成等の「基盤サービス」等がある。
た
地産地消
国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるものに限る。)を、その生産された地域内において消費する取組。食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取組等を通じて、6次産業化にもつながるもの
な
中食
レストラン等へ出掛けて食事をする「外食」と、家庭内で手づくり料理を食べる「内食」の中間にあって、市販の弁当や総菜、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校等で、そのまま(調理加熱することなく)食べること。これら食品(日持ちしない食品)の総称としても用いられる。
認定農業者(制度)
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を実施
農業集落
市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用を中心に、家と家とが地縁的、血縁的に結び付いた社会生活の基礎的な地域単位のこと。農業水利施設の維持管理、農機具等の利用、農産物の共同出荷等の農業生産面ばかりでなく、集落共同施設の利用、冠婚葬祭、その他生活面に及ぶ密接な結び付きの下、様々な慣習が形成されており、自治及び行政の単位としても機能している。
農業水利施設
農地へのかんがい用水の供給を目的とするかんがい施設と、農地における過剰な地表水及び土壌水の排除を目的とする排水施設に大別される。かんがい施設には、ダム等の貯水施設や、取水堰(せき)等の取水施設、用水路、揚水機場、分水工、ファームポンド等の送水・配水施設があり、排水施設には、排水路、排水機場等がある。このほか、かんがい施設や排水施設の監視や制御・操作を行う水管理施設がある。
農地の集積・集約化
農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大することをいう。農地の集約化とは、農地の利用権を交換すること等により、農地の分散を解消することで農作業を連続的に支障なく行えるようにすることをいう。
農泊
農山漁村地域に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のこと。宿泊・食事・体験等農山漁村ならではの地域資源を活用した様々な観光コンテンツを提供し、農山漁村への長時間の滞在と消費を促すことにより、地域が得られる利益を最大化し、農山漁村の活性化と所得向上を図るとともに、農山漁村への移住・定住も見据えた関係人口創出の入口となることが期待される。
は
バイオマス
動植物に由来する有機性資源で、化石資源を除いたものをいう。バイオマスは、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素から、生物が光合成によって生成した有機物であり、ライフサイクルの中で、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源である。
フードバンク
食品関連事業者等から未利用食品等の寄附を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを無償で提供するための活動を行う団体
豚熱
CSFウイルスによって引き起こされる豚やイノシシの伝染病であり、発熱、食欲不振、元気消失等の症状を示し、強い伝播(でんぱ)力と高い致死率が特徴。アジアを含め世界では本病の発生が依然として認められる。我が国は、平成19(2007)年に清浄化を達成したが、平成30(2018)年9月に26年ぶりに発生した。なお、豚、イノシシの病気であり、ヒトに感染することはない。
や
遊休農地
以下の<1>、<2>のいずれかに該当する農地をいう。
<1>現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
<2>その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(<1>に掲げる農地を除く。)
ら
6次産業化
農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の者の協力を得て主体的に行う、1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組
わ
和食
平成25(2013)年12月に、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録された。この「和食」は、「自然を尊重する」というこころに基づいた日本人の食慣習であり、以下の四つの特徴を持つ。<1>多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、<2>健康的な食生活を支える栄養バランス、<3>自然の美しさや季節のうつろいの表現、<4>正月等の年中行事との密接な関わり
(2)アルファベット順
E
EPA/FTA
EPAはEconomic Partnership Agreementの略で、経済連携協定、FTAはFree Trade Agreementの略で、自由貿易協定のこと。物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的として特定国・地域の間で締結される協定をFTAという。FTAの内容に加え、投資ルールや知的財産の保護等も盛り込み、より幅広い経済関係の強化を目指す協定をEPAという。「関税及び貿易に関する一般協定」(GATT)等においては、最恵国待遇の例外として、一定の要件((1)「実質上の全ての貿易」について「関税その他の制限的通商規則を廃止」すること、(2)廃止は、妥当な期間内(原則10年以内)に行うこと、(3)域外国に対して関税その他の通商障壁を高めないこと等)の下、特定の国々の間でのみ貿易の自由化を行うことも認められている(「関税及び貿易に関する一般協定」(GATT)第24条ほか)。
ESG
Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動のこと
G
GAP(ギャップ)
Good Agricultural Practicesの略で、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のこと
GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)
ドイツのFoodPLUS GmbHが策定した第三者認証のGAP。青果物及び水産養殖に関してGFSI承認を受けており、主に欧州で普及
H
HACCP(ハサップ)
Hazard Analysis and Critical Control Point の略で、危害要因分析及び重要管理点のこと。原料受入れから最終製品までの各工程で、微生物による汚染、金属の混入等の危害の要因を予測(危害要因分析:Hazard Analysis)した上で、危害の防止につながる特に重要な工程(重要管理点:Critical Control Point、例えば加熱・殺菌、金属探知機による異物の検出等の工程)を継続的に監視・記録する工程管理のシステム。令和3(2021)年6月から、「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づき、原則全ての食品等事業者(食品製造、調理、販売等)に対して、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務化
I
ISO
International Organization for Standardizationの略で、スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関「国際(こくさい)標準化(ひょうじゅんか)機構(きこう)」のこと。ISOが制定するISO規格には、製品やサービスに関する規格のほか、組織の活動を管理するための仕組み(マネジメントシステム)に関する規格が存在する。
J
JAS
Japanese Agricultural Standardsの略で、日本農林規格のこと。JAS制度とは、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づき、食品・農林水産品の品質やこれらの取扱方法等についての規格(JAS)を国が制定するとともに、第三者機関から認証を取得することでJASを満たすことを証するマーク(JASマーク)を、当該食品・農林水産品や事業者の広告等に表示できる制度
JFS
Japan Food Safetyの略で、一般財団法人食品安全マネジメント協会が策定した第三者認証の食品安全マネジメント規格のこと。規格レベルが3段階から成り、順次ステップアップでき、また、GFSIに承認された国際標準レベルの規格を含めて要求事項が全て日本語を原文としていて中小事業者にも取り組みやすい。さらに、規格に柔軟性があり、日本特有の食文化である生食や発酵食等の食品製造においても導入しやすいといった特徴を有する。
O
OIE
国際獣疫事務局の発足当時の名称であるOffice International des Epizooties(フランス語)の略。現在の名称はWorld Organisation for Animal Health。大正13(1924)年に発足した動物衛生の向上を目的とした政府間機関。我が国は昭和5(1930)年に加盟。主に、アフリカ豚熱等の動物疾病防疫や薬剤耐性対策等への技術的支援、動物・畜産物貿易、アニマルウェルフェア等に関する国際基準の策定等の活動を行っている。
S
SDGs(持続可能な開発目標)
Sustainable Development Goalsの略。平成27(2015)年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、令和12(2030)年を期限とする国際社会全体の開発目標。飢餓や貧困の撲滅、経済成長と雇用、気候変動対策等包括的な17の目標を設定。法的な拘束力はなく、各国の状況に応じた自主的な対応が求められる。我が国では、平成28(2016)年5月に、「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」を設置。SDGs実施のための我が国のビジョンや優先課題等を掲げた「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」や、我が国のSDGsモデルの発信に向けた方向性や主要な取組を盛り込んだ「SDGsアクションプラン」を同本部で決定
17の目標に係るアイコンは以下の通り

T
TPP
Trans-Pacific Partnershipの略で、環太平洋パートナーシップのこと。TPP協定は、アジア太平洋地域において、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引等、幅広い分野でルールを構築する経済連携協定。TPP協定交渉は、平成27(2015)年に大筋合意に達し、平成28(2016)年に12か国(豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナム)による協定への署名が行われた。その後、平成29(2017)年の米国の離脱表明を受け、米国を除く11か国により協議が行われた結果、平成30(2018)年に「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)が発効した。CPTPPはComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipの略
W
WCS
WCSはWhole Crop Silageの略で、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料のこと。WCS用稲は、WCSとして家畜に給与する目的で栽培する稲のことで、水田の有効活用と飼料自給率の向上に資する。
WTO
World Trade Organizationの略で、世界貿易機関のこと。ウルグアイ・ラウンド合意を受け、「関税及び貿易に関する一般協定」(GATT)の枠組みを発展させるものとして、平成7(1995)年1月に発足した国際機関。本部はスイスのジュネーブにあり、令和5(2023)年1月時点、164の国と地域が加盟。貿易障壁の除去による自由貿易推進を目的とし、多角的貿易交渉の場を提供するとともに、国際貿易紛争を処理する。
○「基本統計用語の定義」については、以下の特設ページを参照

令和4年度食料・農業・農村白書
URL:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r4/index.html
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




