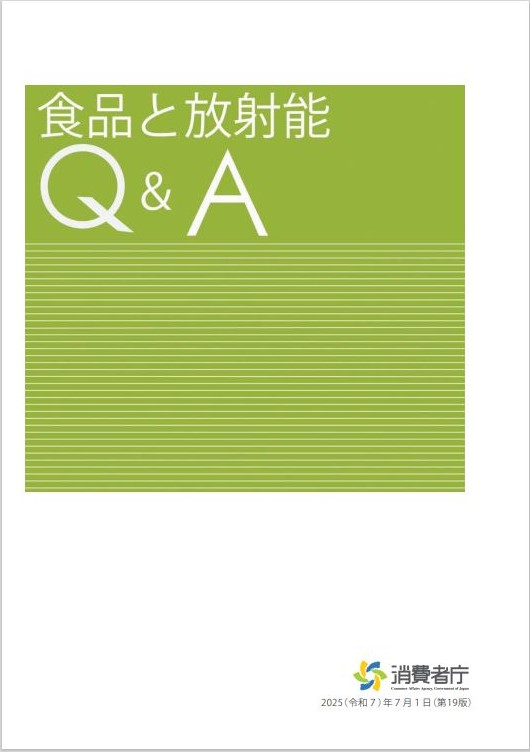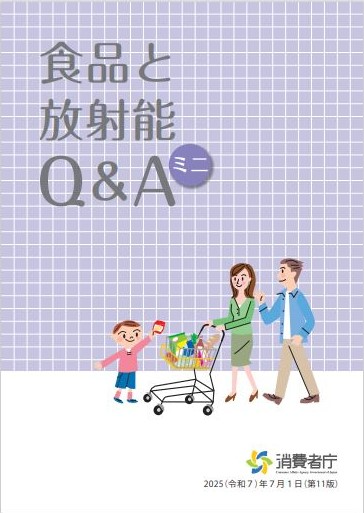食品中の放射性物質について知りたい方へ(消費者向け情報)
掲載日:平成27年1月30日
更新日:令和 7年8月25日
平成23年に発生した東日本大震災では、福島第一原子力発電所の事故の影響により、放射性物質が食品の安全対策の課題の一つになっています。
食品の安全性確保に向けた取組や被災地を応援する取組についてまとめました。
トピックス
- 食品中の放射性物質の最近の検出状況[令和7年7月18日]

- 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正 (原子力災害対策本部策定) (外部リンク:厚生労働省) [令和7年3月31日]
- 水産物のトリチウム調査結果について(水産庁ホームページ)
- 「岩手県、宮城県、福島県からの復興便り(令和6年度)」を公開しました[令和7年1月20日]
- 親子で学べる特設ウェブコンテンツ「知ろう!考えよう!食べものと放射性物質」を本日から公開します(外部リンク:消費者庁)[令和2年12月21日]
- オークションサイト・フリマサイトにおける野生の農産物の販売について(外部リンク:厚生労働省)[令和2年10月21日]
- 東日本大震災からの農林水産業の復興支援のための取組
- 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新)
放射線リスクについて知る
私たちは昔から常に少量の放射線を受けていながら、普段の生活では健康への影響を特段意識することなく生活しています。しかし、一度に大量の放射線を受けると影響が現れます。100ミリシーベルト以下の低線量被ばくの影響は、大人と同様に子どもにとっても放射線の影響が他の人体影響のリスク要因と区別できないほど小さなレベルです。また、子どもは、食品中の放射性物質から人体への影響を計算する実効線量係数は大人より大きくなっていますが、食べる量が少ないことなどから、食事による放射性物質から受ける影響は少なくなります。
 |
放射線リスクに関する基礎的情報[外部リンク:復興庁] 福島における放射線の状況や、放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見、被ばく低減にあたっての国際的・専門的な考え方など、基礎的な内容をまとめています。 食品中の放射性物質に関する情報[外部リンク:食品安全委員会] |
基準値設定の考え方と検査結果を知る
食べものに含まれる放射性物質の基準は、国際的な考え方と整合し、すべての年齢の方に配慮して、生涯食べ続けても安全性に問題が生じないように決められています。
基準値の設定について
| 食品群 | 基準値(Bq/kg) |
| 飲料水 | 10 |
| 牛乳 | 50 |
| 乳児用食品 | 50 |
| 一般食品 | 100 |
検査結果について
地方自治体では、基準値を超えた食品が市場に出回らないように、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部)に基づいた検査を行っています。各自治体等で実施された放射性物質の検査結果は、厚生労働省でとりまとめてホームページで公表しています。また、各自治体のホームページでも公表しています。
基準値を超過した食品については、回収、廃棄されるほか、基準値の超過に地域的な広がりが認められる場合には、出荷制限を行い、基準値を超過する食品が市場に流通しないよう取り組んでいます。
農畜水産物の出荷制限の指示及び解除については、厚生労働省が発表する「農林水産物の出荷制限の指示・解除」[外部リンク]をご覧下さい。
▶ 食品中の放射性物質の最近の検出状況[令和7年7月18日]
検査のガイドラインについて
食品中の放射性物質の検査は、原子力災害対策本部が定めた検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定・解除の考え方」を踏まえた「地方自治体における検査計画」に基づき、実施されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページ[外部リンク]をご覧下さい。
実際の食事から摂取する放射性物質の量を知る
市場に流通する食品を収集して行う調査(マーケットバスケット調査)や、一般家庭で調理された食事を分析する調査(陰膳調査)を定期的に実施し、人々が一年間に受ける線量を推計した結果などを消費者庁が公表しています。
食品中の放射性物質の基準値と摂取量調査 | 消費者庁[外部リンク]
令和5年2-3月以前の調査結果は厚生労働省が公表しています。
食品中の放射性物質への対応 - さらに詳しい情報|厚生労働省[外部リンク]
調査の結果、食品中の放射性セシウムから、人が1年間に受ける放射線量は基準値の設定根拠である年間1ミリシーベルトの1%以下であり、極めて小さいことが確かめられています。
また、実際の流通食品に含まれているセシウム以外の放射性物質も、平成24年から定期的に測定しています。その結果、食品中に放射性ストロンチウムは検出されないか、検出されても低い値(1ベクレル/kg以下)であり、事故以前の値の範囲内でした。
いずれの試料でも、放射性プルトニウムは検出されませんでした(検出限界は最大で0.002ベクレル/kg)。
安全な農林水産物を生産するための現場の取組を知る
営農再開に向けて、生産現場が放射性物質の低減対策等を行う際に参考となる研究・技術開発が行われています。また、復興に向けて生産現場は懸命に取組を進めています。ほんの一部ですが、「岩手県、宮城県、福島県からの復興便り」のページで事例をご紹介しています。
また、「東日本大震災からの農林水産業の復興支援のための取組」では、最近の復旧状況等を踏まえ更新しておりますので、ぜひご覧ください。
生産現場等での取組
基準値を超えない食品のみを出荷するよう、放射性物質の農畜産物への移行・吸収を抑える対策、肥料や土壌改良資材・培土の管理などが行われています。こうした対策によって、農畜産物に含まれる放射性物質は年々減少しています。
しかし、低減対策が容易でない野生きのこ類や山菜、野生鳥獣には基準値を超えたものがあり、引き続き注意が必要です。
水産物は、海水魚及び淡水魚の性質や棲息場所を考慮したモニタリング調査が行われています。魚種によって放射性物質への影響は異なります。基準値(100ベクレル/kg)を超えた魚介類が見つかれば、出荷自粛又は出荷制限等の措置がなされます。
生産現場等での取組および検査結果について詳しく知りたい方は、説明資料「農林水産現場における対応」(外部リンク)をご覧ください。
食品中の放射性物質対策に関する意見交換会・説明会
食品中の放射性物質による健康影響、国や地方自治体が実施する検査の方法、生産現場での取組などについて、消費者の方をはじめとする関係者の方への理解を深めていただくことを目的として、関係省庁の担当者等からの説明、参加者との意見交換等を実施しています。
コミュニケーション資料
食品と放射能Q&A(消費者庁)
消費者庁は、放射線の基礎から、食品中の放射性物質の基準値や検査結果についてまとめた冊子「食品と放射能Q&A」を作成しています。また、理解のポイントを整理しハンディタイプにまとめた「食品と放射能Q&Aリーフレット」も併せてご利用ください。
|
食品と放射能Q&A |
食品と放射能Q&A ミニ |
|
|
冊子(第19版) |
|
冊子(第11版) |
|
【詳しく知りたい方は】 食品中の放射性物質に関する広報の実施について[外部リンク:消費者庁] |
||
食べものと放射性物質のはなし
「ほんとうに大丈夫なの?」というご心配におこたえするため、「食べものと放射性物質のはなし」を作りました(消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省)。
|
ポスター |
||
|
リーフレット |
||
|
その1 |
その2 |
その3 |
被災地応援の取組
被災地やその周辺地域の農林水産物や加工食品を積極的に利用することで、支援の輪が広がっていきます。キャンペーンやフェア情報をご紹介していますので、ぜひご活用ください。みなさまのご参加、ご協力をお願いいたします。
|
食べて応援しよう! |
|
|
被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再生を通じた被災地の復興を応援するための取組を紹介しています。 |
外部リンク集
放射線や除染をはじめとした情報を掲載している、関係府省庁や自治体のサイトをまとめました。
関係省庁
関連都県
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当者:情報発信企画・評価班
ダイヤルイン:03-3502-5719(内線4474)