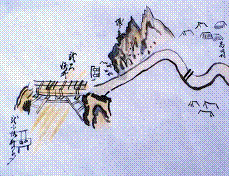江戸時代の技術を現代に伝えた大畑才蔵
農家に生まれ役人に
和歌山県橋本市
1642年(寛永19年)~1720年(享保5年)
|
|
紀の川右岸一帯の水田は、水を雨水や渓流水に頼っていたため、かつて幾度となく水争いが繰り返されました。そのため農民たちは、雨の多い奈良県大台ケ原をみなもととする紀の川をながめ、「この豊かな紀の川の水を、自分の水田に引くことができたら」と願っていました。
大畑才蔵は、1642年伊都郡学文路村:現橋本市)の農家に生まれ、算数の手本と言われる当時の学問を勉強した結果、紀州藩の下級役人にばってきされました。そして用排水路の整備を行うことで米の増収ができると考え、工事にとりかかったのです。
水路は長いため、端から順に作業するより、いくつかの区間にわけてたくさんの人で作業を行ったほうが、工事が早く終わります。ところが高さがうまくあわないと、水路がつながらず水が流れません。当時は高さをはかる測量器がありません。才蔵は算数がよくできたため、「水盛台」という測量器を作ってこれを解決しました。また、水路を作るのに必要な土の量や、工事を行う人の数を細かく計算しました。このやり方は、当時は画期的なことでした。
このようなやり方で、地形が複雑で難しい工事を他にも完成させました。才蔵が作った24キロメートルある「藤崎井用水路」や、完成はできなかったものの30キロメートルある「小田井用水路」は現在でも使われています。
参考情報
- 参考文献:水土を拓いた人びと (社)農業土木学会編
- 主たる施設:龍之渡井 約30メートルの水路橋
関連ホームページ
紀ノ川土地改良区連合ホームページ(外部リンク)
お問合せ先
農村振興局整備部設計課
代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338