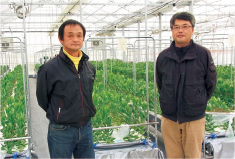特集1 東日本大震災からの復旧・復興 みんなの力で、未来(あした)へ(3)
花きの復旧・復興現場レポート
震災からの復興のために、先端技術を駆使した新しい農業技術に着目。
農家と研究者が協力して通年出荷できるトルコギキョウの水耕栽培にチャレンジ!
(独)農研機構花き研究所(茨城県つくば市)
| 太平洋に面した福島県浜通り地区は県内でも温暖な地域です。その気候を生かした花き栽培が盛んですが、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で、一部は避難エリアとなり、農家は甚大な被害を受けました。水稲の作付けや野菜出荷などが規制されたなか、震災前後で市場価格に大きな変化がなかったのが県内産の切り花です。 そこで農研機構と浜通り地区(いわき市・南相馬市・新地町)の農家が連携。農林水産省と復興庁が実施する、食料生産地域再生のための先端技術展開事業(「先端プロ」)のひとつとして、平成25年から、花き栽培を基盤とした地域復興に向けた実証研究を開始しました。 「研究は復興支援の一環ですが、震災前の状況に戻すのではなく、新しい技術を導入することで、より生産性の高い花き栽培を目指すのが目的です」と語るのは農研機構花き研究所の福田直子さん。 「戻す」のではなく、さらなる飛躍への挑戦として、「大規模水耕栽培によるトルコギキョウの高品質周年生産システムの構築」「夏秋トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせによる効率的周年栽培技術の確立」という実証研究を行っています。 トルコギキョウの高品質周年生産の実証研究では、育苗期間の短縮のほか、複合環境制御と生産性の高いNFT水耕栽培を組み合わせることで、年間9回の出荷を目指します。昨年11月には、このシステムによりいわき市で栽培したトルコギキョウが、初出荷されました。 「トルコギキョウの水耕栽培は国内初の取り組みです。従来の土耕栽培に比べ、花がひと回り以上大きく育つことも実験で明らかになりました」と福田さん。市場評価も高く、農家からの期待も高まっています。 既存の農業施設を活用しながら収益アップ!
既存の農業施設を活用しながら収益を上げることを目指す実証研究も行っています。たとえば夏秋トルコギキョウと低温開花性花きの組み合わせの研究では、トルコギキョウの出荷後、葉菜類ではなくカンパニュラを栽培。電照をかけてカンパニュラの開花期を2月に早めることで、冬でも出荷できるようにしました。実際、カンパニュラに切り替えた農家は、葉菜類よりも収益アップを期待しています。このほか、「露地電照栽培を核とした夏秋小ギクの効率生産システムの実証」もJAそうま新地花卉部会と協力して行っています。 「技術の向上や収益性を重視することはもちろんですが、この実証研究の成果がこれからの花き農業の希望、夢につながってほしい。夢を語ることもだいじですから」と福田さんは話します。 |
  土耕栽培よりも、花がひと回り大きく育つことも市場から高評価 |
コラボの力 その1
緩やかに傾斜した栽培床の底に、培養液を少量ずつ流す水耕栽培で、流れ落ちた培養液はタンクに戻り、ポンプによって再び循環させる。一般的な「DFT水耕栽培」(根全体を培養液に湛水させる方法)と異なり、「NFT水耕栽培」は根の空気に触れている部分から酸素を取り込むことができ、生育促進効果が高くなる。水耕栽培のハウスは3棟設置。1棟につき年3回、3棟で年9回作付けすることで周年出荷が可能に。大規模水耕栽培によるトルコギキョウの高品質周年生産システムの構築
|
 南相馬市で実証研究に取り組む、農家の堀内知子さん  既存の無加温ハウスを使用。葉菜類をカンパニュラに切り替えることで、農業粗収益の増加が期待できる |
コラボの力 その2
トルコギキョウとカンパニュラの組み合わせによる効率的周年栽培技術の確立 組み合わせによる効率的周年栽培
6~11月はトルコギキョウを、冬から春にかけては低温開花性の花きのカンパニュラを生産することで周年出荷体制を構築。カンパニュラの開花は通常4~5月だが、電照をかけることで開花を2月に早めている。労働時間当たりの所得を向上  |
  電照栽培品種として選抜された「精ちぐさ」 |
コラボの力 その3
露地の電照栽培(※)で開花調整できる品種を選抜。電照をかけて栽培し、8月の盆や9月の彼岸時期などの高需要期に同じ品種の継続出荷が可能に。これまでの多品種ではなく1品種で計画出荷するため、選別作業の軽減にもなる露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産 ※花きやイチゴなどの収穫期を、電照を利用して人工的に変動させる栽培方法
|