特集1 今、農学部が熱い!(3)
農学部NEWS 農林水産業の明日へ 知の最先端が挑む!
|
農林水産業の明日を拓く最先端の研究。その一翼を担う農学部のトピックスを、日本全国からお届けします。
|
偶然が生んだ夢のリンゴ
果肉まで赤いリンゴ「紅の夢」の奇跡
それは果樹の神様の贈り物だった!?

【弘前大学農学生命科学部】
「紅の夢」は、「赤肉の品種は渋くて生食に向かない」という問題を初めて克服し、平成22年に品種登録された赤肉のリンゴです。
塩崎雄之輔名誉教授が「紅の夢」の交配に成功したのは平成6年。しかし、過去に赤い果肉が生まれたことのない「紅玉」と「スターキングデリシャス」の交配だったため、理由が分からず研究スタッフを悩ませました。その後、DNAによる親品種の推定で分かったのは、藤崎農場に輸入されてきた"品種名のない樹"から受粉したという事実でした。果樹の世界では「一生懸命育てている人には神様からの贈り物がある」と言われます。長年の地道な交配研究に報いるように生まれた「紅の夢」。塩崎名誉教授の想いを継ぐ松本和浩助教の下、地元企業とも連携して用途拡大にも取り組んでいます。
果肉まで赤いリンゴ「紅の夢」の奇跡
それは果樹の神様の贈り物だった!?

|
弘前大学農学生命科学部の藤崎農場は、日本発祥で、今や世界的なリンゴ品種「ふじ」が生まれた歴史的な場所です。その場所で昭和56年からスタートした新品種開発の成果「紅の夢」は、神様の贈り物でした。
|
「紅の夢」は、「赤肉の品種は渋くて生食に向かない」という問題を初めて克服し、平成22年に品種登録された赤肉のリンゴです。
塩崎雄之輔名誉教授が「紅の夢」の交配に成功したのは平成6年。しかし、過去に赤い果肉が生まれたことのない「紅玉」と「スターキングデリシャス」の交配だったため、理由が分からず研究スタッフを悩ませました。その後、DNAによる親品種の推定で分かったのは、藤崎農場に輸入されてきた"品種名のない樹"から受粉したという事実でした。果樹の世界では「一生懸命育てている人には神様からの贈り物がある」と言われます。長年の地道な交配研究に報いるように生まれた「紅の夢」。塩崎名誉教授の想いを継ぐ松本和浩助教の下、地元企業とも連携して用途拡大にも取り組んでいます。
"自然の草"で牛を育てる
国内の草資源を有効活用した新しい牛肉生産

【九州大学農学部】
農学部附属高原実習場で飼育されている「Q Beef(キュウビーフ)」は平成24年3月に九州大学公式ビーフに認証されたブランドビーフ。後藤貴文准教授が中心となって研究しているのは、穀物飼料を与えず、自然の草だけを食べさせる「放牧飼養」の牛肉生産システムです。
高原実習場では「代謝インプリンティング(刷込み)」理論を牛に応用。これによって、脂肪蓄積能力が高く、草食でも適度にサシの入った牛を生産しています。また、放牧飼養することで、耕作放棄地の有効活用も期待されます。
国内の草資源を有効活用した新しい牛肉生産

【九州大学農学部】
農学部附属高原実習場で飼育されている「Q Beef(キュウビーフ)」は平成24年3月に九州大学公式ビーフに認証されたブランドビーフ。後藤貴文准教授が中心となって研究しているのは、穀物飼料を与えず、自然の草だけを食べさせる「放牧飼養」の牛肉生産システムです。
高原実習場では「代謝インプリンティング(刷込み)」理論を牛に応用。これによって、脂肪蓄積能力が高く、草食でも適度にサシの入った牛を生産しています。また、放牧飼養することで、耕作放棄地の有効活用も期待されます。
地球環境問題の解決に挑む!
【東京大学大学院農学生命科学研究科】
生物・環境工学専攻が掲げる研究テーマは"「農」から「環境」を科学する"。大政(おおまさ)謙次教授が率いる研究室は、その象徴的な存在です。
遺伝子や細胞レベルのミクロな情報から、地域・地球環境レベルのマクロな情報までを、画像情報を中心に、情報工学の最先端の手法を駆使してセンシング(観測)。得られた情報を基に、生物と環境との関係を解明・モデリングすることで、最先端農業や地球環境問題への貢献を目指しています。
中でも、人工衛星や飛行機、ドローンなどによるリモートセンシング(遠隔測定)技術を用いた農業・環境分野への利用に、大きな関心と期待が寄せられています。
【東京大学大学院農学生命科学研究科】
生物・環境工学専攻が掲げる研究テーマは"「農」から「環境」を科学する"。大政(おおまさ)謙次教授が率いる研究室は、その象徴的な存在です。
遺伝子や細胞レベルのミクロな情報から、地域・地球環境レベルのマクロな情報までを、画像情報を中心に、情報工学の最先端の手法を駆使してセンシング(観測)。得られた情報を基に、生物と環境との関係を解明・モデリングすることで、最先端農業や地球環境問題への貢献を目指しています。
中でも、人工衛星や飛行機、ドローンなどによるリモートセンシング(遠隔測定)技術を用いた農業・環境分野への利用に、大きな関心と期待が寄せられています。
~今日のことば~
「希少糖(きしょうとう)」
脱!肥満・糖尿病
【香川大学農学部】
肥満や糖尿病の予防・治療に変革をもたらす可能性を秘めているとして、今、世界の注目を集めている「希少糖」。その希少糖の世界唯一・最先端の研究組織が「国際希少糖研究教育機構」です。何森健(いずもり・けん)客員教授が、1990年代に生み出した「イズモリング」という概念が、希少糖の量産化への道筋をつけ、20兆円規模と言われる世界市場を視野に、産学官連携の動きが加速しています。
「希少糖(きしょうとう)」
脱!肥満・糖尿病
【香川大学農学部】
肥満や糖尿病の予防・治療に変革をもたらす可能性を秘めているとして、今、世界の注目を集めている「希少糖」。その希少糖の世界唯一・最先端の研究組織が「国際希少糖研究教育機構」です。何森健(いずもり・けん)客員教授が、1990年代に生み出した「イズモリング」という概念が、希少糖の量産化への道筋をつけ、20兆円規模と言われる世界市場を視野に、産学官連携の動きが加速しています。
[森林資源の活用]
欧州が先鞭をつけた新建材に次代の林業の可能性を探る
地震に強く居住性の高いエコ素材 普及拡大に向けた実証研究続く
【静岡大学農学部】
欧州では20年ほど前からCLT(Cross Laminated Timber)という木材由来の建材の開発・実用化が進んでいます。CLTは、板を繊維方向が直交するように積み重ねて接着した厚型パネルで、高い断熱性・耐火性・耐震性を持つ構造材です。
近年、CLTの利用は急速に伸びており、欧州各国で中高層の集合住宅などで使われているほか、カナダやアメリカでも規格作りが行われています。日本では、平成25年に「直交集成板」という名称で日本農林規格(JAS)が制定され、木材があまり使われてこなかった中高層建築物への活用が期待されています。
住環境構造学研究室の安村基(もとい)教授が取り組んでいるのは、CLTの耐震性能評価と設計法の検討。イタリア国立樹木・木材研究所(CNR-IVALSA)と協力して行った7階建てCLT建築の実大振動台実験等の経験を基に、期待を現実に変える試みが続けられています。
欧州が先鞭をつけた新建材に次代の林業の可能性を探る
地震に強く居住性の高いエコ素材 普及拡大に向けた実証研究続く
 イタリアとの共同研究として実施された7階建てCLT 建築の実大実験 |
 建築に使われるCLTパネル |
【静岡大学農学部】
欧州では20年ほど前からCLT(Cross Laminated Timber)という木材由来の建材の開発・実用化が進んでいます。CLTは、板を繊維方向が直交するように積み重ねて接着した厚型パネルで、高い断熱性・耐火性・耐震性を持つ構造材です。
近年、CLTの利用は急速に伸びており、欧州各国で中高層の集合住宅などで使われているほか、カナダやアメリカでも規格作りが行われています。日本では、平成25年に「直交集成板」という名称で日本農林規格(JAS)が制定され、木材があまり使われてこなかった中高層建築物への活用が期待されています。
住環境構造学研究室の安村基(もとい)教授が取り組んでいるのは、CLTの耐震性能評価と設計法の検討。イタリア国立樹木・木材研究所(CNR-IVALSA)と協力して行った7階建てCLT建築の実大振動台実験等の経験を基に、期待を現実に変える試みが続けられています。
食嗜好から農学の発展を目指す
【龍谷大学農学部】
食品栄養学科の伏木亨(ふしき・とおる)教授は「おいしさ」「食嗜好」研究の第一人者で、数多くの著作を発表しています。
前職の京都大学時代には、脂肪酸の基礎的な研究を基に、油脂の代替となる食品添加物を開発。おいしさを保ちつつカロリーを抑えたアイスクリームをはじめ、産学連携でさまざまな食品への活用を目指しています。
伏木教授は和食の無形文化遺産登録にも貢献。龍谷大学では「おいしさの視点から食を捉える新しい農学の発展」をキーワードに、和食をさまざまな角度から研究し、学内外から注目を集めています。
【龍谷大学農学部】
食品栄養学科の伏木亨(ふしき・とおる)教授は「おいしさ」「食嗜好」研究の第一人者で、数多くの著作を発表しています。
前職の京都大学時代には、脂肪酸の基礎的な研究を基に、油脂の代替となる食品添加物を開発。おいしさを保ちつつカロリーを抑えたアイスクリームをはじめ、産学連携でさまざまな食品への活用を目指しています。
伏木教授は和食の無形文化遺産登録にも貢献。龍谷大学では「おいしさの視点から食を捉える新しい農学の発展」をキーワードに、和食をさまざまな角度から研究し、学内外から注目を集めています。
肥料原料を確保し収益力向上を実現
【愛媛大学農学部】
肥料の原料となるリン鉱石。日本ではその全量を輸入に頼っており、安定的な確保が課題となっています。
治多(はるた)伸介教授が参画し、環境省のバックアップのもと、平成24年度から産学官連携で実用化を目指しているのが、し尿汚泥等の焼却灰からリンを回収する技術。これまで、コスト等の問題から未使用のまま廃棄されていたし尿や下水の汚泥などのバイオマス系の焼却灰を、有効活用しようという取り組みです。
平成26年度に稼働させた実験プラントでは、回収率約80パーセントを実現。輸入依存からの脱却を可能にし、農業の収益力向上にもつながると期待されています。
【愛媛大学農学部】
肥料の原料となるリン鉱石。日本ではその全量を輸入に頼っており、安定的な確保が課題となっています。
治多(はるた)伸介教授が参画し、環境省のバックアップのもと、平成24年度から産学官連携で実用化を目指しているのが、し尿汚泥等の焼却灰からリンを回収する技術。これまで、コスト等の問題から未使用のまま廃棄されていたし尿や下水の汚泥などのバイオマス系の焼却灰を、有効活用しようという取り組みです。
平成26年度に稼働させた実験プラントでは、回収率約80パーセントを実現。輸入依存からの脱却を可能にし、農業の収益力向上にもつながると期待されています。
ミツバチ研究の総本山
奥深いミツバチの生態解明に挑む

【玉川大学ミツバチ科学研究センター】
ハチミツの生産に限らず、農作物の受粉などで大きな役割を担っているミツバチ。玉川大学ミツバチ科学研究センターは、いまだ謎の多いミツバチの生態解明に挑む、日本唯一の総合研究機関として世界的に知られています。
その歴史は古く、昭和25年から同大農学部で続けられてきた研究を引き継ぐ形で設立。発行する学術誌『ミツバチ科学』(昭和55年創刊)は、理系のみならず、文系の知見までも網羅し、世界中の研究機関が購読しています。
養蜂技術から花粉媒介者としての利用法、「女王蜂」「働き蜂」などの階層があるミツバチ社会のユニークな構造、短い生涯に多くの仕事をこなす働き蜂の生態など、研究されているテーマは基礎から応用まで幅広く、その成果が大いに期待されています。
奥深いミツバチの生態解明に挑む

【玉川大学ミツバチ科学研究センター】
ハチミツの生産に限らず、農作物の受粉などで大きな役割を担っているミツバチ。玉川大学ミツバチ科学研究センターは、いまだ謎の多いミツバチの生態解明に挑む、日本唯一の総合研究機関として世界的に知られています。
その歴史は古く、昭和25年から同大農学部で続けられてきた研究を引き継ぐ形で設立。発行する学術誌『ミツバチ科学』(昭和55年創刊)は、理系のみならず、文系の知見までも網羅し、世界中の研究機関が購読しています。
養蜂技術から花粉媒介者としての利用法、「女王蜂」「働き蜂」などの階層があるミツバチ社会のユニークな構造、短い生涯に多くの仕事をこなす働き蜂の生態など、研究されているテーマは基礎から応用まで幅広く、その成果が大いに期待されています。
"おいしい魚"で養殖魚のイメージアップ

【高知大学農学部】
水族栄養学研究室の深田陽久(はるひさ)准教授が鹿児島県東町漁協と開発・製品化した「柚子鰤王(ぶりおう)」(写真)は「柑橘系養殖魚(フルーツ魚)」の元祖です。深田准教授は「養殖魚の評価を上げるおいしい魚をつくりたい」と考え、柑橘類の抗酸化作用に着目。エサに柚子の皮と果汁を配合し、世界初の"香る"養殖魚として注目を集めました。広島県阿多田島漁協と取り組む「あたたハマチto(と)レモン」など、次なるブランド魚の開発に向けた研究が続いています。

【高知大学農学部】
水族栄養学研究室の深田陽久(はるひさ)准教授が鹿児島県東町漁協と開発・製品化した「柚子鰤王(ぶりおう)」(写真)は「柑橘系養殖魚(フルーツ魚)」の元祖です。深田准教授は「養殖魚の評価を上げるおいしい魚をつくりたい」と考え、柑橘類の抗酸化作用に着目。エサに柚子の皮と果汁を配合し、世界初の"香る"養殖魚として注目を集めました。広島県阿多田島漁協と取り組む「あたたハマチto(と)レモン」など、次なるブランド魚の開発に向けた研究が続いています。
害虫から身を守る植物の不思議な戦略
【京都大学生態学研究センター】
アオムシに食べられたキャベツは、自らの身を守るため、アオムシの天敵である寄生バチを呼び寄せる信号を送っている――。この「植物」「植食性昆虫」「捕食性天敵」の間の不思議なメカニズムは、「生物間相互作用-情報ネットワーク」と呼ばれるもので、高林純示教授がその解明に取り組んでいます。
解明が進めば、農薬に頼らずに害虫の天敵を利用して植物を育てる「生物的防除技術」への活用が可能に。農作物への応用も視野に入れ、研究が進められています。
【京都大学生態学研究センター】
アオムシに食べられたキャベツは、自らの身を守るため、アオムシの天敵である寄生バチを呼び寄せる信号を送っている――。この「植物」「植食性昆虫」「捕食性天敵」の間の不思議なメカニズムは、「生物間相互作用-情報ネットワーク」と呼ばれるもので、高林純示教授がその解明に取り組んでいます。
解明が進めば、農薬に頼らずに害虫の天敵を利用して植物を育てる「生物的防除技術」への活用が可能に。農作物への応用も視野に入れ、研究が進められています。

農学部と私
農学系学部を卒業し、さまざまなジャンルで活躍中の方々に、大学時代の思い出を伺いました。
 |
桝(ます) 太一さん (東京大学大学院農学生命科学研究科修了) 学生時代はアサリの研究に没頭。アサリ採集のため、大揺れの漁船で網を引いたり、真冬の夜に潮干狩りもしましたね。研究には「心技体」どれも大切だと痛感。「学問は、机上ではなく現場で使う術を知って初めて意味を成す」ということを、農林水産の現場で学びました。 日本テレビ・アナウンサー。総合司会を務める「ZIP!」をはじめ多くの番組に出演し、オリコン「好きな男性アナウンサーランキング」では昨年4連覇を達成。 |
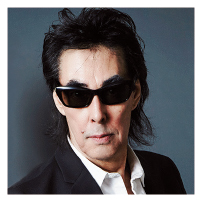 |
鮎川 誠さん (九州大学農学部卒) バンドをとことんやりたくて、浪人して学費の安い国立大学へ入学。ギター漬けの学生時代でした。当時、九州大学では「ファントム墜落事故」に抗議するロックアウトも…。結局、6年かかって卒業しましたが、農政経済学科のロック好きな教授が卒論を指導してくれて、感謝しています。 1970年からサンハウスのリード・ギタリスト/コンポーザーとして活動。78年よりシーナ&ロケッツのギタリストとして活動を続ける。現在、47都道府県ツアーを開催中。 |
 |
斉藤アリスさん (明治大学農学部卒) 映画『もののけ姫』に影響を受け、環境保全に携わる仕事に就きたいと思うようになり、農学部へ。私がいた食料環境政策学科は実習が多く、長野県のりんご農園や中国・青島の牛舎などで働きました。実習先で伺った「おなかではなく命を満たす農業を」という農家の方の言葉が忘れられません。 在学中よりファッションモデルとして活躍。卒業後、ロンドンの美術大学院にてファッションジャーナリズムを専攻(修士号取得)、雑誌への寄稿も。 http://ameblo.jp/10toma10/ |
 |
コロコロチキチキペッパーズ ナダルさん (近畿大学農学部卒) 京都の南山城村出身で、大自然の中で育ちました。魚の生態や水辺の環境に興味があり、水産学科に進学。大学では生物多様性の重要性を学び、自然が人間にとっていかに大切かを知りました。いつか、身近な所に「自然」を作る仕事などにも挑戦してみたいです。 相方の西野創人さん(写真右)と2012年にコンビを結成。LINEスタンプ『しゃべるコロコロチキチキペッパーズ』が人気。第8回沖縄国際映画祭(4月21日~24日)にも登場。 |

「農学部ってどんな場所?」「どんな研究をしているの?」
農学部の先生・学生たちのリアルな姿が垣間見られる、オススメ本をご紹介します。
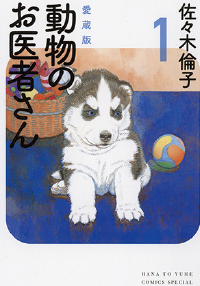 |
『動物のお医者さん』 佐々木倫子 (白泉社) 平成6年の完結後も愛され続ける傑作シリーズ。獣医学部のキャンパスを舞台に、獣医を目指す主人公・公輝とかわいらしさあふれる動物たちの交流を描いた永遠の名作。 |
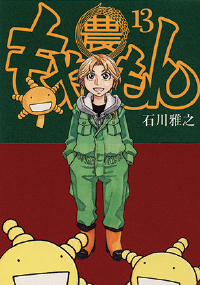 |
『もやしもん(全13巻)』 石川雅之 (講談社) ©石川雅之/講談社 肉眼で菌を見ることができるという主人公をめぐる"農大青春発酵菌漫画"。楽しみながら「菌」や「発酵」などについても学ぶことができる作品。アニメ化、ドラマ化もされている。 |
 |
『農業がわかると、社会のしくみが見えてくる』 生源寺眞一 (家の光協会) 副題の「高校生からの食と農の経済学入門」という言葉どおり、農業を取り巻くさまざまなテーマをやさしく読み解く一冊。 「なぜ日本に農業が必要なのか」という素朴な疑問に、農業経済学の権威が授業形式で答えながら、農業や食をめぐる課題と背景を丁寧に解説した良書。 |
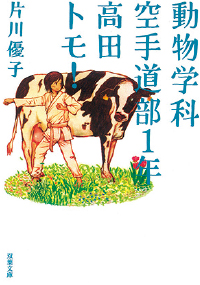 |
『動物学科空手道部1年高田トモ!』 片川優子 (双葉文庫) 著者が麻布大学獣医学部在学中に発表したシリーズ1作目(全3作)。動物学科に入学した主人公が、子牛の世話や空手道部の練習に奮闘する姿をさわやかに描く。 |
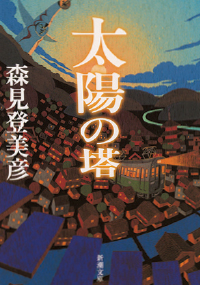 |
『太陽の塔』 森見登美彦 (新潮文庫) 京都大学大学院農学研究科修士課程修了の著者が、在学中に発表したデビュー作。京都の街を舞台に、京大農学部に籍を置く主人公の日常を描く。日本ファンタジーノベル大賞受賞作品。 |
構成/武藤 誠
読者アンケートはこちら




