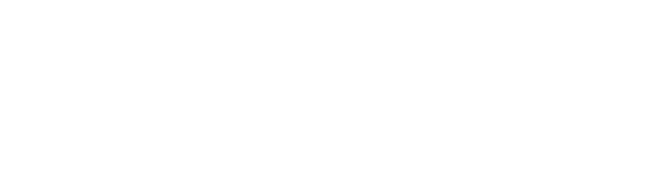美味しさはもちろん、その品質の高さから海外でも高い評価を得ている日本産の農林水産物。輸出に取り組む日本各地の産地では、さまざまな戦略や工夫のもとに、輸出先のニーズにあった産品の輸出を目指しています。今回は、水産物と米の輸出拡大に向けた産地の取り組みに迫ります。
高品質な日本の魚を世界へ
鮮度にこだわった一気通貫型輸出モデル

養殖業が盛んな愛媛県宇和島市に拠点を構えるイヨスイ (株)では、約20もの国や地域へ魚を輸出し、輸出総額は40億円を超えています。同社の最大の強みは、生産から加工、流通、海外販売までの一連の流れを全て自社で行う「一気通貫型」の輸出モデル。産地から自社通関で輸出を行うことで、高鮮度な水産物の迅速な輸出に成功しました。さらに、輸出先のニーズを的確に把握し戦略的な輸出を行うことで、着実に販路を拡大しています。輸出に向けた同社の取り組みに迫ります。
今回教えてくれたのは・・・

イヨスイ(株)
代表取締役
荻原 達也 さん
魚の養殖から加工、流通、そして販路開拓までを自社で行い、「魚の誕生から食卓まで」を担う水産の総合商社であるイヨスイ(株)。代表取締役の荻原さんは、サラリーマン時代に培った「何事にも挑戦する」という学びを元に、国内だけでなく海外への販路開拓も積極的に行う。「海を通じて、世界の人々を幸せに」という企業理念を追求し海への環境配慮はもとより、生産者や消費者視点のサステナブルな事業活動を実施している。
漁業者向けに海外から種苗を輸入していたこともあり、海外動向にはもともと精通していたという同社。日本は“天然”にこだわりがある上、国内市場も縮小傾向といった状況の中、輸出へ活路を見出したそうです。「できないことは自社でやってみる、といった姿勢を続けてきたのが成功の秘訣といえると思います。例えば活魚は鮮度が命ですが、税関の手続きに時間がかかり理想の状態での輸出ができませんでした。それなら自社でやろうと思い、通関業を始めました。」と荻原さんは語ります。
一気通貫型輸出モデルとは?
同社の特徴である、一気通貫型の輸出モデル。その一連の流れを見ていきましょう。
1. 生産
同社では、契約した養殖業者360戸と密に連携し、東アジアには活魚を中心に、また、北米や東南アジア、EUにむけては冷凍加工品を中心に輸出を行っています。活魚を輸出している東アジアに向けては、高品質な魚を鮮度を保ったまま輸出することが望まれます。一方、アメリカにおいては日本では流通しないような、規格が大きくて脂のりがいいものが好まれます。このように、輸出先ごとのニーズを踏まえた魚の生産を行っています。


左上:養殖マダイの出荷風景。 右下:養殖されたブリ。
2. 加工
海外に水産物を輸出するためには、HACCPなど輸出先の国や地域が求める衛生基準を満たす必要があります。このため、同社では、活魚だけでなく、鮮魚や水産加工品についても、より幅広い国や地域に輸出できる体制を目指し、FDA HACCP、EU HACCP、CHINA HACCP、FSSC22000、ISO22000、CoC認証(流通・加工段階の水産エコラベル認証)を取得した自社の水産加工施設で加工を行っています。


左上:生簀に隣接した加工施設。 右下:加工中の様子。
3. 流通
鮮魚の輸出においては、自社の生け簀で畜養しておき、輸出の時間に合わせて締め、パッキングを行っています。さらに、自社通関で活魚運搬船、活魚運搬車、リーファーコンテナ、飛行機を活用し、直接輸出を行っています。こうした取り組みにより、高鮮度な水産物を迅速に輸出することができます。
また、一例として、中国向けの輸出においては、中国からの帰りには稚魚や中間魚を活魚運搬船で持ち帰るなどの工夫を行い、無駄のない輸送に向けた取り組みを行っています。


左上:活魚運搬船。 右下:活魚運搬車。
4. 現地での販売
同社では、インターネットを駆使しながら潜在顧客を探し、直接現地へ足を運ぶことで販路を開拓しています。海外顧客との活発なコミュニケーションのおかげで、どのような魚が市場で求められているのかといったニーズも把握しやすいというメリットもあるそうです。


左上:同社で養殖したブリを使用した寿司。 右下:海外へ出荷されるブリ(ハマチ)フィレ。
アジア向け輸出を目指して
~新魚種「タマクエ」の開発~
同社では、約10年にわたる研究の末、アジア向けの新魚種として、ハタ科最大級“タマカイ”と高級魚として知られる“クエ”の交雑により、“タマクエ”(商標登録済)を開発しました。アジアで人気の高いハタ類は成長率が悪いためコストがどうしても高くなってしまう、という課題から生まれた、同社自慢の新魚種で、今後海外市場でのさらなる差別化が期待されます。

アジア人がハタ類を好むことなどから開発された「タマカイ」と「クエ」とのハイブリッド新魚種「タマクエ」。クエのおいしさを引き継ぎながらも、成長が早いことが特徴。


左上:タマクエの養殖の様子。 右下:タマクエを使用した鍋。
現在では全体の3割が輸出での売上を占めるまでになったという同社。農林水産省が推進するGFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のサポートも活用しながらさらなる展開を目指しています。

同社は平成30年度輸出に取り組む優良事業者表彰で農林水産大臣賞を受賞。
「GFPのサポートの中でも、輸出物流の意見交換を行うコールドチェーン勉強会は、自社だけでは最良の方法が見出しにくい物流のノウハウを共有できる場所として重宝しています。特に東アジアへ輸出している活魚に関しては、輸送中も鮮度を保つことが何よりも大切です。GFPで得られる情報を参考にしながら、品質の高い魚をこれからも輸出していきたいと思います」と荻原さんは語ります。
写真提供:イヨスイ(株)
輸出をはじめたい
あなたをサポート!
GFPを通じた多彩な
コミュニティの場

これから輸出に取り組もうとする現場では、そもそもどうやって輸出をはじめたらよいのか、どのような支援策があるのかなど、輸出に関する情報が不足していることが多いのも現実です。また、輸出には、さまざまな手続きや規制が存在し、個人では継続的に成果を生み出すことが難しいことも。そこで、農林水産省が推進する「農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP)」では、輸出に取り組もうとする生産者、事業者の方々に向け、「GFPコミュニティサイト」を立ち上げ、登録した方を対象にさまざまなサポートを行っており、一丸となって輸出に取り組むコミュニティを構築しています。その取り組みの一部を紹介します。

「輸出の可能性」
診断してみませんか?

農林水産省や (独)日本貿易振興機構(JETRO:ジェトロ)などの輸出の専門家が、輸出に取り組むことを検討している現場に直接出向き、輸出の可能性を直接診断する、無料の「輸出診断」の取り組みを行っています。

自社で生産したブドウを使用した「大阪ならでは」のワインの生産を行うカタシモワインフード(株)(大阪府)の訪問診断の様子。

カラフルで彩り豊かな品種のにんじんやばれいしょの生産を行うAmbitiousFarm(株)(北海道)の訪問診断の様子。

久米島の良質な水を使用した伝統の琉球泡盛の醸造を行う米島酒造(株)(沖縄県)の訪問診断の様子。

エコファーマーの認定をうけた減農薬のりんごや、これを活用したシードルの生産を行う丘の上ファーム原農園(長野県)の訪問診断の様子。
生産者と輸出商社等が
「つながる」

GFPコミュニティサイトをとおして、生産者と輸出事業者が直接つながることができます。たとえば、生産者は、輸出を希望している産品について輸出商社に紹介したり、逆に輸出商社は、海外でのニーズも踏まえ、生産者に向けて「買いたい」商品をリクエストすることができます。
イベントやセミナーの開催
会員同士の交流や意見交換を目的として、さまざまなイベントやセミナー、商談会などを開催しています。コロナ禍においても、オンラインを活用しながらさまざまなイベントを継続しています。

南九州で開催されたGFP 物流セミナーの様子。

オンラインで開催されたGFP輸出産地セミナーの様子。
「輸出産地」をつくる

輸出相手国のニーズや規制に対応し、戦略的に輸出に取り組む「輸出産地」の形成に向けて、「輸出事業計画」の策定や、計画を実施するための体制づくりをサポートしています。
GFPの取り組み
GFPの取り組みについては、公式サイトやFacebookでも紹介しています。さらに詳しく知りたい方は、こちらからご覧ください。
GFP公式サイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/)
GFP公式Facebook(https://www.facebook.com/maff.gfp/)
高い品質を誇る
日本の米を海外へ

日本人の食には欠かせない“米”。しかし近年は、人口減少や食生活の多様化もあり、国内の消費は減少傾向にあります。そうした中で海外へ活路を見出す生産者も増えてきています。宮城県登米市のみやぎ登米農業協同組合では、輸出4年目となる2021年産では目標であった輸出量3000トンを達成し、輸出開始時の3倍以上に伸ばしています。同組合の取り組みに迫ります。
今回教えてくれたのは・・・

みやぎ登米農業協同組合
営農部 部長
伍十川 真治(いそかわ まさはる) さん
平成10年4月に宮城県登米郡内の8農協の合併により発足したみやぎ登米農業協同組合において、主に米穀業務を担当、平成21年にはブランド戦略班マネージャーとして、ブランド事業の立ち上げに携わる。以後、営農業務を中心に担当し、町域営農センター所長等を歴任し、令和3年4月より現職。


平成30年産輸出用米出発式の様子。
「国内の主食米の割合が減少し、作付面積を減らさなければいけない状況でした。飼料用米の生産も試みたのですが伸び悩んでいたところ、大手米卸業者からお声がけを頂いたのが輸出のきっかけです」と伍十川さんは語ります。
同組合が手がけるのは「環境保全米」と呼ばれる、農薬や化学肥料をできるだけ少なくして栽培した米。稲わらを敷料として牛を肥育し、牛の排せつ物と稲わらなどを原料とした堆肥を水田に還元する循環型農業を導入しています。

同組合が栽培する品種はひとめぼれを中心としています。ひとめぼれは、柔らかい食感と程よい粘りが特徴で、甘みと旨みのある味わいなのだそうです。「美味しさはもちろん、環境に配慮した生産が求められている今、それに先駆け2003年から手がけている環境保全米は現代のニーズに合っていると思います」と伍十川さんは語ります。
すでに海外販路を確立している大手米卸業者とタッグを組むことで、海外への販路拡大という点においては目立った困難はありませんでした。一方で、管内の生産者の方々の理解を得るため、コミュニケーションには力を入れたのだそうです。
「長年、国内向けの主食米を作り続けている生産者の方々は、これまでの米作りを尊重されているので、輸出米生産への切り替えを提案してもすぐには聞き入れてもらえませんでした。そこで、同じ作付面積で輸出米とそのほかの用途で流通させる米とを比較し、所得だけではなく、海外輸出へ参画することの将来的なメリットについて説明会などを通し、管内の生産者の方々の理解を得られるよう努めてきました。そのかいもあって、2021年には474名の生産者が取り組むまでになりました」と伍十川さんは語ります。

管内の生産者への輸出米に関する説明会を開催した時の様子。
ひとめぼれは、輸出先の高級レストランを中心に卸しており、価格が高くても食味が良いため現地で支持を得てきました。しかし、輸出先でのさらなる販路拡大に向けて、より低価格で安定した収量を期待できる品種を輸出することが求められました。そこで同組合が輸出用に新たに生産をはじめたのが、「つきあかり」。つきあかりは、ひとめぼれと比較して粒が大きく、同じ作付面積でも約10パーセント多く収穫できるそうです。「つきあかりは、早生系のためひとめぼれより1週間ほど早く収穫できます。生産者には収穫のタイミングが分かれることにより、作業の負担が分散されることもメリットと言えますね」と伍十川さんは語ります。

アメリカでの販促コーナーの様子。
今後の課題としては、短粒種を食べる国が限られていることによる加工の工夫の仕方や、輸送費の問題などが挙げられるといいます。そこで、同組合では、環境保全米の取り組みやその美味しさを海外の消費者にも認知していただくことで、さらなる輸出拡大を目指しています。「地域の生産者の方々や輸出事業者の方々とともに、一丸となって日本が世界に誇る米を世界に広めていきたいですね。」と伍十川さんは強く意気込みを語ります。
日本の「コメ」を
世界に拡げる
「コメ海外市場拡大戦略
プロジェクト」の取り組み
農林水産省では、コメおよびコメ加工品のさらなる輸出拡大に向けて、「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」を推進しています。同プロジェクトの参加事業者(輸出用米の安定的な生産に取り組む「戦略的輸出基地」及びコメ輸出拡大に向けて戦略的に取り組む「戦略的輸出事業者」)に対して、産地と輸出事業者のマッチングや、海外の動向のタイムリーな情報発信、さらには専門家による相談対応などのサポートを行っています。今回紹介したみやぎ登米農業協同組合は、同プロジェクトの「戦略的輸出基地」のひとつです。「戦略的輸出基地」、「戦略的輸出事業者」が一体となって、コメのさらなる輸出拡大を目指します。
コメ海外市場拡大プロジェクトについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらからご覧ください。
写真提供:みやぎ登米農業協同組合

この記事のPDF版はこちら
(PDF : 2,628KB)

-
日本産食材の魅力を世界へ
輸出の「いま」を知る
-
戦略的に海外のニーズに応える
輸出拡大を目指す産地の挑戦
-
オールジャパンで取り組む
日本産食材の海外への
プロモーション
-
「その土地ならでは」の
魅力を保護し、世界へ
地理的表示(GI)を知る
-
輸入規制の撤廃と技術開発で
日本産食材の輸出拡大を支える
編集後記
輸出額が1兆円を突破しました。これからもより多くの海外の方々に日本産食材の良さを知っていただけたら嬉しいですね。今週はイヨスイ(株)さんや、みやぎ登米農業協同組合さんの輸出に向けた取り組みをご紹介しましたが、来週以降もさまざまな産品における取り組みをご紹介していきますのでお楽しみに。(広報室SD)
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449