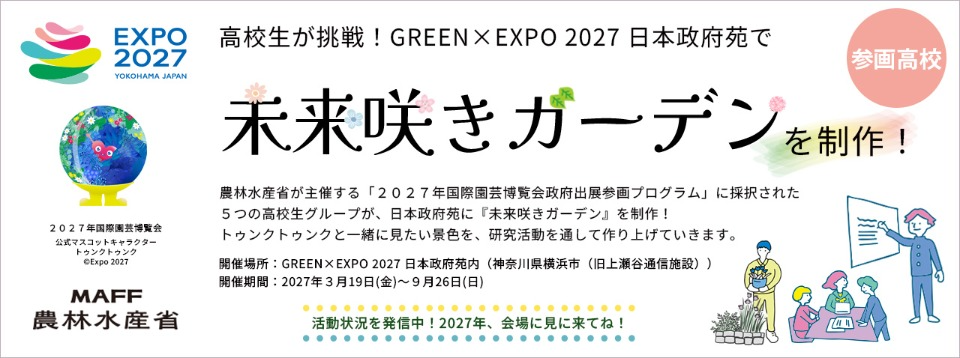活動レポート Vol.1:私たちのガーデン&研究のビジョンを紹介します(京都府立桂高等学校)
京都府立桂高等学校・植物クリエイト科園芸ビジネス科
私たちはこんな取り組みをします!
- ガーデンのテーマ:未来へつなぐ! ~古都の絶滅危惧種と環境を肥料で守る~
- 課題研究テーマ:絶滅危惧種の生息域外保全における循環肥料の利用研究
〇古くから京都に自生する植物が絶滅の危機に
京都府内に生息し、古くからの文献にも登場するフジバカマやキクタニギクは、昔から人々に愛され、無くてはならない植物です。このように古くから愛された植物であっても、絶滅危惧種として自然環境下では少なくなり、危機的な状況に陥っています。その背景は、自然環境の変化や宅地開発などが大きな原因となっています。
そんな京都の絶滅危惧種であるフジバカマやキクタニギクの生息域外保全活動を行っています。
〇植物栽培に欠かせないリン酸肥料も枯渇の危機!
植物栽培に欠かせない肥料原料が世界的に枯渇しており、特にリン酸肥料の原料となるリン鉱石は2060年に枯渇すると考えられています。リン酸は特に花や果実などの生育に必要であり、絶滅危惧種だけでなく生活を彩る花や、食を支える野菜等、農業生産物を育てられなくなってしまいます。私たちは、し尿処理施設から回収される、リンを多く含む肥料リン酸マグネシウムアンモニウム(MAP)を知り、循環資源として枯渇するリン鉱石の代替原料になることを知りました。
しかしMAPは知名度の低さや利用方法の解明が進んでいない事から、現在ミニトマトを使用した作型の調査を行っています。
そこで私たちはこの絶滅の危機に瀕している植物を、MAPを利用し生息域外保全が可能かどうか検証します。
 開花したキクタニギク |
 開花調整したフジバカマ |
 培養中のフジバカマ |
 MAPを用いたトマト栽培 |
ガーデンのデザイン
私たちのガーデンは、日本の美意識と自然観を軸とし、「和」をテーマに構成されています。古来より日本人の暮らしに根ざしてきたキクタニギクやフジバカマを取り入れることで、訪れた人々にどこか懐かしく、心やすらぐ風景を提供する空間を目指しました。 特に印象的な存在として、竹をガーデンの装飾要素に採用しています。竹は「松竹梅」のひとつとして縁起物に数えられると同時に、そのまっすぐな姿と節のある構造から「潔さ」「成長」「節度」といった精神性も内包しています。私たちのガーデンでは、その竹の表面に、フジバカマやキクタニギクをモチーフとしたデザインをあしらい、秋草の繊細な美しさと共に、視覚的なやわらかさと詩情を加えています。
また、水環境への配慮と自然との調和を意識し、庭の随所に「葉に雫が垂れる瞬間」を想起させる植栽演出を設けました。水を大量に使わずとも、視覚と想像で「潤い」を感じられる仕掛けです。こうした小さな表現の積み重ねにより、来訪者に“静けさの中の豊かさ”を届けます。
さらに、日本の原風景のひとつとして記憶に残る「棚田」のイメージも、ガーデン全体の地形構成や植栽の段差設計に反映しています。高低差のある花壇や、曲線を描く園路の構成は、かつての農村風景を思わせるとともに、自然と人が共に生きてきた歴史をさりげなく表現しています。
 9月上旬頃のイメージ |
 植物配置図 |
課題研究の内容と活用方針
組織培養によって大量増殖した苗を順化し、MAPと一般化成肥料を用いて対照実験を行い、追肥不要で花壇を植栽できるか検討します。
〇一般草花へのMAP散布による植物の生育調査
花壇へ利用する一般草花も同様に、MAPと一般化成肥料を用いて対照実験を行い、追肥不要で花壇を植栽できるか検討します。
絶滅危惧種の生息域外保全は公的機関のみでなく、地域団体などのボランティア団体が役割を担っています。そのため、栽培技術の理解不足や高齢化などにより、継続的に栽培ができない問題も起こっています。
MAPは遅効性肥料であり、長期に渡って肥効が続くため、本研究で栽培可能な事が実証できれば、生息域外保全において、難しい肥料計算などが不要になります。私たちの制作するガーデンでも、夏花壇の肥培管理をすることなく、灌水のみで管理ができるので、草花栽培の簡略化が期待できます。
今後の活動に向けた意気込み
私たちが研究しているフジバカマやキクタニギクは、現在守り繋ぐ人たちが少なくなってしまい、絶滅の危機に瀕しています。日本で昔から愛されてきた花が少なくなり、人々に忘れられようとしている中、私たちの研究によって世界中に知っていただき、再び愛されることを願っています。また、世界中の人たちが環境問題について考える機会ができればいいと考えています。私たちの「当たり前」が当たり前でなくなる日が近づいてきている中、MAPを使用することで農業が抱える問題を解決し、これからも持続可能な社会が実現させることができます。
これらの課題はいずれも知名度の低さにあります。国際園芸博覧会を通して「これなら自分もできそう!」と、一人でも多くの方に感じていただけるようなガーデンを制作していきます。


関連リンク
- 活動レポート Vol.2:アドバイザーミーティングを行いました(京都府立桂高等学校)
- 京都府立桂高等学校HP(トップページ)(外部リンク)
- 専門学科(植物クリエイト科・園芸ビジネス科)の取り組み紹介(外部リンク)
~未来咲きガーデンプロジェクト(2027年国際園芸博覧会政府出展参画プログラム)とは?~
2027年、横浜市で日本では37年ぶりとなる最上位クラスの国際園芸博覧会が開催されます。農林水産省と国土交通省は、開催国政府として「日本の自然観を再考し、未来へ進む」をテーマに魅力ある展示の準備を進めています。その一環として、農林水産省は、次世代の花き園芸、造園、農業の担い手となりうる高校生を対象に「花とみどりで創る景色」をテーマとしたガーデン制作と課題研究活動のプログラムを企画しました。
全国から応募のあった中から5グループが採択され、採択された高校生たちは、世界各国から集まる来場者に向けて、来場者に共感や発見を届けるガーデンづくりに仲間と共に挑戦します。活動の様子を随時発信していきますので、応援よろしくお願いします。
~日本政府苑について~
農林水産省と国土交通省は、「日本の自然観を再考し、未来へ進む」をコンセプトに出展します。
日本政府苑が位置するのは、横浜市内を流れる和泉川の流頭部。この貴重な自然環境を引き継いでいくため、流頭部の自然環境を読み解き、既存の樹木や在来の植物を活用し、屋外展示では美しい風景としての「令和日本の庭」をつくりあげます。また、屋内展示ではプラネタリーバウンダリーといった地球規模の課題について、“みどり”で解決する可能性を体感・共感し、来場者が考え、ひとりひとりが取り得る行動への一歩を提案します。
(※現在のイメージです)
お問合せ先
農産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室
代表:03-3502-8111(内線4827)
ダイヤルイン:03-6738-6162