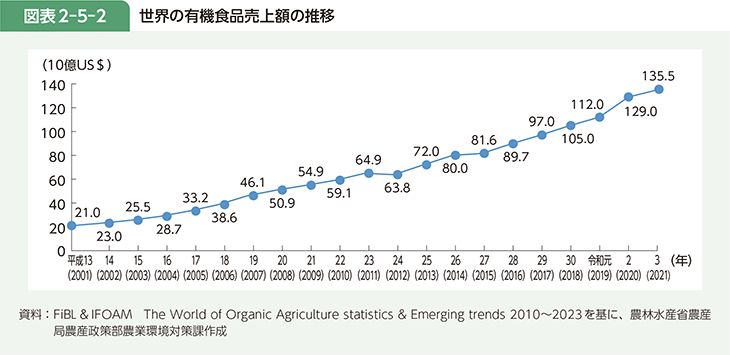2 環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育の推進
我が国の食料・農林水産業は、高品質、高付加価値な農林水産物、食品を消費者に提供するとともに、日本固有の食文化の魅力の源泉として国内外から高い評価を受けています。一方、生産者の減少・高齢化、地域コミュニティの衰退といった課題、国内外で重要性が増している地球環境問題やSDGsへの対応の必要性等を踏まえ、農林水産省では、持続可能な食料システムの構築に向け、令和3(2021)年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。
本戦略の実現に向けては、調達から生産、加工・流通、消費までの食料システムの各段階で課題の解決に向けて、関係者の理解促進と行動変容を進めていくことが鍵となります(図表2-5-1)。
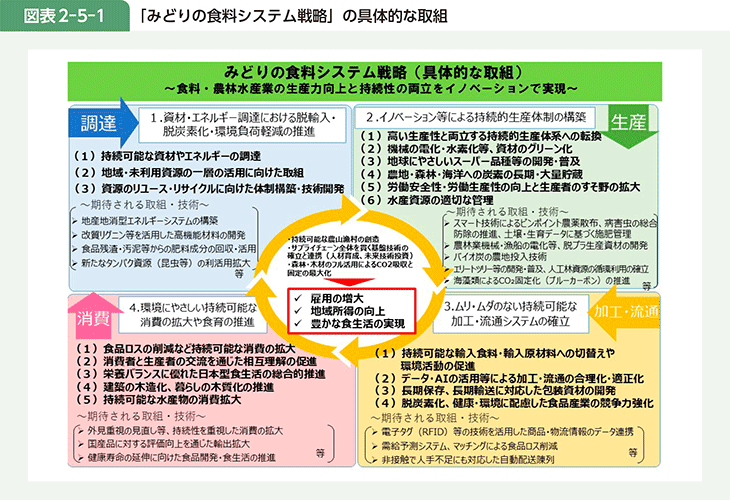
令和4(2022)年7月には、「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号)が施行されました。同法では、消費者の努力として、環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深め、環境への負荷の低減に資する農林水産物等を選択するよう努めなければならない旨を規定しているほか、環境負荷の低減に資する農林水産物等の消費を促進する観点から、食育の推進が位置付けられています。
このため、農産物の生産段階については、生産者の環境負荷低減の努力を「見える化」し、星の数で分かりやすくラベル表示して消費者に伝える取組を行っています。令和4(2022)年度に米、トマト、キュウリの3品目を対象に、化石燃料や化学肥料、化学農薬の低減、農地土壌へのバイオ炭の施用等による農業由来の温室効果ガス削減への貢献を星の数で表示する等級ラベルを付して実証販売を開始しました。さらに、令和5(2023)年度は、米、野菜類、果樹類、いも類等の23品目に対象品目を拡大するとともに、小売店舗を始め、外食、教育機関等の多様な場で実証販売を行いました。令和6(2024)年3月からは、米を対象に、化学肥料や化学農薬の低減、冬期湛水(たんすい)等の水田における取組に応じ、生物多様性保全への貢献を示す表示を追加し、新たなラベルデザインでガイドラインに則った本格運用を開始しています(コラム「環境負荷を低減する生産者の努力の「見える化」」参照)。
また、将来を担う若い世代による環境に配慮した取組を促すため、「みどりの食料システム戦略」に基づいた活動を実践する機会として、「みどり戦略学生チャレンジ(全国版)」を実施しています。
そのほか、消費分野では、見た目重視から持続可能性を重視した消費の拡大等、環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進等が期待されます。食育に関する取組としては、特に「環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進」として、「栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進」の中で、栄養バランスに優れた日本型食生活に関する食育、地産地消の推進や持続可能な地場産物や国産有機農産物等を学校給食に導入する取組の推進等を実施するとしています。
第4次基本計画では、「取り組むべき施策」として「環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育の推進」を掲げており、有機農業を始めとした持続可能な農業生産や持続可能な水産資源管理等、生物多様性と自然の物質循環を健全に維持し、自然資本を管理し、又は増大させる取組に関して、国民の理解と関心の増進のため普及啓発を行っています。
具体的には、学校給食での有機食品の利用等、有機農業を地域で支える取組事例の共有等を行うため、農林水産省は、「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク」の活動として、令和6(2024)年1月のオーガニックビレッジ全国集会において各地方公共団体の事例等を共有するセミナーを開催するなど、関係者の取組が進むよう連携の強化に取り組んでおり、セミナーでは、長野県松川町(まつかわまち)により、町内で有機農業に取り組む生産者により構成される「ゆうき給食とどけ隊」による学校給食における有機農産物の導入や、町内の小学生を対象とした栽培体験等の取組について発表されました(コラム「学校給食における有機農産物の利用についての取組」参照)。文部科学省では、学校給食で地場産物・有機農産物を活用する取組を支援する事業を実施し、学校給食への有機農産物の活用や、それを通じた環境負荷低減に係る理解を促す食育の充実に取り組んでいます。
世界の有機食品市場は令和3(2021)年時点で1,355億ドルであり、ここ10年で2倍以上に拡大しています(図表2-5-2)。日本の有機食品市場についても、直近5年間で約1.2倍に拡大しています(図表2-5-3)。更なる市場の拡大を目指して、国産有機農産物を取り扱う小売事業者や、飲食サービス事業者により構成される国産有機サポーターズ(令和5(2023)年度末時点で111社が参画)の拡大や、国産有機農産物等の消費者需要及び加工需要を喚起する取組への支援を行っています。
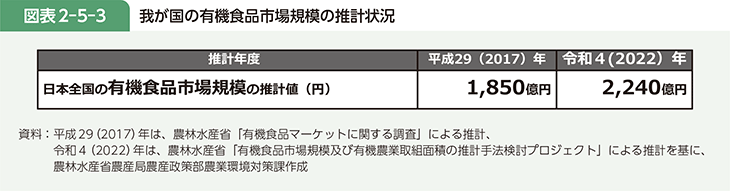
また、農林水産省、消費者庁、環境省が連携し、企業・団体、国が一体となって、食と農林水産業の持続可能な生産と消費を促進する「あふの環(わ)プロジェクト」を令和2(2020)年6月に立ち上げ、様々なイベントや、勉強会、交流会等を行っています。
具体的には、「食と農林水産業のサステナビリティ」について知ってもらうため、一斉に情報発信を行うサステナウィークを開催し、「あふの環(わ)プロジェクト」のメンバーが小売店舗等でのイベントを実施し、サステナブルな商品や、生産者の温室効果ガスの削減努力を分かりやすく表示した「見える化」農産物の販売、飲食店における「見える化」農産物を使用した料理の提供を行いました。
「あふの環(わ)プロジェクト」で開催した「サステナアワード2023」では、食や農林水産業に関わる地域・生産者・事業者のサステナブルな消費、生産等(環境との調和、脱炭素、生物多様性保全、資源循環等)の取組を分かりやすく紹介する動画を表彰しました。コープデリ生活協同組合連合会の「畜産の未来を育む 産直はなゆき農場有機牛」が農林水産大臣賞、株式会社樫村(かしむら)ふぁーむの「地域でつなぐサステナブル」が環境大臣賞、北アルプスオーガニックプロジェクトの「持続可能な循環型まちづくりへの挑戦」が消費者庁長官賞、アグリシステム株式会社の「ベーカリーが応援する環境再生型農業の取組」がAgVenture Lab(アグベンチャーラボ)賞を受賞しました。
世界的に健康志向や環境志向等、食に求める消費者の価値観が多様化していること等を背景に、生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルであるフードテック(*1)への関心が高まり、新たな食の可能性として注目されています。農林水産省では、令和2(2020)年10月、食品企業や、スタートアップ企業、研究機関、関係省庁等の関係者で構成する「フードテック官民協議会」を立ち上げ、同協議会には令和6(2024)年1月現在、約1,300人が入会しています。同協議会では、植物性タンパク質を用いた食品の普及推進等、専門的な議論を行う作業部会(ワーキングチーム)を設置し、協調領域の課題解決と新規食品への消費者理解の増進等の新市場開拓に向けた議論を行っています。
*1 我が国においては、大豆ミートや、健康・栄養に配慮した食品、人手不足に対応する調理ロボット、昆虫を活用した環境負荷の低減に資する飼料・肥料の生産等の分野で、スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を実施している。
コラム:学校給食における有機農産物の利用についての取組
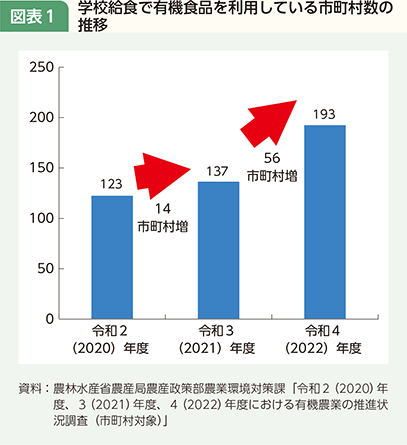
学校給食における有機農産物の活用は、有機農産物の安定的な消費先となることに加えて、子供たちや地域の方々に、環境に配慮した農業への理解を深めていただく、食育の観点からも有意義な取組と考えています。
全国で、学校給食に有機食品を利用している市町村数は、令和3(2021)年度末時点の137市町村から、令和4(2022)年度末時点で193市町村に増加しています。
各地の取組として、兵庫県豊岡(とよおか)市では、地元産の有機米である「コウノトリ育むお米」を学校給食に提供する取組を令和4(2022)年度から開始し、令和9(2027)年度までに米飯の全量を有機米にする計画としています。
また、長野県松川町では、地元の生産者の方たちが「ゆうき給食とどけ隊」を結成し、有機のニンジン、タマネギ等を学校給食に提供しています。
こうした取組と合わせて、町内小学生を対象とした有機農産物の栽培体験や水田での生き物調査、生産者との交流活動等の食育に資する取組が行われているところです。
農林水産省では、有機農業に取り組む先進的な市町村を「オーガニックビレッジ」として応援しており、学校給食への有機農産物の導入段階の支援等により、こうした地域の取組を後押ししています。
コラム:環境負荷を低減する生産者の努力の「見える化」
持続可能な食料システムの構築に向けて、調達、生産、加工・流通、消費それぞれの段階で、環境負荷低減の取組への関係者の理解促進と行動変容を進めていくことが重要です。
このため、農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、生産者の環境負荷低減の努力をわかりやすく表示し、消費者等の選択に資する「見える化」の取組を行っています。
令和4(2022)年度に米、トマト、キュウリの3品目を対象に、化石燃料や化学肥料、化学農薬の低減、農地土壌へのバイオ炭の施用等による農業由来の温室効果ガス削減への貢献を星の数で表示する等級ラベルを付して実証販売を開始し、令和5(2023)年度は対象品目を、米、野菜類、果樹類、いも類等の23品目に拡大するとともに、小売店舗を始め、外食、教育機関等の多様な場で実証販売を行いました(実績:全国累計773か所(令和6(2024)年2月29日時点))。
また、「見える化」に対する消費者の理解を促進するため、インフルエンサー向けのイベントや小中学生が多く来場する環境に関するイベントも活用し、分かりやすい広報・普及に取り組みました。
さらに、令和5(2023)年4月に宮崎県で開催されたG7農業大臣会合では、各国代表団を始めとした来場者に、温室効果ガス削減の取組を「見える化」した野菜をサラダ・バーとして提供するなど、海外に対しても情報発信を行いました。
令和6(2024)年3月からは、米を対象に、化学肥料や化学農薬の低減、冬期湛水等の水田における取組に応じ、生物多様性保全への貢献を示す表示を追加し、新たなラベルデザインでガイドラインに則った本格運用を開始しています。

新たなラベルデザイン
今後は、ガイドラインに則った「見える化」の取組を着実に増やすとともに、対象品目を畜産物等に広げるなど、引き続き、環境負荷低減の取組の「見える化」を進めていくこととしています。
事例:有機農業の現場から地域に広がる食育
~栽培体験や学校給食への食材提供、料理教室や出前授業を通じて~
(第7回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)
株式会社大地のMEGUMI(めぐみ)(北海道)
北海道網走郡大空町(あばしりぐんおおぞらちょう)に拠点を置く株式会社大地のMEGUMIでは、有機農業ならではの苦労や、有機野菜がなぜ環境に優しいのかといったことを理解してもらい、地元の農産物の魅力を伝えるための様々な取組を行っています。例えば、圃場(ほじょう)において実際に栽培を体験してもらったり、地元の小中学校に給食用食材として有機栽培の野菜を無償提供したりしています。
具体的には、町内の小学校6年生の「総合的な学習の時間」において、有機圃場における「かぼちゃ栽培体験」授業を実施しています。授業では、種まきから収穫までの実習を圃場で行うほか、収穫したかぼちゃを道の駅で子供たち自らが販売することで、栽培から消費までの一連の流れを経験します。こうした活動の中で、無消毒の種の播種(はしゅ)、除草剤に頼らない手による草取り、マルチビニールの回収など、子供たちは人にも環境にもやさしい有機農業を実践しながら、農作物を育てることについて学んでいます。
授業をきっかけに、子供たちの親を含む地域の農家においても環境に優しい農業が広まってきているほか、授業に携わった農家自身も食育について考えるようになりました。また、専門家を招いて、小学生以外に対しても料理教室や特別授業を行い、地元の農産物の良さを広めています。
昨今、化学肥料をはじめとする農業生産資材の価格は高騰しており、その大部分は輸入に頼っている状況です。有機農業の拡大は、食料安全保障の観点からも、農業の持続可能性を高める上で重要な手法であり、今後も有機農業を通じて、農業従事者を含め子供たちに関わる全ての人が、農業とともに成長していけるような活動を継続していきたいと考えています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4551)
ダイヤルイン:03-3502-1320