第4章 食育推進運動の展開
食育推進基本計画において、毎年6月を「食育月間」と規定。全国規模の中核的行事として、平成28年度は、6月11日、12日に福島県郡山市において「第11回食育推進全国大会inふくしま」を開催。平成29年度は6月30日、7月1日に岡山県岡山市で「第12回食育推進全国大会inおかやま」を開催予定。
農林水産省では、広く国民の理解を深めるため、食育基本法や第3次食育推進基本計画等の食育に関する基本情報をはじめ、都道府県・市町村の食育推進計画の作成状況など、食育推進の施策に関する総合的な情報を提供。
農林水産省では他の地域においても参考となり得るような若い世代の食生活の改善を対象としたボランティアについて、「食育推進ボランティア表彰」を実施。
コラム:「第11回食育推進全国大会inふくしま」を通じた普及啓発

第11回食育推進全国大会
inふくしまポスター
「第11回食育推進全国大会inふくしま」は、大会テーマを、復興のあゆみを全国に感謝を込めて伝えていくことを盛り込んだ「チャレンジふくしま!おいしくたのしく健康長寿~復興のあゆみ。全国のみなさまへ感謝の気持ちを込めて~」と設定。北海道・東北ブロックで初めての大会として開催。
会場をビッグパレットふくしま(郡山市)とし、開会式、食育推進ボランティア表彰をはじめ、講演、シンポジウム、ワークショップ、展示(139団体、131ブース)等が行われ、2日間で約2万6千人が来場。
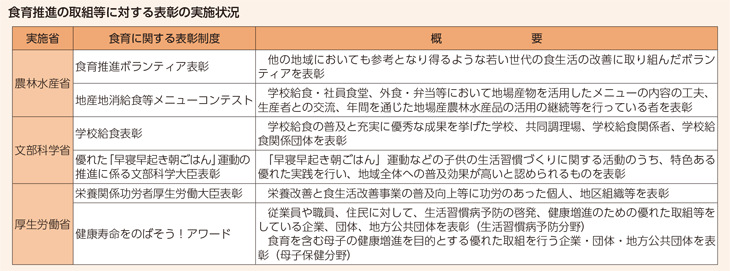
事例:奈良県内の4つの大学サークルが連携 ~「ヘルスチーム菜良(なら)」~
〔平成28年度 食育推進ボランティア表彰 受賞〕

「ヘルスチーム菜良」は、奈良県内の4大学(畿央大学・近畿大学・帝塚山大学・奈良女子大学)の200名を超える管理栄養士養成課程の学生で構成する食育ボランティアサークル。
4大学連携で、県・市町村や関係団体が実施するイベントに参加するほか、企業との連携による奈良県産の材料にこだわったお弁当等の開発、県と連携した若い世代向けの啓発媒体の作成など、幅広い活動を展開。
協議会を結成することで、それぞれ主体的な活動をしてきた4大学がつながって大きなパワーを発揮。
事例:五感を育み、食べる楽しさを伝える ~「味覚の一週間」®~

「味覚の一週間」®は、フランスで行われてきた27年にも及ぶ味覚教育の活動。日本でも平成23年から同様の取組を開始。6年目となる平成28年は、10月17日から23日の一週間に、日本各地の小学校やレストラン等において、五感を使って味わうことの大切さや食の楽しみを体感できる様々な取組を展開。
活動の中心である「味覚の授業」は、和・洋・中の料理人や生産者等が講師としてボランティアで小学校を訪れるもので、平成28年には約300人の講師が全国189校、約1万4千人の児童に向けて実施。
以下の要素で構成することを基本としつつ、講師はそれぞれの専門分野や個性をいかした体験型学習を展開。
「味覚の授業」の基本構成
- 五感の働きと5つの基本の味(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味)を教えること
- 五感で味わうことによって広がる食の豊かさを教えること
- 食品の産地や生産方法について情報を伝えること
- 仲間と「おいしさ」を共有することの楽しさを教えること
- 講師自身の経験や料理に対する思いを伝え、「食」に興味を持つきっかけを作ること
また、公立大学法人福岡女子大学と連携して「味覚の授業」の効果を把握するための検証を実施。福岡県篠栗町立北勢門小学校では、平成24年から毎年4年生に「味覚の授業」をしており、平成27年には「味覚の授業」前後に調査を実施。5味識別テスト(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の低濃度溶液と水3、計8検体を識別)の結果、受講前における正答数の最頻値は4、受講後には8(満点)に変化。また、正答数6以上の児童が約2倍に増え、味の識別能力が向上したことがわかった。なお、未実施校(対照校)における4年生の正答数の最頻値は4であり、北勢門小学校(実施校)における「味覚の授業」受講前と同様の結果で、受講後の結果との間に有意差が認められた。
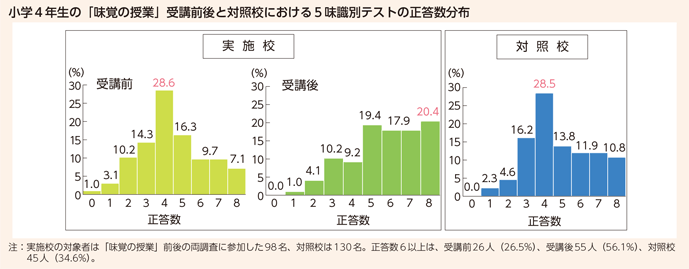
さらに、北勢門小学校の5・6年生が、4年生の時に受けた「味覚の授業」後に変わったと思うことについて調査した結果、嗅覚や味覚、触覚、視覚、聴覚を使うようになったと答えた児童が多く、「味覚の授業」が五感を使って料理を味わうきっかけになったことがわかった。また、その他の食行動に関しても、“食に興味を持つようになった”、“一緒に食べることが多くなった”、“会話が増えた”、“手伝いが楽しくなった”など、「味覚の授業」が食への関心を高め、食行動に好影響を与えたこともわかった。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974







