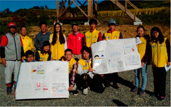第5章 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
農林水産省では、農林漁業体験の取組を広く普及するため、教育ファームについて、「運営の手引き」の普及、学校の教科学習と関連づけた教材、「企業向け導入マニュアル」の普及を実施。
農林水産省では、グリーン・ツーリズムを通じた都市住民と農林漁業者の交流を促進するため、農山漁村において行う体験プログラム作りや、受入体制構築、地域間交流拠点の整備等に対して支援。
総務省、文部科学省、農林水産省では、子供の農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を実施し、食育等に資する都市農村交流の取組を実施。
農林水産省では、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しむ滞在である「農泊」を推進するため、地域一丸となって、ビジネスとして実施できる体制の整備、農林漁業体験プログラム等の開発や古民家の改修等による魅力ある観光コンテンツの磨き上げへの支援をするための枠組みを構築。
農林水産省では、直売所を中心とした取組の推進や、学校給食や企業の食堂における地場産物の活用の促進等を図るため、地産地消に関するホームページによる情報提供、メールマガジンの配信、農産物加工施設及び直売施設の整備に対する支援、「地産地消等優良活動表彰」、「地産地消給食等メニューコンテスト」等を実施。
事例:「教える前に体験しなきゃ!」 先生のための農村ホームステイ
北海道農協青年部協議会は、小学校・中学校・高校の先生のための「農村ホームステイ」を平成25年度から実施。若手農業者が先生を1泊2日で受け入れ、農家宅のありのままの生活や農作業を体験してもらう取組で、「教育のプロ」である学校の先生と、「農業のプロ」である農業者やその家族との交流を通じて、共に「食や地域の大切さ」を子供たちへ伝えることについて考える。
平成25年度に道内4地区での取組からスタートし、平成26年度以降は全道に展開、平成28年度は全道で29事例の取組を実施。さらに、北海道教育委員会が実施する新規採用栄養教諭研修のプログラムとしても「農村ホームステイ」が組み込まれるようになるなど、取組が広がっている。
先生たちに農家宅へ泊まってもらい、農家の家族との時間を一緒に過ごしてもらうことにより、農作業体験だけでは伝えられない農家の想いや、学校・地域のことなど様々な事を話す機会になっている。「農村ホームステイ」を終えた先生たちは、自分自身の体験を学校に持ち帰って子供たちに伝えている。
事例:「土佐天空の郷」の棚田で大学生たちが農業体験
高知県の中山間地域に位置する本山町では、棚田の保全に加えて、農業体験を通じた食育活動に取り組んでいる。
本山町特産品ブランド化推進協議会では平成22年度から高知大学の学生らとの交流を主体とした農業体験活動を進めており、平成28年には延べ約250人が参加。特に「田んぼアート」は、カラー稲を組み合わせて、本山町の棚田の景観をPRする巨大な絵をつくりあげるもの。自身で植え付けた稲の生育を経て完成した図柄を見たときの満足感と相まって、一層、大学生たちの心に残る体験となっている。
また、各体験の後には、協議会関係者らと大学生とで、本山町農業を考えるワークショップを開催。地域活性化につながる加工品開発、観光メニュー、移住促進等について話し合い、大学生たちの新しい発想や視点から、農村の魅力を広く伝えるためのヒントが得られるなど、地域興しへの新たな波及効果も期待。
国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(2015年)において、小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料廃棄の半減等の目標を設定。
関係省庁が連携して、食品ロスの一つの要因となっている納品期限(いわゆる1/3ルール)等の商慣習について、商慣習見直しの取組の効果や実施に当たってのポイント等を分析・整理し、他の事業者による食品ロス削減の実践を促す取組を実施。また、フードバンク活動を行う団体が食品関連事業者からの信頼を向上させ、団体における食品の取扱いを促進。農林水産省では、平成28年11月に「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」を作成・公表。
地方公共団体、食品関連事業者及び消費者を対象とした「もったいないを見直そう~食品ロス削減シンポジウム~」(消費者庁、農林水産省、環境省主催、文部科学省後援)を平成28年10月に開催。
食品ロスを削減することを目的とした、自治体間のネットワーク「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」を平成28年10月に設立。
全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会活動内容
■「食べきり運動」の普及・啓発
■「食べきり運動」に関する取組や成果の情報共有及び情報発信
■前項のほか、食品ロス削減に関する取組や成果の情報共有及び情報発信
■国、民間団体、事業者等との連携及び協働
■その他、前条の目的を達成するために必要な事業
食品廃棄物等について、食品リサイクル法に基づき、発生抑制と減量化により廃棄物として排出される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料とするリサイクル等を推進。食品関連事業者の再生利用等実施率は、平成25年度に85%。
食品リサイクル・ループ認定制度については、平成28年12月末現在で55の計画を認定。地方環境事務所、地方農政局等による食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者、地方公共団体のマッチングの強化や、食品リサイクル・ループ形成に向けた主体間の連携を促すことが必要。環境省では平成27年度から「食品リサイクル推進マッチングセミナー」を開催しており、平成28年度は秋田県、大阪府、沖縄県の3か所で実施。

ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974