Topic 食文化の継承に向けた食育の推進
食文化の継承に向けた食育の推進
- 近年、日本の優れた伝統的な食文化が十分に継承されず、その特色が失われつつあることや、2013年には「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを踏まえて、第3次食育推進基本計画では「食文化の継承に向けた食育の推進」が重点課題の一つとなっていました。
食文化の継承に関する考え方や実践状況
- 食文化を受け継ぐことについて、約9割が重要と思っています。また、約7割が食文化を「受け継いでいる」と答えました。
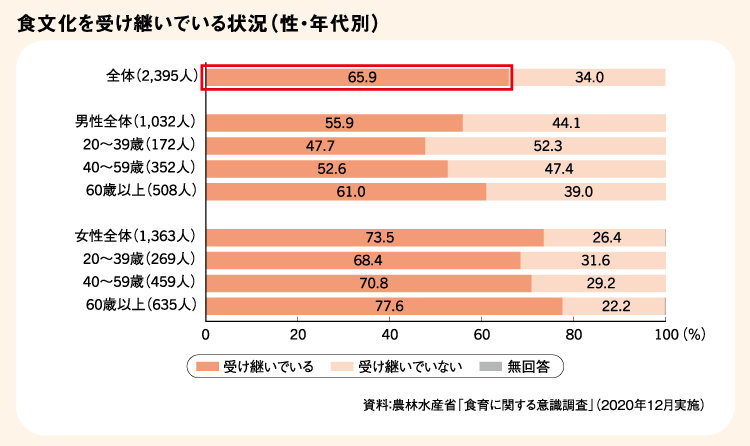
- 食文化を受け継ぐために必要なことは、「親等から家庭で教わること」が最も多く、次いで、「子供の頃に学校で教わること」、「ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理かを知る機会を増やすこと」でした。

(事例)地域と共に生きる力を育む食育カリキュラム「高倉(たかくら)スタンダード」の開発
(京都府)京都市(きょうとし)立高倉(たかくら)小学校
- 小学校6年間の食育カリキュラムとして、地域の教育資源や人材を活用しながら系統立てた「高倉スタンダード」を開発しました。
- 1年生では地域の高齢者と給食を食べる「スマイル給食」、4年生では地元企業の屋上農園を利用した農業体験、5、6年生では日本料理の料理人から学ぶ「だしの授業」や日本料理の盛り付け体験など様々な取組を行います。
- 教育課程の中で食育がどのように位置づけられているかを「見える化」していることが「高倉スタンダード」の特徴です。

5年生・だしの授業の様子

6年生・日本料理の盛り付け体験の様子
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P36

伝えたい日本の伝統的な食文化
- 日本の伝統的な食文化について、その特長や食文化の継承に取り組む事例を紹介します。
[column]日本の伝統的な主食「ごはん」
日本で古くから主食として食べられてきた「ごはん」は、主食・主菜・副菜を組み合わせやすいといわれており、実際、「ごはん」を食べる頻度が高い人は、栄養バランスに配慮した食事(主食・主菜・副菜を組み合わせた食事)を1日2回以上ほぼ毎日食べている人が多いという結果があります。

一方、5年前と比べた自身の米の消費量について、「減ってきている」と回答した人は「増えてきている」と回答した人の2倍となっています。
特に、女性の50歳以上、男性の60歳以上では「減ってきている」と回答した人が約4割を占めました。

もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P46~51
(事例)「味噌」を通した食文化の継承と食育の推進
(愛知県)合資会社野田(のだ)味噌商店

味噌蔵見学の様子
- 若い世代に食文化を継承することを目的に、味噌蔵見学や味噌作り体験を行っています。
- 地域の飲食店と連携し、地元の郷土料理「五平餅」の継承の取組を実施するなど、地域の食文化の伝承にも努めています。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中でも、オンラインでの味噌蔵見学や自宅で味噌を作れる味噌仕込みセットを使った味噌づくり体験を実施しています。
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P56
(事例)日本食パターンと死亡リスクとの関連
(東京都)国立研究開発法人国立がん研究センター
- 国立がん研究センターでは、様々な生活習慣と病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。
- 日本食パターンと死亡リスクの関連を調べたところ、日本食パターンのスコア(※)が高いグループでは、低いグループに比べて、全死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡のリスクが低くなることが分かりました
※日本食インデックス(JDI8;8-item Japanese Diet Index)の7つの項目(ご飯、みそ汁、海草、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶)では、男女別に、摂取量が中央値より多い場合に各1点、牛肉・豚肉では、摂取量が中央値より少ない場合に1点として、合計0~8点で算出しました。

もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P58~59
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班
電話:03-3502-8111(内線4578)
FAX:03-6744-1974




