第2章 学校、保育所等における食育の推進
(学校における食育の推進)

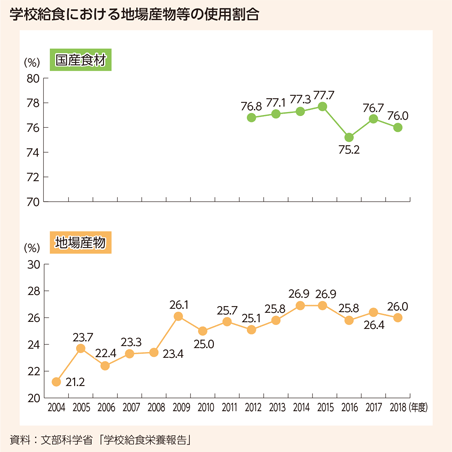
公立小・中学校等の栄養教諭配置数は、全国で6,488人(2019年5月1日現在)。
2017年から2019年に改訂された各学習指導要領等においては、引き続き、「学校における食育の推進」を総則に位置付け。
学校を核とした家庭を巻き込んだ取組により、子供の食に関する自己管理能力の育成を目指す「つながる食育推進事業」を、2019年度は全国で9事業(実施校21校)実施。
学校給食は、全小学校数の99.1%、全中学校数の89.9%で実施(2018年5月現在)。
学校給食における2018年度の国産食材の使用割合は76.0%、地場産物の使用割合は26.0%(全国平均、食材数ベース)。
学校給食において地場産物が一層活用されるよう、文部科学省では、食品の生産・加工・流通等における新たな手法等の開発と全国的な普及を図る「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」を実施。また、農林水産省では、生産者と学校等との調整役となる地産地消コーディネーターの育成や派遣を実施。
各都道府県の現行食育推進計画の約8割において、学校給食における地場産物の活用に関する目標を設定。
事例:地域とともに取り組む学校給食を活用した「食品ロスの削減」と「地産地消の推進」
(社会的課題に対応するための学校給食の活用事業における取組)
徳島県教育委員会では、上板町(かみいたちょう)を中心として関係者と連携し、学校給食を活用した「食品ロスの削減」と「地産地消の推進」に取り組んだ。
一次収穫を行った後の畑で、児童が、商品として流通できない規格外農作物の二次収穫を行い、加工業者が「みじん切り」や「ペースト」等に加工・冷凍して、それらを学校給食に使用。
こうした取組を通じて、規格外農作物等の学校給食への活用回数や地場産物活用率等が向上。
事例:学校給食における地場産農産物の活用について
東京都小平市(こだいらし)では、学校給食における地場産農産物の活用を進めるため、行政、生産者、JA東京むさし小平(こだいら)支店による研究会を立ち上げ。
農産物の配送に関わる課題を解決するため、JAが配送業務を担う学校給食事業を開始。
2006年度時点で小学校5.5%、中学校6.0%だった地場産農産物の使用割合が、2018年度にはそれぞれ29.3%、26.9%に上昇。
(就学前の子供に対する食育の推進)
保育所では「保育所保育指針」、幼稚園では「幼稚園教育要領」、認定こども園では「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、教育・保育活動の一環として、計画的に食育の取組を実施。
事例:幼稚園・小学校・家庭・地域が一体となった食育の取組
~郷土の料理「ねったぼ」作りを通して~
宮崎県都城市(みやこのじょうし)立石山(いしやま)幼稚園では、併設された小学校の1年生から3年生までの児童とともに、5月からサツマイモを栽培。さらに、収穫した芋を小学4年生から6年生までの児童が栽培した餅米と合わせて、郷土料理「ねったぼ」作りを行う「すこやかフェスタ」を実施。
「すこやかフェスタ」には、小学生・保護者・地域の高齢者や食生活改善推進員等が参加し、多世代の交流の場に。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974







