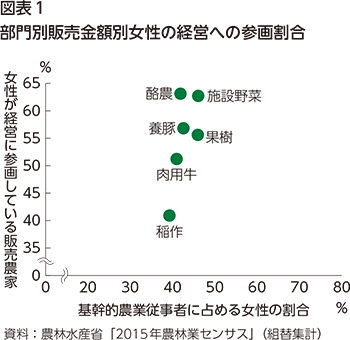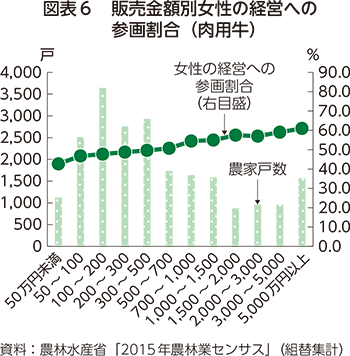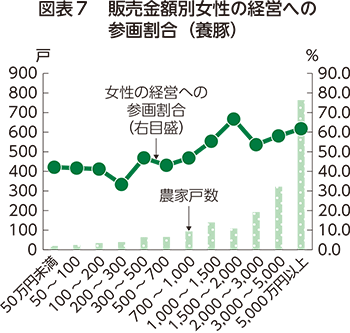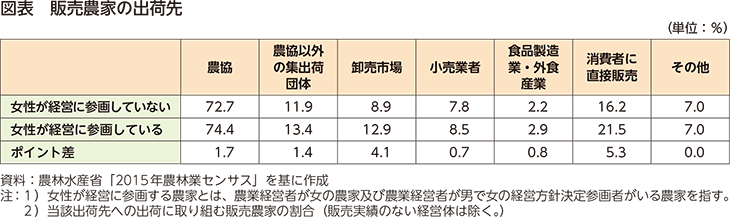(2)現場で輝きを増す女性農業者 ~この20年間を振り返って~
ここでは、女性農業者の農業経営や地域農業への参画状況について、おおむね20年間の推移を分析します。
(女性の基幹的農業従事者は減少、女性割合も低下)
女性の基幹的農業従事者(*1)は、平成11(1999)年から平成31(2019)年までの20年間で108万人から56万人まで減少しています(図表 特2-6)。この要因としては、農業以外の産業において女性が活躍する場が増えたことや、高齢によるリタイアが考えられます。
また、基幹的農業従事者に占める女性の割合を見ても46%から40%へと減少傾向にあります。
その要因を分析するために、平成17(2005)年及び平成22(2010)年の調査時の基幹的農業従事者が、そのまま5年後、10年後の平成27(2015)年も営農を続けていると仮定した数と、平成27(2015)年の実数を年齢階層別に比較しました(図表 特2-7)。これによると、この10年間で、男性においては60歳から69歳までの層で基幹的農業従事者数に大幅な増加が見られます。これは、定年退職等を契機として新たに就農したり、農外勤務を主体としていた男性が農業主体に移行したこと等が影響していたと考えられます。これに対して、女性では、この10年間で、男性と比べると60歳から69歳までの層での増加は小さくなっています。
若年層については、平成17(2005)年の値を10歳平行移動した数と平成27(2015)年の実数を比較すると、25歳から59歳までの全ての階層で、60代の層での増加数と比べると小さいものの、男女ともに基幹的農業従事者数は僅かに増加しています。ただし、若年層においても、女性の基幹的農業従事者の増加は男性に比べて低い水準となっています。
*1 用語の解説1、2(4)を参照
(女性の新規就農者は全体の4分の1、新規雇用就農で女性割合が高い)
平成30(2018)年における女性の新規就農者(*1)数は1万3千人で、そのうち49歳以下は5千人となっています。
また、新規就農者に占める女性の割合は、調査が開始された平成18(2006)年の30%から平成30(2018)年には24%へと低下しました(図表 特2-8)。これは、後述するように、農作業の体力的なきつさや栽培技術の習得等の課題に加え、女性労働力の確保に関する他産業との競合が強まっていること等が背景にあると考えられます。
新規雇用就農者(*2)については、女性が全体の32.6%となっており、雇用就農において女性の割合が高くなっています。この要因としては、一般的に法人等では、育児・介護休暇等の就業条件が整備されていることや未経験の女性でも農業技術を習得しやすいこと等が考えられます。

データ(エクセル:116KB / CSV:1KB)
*1、2 用語の解説2(5)を参照
(男女で異なる新規就農者の就農理由)
新規就農者の就農理由は、性別によってその傾向が異なっています。
「新規就農者の就農実態に関する調査結果」(*1)によると、男性は就農理由として、「自ら経営の采配を振れるから」、「農業はやり方次第で儲かるから」との回答が上位になっています。一方、女性の場合は、「農業が好きだから」、「家族で一緒に仕事ができるから」という回答が上位を占めています。また、女性は、「子供を育てるには環境が良いから」という理由を選択する割合が男性に比べて高く、家族や子供が重要な要素になっていることがうかがえます(図表 特2-9)。また、男性に比べ女性が「食べ物の品質や安全性に興味があったから」と回答する割合が高いことも特徴的です。
*1 一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談センター調べ
(女性の認定農業者数は20年間で5倍に増加)
女性の基幹的農業従事者が減少する一方で、地域農業を支える担い手となる女性農業者は大きく増加してきました。女性の認定農業者数は平成11(1999)年には2千人でしたが、平成31(2019)年3月では1万1千人と5倍に増加しています(図表 特2-10)。この要因としては、平成15(2003)年に、認定農業者制度における農業経営改善計画の共同申請が可能となったことにより、夫婦での申請が増加していることが挙げられます。全体の認定農業者数に占める女性の割合も20年間で3倍(1.6%から4.8%)に増加しています。
しかし、まだその割合は低いことから、今後も引き続き、共同申請を促すなど一層の推進に取り組む必要があります。
(女性農業者の経営への参画は約5割)
女性がどの程度農業経営に参画しているかを見てみます。女性が経営に関与する販売農家(*1)は全体の47%を占めており、そのうち、認定農業者がいる販売農家では61%、家族法人経営(一戸一法人)では62%において女性が経営に関与しています(図表 特2-11)。
*1 用語の解説1、2(2)を参照
(農業法人役員に占める女性割合は約2割)
公益社団法人日本農業法人協会(にほんのうぎょうほうじんきょうかい)の調べによると、平成28(2016)年度において農業法人の役員に占める女性の割合は21.8%となっています。この割合は平成24(2012)年度から10ポイント増加しています。
また、これを他産業と比較すると、医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業等には及ばないものの、建設業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業とほぼ同じかそれよりやや高い水準となっています。従業員数や売上高等の事業規模が異なるため一概に比較することは難しいものの、農業法人において経営に参画する女性が増えていることが分かります(図表 特2-12)。
事例:女性が輝く女性だけの農業法人(大分県)
大分県国東市(くにさきし)の平山亜美(ひらやまあみ)さんは、農業分野の新時代は女性が創るとの思いを込めて、平成27(2015)年に、女性だけでウーマンメイク株式会社を立ち上げ、水耕ハウスでのレタス栽培を行っています。消費者としての女性の感性を活かし、ライフスタイルやニーズに合った商品開発を行い、独自ブランドを全国展開しています。
平山さんは、働きたいという意欲ある女性が働けない現状を改善すべきと考え、女性が長く働くことができる職場づくりを進めています。子育て中、子育て後のライフサイクルに応じた勤務時間の設定や、子連れ勤務を可能としていること等により、女性の就職先として人気が高く、役員3人、従業員12人全員が女性です。
レタスの売上げは平成28(2016)年度の4,200万円から平成30(2018)年度には7,200万円まで増加し、安定的に利益が上がっています。このような取組が評価され、国内外からの視察も増加するとともに、平成29(2017)年には「農業の未来をつくる女性活躍経営体100選(WAP100)」(*1)に選定されるとともに、平成30(2018)年には第5回「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(*2)に選定され、特別賞も受賞しました。また、令和元年度農山漁村女性活躍表彰農林水産大臣賞を受賞しました。
*1 農林水産省では、平成27(2015)年度から29(2017)年度にかけて女性活躍に向けて先進的な取組を実践している農業経営体の情報収集を行い、後に続くモデルとなる102経営体を認定。WAPとはWomen’s Active Participation in Agricultural Managementの略称
*2 農林水産省と内閣官房が、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例として選定する取組
(女性の経営への関与と収益の増加には相関関係)
女性は農業の経営面においても重要な役割を担っています。株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)(以下「公庫」という。)が行ったアンケート調査結果によると、農業経営体の女性の経営への関与と収益の増加には相関関係があることが示されています(図表 特2-13)。
今後も女性の感性を活かした経営の展開を通じて、農業経営の発展、農業・農村の活性化につながることが期待されます。
コラム:部門別の女性の経営参画と販売金額の関係
女性の経営への関与と収益の増加には相関関係が見られましたが、これを部門別に見てみます。
女性の経営参画割合を部門別に見ると、最も高い部門は酪農で63.1%である一方、稲作では40.9%となっており、部門によってばらつきがあることが見受けられます。(図表1)。
次に部門ごとに販売金額別に女性の経営参画割合を見てみると、稲作、施設野菜、果樹、酪農、肉用牛、養豚のいずれの部門においても、販売金額が増加するにつれて女性の経営参画割合が高くなっています(図表2~7)。稲作では、販売金額が小さい層に多くの農家が分布しており、他方、酪農では販売金額が大きい層に多くの農家が分布しています。
いずれの部門でも販売金額が大きくなれば女性の経営参画割合も上昇しており、部門別に見ても女性の経営参画割合と販売規模が関係していることがうかがわれます。
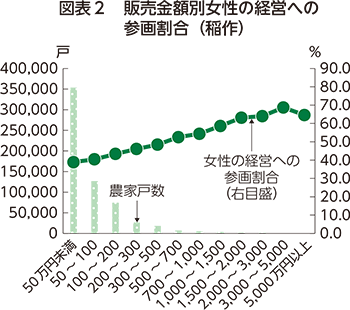
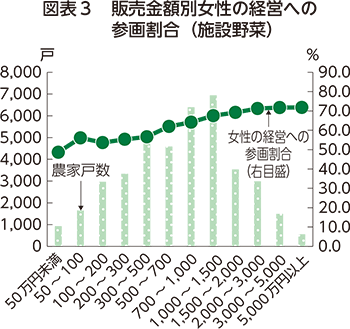
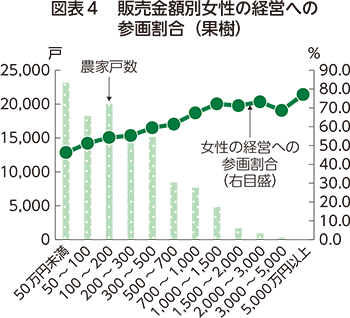
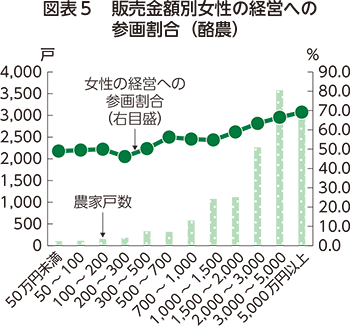
(多様化による経営への効果)
女性が経営に参画すると収益性が高い傾向は、他産業でも明らかになっています。実際に、女性を含む多様な人材を経営に活用する「ダイバーシティ経営」が企業のパフォーマンス向上につながるとして推進が進んでいます。従来男性が中心であった経営に女性を含む多様な人材を登用することで、経営にメリットがあると言われています。
マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査によると、女性の参画を含む経営陣の多様化によって、顧客との関係の強化、従業員満足度の向上、意思決定の改善、企業イメージの向上がもたらされ、企業としての高いパフォーマンスにつながるとの分析がされています(図表 特2-14)。
女性が経営に参画して活躍できる企業は、固定観念にとらわれない雰囲気や仕事の実績を正当に評価できるような仕組みを構築し、それにより収益の向上につなげようとしています。農業においても、女性を含む多様な人材が活躍できる土壌をつくり、収益向上やイノベーションにつなげていくことが重要です。

コラム:女性の経営参画と農産物の出荷先
下の図表は、女性が経営に参画する販売農家と参画しない販売農家について、「農協」、「農協以外の集出荷団体」、「卸売市場」、「小売業者」、「食品製造業・外食産業」、「消費者に直接販売」等の出荷先に出荷した農家の割合を示しています。いずれの出荷先を見ても、女性が経営に参画する販売農家の方が、出荷に取り組む割合が高くなっていることが分かります。
特に、女性が経営に参画する場合には、「消費者への直接販売」に取り組む農家割合が高くなることが見てとれます。農産物を購入する消費者は女性であることが多く、女性農業者は消費者ニーズに敏感であり、消費者に直接販売を志向することが考えられます。消費者への直接販売では、消費者の反応を的確に把握することができ、効果的なブランド戦略の展開にもつながります。
(グループによる起業から個人による起業へ)
先に見たとおり、平成4(1992)年の中長期ビジョンでは、女性の起業支援が提言されました。実際に、農村在住の女性が自立的に地域農産物を活用した特産品づくりや、農産物直売所での販売等の起業活動を行ってきました。
農村における女性による起業数は平成9(1997)年度に4,040件でしたが、平成28(2016)年度には9,497件となり、20年間で2倍以上増加しました(図表 特2-15)。
また、起業数を経営の種類別に見ると、平成18(2006)年頃までは、グループによる起業が多くなっています。これは生活改善普及事業において組織された生活改善実行グループや農協婦人部等を母体として起業活動が盛んであったためと考えられます。近年、高齢女性のリタイアや女性の組織数の減少等からグループによる起業数は減少していますが、個人による起業は増加傾向にあります。これは、農業にビジネスチャンスを見い出し、グループから独立したり、農外から参入するなどの事例が生まれていることを背景としているものと思われます。また、平成28(2016)年度において、グループ経営では、経営者の平均年齢が60歳以上の経営体が全体の76.3 %であるのに対し、個人経営では57.8 %となっており、個人経営では若年層の比率が高いことが分かります。女性の活躍の形も主体も、時代とともに変化し、多様化してきています。
平成28(2016)年度における起業活動内容を見ると、特産品づくり等の食品加工が最多の70.7%、次いで農産物直売所等の流通・販売に関する取組が69.1%、体験農園、農家民宿等の都市との交流が30.5%となっています。女性が加工や販売等の6次産業化部門を担当する場合には、女性の目線による細やかな気配りや対応、女性ならではのアイデアが経営面において強みとなっていると考えられます(図表 特2-16)。
(家族経営協定の締結は進展)
先にも見たとおり、家族経営協定は、家族経営体において、労働時間、報酬、休日等の就業条件を取り決め、農業経営を家族全員にとって魅力的でやりがいのあるものにするとともに、構成員の主体的な経営参画につなげようとするものです。
家族経営協定の締結は制度開始時から順調に増加しており、平成8(1996)年の5,335戸から平成31(2019)年には10倍以上の5万8,182戸となりました(図表 特2-17)。増加の要因としては、青年等就農計画及び農業経営改善計画の夫婦共同申請や、農業者年金の加入を契機とした締結が増えていること等が考えられます。
平成31(2019)年の締結数を都道府県別に見ると、北海道(5,770戸)、熊本県(3,831戸)、栃木県(3,751戸)、長野県(3,025戸)、茨城県(3,002戸)の順で多くなっている一方、約半数の都道府県で締結数が1,000戸以下にとどまっています。新規の締結を増やすため、時代に合った締結推進方法を検討することが課題です。
(農業委員、農協役員に占める女性の割合は増加し、約1割に)
地域農業の方針策定への参画の指標として、農業委員に占める女性の割合及び農協の役員に占める女性の割合を見ると、前者は平成12(2000)年の1.8%から令和元(2019)年には12.1%へ、後者は同期間に0.6%から8.4%へ増加しました(図表 特2-18)。
この間、平成15(2003)年には、政府は「社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度となるよう期待する」との目標を掲げ、平成27(2015)年に策定された第4次男女共同参画基本計画において、農業委員や農協役員の女性割合についての成果目標が設定されました(図表 特2-19)。
平成28(2016)年4月に改正された農業委員会等に関する法律及び農業協同組合法では、農業委員や農協役員について、年齢や性別に著しい偏りが生じてはならない旨の規定が設けられ、女性の参画を後押ししています。
他方、世界経済フォーラム(*1)によれば、我が国は、政治、経済における意思決定への参画等で男女格差が大きく、ジェンダー・ギャップ指数(*2)は153か国中121位となるなど、諸外国と比べて女性の参画は低い水準にとどまっています。こうしたことも踏まえ、女性活躍の推進を最重要課題の一つとして、農業分野でも成果目標を達成できるよう、一層の取組を推進することが必要です。
*1 世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」(2019)
*2 スイスの非営利財団「世界経済フォーラム」(ダボス会議)が、世界各国の男女間の格差を、経済、教育、健康、政治の4分野の14指標を用いて測定し、毎年公表しているもの。
事例:男女共同参画の社会を目指して地域の女性農業者と連携(熊本県)
那須眞理子(なすまりこ)さんは、昭和49(1974)年、結婚と同時に就農しました。熊本県菊陽町(きくようまち)で当初は施設園芸をしていましたが、昭和58(1983)年に肉用牛の繁殖経営に転換、現在では、家族3人で黒毛和種と褐毛和種を合わせて、繁殖牛約70頭、肥育牛約50頭の繁殖肥育一貫経営を確立しています。
地域に残る性別による固定的な役割分担意識が地域の発展を妨げていると感じた那須さんは、これを解消するため、昭和58(1983)年に地域内の女性達と「みずき座(ざ)」を結成、自ら脚本を書き「男女共同参画」を啓発する演劇を行うなど、地域の仲間づくりや社会への啓発活動を行ってきました。
また、農業に関わる女性の地位向上のため、平成15(2003)年から12年間農業委員を務め、農業委員の意識改革、女性委員の登用拡大に努め、平成23(2011)年には女性としては菊陽町初の農業委員会会長に就任しました。平成27(2015)年には、菊陽町議会議員に当選し、菊陽町男女共同参画推進条例の制定にも尽力されました。
那須さんは、「これからも引き続き、性別の違い等を互いに理解し応援できる男女共同参画社会を推進していきたい」と意欲を述べています。このような取組が評価され、令和元(2019)年度農林水産祭で内閣総理大臣賞「女性の活躍」を受賞しました。
事例:農協における男女共同参画の取組(滋賀県)

滋賀県においては、全ての農協で女性の役員登用を図り、令和元(2019)年度の役員全体に占める女性の割合は15.1%と、第4次男女共同参画基本計画における成果目標15%を全国に先駆けて達成しました。
滋賀県における平成26(2014)年の農協女性役員比率は8.7%でした。平成28(2016)年の農業協同組合法の改正を受け、県内全ての農協に「JA役員体制検討委員会」を設置し、同委員会の「検討指針」に第4次男女共同参画基本計画に基づく「女性登用目標」の実現に向けた対応を図ることを盛り込みました。農協役員への女性の登用により、女性役員が農協と女性組合員の重要なつなぎ役となっています。女性役員が、暮らしや健康、食といった生活に密着した女性組合員の声を理事会に届け理解を促すと同時に、女性組合員にも農協の組織や運営の考え方等をしっかりと伝えることで相互理解が深まり、女性組合員の農協運営への参画意識が育まれました。これは県下で取り組んでいる、組合員が積極的に事業や活動に参加する「アクティブ・メンバーシップ」にもつながっています。
滋賀県の農協では、組織運営の活性化に向け、引き続き女性の役員登用に取り組んでいます。
(農業高校の女子生徒は増加、農業大学校の女性卒業生の就農割合も増加)
未来の農業を支える人材を育成する教育機関でも女性の割合が増加しています。農業に関する専門技術や知識を習得するための学科が設置されている高等学校(以下「農業高校等」という。)の生徒数が近年減少傾向にある中で、女子の比率が大きく伸びています。令和元(2019)年度の農業高校等の女子比率は48.9%ですが、これは平成11(1999)年度と比べて10.3ポイント増加しています(図表 特2-20)。この要因としては、農業高校等においては、栽培技術の学習だけでなく、加工・販売等女子に人気の高い職業に関連する幅広い科目を設定する学校が増えていること、学校内にとどまらずより実践的に地域農業を学ぶ授業や、校内で生産した農産物の6次産業化等に取り組む学校が多くなったこと等が考えられます。
農業大学校については、令和元(2019)年度の入校者の女子比率は、21.4%となっており、20年間の推移を見ても平成30 (2018)年度が25%と高かった以外は、ほぼ同じ水準で推移しています(図表 特2-21)。
また、農業大学校の女性卒業生の就農割合を見ると、男性卒業生の就農割合より低いものの、男女別でのデータがある平成16(2004)年度から11ポイント増加し、平成30(2018)年度には50%となっています(図表 特2-22)。引き続き、農業を職業として選択する農業高校や農業大学校の女性の卒業生が増えるよう、農業のやりがいや魅力に接する機会を増やしていくこと等が重要です。
前述のとおり、平成28(2016)年に農業女子プロジェクトにおいて「チーム“はぐくみ”」を結成し、高校・大学校等の教育機関によるプログラムと活躍する農業女子メンバーが連携することで、新規就農につながる取組も進めています。これにより、参画する教育機関から農業大学校への進学や就農する生徒や学生が出てきています。今後は、教育機関間の交流、連携を行い、活動を広げていくこととしています。
また、農業高校の生徒に幅広い経験を積ませることは将来の職業選択時に農業を選択する可能性を高めると考えられます。実際に、農業高校の女子生徒が海外の畜産を学び、日本の畜産業を発展させていく方法を考え、学んだことを同級生等に広げていくことを目的とした未来の畜産女子育成事業でニュージーランドを訪れて畜産体験を行った農業高校の女子生徒が、ニュージーランドのように日本で酪農の価値を高めたいと考えて就農した事例も出てきています。
事例:非農家出身の女性が心機一転こんにゃく生産者の経営を継承(群馬県)
遠藤春奈(えんどうはるな)さんは、平成17(2005)年に、夫の地元である群馬県沼田市(ぬまたし)で、廃業寸前のこんにゃく生産者の経営を引き継ぐ形で新規就農しました。夫婦共に非農家出身で、こんにゃくいもの栽培について、何も分からないままで始めたため、最初の10年間は思うように収穫できない畑が発生するなど苦労しましたが、遠藤さんのこんにゃくの消費を拡大していきたいという強い想いが、次第に周辺の生産者にも伝わり、こんにゃくの消費拡大活動への理解や協力を得られるようになりました。
平成26(2014)年から6次産業化にも取り組み、こんにゃくと地元群馬の農家が生産する果物や野菜を使って共同開発した商品や、丸く一口サイズに加工したあく抜き不要のこんにゃく(ちゅるりん玉)を開発し、The Wonder 500(ザ ワンダー ファイブハンドレッド)の認定商品(*)にも選定されました。
また、農業女子プロジェクトの「チーム“はぐくみ”」パートナー校である蒲田女子(かまたじょし)高等学校で特別講師を勤め、こんにゃく作り実習及び講座を開催したり、農業大学校からインターンを受入れたりするなど次世代の教育活動にも貢献しています。
* 経済産業省が推進する地方発の「クールジャパン」プロジェクトの一環として、「世界にまだ知られていない、日本が誇るべき優れた地方産品(ものづくり・食・観光体験)」として選定された商品
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526