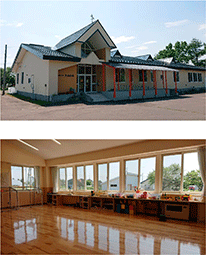(3)もっと輝くために ~女性農業者を取り巻く課題と方策~ ア 女性が働きやすく、暮らしやすい農業・農村の環境整備
(農村の子育て世代では男性に比べて女性の減少が大きい)
農村地域の女性人口は近年減少しています。農村地域女性人口は、平成12(2000)年から平成27(2015)年までの間に12%減少し、1,268万人となっています。そのうち子育て世代である25~44歳の女性人口は、同期間で21.7%減少し246万人となっており、他の世代に比べて、減少が顕著であることが分かります。これは、農村地域では進学や就職を契機に都市部へ人口が流出するためと考えられます。また、同期間での農村地域女性割合には変化がないことから、人口減少は男女ともに同様に起きていることが分かりますが、子育て世代では女性人口割合が1.2ポイント低下しており、子育て世代では男性より女性の減少が大きいことが分かります(図表 特2-23)。
(農村においては、家事や育児は女性の仕事と認識され、男性に比べ負担が大きい)
農村においては、依然として、家事や育児は女性の仕事であると認識され、男性に比べて負担が重くなっている傾向が残っています。総務省の社会生活基本調査(*1)によると、女性農林漁業者の一日の仕事・家事・育児の合計時間は7時間7分で、男性農林漁業者に比べ1時間19分多くなっています。一方、農林漁業以外の有業者の女性と比べても、女性の農林漁業者は家事の負担が49分大きくなっています(図表 特2-24)。
女性農業者等に対して、女性農業者が農業や地域で活躍するために必要なことを聞いたところ、「家事・育児への家族の協力」、「周囲(家族・地元)の理解」との意見がそれぞれ5割を超えています(図表 特2-25)。
*1 総務省「平成28年社会生活基本調査」
(農村地域では女性の労働力確保に関する競合が強まり)
一方で、農村地域と都市的地域(*1)の女性を比較すると、15~24歳を除き全ての年齢階層で農村地域の女性の就業者割合が都市的地域より高くなっています(図表 特2-26)。しかしながら、農村地域においては、医療・福祉分野へ就業者割合が増加している一方、飲食・宿泊業を除いて農業を始めとする他産業では就業者割合が低下しており、医療・福祉分野での需要増加により、女性労働力の確保に関する競合が強まっていると考えられます(図表 特2-27)。他産業において女性の活躍推進に向けた取組が進展している中、農業において女性の新規就農者を増やすためには、女性が働きやすい農業をつくるための取組を危機感を持って迅速に進めることが重要です。
*1 用語の解説2(6)を参照
(女性の新規就農者は農作業のきつさ、栽培技術、子育て等に悩みを抱える傾向)
女性の新規就農を促進するためには、女性の新規就農者が抱える課題を分析し、その解決に向けて取り組むことが重要です。一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談センターの新規就農者を対象とした調査(*1)によると、女性の新規就農者は様々な悩みを抱えています。
生活面では、最大の悩みが「健康上の不安(労働がきつい)」となっており、続いて「思うように休暇がとれない」、「子供の教育」となっています。一方で、男性は、最も多い悩みが「思うように休暇がとれない」ことであり、「健康上の不安(労働がきつい)」、「集落の人間関係」が続いています(図表 特2-28)。これらのことから、機械化等が進んできたとはいえ、農業には重いものの運搬等肉体的にきつい作業があり、農作業の体力的なきつさが女性農業者にとって大きな負担となっていることが推察できます。
経営面では、男女ともに「所得が少ない」、「技術の未熟さ」を挙げていますが、女性は続いて「栽培計画・段取りがうまくいかない」と回答した割合が高く、男性に比べ、技術習得や栽培面での悩みを感じている様子がうかがえます(図表 特2-29)。女性農業者に対するきめ細かな技術指導が重要と考えられます。
また、女性農業者を対象とした調査によると、「自身がリフレッシュする時間がとれない」、「妊娠中に仕事が休めない」、「子供が病気の時に預かってもらえる人や場所がない」といった悩みも抱えています(図表 特2-30)。
さらに、今後は高齢化の進行とともに、農村における介護の問題も大きくなるものと考えられます。
*1 一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談センター「新規就農者の就農実態に関する調査結果」
(農村における意識改革を進め、女性農業者が働きやすく、暮らしやすい農業・農村をつくる必要)
男性・女性が家事、育児、介護等と農業への従事を分担できるような環境を整備することは、女性がより働きやすく、暮らしやすい農業・農村をつくるために不可欠です。そのためには、家事や育児、介護は女性の仕事であるという意識を改革し、女性の活躍に関する周囲の理解を促進する必要があります。仕事や家事、育児、介護等の役割分担、報酬、休日等について家族で話し合い、明確化する取組である家族経営協定の締結は、意識改革の実現のための有力な方法の一つであり、実際に、経営やワーク・ライフ・バランスの改善に役立つと考える農業者は、農林水産省が令和元(2019)年8月に行ったアンケート調査結果によると、回答者の7割を超えています(図表 特2-31)。
また、女性農業者は共同経営者であるという意識改革を促すため、農業経営改善計画における共同申請を促進していくことも必要です。
さらに、意識改革は家族だけでなく、地域の住民等、周囲にまで広げることが必要です。地域の意識改革を進めるためには、女性農業者の横のつながりを強化し、働きやすく、暮らしやすい農業・農村のモデルケースを広く伝えることにより、変化を促していくことが有効です。
事例:家族経営協定の締結で農作業や子育てを分担(三重県)
三重県伊勢市(いせし)の南圭輔(みなみけいすけ)さん、絵美(えみ)さんは、平成18(2006)年に夫婦で就農し、いちご生産を行っています。就農から7年が経過し、経営も軌道に乗りつつあった頃、二人目の子供の出産もあり、普及指導員の勧めで家族経営協定を締結しました。
家族経営協定では、月一回の経営作戦会議を持つことや、決定に関しては二人の賛成を必要とすること等、常に二人で話し合いながら経営していくことを明文化しました。また、日々の役割分担についても、作業ごとに担当を明記し、経営主である圭輔さんと絵美さんの作業内容が明確になりました。さらに、子育てについては、圭輔さんも主担当に位置付け、学校行事や子供の習い事、子供の世話等生活面をサポートし、積極的に育児参加をしています。
家族経営協定の締結前は、圭輔さん一人で決断してしまうこともありましたが、家族経営協定を締結したことで、常に二人で相談しながら決定できる環境となりました。育児も二人で協力して行い、子供の生活スタイルに応じて休日を設定するなど、就業環境は家族経営協定の締結前より改善され、家族が楽しく暮らしていける経営を築くことができました。
(子育ての悩みを解消するためには育児を地域でサポートする仕組が必要)
新規就農者を含め女性農業者の悩みを軽減するには、子育て支援も重要です。農業において農繁期には、収穫作業が早朝から行われたり、夜遅くまで作業が続くなど、仕事を休めない状況になることがあります。また、農村地域では近隣に保育所や学校がないことも多く、育児の大部分を担っている女性農業者は、子供を遠方まで送迎する必要や、時間的に融通が利かないといった問題もあります。さらに、病児保育所やファミリーサポート等の整備が不十分なことから、子供が病気の際に思うように働けないなどの悩みもあります。以前は、祖父母と同居したり、地域で子育てをする中で解決されてきましたが、農村においても核家族化の進行や、新規参入就農や新規雇用就農により農外から就農する例も多くなり、女性農業者の子育てを支援する仕組みづくりが重要となっています。こうした中、育児を地域でサポートするネットワークを構築する動きも見られており、このような取組を推進していくことが必要です。
(農作業のきつさの解消のためには外部支援サービスの活用等が必要)
農作業の体力的なきつさの解消のためには、作業の一部を外部支援組織へ委託することも有効です。特に自動走行農機等の先端技術を活用した作業代行や、食品関連事業者と連携した収穫作業等、次世代型の農業支援サービスの提供も始まっており、今後、女性農業者のニーズに合わせたサービスの広がりが望まれます。また、スマート農業の導入や、女性が作業しやすい農機具の普及も必要です。例えば、女性向けに開発されたアシストスーツや自動草刈機を農協等新規就農者の受入れを支援する組織が購入し、貸し出して、女性の新規就農者が共同で使えるようにすることも解決策の一つです。
(技術習得のためには農業経営等の研修機会の確保が必要)
技術の習得が難しいと考える女性農業者に対しては、研修等への参加を促すことが必要です。国や地方公共団体等で農業経営に係る様々な研修を実施しているほか、農業大学校等の教育機関においてリカレント教育を実施する動きも広がっています。また、こうした研修に女性農業者が参加できるよう家族や周囲の人たちが支援することや、女性農業者自身も積極的に情報を入手して参加することが望まれます。一方で、農村の子育て中の女性農業者が頻繁に遠方まで通学することは容易ではありません。このため、自宅で学習できるアプリやe-learningの充実が必要です。
(農業法人の就業環境の整備も重要)
農業法人で技術を学ぶことも有効です。近年、農業法人においてはフレックス勤務や従業員の子育てと仕事の両立のための託児所開設、介護休暇の取得といった前向きな取組が見られます。一方、休日が少ない、男女別トイレや女性用更衣室が整備されていない、育児休業制度がないなど女性農業者の受入れに課題を抱える法人もあります。今後、女性農業者の就農促進に向けて、働き方改革の推進や男女別トイレ等の施設整備、育児休業制度や介護休暇の導入等、農業法人での就業環境の整備を推進する必要があります。
事例:農協、地域による託児支援(北海道、熊本県、群馬県)
(1)町と農協が連携して児童館機能を集約した託児所を開設
(北海道中標津町(なかしべつちょう))
北海道中標津町では酪農新規就農者の増加により、子育て支援ニーズが高まっていました。そこで計根別(けねべつ)農協と中標津町、北海道根室振興局、根室農業改良普及センターが連携し、平成29(2017)年から子育て支援の検討を始め、第一段階として、計根別農協事務所内で親子サロン・お試し一時預かりに取り組みました。農業者等からの評判が高かったことから、計根別農協管内の酪農家だけでなく、地域住民も一緒に利用ができる中標津町営の託児所兼児童館施設が平成31(2019)年4月、計根別地区に開設されました。
(2)地域で取り組む育児支援(熊本県南阿蘇村(みなみあそむら))
育児支援を軸に農山漁村への定住を促進する動きも始まっています。平成29(2017)年度に農山漁村振興交付金による地域活性化対策地区として採択された熊本県南阿蘇村両併(りょうへい)地区ローカルリソース活用協議会では、自然豊かな農村での子育てを希望する若い世帯を対象に、託児サービスを実施しています。多い時は10人ほどの幼児を保育士1人と保護者1人で預かり、田畑や鎮守の森で子供たちを遊ばせています。南阿蘇村には幼稚園がないことから、移住者以外からもニーズがあることが分かったほか、自然の中でのびのびと子育てをしたいという家族の移住につながっています。
(3)農業法人で事業所内託児所を開設(群馬県昭和村(しょうわむら))
群馬県昭和村の株式会社野菜くらぶは、志を同じくする生産者78人が集まって、900haの農地でレタス、トマト、キャベツ等の生産販売を行い、関連会社が漬物、こんにゃく、冷凍野菜、ミールキット等の加工、販売等を行っています。加工場等では人手が必要ですが、募集をしてもなかなか労働力が確保できず困っていたことから、労働力確保のために事業所内託児所を整備しました。託児所を整備したことにより、新規の人員確保が容易になっただけでなく、従来から働いていた女性社員の産休からの早期復帰が可能となりました。事業所内託児所では昼休みに授乳することも可能となり、働く女性に喜ばれているほか、男性社員からも子供の姿が見えることで会社の雰囲気が明るくなったとの声も聞かれています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526