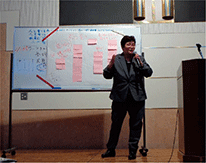(3)もっと輝くために ~女性農業者を取り巻く課題と方策~ イ 地域農業の方針策定への女性の意見の反映
(農業・農村の持続的発展のためには女性の声を反映することが重要)
世界的に見ても、女性を含め多様な人材が能力を発揮する企業では、パフォーマンス向上につながっていることが明らかになっています。また、社会は女性なくしては成り立ちません。女性が働きたいと思うような農業、女性が暮らしたいと思うような農村をつくっていくことは農業・農村の持続的発展の観点から重要です。そのためには、地域農業の方針策定に女性がより一層参画することにより、農業者としての立場に加え生活者や消費者として多様な視点を持つ女性の声を反映していくことが重要となっています。
(地域農業をリードする女性農業者の育成、人・農地プランの話合いの場への女性の参画等が必要)
地域農業の方針策定への女性の参画を推進するには、女性自身が学び、スキルを向上させ、地域農業をリードする女性農業者を育成することが必要です。これには、女性農業者の学びの場の充実が望まれます。併せて男性や地域でも意識改革を行うことが必要です。
また、これまで農村を支えてきた女性農業者は、生活面や経営面で悩みを感じ、集まって様々な工夫をし、解決に取り組んできました。こうした過去の知見や経験を新しい世代に伝えることや、学びの場となるグループを作り、グループ同士のネットワークをつなげることも有効と言えます。
若手女性農業者が地域の先輩女性農業者と交流を進める動きや、20年前に発足した女性農業者を中心とした団体を若手女性農業者が受け継ぎ、世代交代を図りつつ発展する動きも各地で見られます。このような交流を全国で活発化することが重要です。
さらに、女性農業者が持つ生活者や消費者視点を活用し、農業者の枠を超えたネットワーク形成が進むことも期待されます。特に先に見たとおり、食の品質や安全性に関心を持つ女性新規就農者も多いことから、消費者とのネットワークの構築、教育機関との連携による食育の実施や、福祉分野との連携による農福連携の展開を行うことも期待されます。このように活動の幅を更に広げていくことで、農業・農村に新しい視点をもたらすとともに、女性農業者の農業・農村での存在感向上にもつながると考えられます。
また、農業委員及び農協役員に関しては、優良事例やデータ収集を強化することにより女性参画の正の効果を分析して、その結果を情報発信すること等により、女性の登用を一層推進することが重要です。
さらに、「人・農地プラン」の実質化(*1)においては、市町村が設置する検討会への女性の参画が義務付けられています。今後地域における話合いの場へ女性農業者が積極的に参画していくことが望まれます。
こうした取組を集落営農(*2)組織や土地改良区における方針決定等農村地域での様々な意思決定の場にも拡大することが必要です。
本特集では、過重労働から徐々に解放され、自ら経営に参画したり、ビジネスチャンスを見い出しながら、輝きを増す女性農業者の姿を取り上げました。一方で、明らかになった課題については、更なる取組が必要です。女性が能力を発揮し、活躍できる農業や、女性が暮らしやすい農村を実現することは、女性農業者のためだけではなく、農業・農村に新たな視点や活力をもたらし、農業・農村の持続的な発展につながるものです。農林水産省を始めとする行政機関、農業関連機関はもとより、教育・研究機関においても課題解決に向け積極的な取組を行うとともに、農業・農村の現場でも意識や行動を柔軟に見直していくことが重要です。
*1 農業者の年齢や後継者の有無を「見える化」した地図を用いて、地域の農業者が話し合い、将来の農地利用を担う経営体の在り方を決めていく取組
*2 用語の解説3(1)を参照
コラム:農業を始めてみたけれど・・・
男性には分からない女性の悩み。就農に当たり苦労したことを紹介します。
女性が新規就農するに当たり、「女性の方が苦労が多いと思ったことはない」との声が多く、「色んな人が覚えてくれた」、「気さくに声をかけられ、栽培方法を教えてくれた」など温かい励ましや支援を受けられたとの声がある一方で、「女性が独立就農するのは無理」、「女一人で農業をするのはやめておけ」、「農業やりたいなら農家に嫁に行け」などの言葉を周囲の方から投げかけられたといった声もあります。
「農業は結婚すれば旦那が主人となり、代表者となる職業」、「農業の窓口は通帳を含め全て夫の名前で自分は常に表に出られない」、「農業者同士の交流は男性主体で女性は交流がなく、孤独」との声もあり、農業現場は依然として男性中心であることが見受けられます。
また、女性農業者からは、農作業が肉体的にきつく、「体力的に男性に及ばない」、「機械等の修理、力仕事で困った」といった声も聞かれます。一方で、「一人で出来ないことは周りの方々に手伝ってもらったり、業者に頼む」、「作物を軽いものにし、大型の機械や設備を導入しなくても良い栽培法を選んだ」など、工夫をしている声も聞かれます。
さらに、「出産前後でも同じように仕事をしなければならない」、「お腹に子供がいたので高所作業が難しかった」など妊娠・出産にまつわる不安や、ほ場や事務所に男女別のトイレがなく、「トイレは近くの公園やスーパーで借りる」などの苦労もあります。これらは男性にとっては気づきにくいことかもしれませんが、女性にとっては大きな問題で、早急に解決すべき課題です。
これまでも、女性は労働力としてだけでなく、経営のパートナーとして農業を支えてきました。また、マーケットインの発想で能力を発揮している女性農業者も増加しています。農業・農村を持続的に発展させていくためには、女性が働きやすく、暮らしやすい農業・農村をつくる必要があり、そのためには、女性の声を受け止め、女性の声を農業・農村の現場に反映していくことが必要です。
資料:全国農業会議所「女性の視点に立った新規就農の課題や支援施策のあり方調査結果」(平成24(2012)年)
事例:横に縦に深まる女性農業者の交流(兵庫県)
兵庫県南(みなみ)あわじ市(し)の堤由美(つつみゆみ)さんは、平成20(2008)年に農家の長男と結婚し、南あわじ市に移住したことを契機に、農業を始めました。最初の頃は作業や段取りへの戸惑いや、体力的に大変なことも多かったものの、おいしく高品質な野菜を直接消費者に届けられるような、強気で自立した農家を目指して取り組んできました。
地域農業には、後継者不足や遊休農地等の課題がある中で、次世代を担う同世代の女性にも農業が楽しく、やりがいもあり、かっこいいことを伝えたいと、SNS等で農業の魅力発信を始めました。
平成30(2018)年には農林水産省の「女性農業コミュニティリーダー塾」に参加したことで刺激を受け、地域の女性農業者と横のつながりを強化するため「AWAJI プラチナ農業女子(のうぎょうじょし)グループ」を立ち上げ、女性農業者同士の交流会や勉強会開催、マスコミを通じた情報発信等、淡路島の農業をより活性化させるため、精力的に活動を始めています。堤さんは、横のつながりだけでなく、縦のつながりも重要であると考えており、長年農業・農村を支えてきた母世代、祖母世代が所属する生活研究グループ(旧生活改善グループ)とも交流し、これまでの知恵や経験を受け継いでいきたいと考えています。
事例:「しべちゃ町農業女性カレッジ」による幅広い交流を展開(北海道)
北海道標茶町(しべちゃちょう)の千葉澄子(ちばすみこ)さんは、北海道外から標茶町に嫁いで就農した一人です。自分を育ててくれた地域に恩返しがしたい、これからは女性の経営参画が経営の発展には欠かせないとの強い思いから、平成19(2007)年、学習活動組織「ナラの木学級」を標茶町に嫁いだ女性農業者の有志で立ち上げました。地元出身者でも参加できる場、酪農技術を学べる場、女性農業者の交流の場として設けましたが、北海道外出身者のみが参加できる場と誤解している人も多かったことから、10年間の活動を一区切りとして発展的に解散し、平成29(2017)年「しべちゃ町農業女性カレッジ」として活動再開しました。
このカレッジでは、農協、農業共済組合、標茶町、普及センター等と連携して、年5回程度の酪農に関する学習会や視察研修等を実施しています。生産技術を学ぶだけでなく、女性農業者の交流、相談できる仲間づくりの場として活用され、最近では標茶町外の参加も増えてきています。
代表の千葉澄子さんは、「これからは、次世代の若手女性リーダー育成や標茶町だけにとらわれず、広い地域での交流、勉強会の開催を目指していきたい。」と考えています。
事例:世代交代を成し遂げた田舎のヒロインズ(熊本県)
平成6(1994)年に発足した「田舎(いなか)のヒロインわくわくネットワーク」は女性農業者を中心に都市農村交流や農産物加工品づくり等、農業・農村の魅力や可能性を伸ばす取組を行ってきました。しかし、会員の多くが高齢化して解散の危機に直面する中、初代代表の山崎洋子(やまざきようこ)さんは、疲弊する農村を女性の力で活性化させるため、世代交代を提案。熊本県南阿蘇村(みなみあそむら)の大津愛梨(おおつえり)さんにバトンを託しました。
こうして、平成26(2014)年に、「田舎のヒロインわくわくネットワーク」は「NPO法人田舎(いなか)のヒロインズ」と名称を変え、代表の大津さんに加え40歳以下の現役若手女性農業者を役員として、新たに出発しました。現在は農業後継者不足の解消を目指して、情報発信、農業研修や視察等の受入れ等に取り組んでいます。
代表の大津愛梨さんは、「都市には都市の役目があると同時に、今こそ田舎には田舎の役目がある。そこに住む女性たちを中心に、より多くの方と共感し、協働できる組織を目指していきたい。」と述べています。また、再出発した平成26(2014)年から継続的に取り組んできた農業・農村における再生可能なエネルギーの普及啓発・導入促進の活動が評価され、令和2(2020)年2月に開催された「脱炭素チャレンジカップ2020」では環境大臣賞のグランプリを受賞しました。女性農家らによる地球温暖化防止の具体策として今後の広がりが期待されています。令和2(2020)年度以降は教育機関への出前授業や農業現場でSDGsを学ぶプログラムの開発等に取り組んでいく予定です。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526