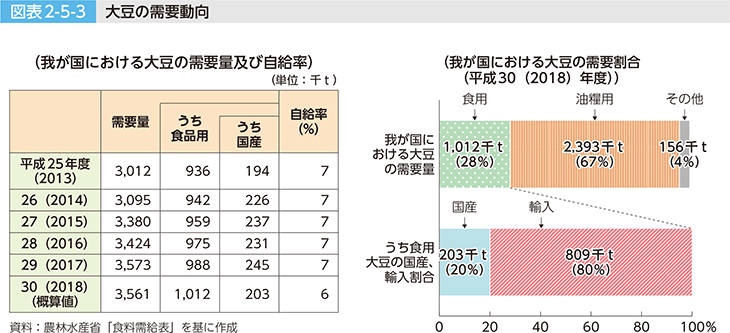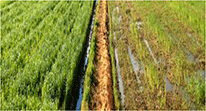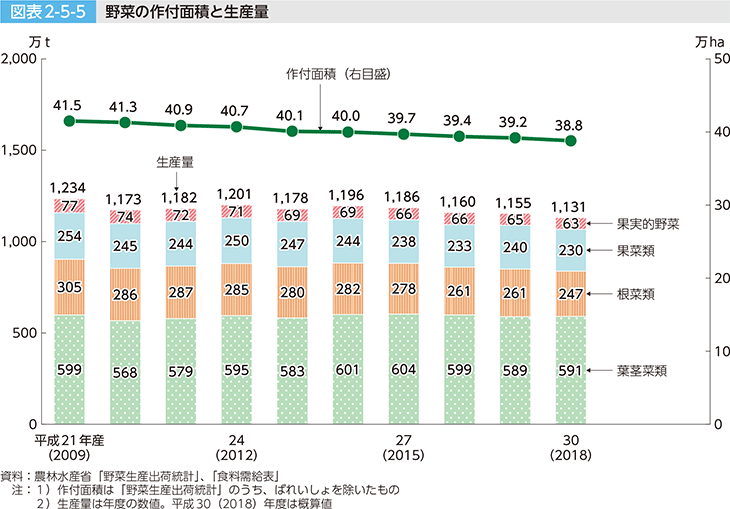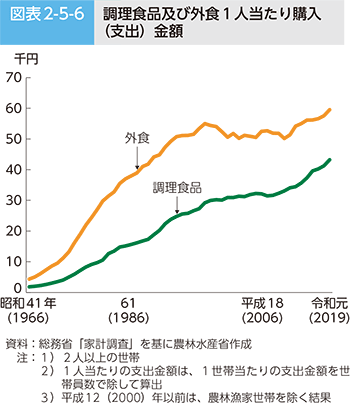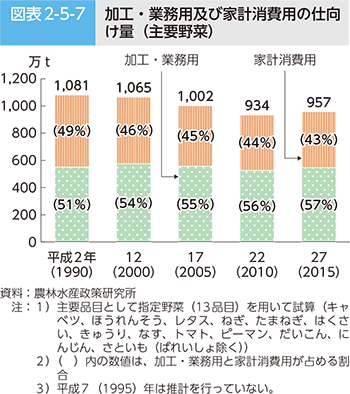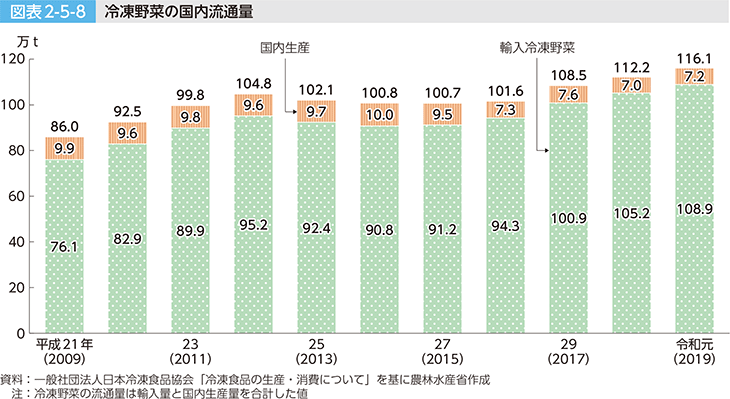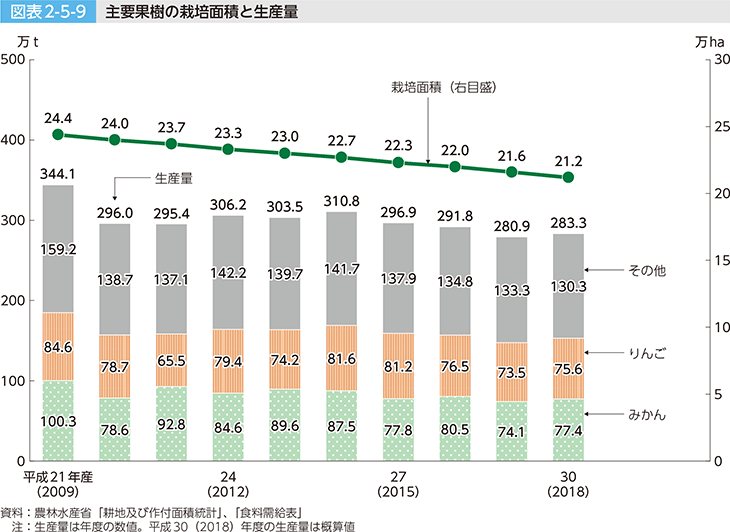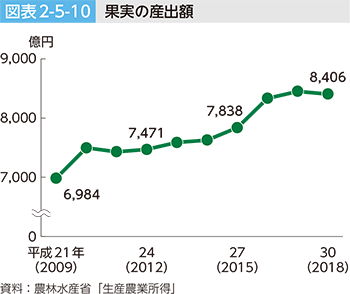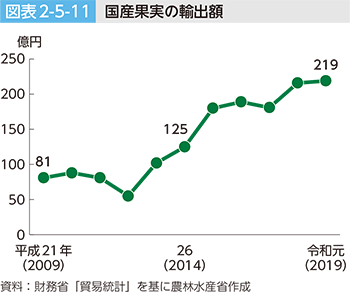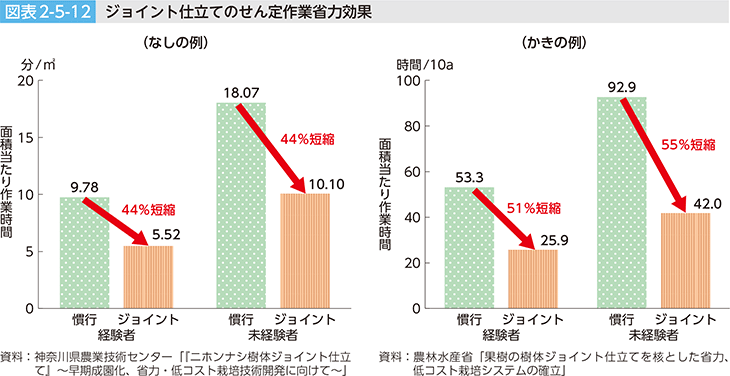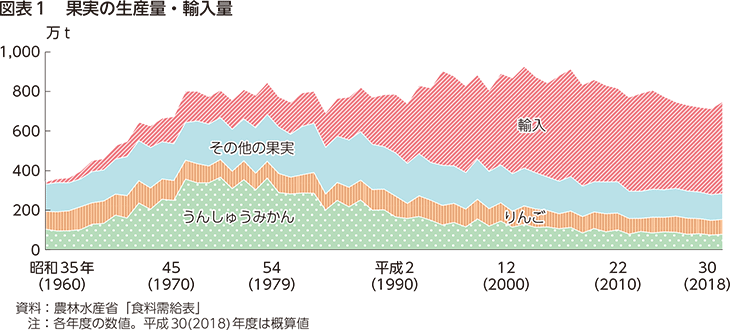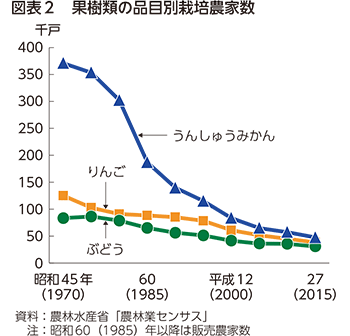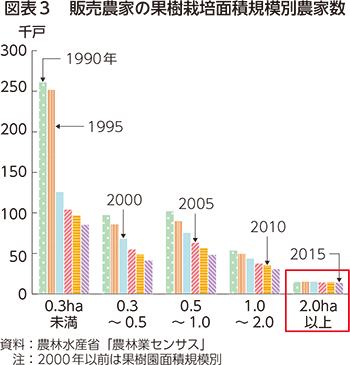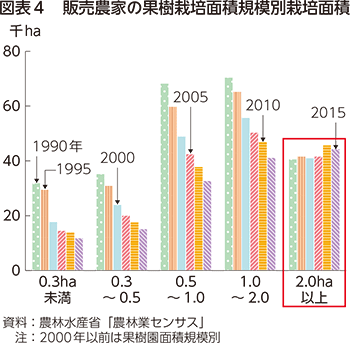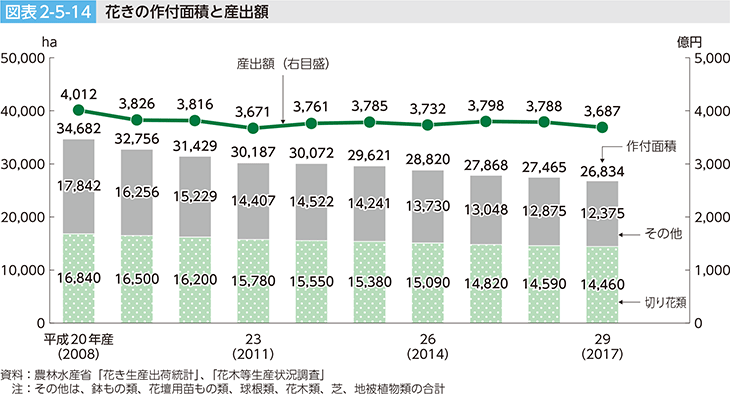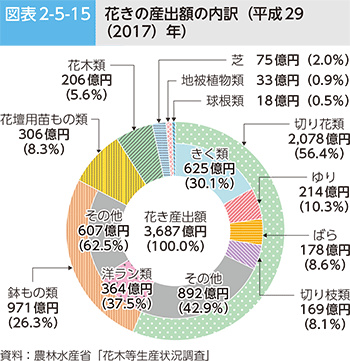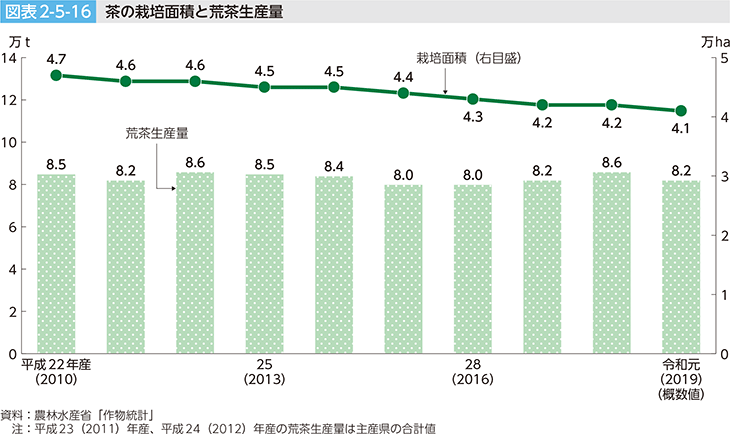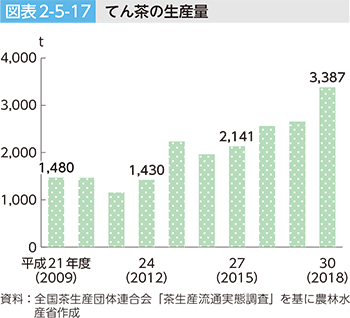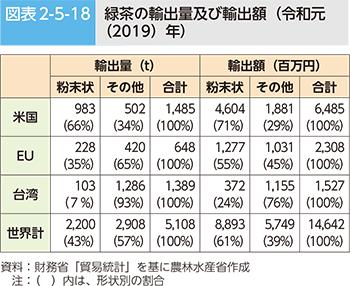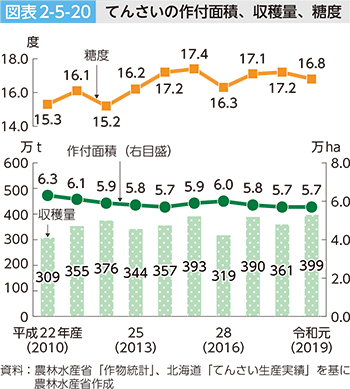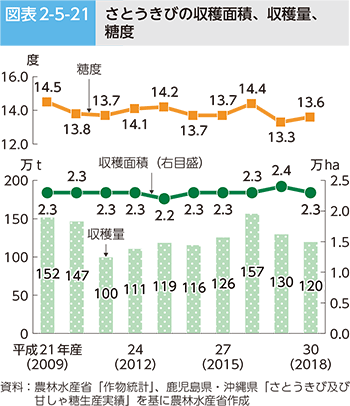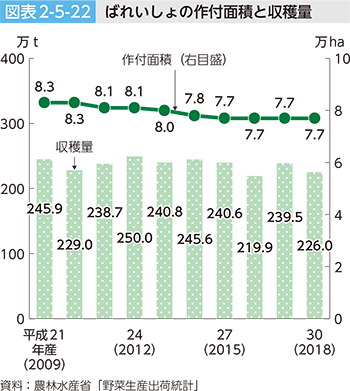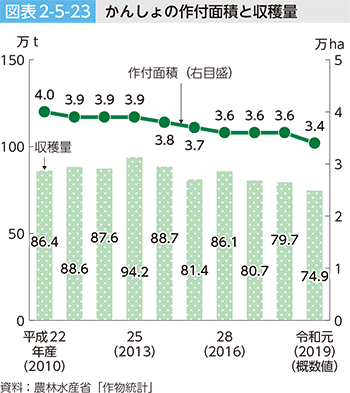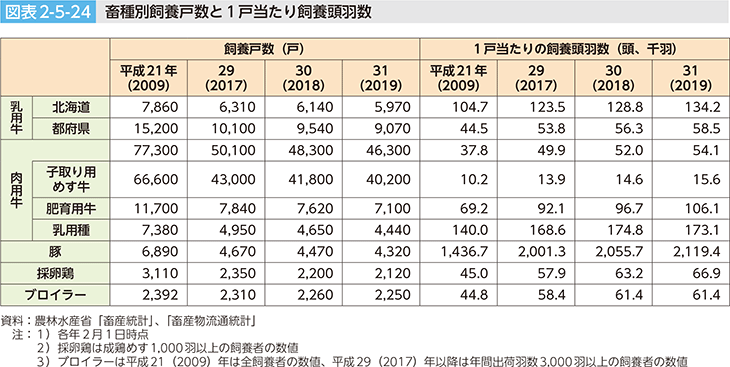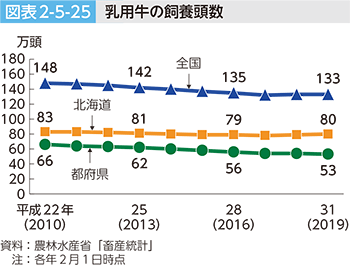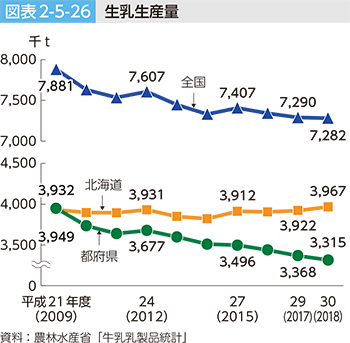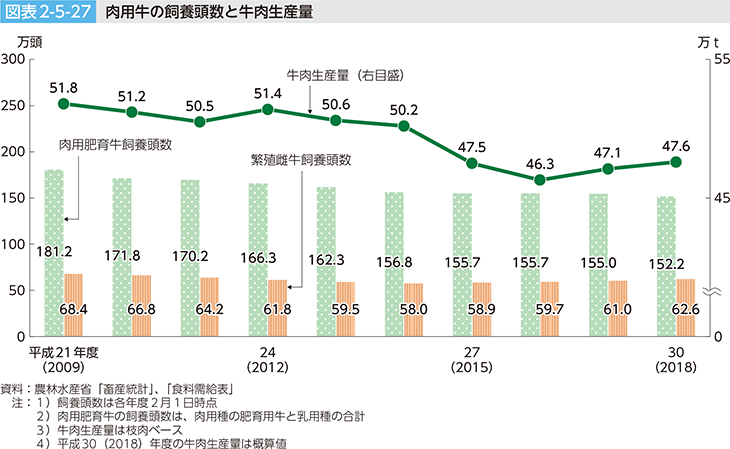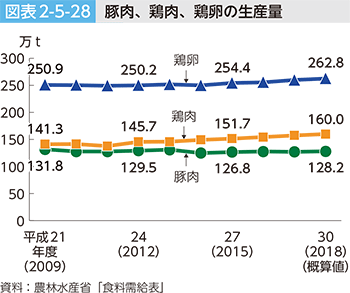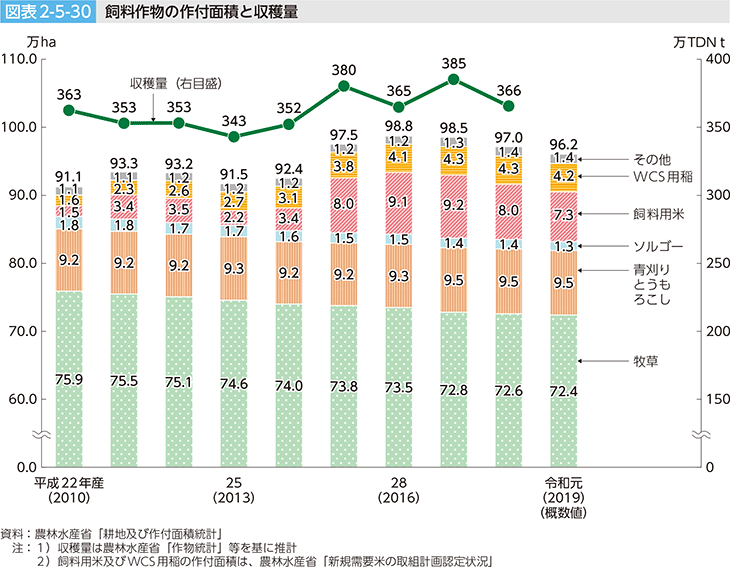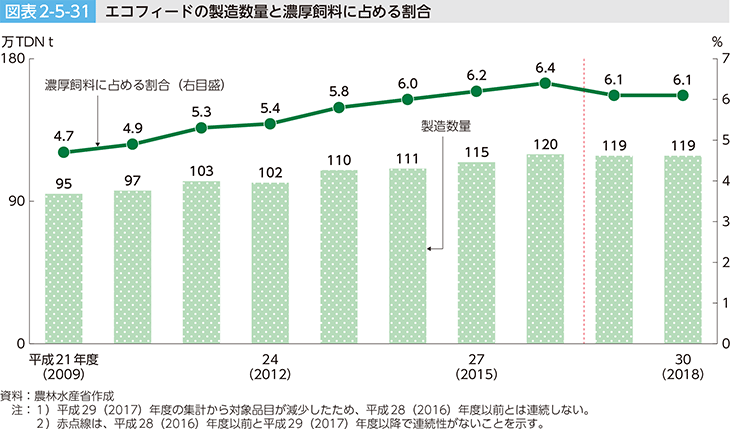第5節 主要農畜産物の生産等の動向
我が国では、各地域の気候や土壌等の条件に応じて、麦、大豆、野菜、畜産物等の様々な農畜産物が生産されています。消費者ニーズや海外市場、加工・業務用等の新たな需要に対応し、国内外の市場を獲得できるよう生産体制の強化や新品種の開発・普及を進めることが重要です。
(1)小麦・大豆
(小麦の収穫量は前年産より増加)
令和元(2019)年産の小麦については、作付面積は前年とほぼ同水準の21万2千haとなり、収穫量は天候に恵まれ生育が順調で登熟も良好であったこと等から、前年産に比べ36%増加し、103万7千tとなりました(図表2-5-1)。
(大豆の収穫量は前年産と同程度)
令和元(2019)年産の大豆の作付面積は、他作物への転換等により、前年産に比べ2%減少し、14万4千haとなりました。収穫量は台風や天候不順による播種遅れ等の影響により、21万8千tと、前年産と同程度の低い収量となりました(図表2-5-2)。
(需要に応じた品質の実現・安定化が必要)
国産小麦は、外国産小麦と混ぜ合わせて使用されることが一般的ですが、近年、加工適性に優れた新品種の導入・普及が進んだことや、消費者の国産志向の高まりを受け、国産小麦のみを使用した商品が増えてきました。
しかし、国産小麦は、収穫期が降雨の時期に重なること、赤カビ等の病害が発生しやすく、また、外国産小麦に比べてタンパク含有量のばらつきが大きいこと等、品質上の課題もあります。
また、大豆については、平成30(2018)年度の需要量は356万tで、近年では食品用を含めた大豆全体の需要が増加傾向となっています(図表2-5-3)。このうち、国産大豆については、実需者からは味の良さ等の品質面が評価され、ほぼ全量が豆腐、煮豆、納豆等の食用に向けられています。豆腐は製品歩留まり、煮豆は粒の大きさや見栄え、納豆は色、硬さ等、食品の用途によって求められる特性が異なります(図表2-5-4)。
実需者の求める量・品質・価格に着実に応え、国産小麦・大豆の増産と安定供給を図るため、食品産業との連携強化を図るとともに、作付けの連坦(たん)化・団地化やスマート農業による生産性向上等を通じたコストの低減、基盤整備による水田の汎用化、排水対策の更なる強化、耐病性・加工適性等に優れた新品種の開発・導入、収量向上に資する土づくり、農家自らがスマートフォン等で低単収要因を分析してほ場に合わせた単収改善に取り組むことができるソフトの普及等を推進していきます。
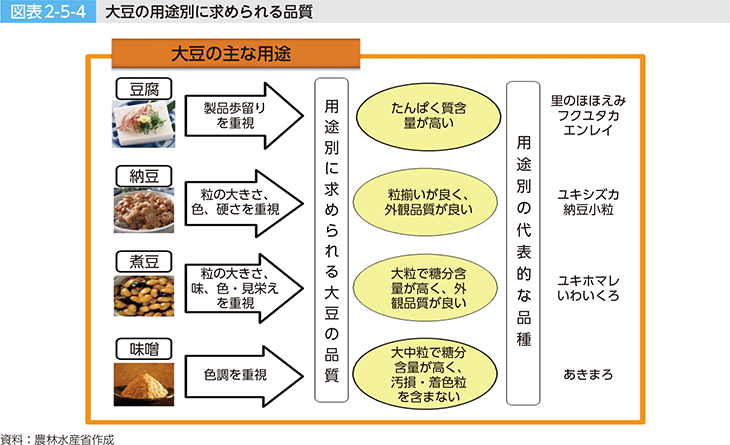
コラム:水田でも高単収の麦・大豆を目指して~スマートフォンで簡単診断~
麦・大豆は、都府県では主に水田で栽培されていますが、近年、都府県の麦・大豆の単収が低下傾向にあり、この改善が強く求められています。麦・大豆が低単収となる要因は複合的な場合が多く、ほ場条件によっても異なるため、どのような対策をとれば良いのか判断が難しい場合が多くあります。
このため、農研機構では、1,000筆以上のほ場データを分析し、低単収となる主な要因を6つ(湿害、土壌肥沃度、雑草害等)の要因に分類し、それぞれの要因ごとに必要となる適切な対策技術(排水対策技術、雑草防除技術等)の導入をサポートするマニュアルを作成しました。さらに、生産者自らがスマートフォンやタブレットを使ってほ場の状態を簡単に選択するだけで低単収要因の診断結果が示されるとともに、上述のマニュアルも利用できるWebサイトを令和2(2020)年3月に公開しました。
このWebサイトには、多くの水田で課題となっている排水対策等に役立つ最新の機械や技術等が紹介されており、低単収に悩んでいる生産者が、それぞれのほ場の課題にあった具体的な対応策を知ることができるようになります。その結果、ほ場によって異なる課題が解決され、麦・大豆の収量の向上・安定が大きく進むことが期待されます。
事例:在来種で地域活性化!佐用もち大豆(兵庫県)
大豆は、日本人の食生活に欠かせない、古くから日本人と共にある農作物です。このため、特徴ある在来種が各地に存在し、根強い人気を誇るとともに、ブランド化され地域の活性化に一役買っている場合もあります。
兵庫県佐用町(さようちょう)で約30年前から生産される佐用(さよう)もち大豆(だいず)は、大粒で甘みが強く、何よりも加熱した時のもちもちした食感が最大の特徴です。味噌や豆腐等に加工され、町の特産品として町内外から広く認識されています。また、実需者からの評価も高く、佐用もち大豆を使用した豆腐が全国豆腐品評会で賞を受賞したこともあります。
佐用町では、佐用もち大豆を地域資源として活かすため、町、農協、町内の農家が連携して佐用もち大豆振興部会を立ち上げ、種子の厳格な管理による優れた特性の維持に努めており、現在は、約400人の生産者が佐用もち大豆の生産に取り組んでいます。
令和元(2019)年5月には、佐用もち大豆が地理的表示(GI)保護制度に登録されました。佐用町では、これを契機に、佐用もち大豆の更なるブランド化に地域を挙げて取り組み、味噌や豆腐の販路拡大、観光振興等、町の活性化にもつなげていく考えです。
(2)野菜
(野菜の生産量は前年産より減少)
野菜の作付面積は、農業従事者(*1)の減少や高齢化の進行により近年緩やかに減少しており、平成30(2018)年産も前年産に比べて3,900ha減少の38万8千haとなりました。生産量は、近年、天候の影響を受けて増減しているものの、おおむね横ばいで推移していますが、平成30(2018)年産は長雨や低温等の天候不順の影響で、前年産に比べ2.1%減少の1,131万tとなりました(図表2-5-5)。
*1 用語の解説1、2(4)を参照
(加工・業務用向けの需要が高まり)
昭和40年代以降、社会構造・消費構造の変化に伴い、加工・業務用向けの需要が拡大してきており、近年では需要全体の6割を占めています(図表2-5-6、図表2-5-7)。今後も食の外部化(*1)や簡便化の傾向は続くと見込まれ、加工・業務用需要の増加傾向は更に進展すると考えられます。
加工・業務用野菜は、実需者等からの国産需要が高いものの、かぼちゃ等国産が出回らない時期がある品目や、たまねぎ等皮むき等の一時加工をしてから輸入される品目では、一定量の輸入が定着している状況となっています。
一方、キャベツやはくさい等は、天候不順等により国内産が不作になった時にスポット的に輸入されており、年により輸入量が大きく変動する傾向にあります。
また、冷凍野菜は、長期保存が可能で調理の利便性が高いこと等を背景に、国内消費量が増加傾向にあり、国内流通量も、平成24(2012)年以降100万tを上回る水準で推移しています(図表2-5-8)。
一方、冷凍野菜の国内生産量は、平成元(1989)年以降8万tから10万t前後で推移しており、これまでに国内流通量が増加した分の大半が輸入冷凍野菜となっています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(農業生産基盤強化プログラムにより野菜の生産体制強化を推進)
令和元(2019)年12月に決定された農業生産基盤強化プログラムでは、加工・業務用野菜等の新たな需要に応える園芸作物の生産体制を一層強化することとされました。
これを踏まえて、農林水産省では、複数産地と連携して実需者への安定供給を果たす拠点事業者の育成、水田を活用した新たな産地の形成、端境期の野菜の生産拡大、労働生産の向上に必要となる機械化一貫体系の導入等の施策を推進することとしています。
(3)果実
(果樹の生産量は前年産より増加)
果樹の栽培面積は、生産者の高齢化が進み、栽培農家数も減少傾向にあること等から近年緩やかに減少しており、平成30(2018)年産も前年産に比べ4千ha減少の21万2千haとなりました。また、平成30(2018)年産の生産量は、天候不順等の影響を受けた前年産に比べ、0.9%増加の283万3千tとなりました(図表2-5-9)。
(労働生産性の向上に向けて省力樹形の導入を推進)
国産果実の産出額は増加傾向で推移しています(図表2-5-10)。この背景として、簡便化志向や健康志向等の消費者ニーズを踏まえ、優良品種・品目への転換等により、高品質な国産果実が生産されていることが挙げられます。
また、その高い品質がアジアを始めとする諸外国で評価され、輸出額も近年増加傾向で推移しており、10年で3倍近くに増加しています(図表2-5-11)。
このように、高品質な国産果実は、国内のニーズや輸出品目としてのポテンシャルが高い一方で、農家数の減少や高齢化等により栽培面積や生産量は減少傾向で推移しています。
生産基盤が脆弱化(ぜいじゃくか)する中で、国内外の需要に応じた生産を確保していくためには、労働生産性の向上が重要です。
果樹農業は、水稲等の他品目と比較して、単位面積当たりの労働時間が長く、労働集約的な構造となっています。また、労働ピークが収穫時期等の短期間に集中していることから、労働生産性の向上には、作業時間の削減や単収の増加が可能な省力樹形の導入が有効です(図表2-5-12)。
従来の果樹栽培で用いられてきた慣行樹形は、大木がほ場内に散在する形になり、作業動線が複雑となるため、効率的な作業が困難になります。また、樹冠内部等への日当たりが悪く、品質がそろいにくくなります。
一方の省力樹形は、小さな木を密植して直線的に植えるため、作業動線が単純で効率的になります。また、均一な日当たりとなり、品質がそろいやすく、密植することで高収益が可能になります。
開発された省力樹形の例として、りんごの樹を薄い垣根状に密植する「トールスピンドル栽培」や、接ぎ木により樹を直線的に連結した「ジョイント栽培」等があります。慣行栽培に比べて、トールスピンドル栽培では収量を1.7倍に、ジョイント栽培ではせん定に係る作業時間を4割削減することが可能です。
農林水産省では、このような省力樹形の導入を推進しています。
(消費者のニーズに応じた生産が重要)
公益財団法人中央果実協会(ちゅうおうかじつきょうかい)の調査によると、果物の摂取頻度について、週1日以上食べると回答した人の割合は、60代では約8割となった一方、20から50代では、5から6割に留まっています。一方で、年代が低いほど、今後の果物の摂取量を増やしたいという意向が高い傾向にあり、20代では半分以上を占めています(図表2-5-13)。
果物を毎日食べない理由として、「他の食品に比べて値段が高いから」と回答した人が最も多く、「日持ちがせず買い置きができないから」、「食べるまでに皮をむくなど手間がかかるから」と続いています。また、果物の消費を増加させる方法としては、カットフルーツ、ストレートジュース等が上位になっています。
このことから、手頃な価格で手軽に摂取できる果実や果実加工品の需要が高いことがうかがえます。
ライフスタイルの変化に伴う食の外部化・簡便化の進展等、消費者ニーズの変化を踏まえ、食べやすいカットフルーツや冷凍フルーツ、種なしで皮ごと食べられる品種等、「より美味しく、より食べやすく、より付加価値の高い」果実及び果実加工品を供給することが重要です。このため、農林水産省では、消費者ニーズの多様化・高度化に対応した新品種の開発・普及等を推進しています。
コラム:うんしゅうみかんの生産構造
戦後の果樹の生産構造の変化について、うんしゅうみかんを例にとって考えます。
農業基本法の下でとられた「選択的拡大」等により、果樹の生産は大きく増加しました。特にうんしゅうみかん生産は西日本各地で広がり、生産量の増加は著しく、昭和35(1960)年の330万7千tから昭和54(1979)年にはピークの684万8千tに達しました(図表1)。
しかしながら、増産により生産過剰となり、昭和47(1972)年には、豊作も重なり、「みかん危機」といわれる価格の大暴落が起こりました。その後、うんしゅうみかんの生産調整が行われ、他品目への改植や廃園により、生産量も減少に転じました。
果樹の栽培農家数の推移を見ると、全体的に減少傾向にありますが、特にうんしゅうみかん農家の減少が大きいことが分かります(図表2)。
近年は高齢化による農家数の減少も重なり、産地では、農家数の減少が園地の荒廃を招いており、地域の活力の減退につながっているとの声も聞かれます。
うんしゅうみかんの栽培面積に目を向けると、昭和45(1970)年の13万8千haから平成17(2005)年には3万8千haとなっています。この間、農家数全体が減少する中で、1農家当たりの栽培面積の増加があまり見られなかったためです。特に、平成2(1990)年以降を見ると、2.0ha以上の面積で栽培する農家数はほとんど増加していません(図表3、図表4)。
これは、果樹生産には、収穫等の機械化が困難な作業や、せん定等の高度な技術が必要な作業が多く、労働集約的な構造となっていること、労働ピークが収穫時期等の短期間に集中し、臨時的な雇用が必要となること等がネックとなり、規模拡大が難しいためと考えられます。
今後も、農業者の減少が見込まれる中、地域の活力を回復し、生産基盤を強化させるためには、作業を省力化・効率化し、同じ労働力、同じ時間でより広い面積を管理すること、すなわち労働生産性を向上させることが必要です。
労働生産性の向上のため、省力樹形を導入することで、作業動線が単純となり、収穫作業等の省力化や、機械作業体系の導入が可能となります。機械作業体系としては、現在、ロボットによる除草や収穫作業の自動化、ドローンによる受粉や農薬散布等の技術が開発されています。
他方、うんしゅうみかん等のかんきつ類は中山間地域の急傾斜地等の厳しい条件の下で生産されていることが多く、省力樹形や機械作業体系を導入するためには、基盤整備を実施することにより、傾斜の緩和、農道や園内作業道の設置、かん水施設及び排水路の整備を進めていくことが必要です。
基盤整備の実施と省力樹形及び機械作業体系の導入を一体的に行うことで、労働生産性の向上につながり、担い手への園地集積や、規模拡大が可能となります。
事例:徹底した作業の効率化を進めて規模拡大に成功(和歌山県)
和歌山県有田川町(ありたがわちょう)の稲住昌広(いなずみまさひろ)さんは、うんしゅうみかんを中心にかんきつ類を栽培しています。
団体職員を辞めて実家の経営を引き継いだ直後に、うんしゅうみかんの価格低迷を経験し、経営改善のために生産を拡大しなければならないという危機感を持ったことから、自ら重機を操り、1haの基盤整備をするなど、着実に規模拡大を進めてきました。同時に、労働時間が長いかんきつ類を少しでも効率よく栽培するため、経営や作業の方法を一から見直す必要があると考え、家族経営協定の締結や作業時間のきめ細かな記録、園内道の拡張等の様々な改善に取り組んできました。
このような一つ一つの取組の結果、現在は、就農直後より2ha広い4.6haまで経営面積を拡大していますが、年間の労働時間は就農時より10%以上削減することに成功しています。
稲住さんは「更に効率化を進めるため、今後はスマート農業にも挑戦してみたい」と話しています。
(4)花き
(花きの産出額は前年産より減少)
平成29(2017)年産の花きは、前年に比べ作付面積が2.3%(0.6千ha)減少の2万7千haとなり、産出額は2.7%(101億円)減少の3,687億円となりました(図表2-5-14)。
近年、花きの産出額は緩やかな減少傾向で推移していますが、その内訳は、切り花類が2,078億円と全体の約6割を占めています(図表2-5-15)。続いて、鉢もの類が971億円、花壇用苗もの類が306億円、花木類が206億円となっています。
きく類の産出額は切り花類の3割を占めますが、近年減少傾向にあり、対前年比8.1%の減少、平成19(2007)年と比較すると21.8%減少しています。これは、お盆やお彼岸といった行事における利用が減少傾向であるとともに、農家の高齢化等による離農に伴い作付面積や生産量が減少傾向であるためと考えられます。
切り枝類の産出額は近年増加傾向で推移しており、対前年比1.2%の増加、平成19(2007)年と比較すると32.0%増加しています。切り枝類はフラワーアレンジメントの材料、ホテルや店頭での装飾、イベント、インテリア等様々な場面で需要が増加しているためと考えられます。
洋ラン類(鉢)の産出額は平成19(2007)年から減少傾向にありましたが、平成22(2010)年以降増加傾向で推移しています。洋ラン類はお祝い事の贈答品に用いられること等、一定の需要があり、近年は消費者のニーズにあったものが生産されるようになったためと考えられます。
また、切り花類の輸入状況については、切り花類の輸入量全体のうち、カーネーションが27%、きくが25%を占めています。海外の主要産地においては、生産に適した気象条件や栽培条件の面から、1本当たりの生産コストが国産の半分以下となっており、さらに、採花後の品質管理により、長時間の輸送に耐えられるようになったことから、輸入が増加傾向となっています。このため、国産花きの温度管理等による品質管理の徹底や作業の機械化等による低コスト化、省力化を進め、輸入花きに対する品質面・価格面での競争力を高めることが必要です。
(5)茶
(荒茶の生産量は前年産より減少)
令和元(2019)年産の茶は、栽培農家数の減少等により、栽培面積が前年産に比べて900ha減少の4万1千haとなりました。また、生産量は栽培面積の減少に加えて、主産地である静岡県において生育期間の天候不順等により生育が抑制されたこと等から、前年産に比べて5%減少し、8万2千tとなりました(図表2-5-16)。
(茶園の若返りと軽労化が重要)
全国の茶園面積の4割は収量や品質の低下が懸念される樹齢30年以上の老園であり、茶園の4割が中山間地に位置し、傾斜の要因により乗用型機械の導入が遅れている地域もあります。優良品種への改植や、早生(わせ)、晩生の品種導入による摘採期の分散等、茶園の若返りと軽労化が重要となっています。
(海外でのニーズが高くなり輸出は増加傾向)
茶の輸出は、海外の日本食ブームや健康志向の高まりにより近年増加傾向にあり、特に抹茶は海外でのニーズが高くなっています。これに伴い、抹茶の原料となるてん茶の国内生産量も増加しています(図表2-5-17)。
また、緑茶の輸出統計品目表が改正され、平成31(2019)年1月から緑茶を粉末状のものとその他のものに分割したことから、輸出相手国・地域ごとに粉末状の割合を把握することが可能となりました。例えば、令和元(2019)年は、米国向けの輸出額の71%、EU向けの輸出額の55%が抹茶を含む粉末状のものとして輸出されています(図表2-5-18)。
抹茶を始めとする茶の輸出を拡大するためには、輸出先国の残留農薬基準をクリアする必要があります。このため、輸出相手国において我が国で使用されている主要な農薬の残留農薬基準の設定に必要なデータの収集や相手国への申請を進めるとともに、病害虫防除マニュアルの作成や各地での防除体系の確立を推進しています。
(6)葉たばこ
(収穫面積、収穫量ともに減少傾向)
葉たばこの収穫面積及び収穫量は、耕作者の高齢化等から減少傾向にあり、平成30(2018)年も前年に比べて収穫面積は6.7%減少の7,100ha、収穫量は10.6%減少の1万7千tとなりました(図表2-5-19)。
葉たばこは、東北地方や九州地方で地域経済を支える重要な作物の一つですが、健康志向の高まりによる喫煙率の低下や加熱式たばこの需要の拡大等に伴い、紙巻きたばこの販売数量は減少傾向にあります。
農林水産省では、廃作に対する他品目への転換の支援等の措置を行ってきました。日本たばこ産業株式会社(JT)においても生産性向上に向けた支援を行っています。
(7)甘味資源作物
(てんさいの収穫量は増加、さとうきびの収穫量は減少)
てんさいは、他の作物に比べて面積当たりの労働時間が長いことから、労働力不足等を背景に他作物への転換が進み、令和元(2019)年産の作付面積は前年産に比べて1%減少の5万7千haとなりました(図表2-5-20)。一方で、6月以降天候に恵まれ作柄が良く単収が12%増加したことから、収穫量は前年産に比べて10%増加の398万6千tとなりました。糖度は前年産に比べて0.4ポイント低下し16.8度となりました。
さとうきびは、平成30(2018)年産の収穫面積は前年産に比べて5%減少し2万3千haとなりました(図表2-5-21)。収穫量は収穫面積の減少に加えて、台風第24号・第25号が襲来し、鹿児島県において倒伏の被害が発生したことから、前年産に比べて8%減少し119万6千tとなりました。糖度は前年産に比べて0.3ポイント上昇し13.6度となりました。
(てんさいは風害軽減対策、さとうきびは新品種の導入等を推進)
てんさいは、北海道の畑作地帯において輪作体系に組み込まれる重要な作物であり、さとうきびは、沖縄県や鹿児島県南西諸島において、台風等の自然災害に強い基幹作物です。
てんさいは、投下労働時間が多く省力化が課題です。このため、直播(ちょくはん)栽培の普及や大型機械導入の実証試験等が行われています。しかし、直播栽培は収量がやや低いこと、春先の風害に弱いなどの傾向があることから、狭畦(きょうけい)栽培(*1)、盛土による風害軽減対策等の開発・普及を進めています。
さとうきびは、高齢化や人手不足から管理作業の機械化・省力化や担い手確保が大きな課題となっています。これを受けて、鹿児島県徳之島(とくのしま)と沖縄県南大東島(みなみだいとうじま)では「スマート農業実証プロジェクト(*2)」に参加し、スマート技術の導入による生産等への効果を検証することとしています。また、多収性に優れ、機械収穫や株出栽培(*3)に適した新品種である「はるのおうぎ」の普及に向けた実証を実施しています。
*1 日本では一般的に畦間が60cmから66cmであるところ、畦間を45cmから50cmとする栽培様式。欧州では普及しており、直播栽培技術と大型機械を導入することで生産コストの抑制を見込める。
*2 国、研究機関、民間企業、農業者の活力を結集し、ロボット・AI・IoT等の先端技術を活用したスマート農業の全国展開を加速化するため、モデル農場における体系的かつ一貫した形での技術実証を支援する事業
*3 収穫した古株から出てきた芽を育てる栽培
(砂糖の需要拡大に向け「ありが糖運動」を展開)
砂糖は脳とからだのエネルギー源となる重要な品目です。しかしながら、消費者の低甘味嗜好(しこう)や他の甘味料の使用の増加等により、近年、その消費は減少傾向で推移しています。このような中、農林水産省は砂糖の需要拡大を応援する取組として、Webサイトで情報発信を行うなどの「ありが糖運動」を展開しており、砂糖に関する知識や、砂糖や甘味(糖分)に由来する食文化等の魅力を広く発信しています。
(8)いも類
(ポテトチップス、焼きいも等の需要に応じた生産拡大が重要)
平成30(2018)年産のばれいしょは、作付面積は前年産並となったものの、北海道における天候不順により、作柄の良かった前年産に比べ、単収が5%減少したため、収穫量は前年産に比べて6%減少の226万tとなりました(図表2-5-22)。
国産ばれいしょの生産量が減少傾向で推移する中で、ポテトチップスやサラダ用等の加工用ばれいしょの需要は増加傾向にあります。特に、メーカーからの国産原料の供給要望が強いことから、加工用ばれいしょの増産が課題となっています。しかし、植付や収穫に係る労働時間が大きいこと等から、労力・人員の確保が難しくなってきており、より省力的・集約的な作業体系を導入することが重要となっています。
令和元(2019)年産のかんしょは、作付面積が前年産に比べて4%減少したこと、鹿児島県及び宮崎県で発生したサツマイモ基腐病(もとぐされびょう)の被害により単収が2%減少したことから、収穫量は前年産に比べて6%減少の74万9千tとなりました(図表2-5-23)。
かんしょは、近年、粘質性が高く良食味の品種の開発や、電気式自動焼きいも機による小売店での固定販売の普及を背景に、食べ方としての焼きいもが注目されており、今後も堅調な需要が見込まれます。また、香港、シンガポール、タイ等のアジア諸国を中心に日本産のかんしょの需要が高まっていることから、令和元(2019)年の輸出量は前年に比べて23%増の4,347tとなりました。
需要に応じた生産を図るためには、病害虫抵抗性品種の導入や適切な栽培管理等による単収向上、省力化機械の導入等による作付面積の拡大が重要となっています。
(9)畜産物
(飼養戸数が減少する中、大規模化が進展)
飼養戸数は全ての畜種で減少する一方、1戸当たり飼養頭羽数は増加傾向で、大規模化が進展しています(図表2-5-24)。養豚、養鶏の生産現場では、以前から他の畜種と比較して大規模経営が定着していましたが、酪農経営においても、成畜を300頭以上飼養する経営体が10年前と比べて1.5倍増加し大規模化が進展しています。一方、肥育牛経営では、500頭以上飼養する経営体が10年前と比べて1.1倍と僅かな増加にとどまっています。
一方、中小規模の経営の生産基盤強化を図るためには、労働負担の軽減や、胎児死や初生牛の死亡等子牛の事故率の低減を図ることが重要となっています。そのため、ICT(*1)等の新技術を活用した発情発見装置、分娩監視装置等の機械装置の導入を支援し、生産性の向上と省力化を推進しています。
*1 用語の解説3(2)を参照
(酪農の生産基盤の維持・強化を推進)
乳用牛の飼養頭数は平成14(2002)年以降減少を続けていましたが、子牛の出生頭数が増加したことから、平成31(2019)年は133万頭と前年に比べて4千頭増加し、2年連続で増加しました(図表2-5-25)。また、1戸当たり経産牛飼養頭数は全国的に増加傾向で推移しており、大規模化が進展しています。
平成30(2018)年度における生乳生産量は728万2千tで、北海道で増加する一方、都府県で減少していることから、依然として減少傾向となっています(図表2-5-26)。
他方、黒毛和種の交配率の上昇等により、乳用雌子牛の出生頭数が減少してきたことを背景に、性判別精液の活用等による後継牛確保の取組を推進してきました。その結果、今後の乳用後継牛となる2歳未満の未経産牛の飼養頭数が増加していることから、生乳生産量の回復が見込まれています。
引き続き、後継牛確保の取組を推進するとともに、育成牛の預託等を通じて雌子牛を着実に育成することにより、生乳生産の増加につなげていくことが重要となります。
生乳の需要については、飲用にあっては牛乳の健康機能が注目されたこと等から僅かに増加しており、乳製品にあってはチーズ、生クリーム等で拡大していますが、生乳の国内生産量の減少により乳製品の輸入量が増加傾向にあります。今後、増加する国内需要に応じた生産を確保することにより、輸入で補っている需要を国産に置き換えていく必要があります。また、後継者のいない経営資産(施設、機械、生体)を、第三者に経営継承することで生産基盤の維持・強化を図ることが必要となっています。
このため、農林水産省では、生乳生産量が減少している都府県酪農の生産基盤強化を図るための増頭奨励金の交付等を推進するとともに、中小・家族経営の施設整備による経営基盤の継承等を推進し、環境整備を図ることとしています。
(肉用牛の生産基盤の維持・強化を推進)
肉用牛の飼養頭数は、平成22(2010)年度以降、減少傾向にありましたが、農家の規模拡大や、キャトルブリーディングステーション(CBS)(*1)やキャトルステーション(CS)(*2)の活用等により、平成27(2015)年度以降、繁殖雌牛については増加に転じており、平成30(2018)年度には、62万6千頭となりました。牛肉生産量は、平成29(2017)年度から2年連続で増加し、平成30(2018)年度は47万6千tとなりました(図表2-5-27)。
我が国の牛肉の消費量は、近年、肉ブーム等を背景に増加しており、輸入量も増加傾向にありますが、アジア地域の経済成長に伴う需要拡大や、ASF(*3)の発生により中国が食肉の輸入量を急速に増加させていることにより、世界的な牛肉の需給バランスに変化が生じています。また、和牛の海外での認知度向上等を背景に、牛肉輸出量は年々増加しています。
このような状況の中で、将来にわたり国民に安定的に牛肉を供給するとともに、新たな市場獲得を図るためには、国内の生産基盤を強化し、国産牛肉の生産量を増加させる必要があります。また、後継者がいない家族経営の資源を計画的に継承する仕組みを構築し、生産基盤の維持・強化を図ることが必要となっています。さらに、流通面では、生産現場が脆弱化(ぜいじゃくか)するとともに、生産者の顔が見える商品を求める消費者ニーズが高まる中、生産者と消費者の結節点として、高品質な食肉を安定的に供給していくことが重要となっています。
このため、農林水産省では、引き続き、畜産クラスター事業等による体質強化等を進めるとともに、輸出の拡大に向けて和牛の増産を強力に進めるため、繁殖雌牛の増頭奨励金の交付、和牛受精卵の利用の推進等による生産基盤の強化を図るとともに、中小・家族経営の施設整備による経営基盤の継承等を推進し、環境整備を図ることとしています。さらに、国産食肉の生産・流通体制を強化するため、生産現場と結びついた流通の改革を推進することとしています。
*1 繁殖経営で多くの時間を費やす、繁殖雌牛の分べん・種付けや子牛のほ育を集約的に行う組織
*2 繁殖経営で生産された子牛のほ育・育成を集約的に行う組織であり、繁殖雌牛の委託を行う場合がある。
*3 用語の解説3(2)を参照
(豚肉、鶏肉、鶏卵の生産量は微増傾向)
豚肉の生産量は、近年横ばいで推移しており、平成30(2018)年度は128万2千tとなりました(図表2-5-28)。一方、平成29(2017)年の世界の豚肉輸入量は546万tで、そのうち我が国は93万t、中国が146万tとなっており、この2か国で世界の豚肉輸入量の4割を占めています(図表2-5-29)。特に中国は、ASFの発生により輸入量を増やしており、世界的な豚肉の需給バランスに変化が生じています。関係者からはこのような状況下では十分な豚肉の輸入量の確保が難しくなると懸念されています。このため、更なる国内生産の維持・拡大が重要となっています。
鶏肉は、消費者の健康志向の高まりを受け、価格が堅調に推移していることから、生産が拡大し、平成30(2018)年度の生産量は160万tと5年連続過去最高となりました。
鶏卵は、平成25(2013)年度以降の堅調な価格を背景に生産が拡大し、生産量は4年連続で増加し、平成30(2018)年度は262万8千tとなりました。
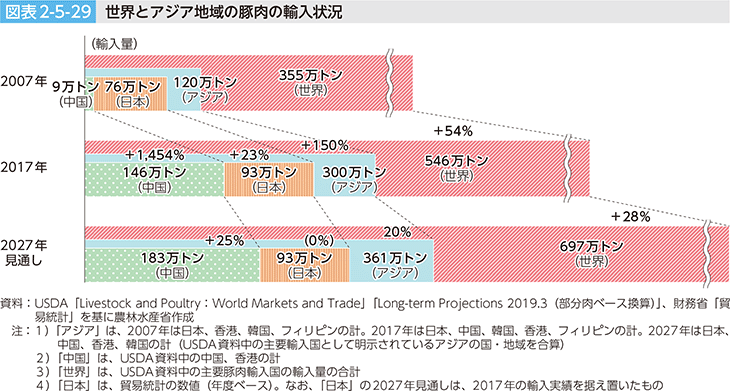
(飼料作物の作付面積は減少、エコフィードの製造数量は横ばい)
令和元(2019)年度の飼料作物の作付面積は、飼料用米及びWCS用稲(*1)の減少等により、前年に比べて9千ha(0.9%)減少の96万2千haとなりました。また、平成30(2018)年度の飼料作物のTDN(*2)ベース収穫量は、天候不順による生育抑制等により、前年に比べて19万TDNt(5.0%)減少の366万TDNtとなりました(図表2-5-30)。
エコフィード(*3)の製造数量は、平成30(2018)年度は前年同様、119万TDNtとなりました(図表2-5-31)。
エコフィードの生産・利用の拡大については、食品残さ等を排出する食品産業、食品残さの飼料化事業者(エコフィード製造事業者)及び利用する畜産農家の連携が進むように、エコフィード製造事業者の情報が公益社団法人中央畜産会(ちゅうおうちくさんかい)のWebサイトで公開されています。
経営費に占める飼料費の割合は、肥育牛で3割、養鶏で6割を占めています。このため、国際相場や為替レート等の影響で価格が乱高下しやすい輸入飼料原料を、国産の飼料用米や子実用とうもろこし、エコフィード等国内の飼料資源に置き換えていくことが、我が国の畜産業の生産基盤を強化する上で重要となっています。
また、粗飼料についても全て国産にするため、青刈りとうもろこしの生産や放牧等を推進しています。
*1 用語の解説3(2)を参照
*2 Total Digestible Nutrientsの略で、家畜が消化できる養分の総量
*3 用語の解説3(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526