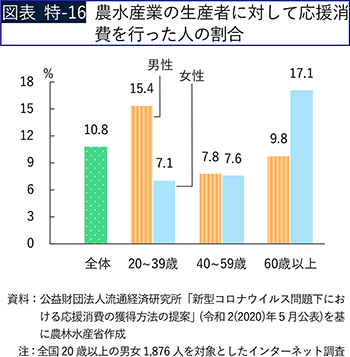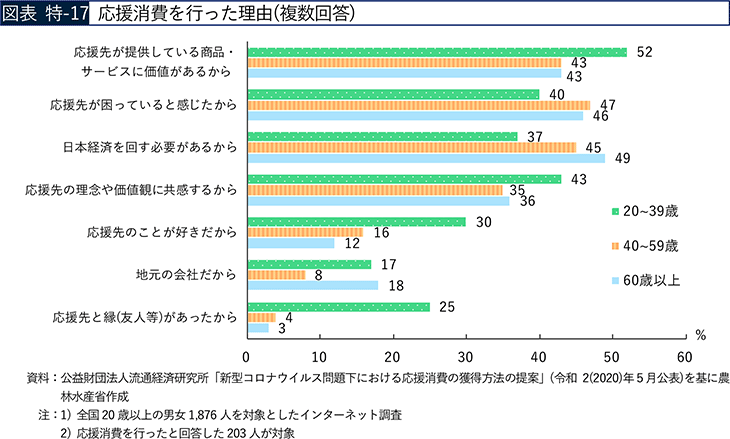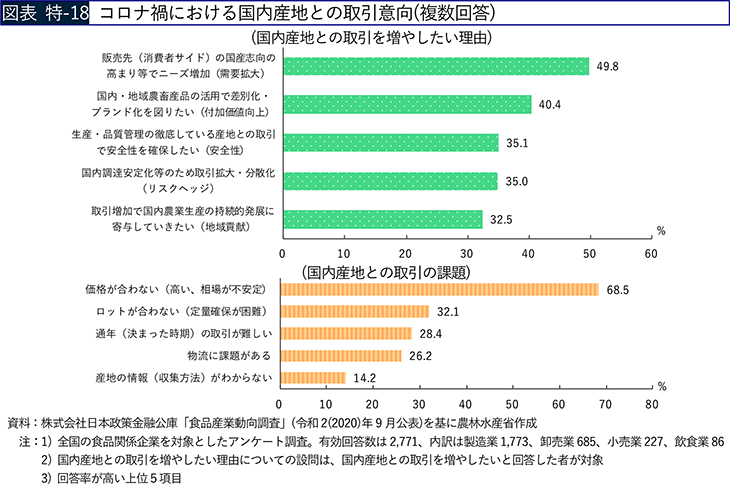(1)食料消費面での影響と新たな動き イ 食料、農産物需要をめぐる新たな動き
(外食事業者によるテイクアウト、フードデリバリーの取組が増加)
外食事業者の中には、提供する料理を消費者が持ち帰る「テイクアウト」や、料理を自宅に宅配する「フードデリバリー」への取組を拡大する動きが見られます。
エヌピーディー・ジャパン株式会社が令和3(2021)年2月に公表した調査によれば、令和2(2020)年4月以降、外食事業者のデリバリー部門の売上げは対前年同月比で増加して推移し、特に同年5月は204%増加しました(図表 特-14)。
ファミリーレストラン等を全国展開する、株式会社すかいらーくホールディングスは、令和2(2020)年4月以降、店内飲食による売上げが半減したため、テイクアウトやフードデリバリー用の商品開発に取り組み、これらのサービスの令和2(2020)年の売上げを対前年比で約6割増加させました。また、フードデリバリーについては、自社で配達するほか、宅配ニーズの急増に対応するため、フードデリバリーを専門に行う代行業者への委託も増加し、令和2(2020)年では、フードデリバリーの売上げ全体の1割となっています(図表 特-15)。
(消費者によるフードデリバリー専門事業者の利用が増加)
消費者によるフードデリバリーの専門事業者の利用は増加しています。
フードデリバリーサービス事業者の株式会社出前館を利用する消費者は令和2(2020)年8月現在で300万人(*1)を超え、加盟する飲食店数は、同年12月時点で前年に比べ2.5倍に増加し約5万店になりました。また、フードデリバリーサービス事業者のUber Japan株式会社においても、加盟する飲食店数は、同年12月時点で前年に比べおおむね4倍に増加し約7万店になりました。
*1 直近1年間に1回以上オーダーしたユーザー数
(消費者の1割が国内生産者への応援消費を実施したと回答)
新型コロナウイルス感染症の拡大により販路を失った国内生産者から農水産物を購入する「応援消費」の動きが見られました。公益財団法人流通経済研究所が令和2(2020)年4月に実施した調査では、「コロナ問題で被害を受けた生産者・事業者に貢献する意図での買い物」を行ったと回答した消費者が全体の1割いました。特に20~39歳の男性と60歳以上の女性において割合が高くなっています(図表 特-16)。
応援消費を行った理由としては、「商品・サービスに価値がある」、「応援先が困っていると感じた」が多くなっています(図表 特-17)。
(事例)JAグループが農産物の販売を支援するキャンペーンを実施

送料無料キャンペーンの
バナー画像
資料:JA全農
全国農業協同組合連合会(以下「JA全農」という。)は、平成13(2001)年より、全国の農業協同組合(以下「農協」という。)や生産者が農畜産物や加工品等を産地直送するインターネット販売サイト「JAタウン」を運営してきました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、農産物の売り先に困っていた生産者を支援するため、令和2(2020)年5月から、和牛、果実、乳製品、花きを対象に、送料をJAグループが負担する「さんち直送おうちごはん 送料無料キャンペーン」を実施しました。開始当初の対象アイテム数を1か月間で約5倍の1,000アイテムまで増加し、消費が低迷した農畜産物の販売拡大を継続的に支援しています。
このような産地支援や旺盛な巣ごもり需要の影響を受けて、キャンペーンの効果もあり、令和2(2020)年のJAタウンの売上高は前年比で約2倍に増加しました。また、サイトの登録会員数も同様に増加し、特に20~30歳代の若い世代の利用が増加しました。JA全農の担当者は、「今後も、継続的なキャンペーンの実施、会員向けの特典の充実等により、コロナをきっかけに会員となった方々が繰り返し利用したくなる仕組みを整備していきたい。」と話しています。
(コロナ禍で食品産業の3割が国内産地との取引を増やしたいと回答)
株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)(以下「公庫」という。)が令和2(2020)年7月に実施した調査では、コロナ禍における国内産地との取引意向について、食品産業の3割が国内産地との取引を増やしたいと回答しています。
その理由としては、「販売先(消費者サイド)の国産志向の高まり等でニーズ増加」が5割と最も多く挙げられています(図表 特-18)。一方で、国内産地との取引の課題としては、「価格が合わない(高い、相場が不安定)」との回答が7割となっています。
(フードバンクを通じて未利用食品を「こども食堂」等に提供)
外食向けに販売予定であった未利用食品を、フードバンク(*1)を通じて「こども食堂」等、食に困っている人へ提供する動きが見られました。
株式会社クラダシでは、在庫を抱える食品メーカー等から協賛価格で商品の提供を受け、手頃な価格で消費者に販売するWebサイトを運営しています。外食向けなどに食品を出荷していた食品事業者が在庫を抱える中、令和3(2021)年2月にフードバンク向けオンラインマッチングシステムを立ち上げました。当システムでは、同社が食品事業者から寄贈品を募り、事前に会員登録したフードバンクが自団体の倉庫の規模や在庫状況を踏まえて寄贈品の引取りを申し込むことができます。寄贈品の配送コストは同社が運営する販売Webサイトの売上げから拠出しており、品代及び配送料ともフードバンク側の負担はゼロとなっています。同月の取組開始から、麺類や菓子類等の寄贈があり、フードバンクで活用されています。
また、神奈川県横浜市(よこはまし)の公益社団法人フードバンクかながわでは、学校給食や各種イベントの中止に伴い、一部の食品で余剰が発生したことや、ひとり親世帯や学生等、食に困っている人の急増に伴う行政、「こども食堂」等の団体からの支援の依頼が増加したことにより、令和2(2020)年度の食品の取扱量は210tと前年度の97tから大幅に増加しました。
*1 用語の解説3(1)を参照
(ロシアなど穀物の輸出国等の19か国が輸出規制を実施)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和2(2020)年度においては、小麦の主要輸出国であるロシア等19か国で輸出規制が行われました(図表 特-19)。
このような中、我が国は、国際的な枠組みを活用し、不当な輸出制限措置の導入回避を含む、新型コロナウイルス感染症による食料安全保障(*1)等の諸課題への対応について国際協調を推進しました。
例えば、令和2(2020)年4月に開催されたG20農業大臣会合では、新型コロナウイルス感染症対策を理由に不必要な輸出規制は厳に行うべきでないこと、同年9月に開催されたG20農業・水大臣会合では、食料や農業のサプライチェーンの強靱(きょうじん)化のために、各国が輸出規制等の措置を行わず、国際的な市場の透明性と信頼性を向上させる必要があること等を発言し、それぞれ、我が国の主張が反映された大臣声明も採択されました。
そのほか、令和2(2020)年11月に開催されたカナダ政府主催WTO(*2)非公式閣僚会合では、輸出規制を真に必要最小限なものに抑制し、国際価格の高騰の防止に向けて議論を継続すべきこと、令和3(2021)年1月に開催されたベルリン農業大臣会合では、疾病による世界の食料供給への影響に備えるため、サプライチェーンの各段階での取組が重要であること、同月に開催されたスイス政府主催WTO非公式閣僚会合では、輸出規制の規律の明確化と透明性の向上を第12回WTO閣僚会議に向けた優先事項の一つとすべきこと等を提案し、各国に協力を呼び掛けました。
輸出規制を実施した国の多くはその後、輸出規制を解除しましたが、引き続き、不当な輸出規制が導入されることのないよう各国の動向を注視していく必要があります。
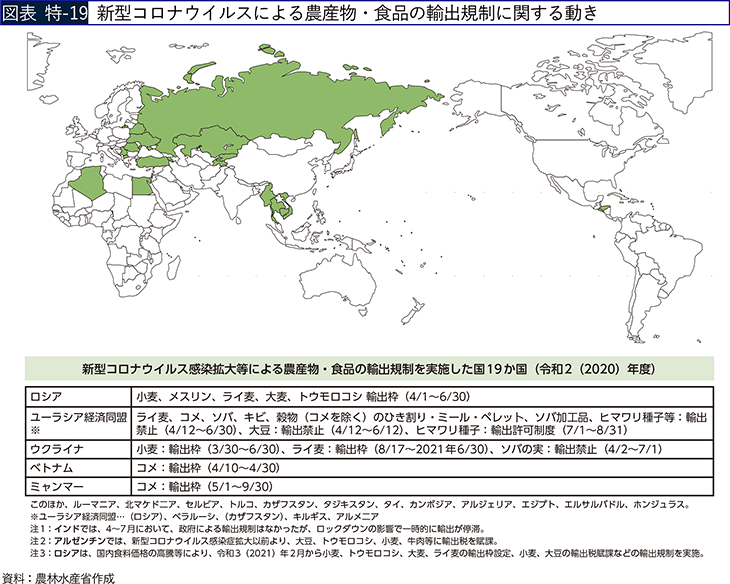
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 用語の解説3(2)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883