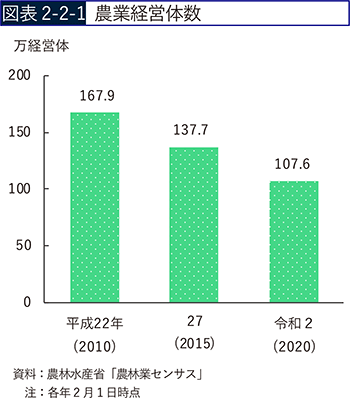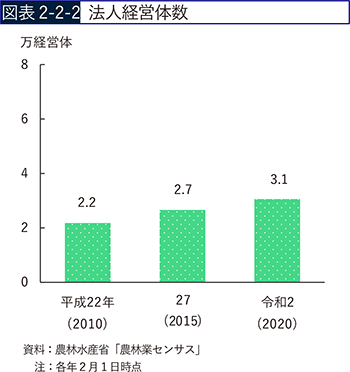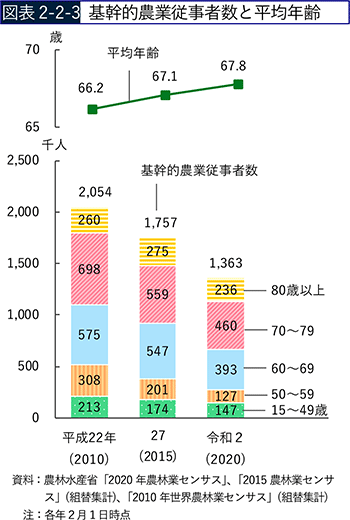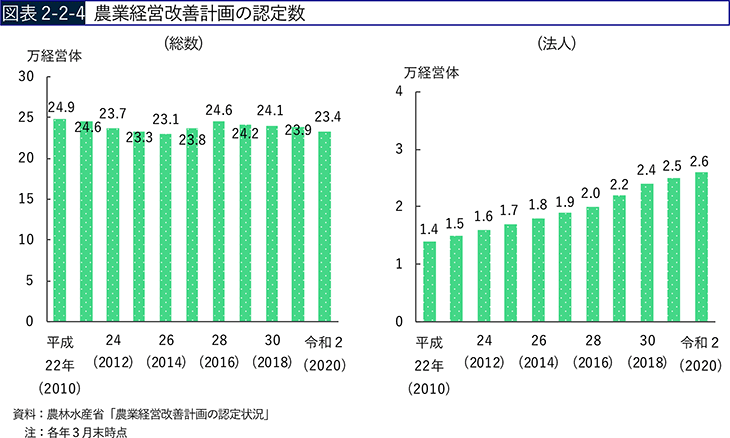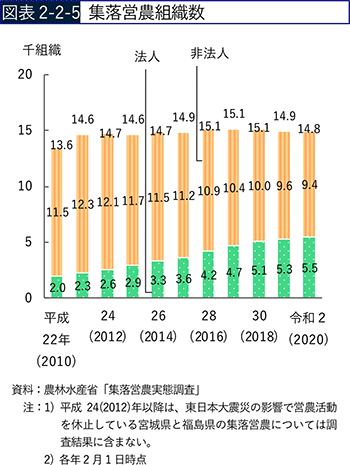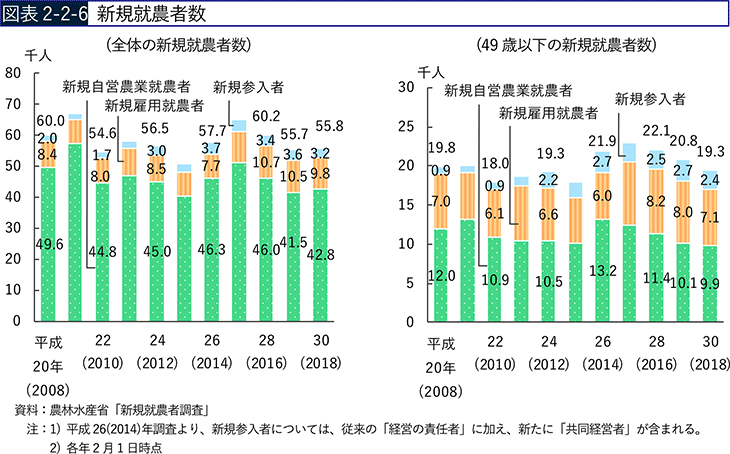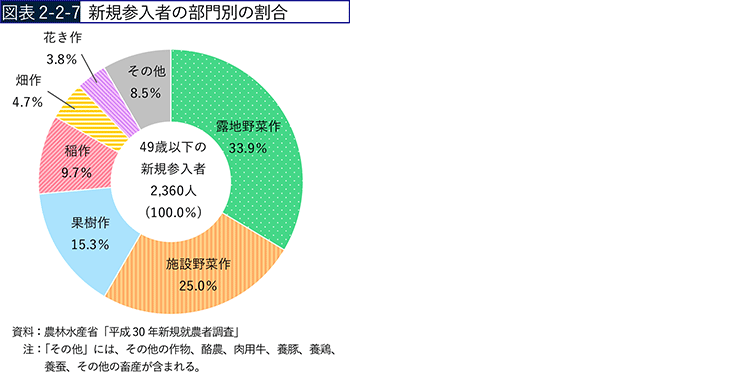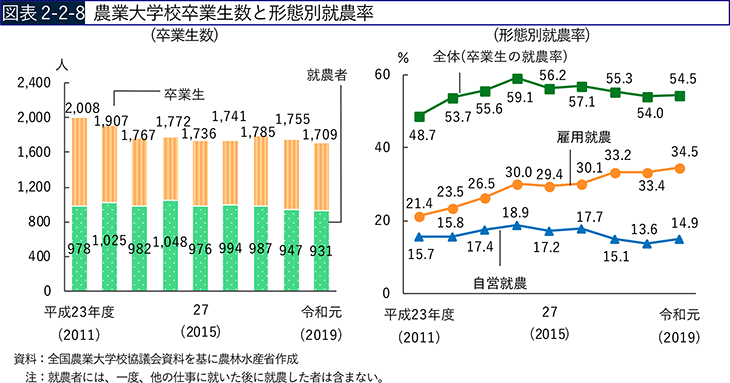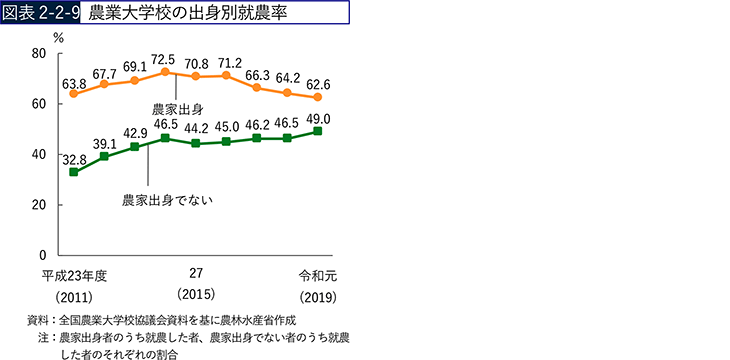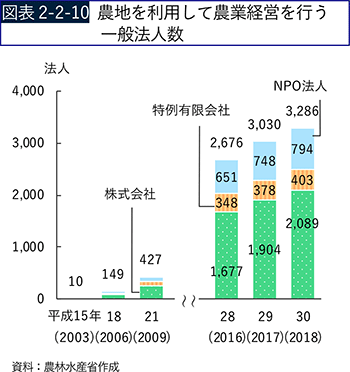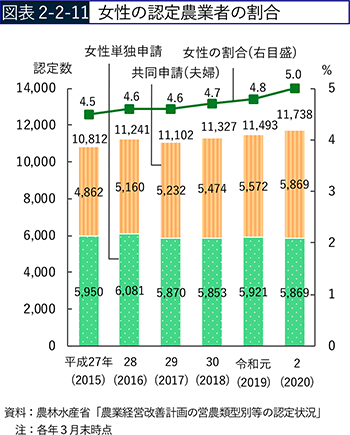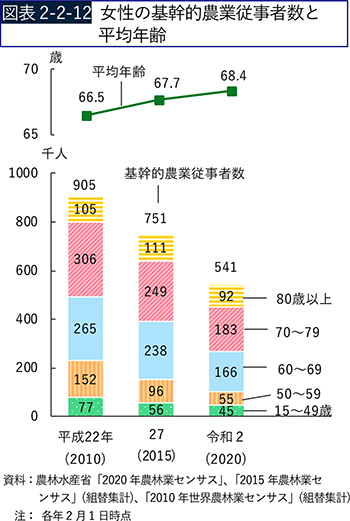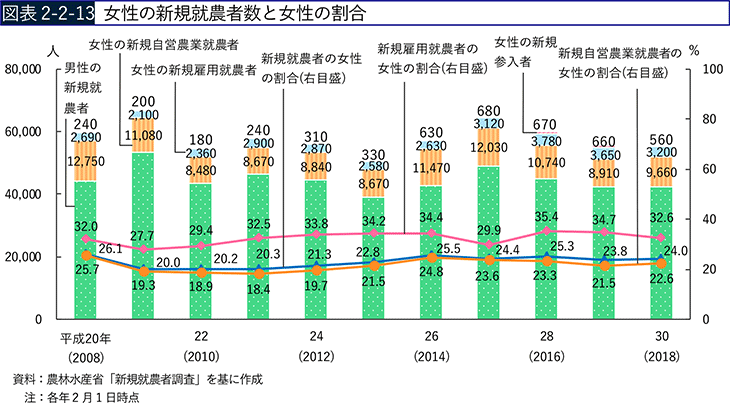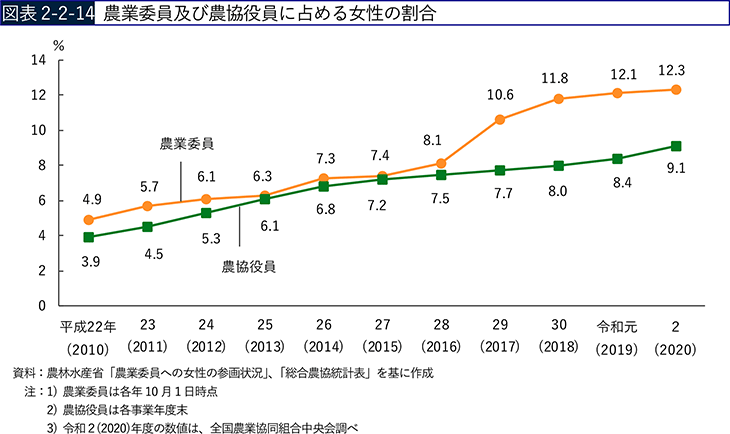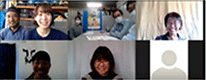第2節 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保
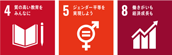
我が国農業が成長産業として持続的に発展していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を目指す経営体等の担い手の育成・確保が重要です。本節では、認定農業者(*1)制度、法人化、新規就農者(*2)、女性農業者等の状況について紹介します。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 用語の解説2(6)を参照
(1)認定農業者制度や法人化等を通じた経営発展の後押し
(農業経営体のうち法人経営体数は増加傾向)
令和2(2020)年における農業経営体(*1)数は、107万6千経営体となり、5年前の137万7千経営体と比べて21.9%減少しています。このうち法人経営体(*2)数については、3万1千経営体で5年前の2万7千経営体と比べて13.3%増加し、農業経営の法人化は着実に進展しています(図表2-2-1、図表2-2-2)。
農業経営の法人化に関しては、経営管理の高度化、安定的な雇用の確保等の利点があることから、都道府県に設置した農業経営相談所において専門家派遣等による相談対応が実施されています。
*1 用語の解説1、2(1)を参照
*2 農業経営体のうち、法人化して事業を行う者(一戸一法人及びサービス事業体を含む。)
(個人経営体の基幹的農業従事者の高齢化、減少が進行)
基幹的農業従事者(*1)の平均年齢は令和2(2020)年に67.8歳となり、10年前の66.2歳から約2歳高齢化が進んでいます。また、令和2(2020)年の基幹的農業従事者数は136万3千人と10年前に比べ33.6%減少し、年齢層別に10年前と比べると49歳以下の青年層で 30.7%減少、59歳以下の層では47.3%減少しています(図表2-2-3)。
*1 用語の解説1、2(5)を参照
(法人の農業経営改善計画の認定数は増加傾向)
農業者が作成した経営発展に向けた計画(農業経営改善計画)の認定数は、令和2(2020)年3月末時点では23万4千経営体となっており、このうち法人のものは一貫して増加し、令和2(2020)年3月末時点で5年前に比べ37.1%増加の2万6千経営体となりました(図表2-2-4)。
認定農業者制度は、農業者が作成した農業経営改善計画を市町村等が認定するもので、認定を受けた農業者(認定農業者)には、計画の実現に向け、農地の集積・集約化(*1)や経営所得安定対策、出資や低利融資等の支援措置が講じられています。
また、近年、農業者の営農活動が広域化していることを踏まえ、令和2(2020)年4月に改正された農業経営基盤強化促進法により、都道府県の区域や市町村の区域を越えた農業経営改善計画の認定が可能となりました。同年度には、5道県20市町村と広域にわたる同計画の認定も出てきており、認定農業者の創意工夫を発揮した経営の展開が期待されています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(集落営農組織の法人化が進行)
集落営農(*1)組織は、農業機械の共同利用や生産・販売の共同化によって農業経営の効率化を目指す個人の担い手が少ない地域において、地域の農業生産を担ってきました。近年では、米、麦、大豆以外の高収益作物等の生産や農産加工品の製造・販売等により収益の向上に取り組む組織が増加しています。また、農産物のブランド化や後継者確保の観点から法人化が進展しており、令和2(2020)年2月時点では5,458法人と5年前の3,622法人から50.7%増加しています(図表2-2-5)。
また、労働力の確保や農業機械の効率的な利用の観点から、複数の集落営農組織が連携して法人を設立する取組や集落営農組織同士が合併する取組も進められています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(2)経営継承や新規就農、人材育成・確保等
(担い手の着実な経営継承の取組を促進)
基幹的農業従事者の高齢化、減少が進む中、地域農業を持続的に発展させていくためには、農地や機械・設備等の有形資産とともに、技術・ノウハウ・人脈等の無形資産を次世代の経営者に引き継いでいく経営継承が重要です。
このため、農林水産省は都道府県に設置した農業経営相談所において税理士や中小企業診断士等の専門家による相談対応を進めるとともに、経営を継承した後継者の経営発展を支援し、担い手の着実な経営継承を促進しています。このほか、農地の贈与税・相続税に関する納税猶予等の各種税制特例や、農業用ハウス、畜舎等の補修等を行い、担い手等に資産を引き継ぐための取組の支援等を実施しています。
(平成30(2018)年の新規就農者数は5.6万人)
平成30(2018)年の新規就農者は5万6千人となっています。このうち、自営農業に就農する新規自営農業就農者(*1)が全体の76.6%を占め4万3千人となり、農業法人等に雇われる形で就農する新規雇用就農者(*2)は9,820人となっています(図表2-2-6)。
将来の担い手として期待される49歳以下の新規就農者は、近年2万人前後で推移し、平成30(2018)年は1万9千人となっています。
また、土地や資金を独自に調達(相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。)し、新たに農業経営を始めた49歳以下の新規参入者(*3)の経営部門を見ると、平成30(2018)年は、露地野菜作が33.9%、施設野菜作が25.0%、果樹作が15.3%と、この3部門で全体の7割以上を占めています(図表2-2-7)。
*1~3 用語の解説2(6)を参照
(青年の新規就農を支援)
青年層の新規就農を促進し、世代間バランスのとれた農業労働力の構造を実現していくことにより地域農業を維持していくため、農林水産省では、平成24(2012)年度から就農準備段階や、経営開始時の支援を行う資金を交付しています。令和元(2019)年度の交付実績は、準備段階の支援が1,756人、経営開始時の支援が1万753人となりました。令和元(2019)年度からは、交付要件を原則44歳以下から49歳以下に拡大しています。
なお、平成29(2017)年度に農業次世代人材投資事業(経営開始型)の交付を終了した者のうち、翌年度末の営農を継続している者の割合は94.8%となっています。
また、平成20(2008)年度から、青年の雇用就農を促進するため、49歳以下(*1)の新規就農者への実践研修、新たな法人設立に向けた研修の実施や多様な人材の確保等を支援する「農の雇用事業」を実施しています。令和元(2019)年度に本事業を活用して研修を実施した青年就農者は、5,319人となりました。
そのほかにも、認定新規就農者(*2)には、農業経営の開始に必要な機械や施設を取得する際の資金を無利子で借入れできる青年等就農資金等の支援策を用意しています。
*1 農の雇用事業における研修生の対象年齢は、平成20(2008)~23(2011)年度は制限なし、平成24(2012)~30(2018)年度は44歳以下、令和元(2019)年度以降は49歳以下となっている。
*2 新たに農業経営を営もうとする青年等で、市町村から青年等就農計画の認定を受けた者
(「農業をはじめる.JP」をスタート)
市町村や農協、農地バンク等地域の関係機関が連携して、就農相談や短期農業体験、実践研修、農地や住宅のあっせん、就農後の農業技術向上や販路確保等に対しての支援を行うことにより、新規就農者の経営発展や地域への定着が進んでいます。
農林水産省は、地域の新規就農者の受入体制を調査・分析し、受入体制の構築を進めるとともに、受入体制等の新規就農に係る情報を一元的に提供するWebサイト等の充実を行っています。
令和2(2020)年12月から本格スタートしたポータルサイト「農業をはじめる.JP」は、農林水産省や新規就農相談センターからの情報だけでなく、関係省庁や地方公共団体、農協等が行っている支援サービス等も紹介するとともに、都道府県・市町村や民間企業、団体等から提供された農業体験や農業研修、就農相談会等に関する情報も掲載しています。
就農に向けた検討段階に応じて必要な情報が見つけられるように、「農業を知る」、「体験する」、「相談する」等、情報を分類ごとに配置しているほか、都道府県・市町村の就農支援策や、全国の新規就農相談センターが収集した求人情報も検索できる機能も設けています。
(事例)地方公共団体・農協・地域農業者等が連携して新規就農者を受入れ(北海道)
北海道最大のトマト産地である平取町(びらとりちょう)では、平取町農業支援センターが平成10(1998)年より、新規に農業参入を希望する研修生を受け入れており、令和2(2020)年までに27人が就農しています。
同センターでは、2年間の農業研修プログラムを設置しています。1年目は地域内の農家の下でトマト栽培技術を学び、2年目は町が所有する研修ハウスで、生産から販売までの全工程を研修生自身が行うなど、実践的なプログラムを通じて生産技術と農業経営のノウハウを習得しています。また、経営開始時にはびらとり農業協同組合が整備したハウスを貸し出すとともに、平取町から施設整備、機械導入の補助を受けることにより、新規就農者の負担低減が図られています。
このほか、びらとり農業協同組合、日高(ひだか)農業改良普及センター等の関係機関に加え、地域農業者による支援グループがあり、農業技術から農村生活全般まで幅広くアドバイスするなど、新規就農者がスムーズに地域に定着できるよう、地域のサポート体制も充実しています。
(農業高校ではGAP認証取得の取組が増加)
農業高校は全国に370校あります。農業高校の生徒は、農業技術や農業経営等について学ぶとともに、農業に関する研究等を生徒が主体的に行う「農業クラブ活動」等、意欲的かつ実践的な学習を行っています。
実践的な学習に関する取組の一つとしては、農業生産工程管理(GAP(*1))の認証取得が挙げられます。GAP認証を取得している農業高校は増加しており、「GAP普及大賞」や「ディスカバー農山漁村(むら)の宝(*2)」等においても、農業高校生のGAPへの取組が評価されています。
また、平成28(2016)年度からは、農業高校生の国際的な視野を広げる取組として、日本とフランスの農業高校間の交流を進めています。新型コロナウイルス感染症により往来による交流が困難なため、令和2(2020)年度に、合同オンライン交流を開催し、両国から計16校が参加しました。
*1 用語の解説3(2)を参照
*2 「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出し、地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信するもの。詳細は第3章第6節を参照
(事例)岐阜県立岐阜農林高等学校がGAP認証の取組を支援(岐阜県)
岐阜県立岐阜農林(ぎふのうりん)高等学校は、GLOBALG.A.P.及びJGAPの認証を取得し、地元農家のGAP認証の取得支援として、地域農家にGAP認証のノウハウの公開を行っています。
このほか、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(*)(以下「東京2020大会」という。)のホストタウンとして、GAP食材を利用したおもてなしの企画等にも取り組んでいます。
これらの取組が評価され、第7回「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」において、グランプリを受賞しました。
グランプリの選定を行う有識者懇談会で委員からは、「若い世代、特に高校生の活躍がこのような賞で評価されるということは待ち望んでいたこと。小中高校生の頃から地域の課題を学ばせて解決させていくような教育が必要だと思う。」といったコメントがありました。
* 令和2(2020)年3月に、大会開催を令和3(2021)年に延期することが決定
(農業大学校卒業生の雇用就農割合が増加)
道府県立農業大学校は42道府県に設置されています。令和元(2019)年度の卒業生1,709人のうち、卒業後、就農した者は931人で、卒業生全体の54.5%となっております。
農業大学校卒業生の就農形態を見ると、雇用就農の割合が増加傾向にあります(図表2-2-8)。また、出身別では、農家出身でない学生の就農割合が増加傾向にあります (図表2-2-9)。
このように、農業大学校は、親元への就農を前提として農家子弟が学ぶ場から、雇用就農希望者や農家出身でない者も学び、雇用就農も含めた就農を目指す場へと、その役割の幅を広げてきています。
また、就職氷河期世代等を含む幅広い世代の就農希望者が、農業大学校において農業技術や農業経営に関する教育を受けられるよう、農林水産省としても、カリキュラムを強化させるための支援を進めています。
(一般法人による農業への参入が増加傾向)
農地を利用して農業経営を行う一般法人数は平成30(2018)年時点で3,286法人となっており、農地のリース方式による参入が自由化された平成21(2009)年以前と比較して、1年当たりの平均参入数は5倍のペースとなっています(図表2-2-10)。参入した一般法人の業務形態別の割合を見ると、農業・畜産業が27%、食品関連産業が20%、建設業が10%、特定非営利活動が8%、製造業が4%となっています。
(3)女性が能力を発揮できる環境整備
(女性の認定農業者は増加傾向)
女性の認定農業者数は平成27(2015)年から令和2(2020)年の5年間で8.6%増加の1万1,738人、全体の認定農業者数に占める女性の割合は0.5ポイント増加の5.0%となりました(図表2-2-11)。夫婦での共同申請が増加していることが一因と考えられます。
(女性の基幹的農業従事者は減少)
女性の基幹的農業従事者数は、平成27(2015)年から令和2(2020)年の5年間で、21万人(28.0%)減少し、54万1千人となりました。全ての年齢階層で減少しており、60~69歳で7万2千人と最も多く減少し、次いで70~79歳で6万7千人減少しました(図表2-2-12)。また、令和2(2020)年の女性の基幹的農業従事者の平均年齢は68.4歳で、5年前に比べて0.7歳高くなっています。
(女性の新規就農者数は1.3万人)
平成30(2018)年における女性の新規就農者数は、1万3,420人(新規自営農業就農者9,660人、新規雇用就農者3,200人、新規参入者560人)、そのうち49歳以下は4,980人となっています。
また、新規就農者に占める女性の割合は、平成26(2014)年以降、25%前後で推移しており、平成30(2018)年は24.0%となっています(図表2-2-13)。新規雇用就農において女性の割合は30%前後で推移しており、平成30(2018)年は32.6%と新規自営農業就農者と比較して女性の割合が高くなっています。
(農業委員、農協役員に占める女性の割合は増加)
平成28(2016)年4月に施行された改正後の農業委員会等に関する法律及び農業協同組合法では、農業委員や農協役員について、年齢や性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない旨の規定が設けられました。農林水産省では、農業委員や農協役員への女性の参画を推進するため、研修会等を実施しています。
農業委員や農協役員に占める女性の割合は、令和2(2020)年では、それぞれ12.3%と9.1%となっており、10年前と比べ農業委員は7.4ポイント、農協役員は5.2ポイント増加しています(図表2-2-14)。
(女性の活躍推進に向け農村における意識改革の必要性等を提言)
農林水産省は、女性農業者が活躍できる環境を整えるための具体的方策を検討するため、令和2(2020)年7月に、学識経験者、女性農業者、ジャーナリスト等から構成する「女性の農業における活躍推進に向けた検討会」を立ち上げ、同年12月に本検討会において報告書が取りまとめられました。
報告書では、農村における意識改革、女性農業者の学び合い・女性グループ活動の活性化、地域をリードする女性農業者の育成や地域農業の方針策定への女性の参画等の実現に向けて、女性農業者向けの会合等における託児サービスの提供、女性農業者向けの一元的な相談窓口の設置、地域での話合いにおける女性参画目標の設定等が具体的対策として提言されました(図表2-2-15)。
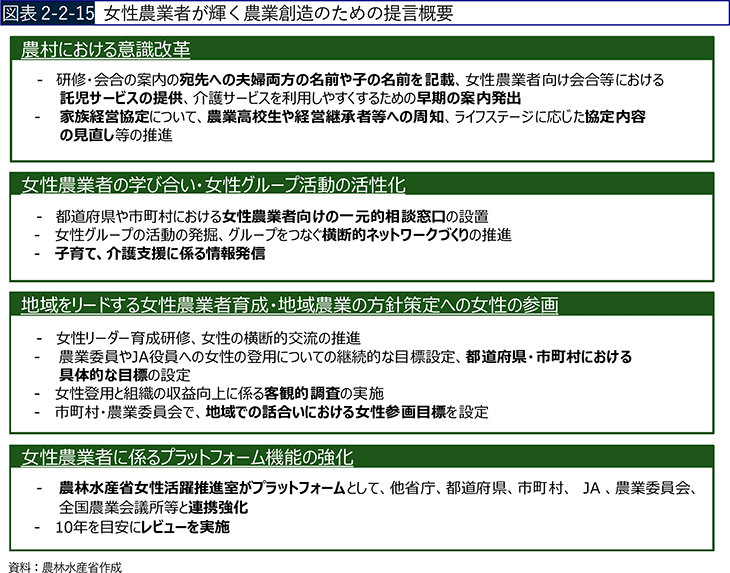
(女性の活躍推進に向け「第5次男女共同参画基本計画」に成果目標を設定)
令和2(2020)年12月に閣議決定した「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」では、第4次男女共同参画基本計画に引き続き、農業委員や農協役員に占める女性の割合、家族経営協定(*1)の締結数について、それぞれ、令和7(2025)年度までに30%、15%、7万件にする成果目標が設定されました。また、女性の農業経営への主体的な関与をより一層推進するため、新たに「認定農業者に占める女性の割合」について、令和7(2025)年度までに5.5%にする成果目標が設定されました。
さらに、土地改良区(*2)についても、新たに「土地改良区 (土地改良区連合を含む。)の理事に占める女性の割合」について、令和7(2025)年度までに10%にする成果目標が設定されました。なお、令和元(2019)年12月に「全国水土里(みどり)ネット女性の会」が発足し、女性役職員の知識・スキルの向上や、女性が土地改良事業の中核を担える環境づくり等の取組が進んでいます。
*1 用語の解説3(1)を参照
*2 農業水利施設等の整備・管理を行う土地改良事業を実施することを目的として、地域の関係農業者により組織された団体。土地改良区地区数は4,403地区(令和2(2020)年3月末時点)
(女性が輝く農業創造に向けて)
農林水産省としては、「女性農業者が輝く農業創造のための提言」を踏まえ、第5次男女共同参画基本計画に基づき、女性が農業・農村で働きやすい環境の整備を進めるとともに、地域をリードする女性農業者を育成し、男女共同参画基本計画の農業委員等の女性割合に係る成果目標達成に向けて、地方公共団体や関係団体と連携して取り組んでいきます。
(事例)地域の女性グループ同士の連携強化へ(しまね農業女子×Happy Farmingいいっちゃない福岡)(島根県、福岡県)
地域をリードする女性農業者を育成するためには、農村において学びの場となるグループを作り、グループ同士のネットワークをつなげることが有効です。
これを踏まえ、農林水産省が事務局を務める農業女子プロジェクト(*1)では、地域版グループ(*2)活動の取組強化及びグループ同士の連携強化を推進しており、現在、7つの地域版グループにおいて、企業や農業大学校等との意見交換や連携活動の実施、勉強会やマルシェを開催するなど、積極的な活動を行っています。
このうち、島根県の「しまね農業女子」は、県内企業、農業大学校との意見交換会や勉強会等を開催しています。また、福岡県の「Happy Farmingいいっちゃない福岡」は「農業の魅力を発信」、「農業者どうしの交流」、「農業以外とのコラボ」を軸に、6次化商品の試食会やマルシェの開催、学校と連携した座談会、圃場(ほじょう)見学会等を実施しています。農業委員を務めるメンバーが、若い世代のメンバーに自らの経験を踏まえたアドバイスや情報提供を行い、グループ内で世代間交流を図っています。
令和2(2020)年10月、お互いに情報交換し、連携することを目的に、「しまね農業女子」と「Happy Farmingいいっちゃない福岡」がリモート座談会を開催しました。座談会では活発な意見交換が行われ、今後は、お互いの取組や地域活性化の成功例の視察、お互いの産地作物を組み合わせたキッチン会の開催、ノウハウを活かし合った共同商品開発等の連携強化に向けた企画の実現を目指す予定です。
*1 女性農業者の知恵を様々な企業の技術・ノウハウ・アイデア等と結び付け、新たな商品やサービス、情報を創造し、社会に広く発信していくためのプロジェクト
*2 メンバーの半数以上を農業女子プロジェクトメンバーが占めることを要件とする農業女子プロジェクト事務局公認のグループ
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883