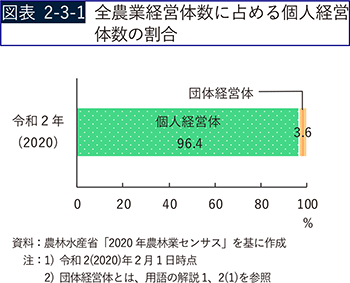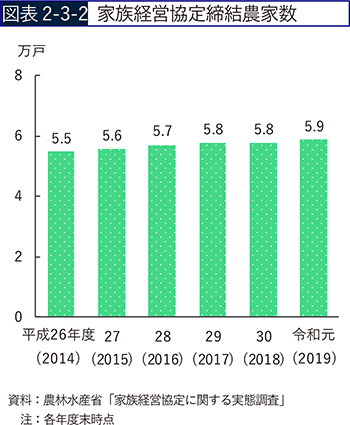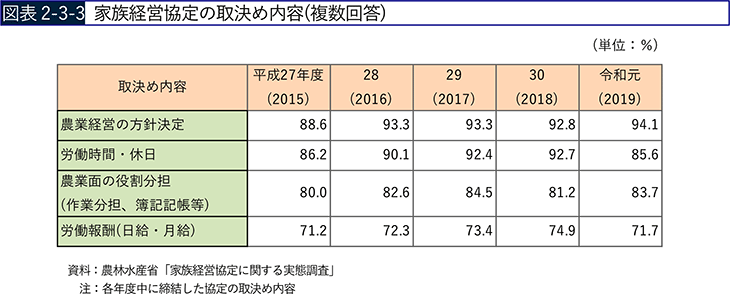第3節 農業現場を支える多様な人材や主体の活躍
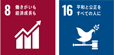
地域の農業生産等を確保し、持続可能なものとしていくためには、中小・家族経営等多様な人材や主体の活躍を促進することも重要です。
本節では、個人経営体(*1)、家族経営協定(*2)、農業の働き方改革等の取組状況について紹介します。
1 用語の解説1、2(1)を参照
2 用語の解説3(1)を参照
(家族経営協定の締結農家数は増加)
生産現場では、中小・家族経営等多様な経営体が産地単位で連携・協働して、農業生産や共同販売を行い、地域社会の維持に重要な役割を果たしています。また、全農業経営体(*1)の大半が個人(世帯)で農業を行う個人経営体となっています(図表2-3-1)。
このような中で、中小・家族経営等の世帯員が意欲とやりがいを持って農業経営に参画するためには、労働時間の管理、休日・休憩の確保、仕事や家事の役割分担について、家族で話し合い、家族経営協定を締結し、ワーク・ライフ・バランスを実現できる環境を整えることが重要です。
令和元(2019)年度末時点の家族経営協定の締結農家数は、前年度に比べ617戸増加の5万9千戸となりました(図表2-3-2)。これは、主業経営体(*2)全体の25.5%を占めています。
締結した協定の内容を見ると、平成27(2015)年度以降、農業経営の方針決定、労働時間・休日については約9割、農業面の役割分担(作業分担・簿記記帳等)については約8割の農家で取決めを行っています(図表2-3-3)。
1、2 用語の解説1、2(1)を参照
(農業の働き方改革に向けた取組が進展)
人材獲得競争が激化する中で、農業を魅力ある職場にすることを通じて現場に必要な人材を確保するため、農林水産省は、農業現場における働きやすい環境づくりに取り組んでいます。
平成29(2017)年度に働き方改革を具体的に進めるためのガイドブックを作成したほか、平成30(2018)年度に女性が働きやすい職場づくりのためのテキスト教材を作成し、令和元(2019)年度にはポータルサイト「Step WAP農業の働き方改革-男女共同参画による経営発展-」を開設するなど様々な支援を行っています。また、令和元(2019)年度から、農業の働き方改革と人手不足解消に取り組む産地を支援する「農業の新しい働き方確立支援」を実施しており、令和2(2020)年度は20地区において、働く環境を整える対策を実施しつつ行う複数産地で連携した労働力確保の取組や、労務管理や労働環境等を学ぶセミナーの実施等を支援しました。
(外国人技能実習制度による外国人材の受入れ)
外国人技能実習制度は、外国人技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした制度であり、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。農業分野においても全国の農業生産現場で多くの外国人技能実習生が受け入れられています。
令和2(2020)年10月末時点での外国人の雇用状況は、農業分野で総数が3万8,064人となっています。このうち、外国人技能実習生が3万3,004人で、前年に比べ1,116人(3.5%)増加しています(*1)。
1 特集(図表 特-36)参照
(特定技能制度による外国人材の受入れ)
深刻化する人手不足に対応するため、平成31(2019)年4月に改正された出入国管理及び難民認定法により、新たな外国人材の受入れのための在留資格である特定技能制度が創設され、農業を含む14の特定産業分野が受入れ対象となり、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れています。
令和2(2020)年12月末時点で、農業分野では2,387人の外国人材がこの制度により働いています。
農林水産省では制度の適切な運営を図るため、受入機関、業界団体、関係省庁で構成する農業特定技能協議会及び運営委員会を設置し、本制度の状況や課題の共有、その解決に向けた意見交換等を行っています。
また、外国人材の受入環境を整備するために、国内外での技能試験の実施や優良事例の収集・周知、制度に関する説明会の開催等を行っています。令和2(2020)年は、6月から順次国内外での農業技能測定試験を実施するとともに、12月に制度に関するオンラインセミナーを開催しました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883