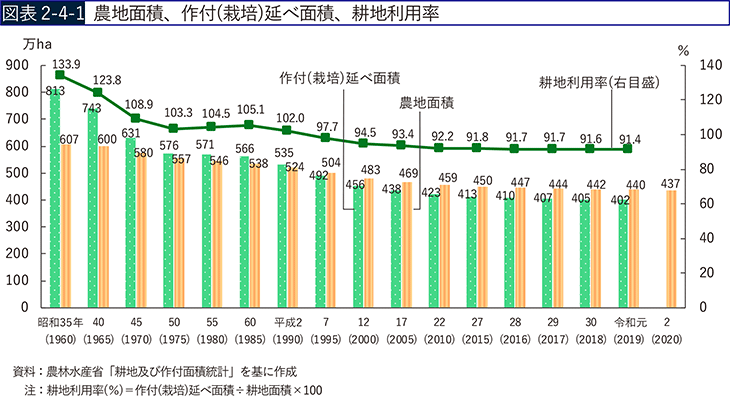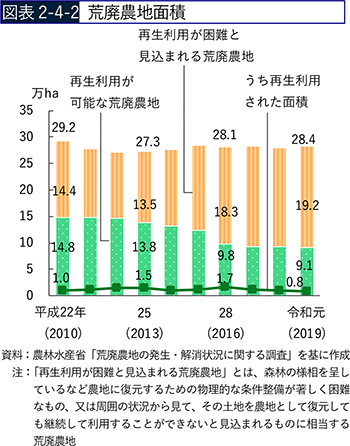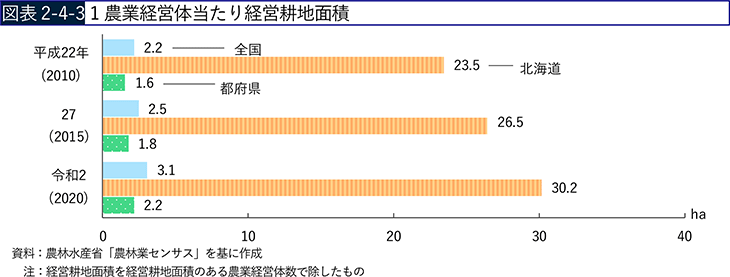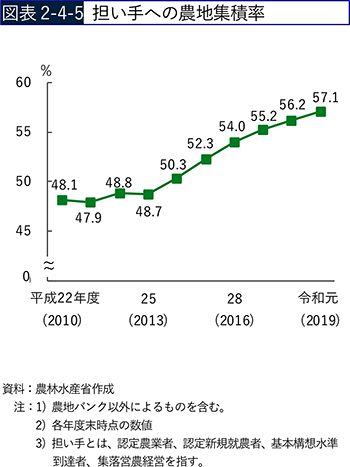第4節 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保

これから10年程度の間に農業者の減少が急速に進むことが見込まれる中で、我が国の農業の生産基盤を維持する観点から、農地の引受け手となる経営体の役割が一層重要となっています。本節では、このような中で進んでいる担い手への農地の集積・集約化(*1)の動きや「人・農地プラン」の実質化に向けた取組等の動きについて紹介します。
1 用語の解説3(1)を参照
(農地面積は緩やかに減少、荒廃農地面積は横ばい)
令和2(2020)年における我が国の農地面積は、荒廃農地(*1)からの再生等による増加があったものの、耕地の荒廃、宅地等への転用、自然災害等による減少を受け、前年に比べて2.5万ha減少の437万haとなりました(図表2-4-1)。作付(栽培)延べ面積も減少傾向が続いており、この結果、令和元(2019)年の耕地利用率は91.4%となっています。
また、令和元(2019)年の荒廃農地の面積は、前年と同水準の28.4万haとなりました。このうち、再生利用が可能なもの(遊休農地(*2))は9.1万ha、再生利用が困難と見込まれるものは19.2万haとなっています(図表2-4-2)。農業従事者(*3)の高齢化や農業者が減少する中、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金等により荒廃農地の発生を防止しつつ、農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)による担い手への農地の集積・集約化や農業委員会による所有者等への利用の働きかけ等により、8千haの農地の再生に努めました。引き続き国内の農業生産に必要な農地を確保するため、地域における積極的な話合いを通じた、担い手への農地の集積・集約化等で荒廃農地の発生を未然に防ぐこと等が重要です。
1、2 用語の解説3(1)を参照
3 用語の解説1、2(5)を参照
(1農業経営体当たりの経営耕地面積は増加)
1農業経営体当たりの経営耕地面積は、令和2(2020)年に3.1haとなり、5年前の2.5haから20.4%増加しています。また、北海道と都府県別に見ると、北海道は26.5haから30.2haと13.9%の増加、都府県は1.8haから2.2haと18.4%の増加となっています(図表2-4-3)。個人経営体(*1)数や基幹的農業従事者(*2)数は5年前と比べて20%程度減少していますが、農地の集積が進んだことで、農業経営体(*3)の総経営耕地面積については、令和2(2020)年は323万haと5年前の345万haから6.3%の減少にとどまっています。
1、3 用語の解説1、2(1)を参照
2 用語の解説1、2(5)を参照
(担い手への農地集積率は年々上昇)
効率的な農業経営を進めていくためには、担い手への農地の集積・集約化を進める必要があります。
このため、平成26(2014)年に発足した農地バンクにおいて、地域内に分散・錯綜(さくそう)する農地を借り受け、まとまった形で担い手へ再配分し、農地の集積・集約化を実現する農地中間管理事業を行っています。
この結果、農地の大区画化が図られ、担い手の労働時間が大幅に短縮された地区や、新規就農モデル団地を設定し、新規就農を促進した地区、集落の農地を一括して農地バンクに預けて担い手に集約した地区等、全国で様々な優良な事例が見られるようになっています(図表2-4-4)。

農地バンクによる取組もあり、近年、担い手への農地集積率は上昇しており、令和元(2019)年度末時点で57.1%になりました(図表2-4-5)。これを地域別に見ると、農業経営体の多くが担い手である北海道では集積率が9割を超えるほか、水田が多く、基盤整備が進んでおり、集落営農(*1)の取組が盛んである東北、北陸では集積率が高い傾向にあります。一方で、大都市圏を抱える地域(関東、東海、近畿)や中山間地を多く抱える地域(近畿、中国四国)の集積率は低い傾向にあります(図表2-4-6)。
1 用語の解説3(1)を参照
(「人・農地プラン」の実質化に向けた取組が全国で進行)
担い手への農地の集積率については、令和5(2023)年度までに8割に引き上げる目標が設定されています。このような中で、目標の達成に向けては、「人・農地プラン」の実質化(*1)、農地中間管理事業の手続の簡素化と農地の集積・集約化の支援体制の一体化を内容とする改正農地バンク法(*2)に基づき、今後は実質化された「人・農地プラン」を核に担い手への農地の集積・集約化を一層加速化させていくこととしています。
これまで、農業者の話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り方等を明確化する地域農業の将来の設計図として「人・農地プラン」の作成を推進してきましたが、この中には地域の徹底した話合いに基づいて作成されているものがある一方、地域の話合いに基づくとは言い難いものもありました。
このため、農林水産省では担い手への農地の集積・集約化を加速させる観点から、真に地域の話合いに基づく「人・農地プラン」の実質化の取組を、令和2(2020)年度に全国で集中的に推進することとしました。「人・農地プラン」の実質化に際しては、5年後から10年後の農地利用についてアンケート調査を行い、農業者の年齢、後継者の有無等を地図により「見える化」し、 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針を作成することとしています(図表2-4-7)。

令和元(2019)年度では、既に「人・農地プラン」が実質化されている地区が1万8,826地区、実質化に取り組んでいる地区が4万8,790地区となりました。今後は、実質化されたプランを核に担い手への農地の集積・集約化の具体化を進めていくこととしています。
1 農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を「見える化」した地図を用いて、地域を支える農業者が話し合い、当該地域の将来の農地利用を担う経営体の在り方を決めていく取組
2 正式名称は「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」
(事例)「人・農地プラン」を契機とした担い手への農地の集約(滋賀県)

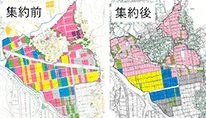
農地中間管理事業による集約化
資料:滋賀県米原市
滋賀県米原市大野木(まいばらしおおのぎ)地区は、水稲作が中心の地域です。
従来は、農業委員会を通じた農地所有者と耕作者間の個別の貸借契約等により農地の集積を進めていましたが、農地が分散し、作業性に課題を抱えていました。
「人・農地プラン」の取組として、地区内の農地所有者に対してアンケートを実施し、農地の集約化についての意向を確認した上で、集落外からの入作者を含む耕作者が話合いを重ね、耕作者ごとに農地の集約を希望するエリアを定めた地図を作成しました。
この地図に基づいた農地の集約を図るため、さらに地区内の農地の賃料の統一も実施しました。これにより借受農地の交換が円滑に進み、地区内の9割の農地について農地中間管理事業を活用し、4人の担い手に集約することができました。
(農地として維持困難な土地を抱える地域での持続的な土地利用の実現に向けた検討)
人口減少や農業の担い手不足等の課題に対処しつつ、食料の安定供給を脅かすリスクを軽減していくことが必要である一方、中山間地域を中心として、担い手への農地の集積・集約化、新規就農、スマート農業の普及等の政策努力を払ってもなお農地として維持することが困難な土地が増加することが懸念されます。
このため、農林水産省は、令和2(2020)年5月に「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」を立ち上げました。同検討会では、中山間地域を中心とした地域において、地域の話合いを通じて、食料供給基盤としての機能は極力維持しつつ、地域の特性に応じた持続可能な土地利用への転換を図るため、(1)放牧等、農地の粗放的な利用、(2)鳥獣緩衝帯等、非常時に農業生産を再開することが容易な土地としての利用、(3)森林としての利用への転換等のための仕組みについて検討し、令和3(2021)年6月までに取りまとめることとしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883