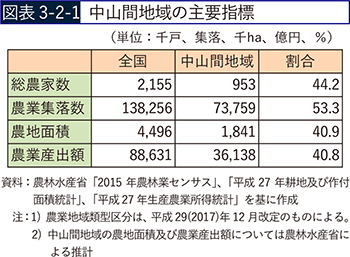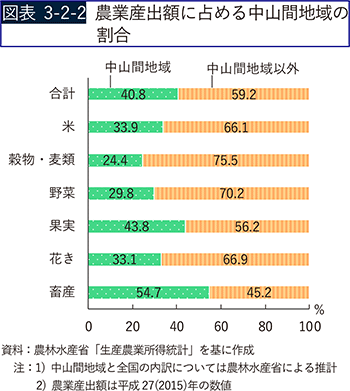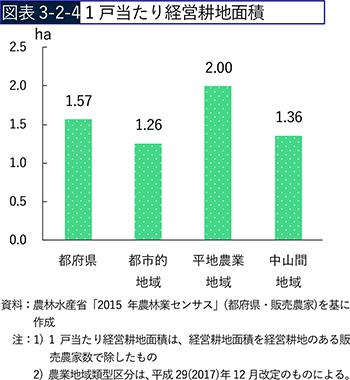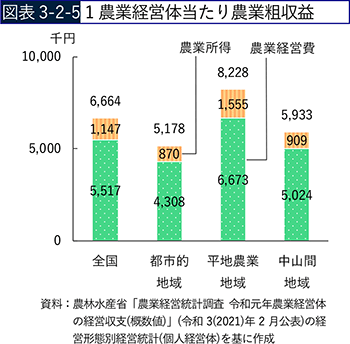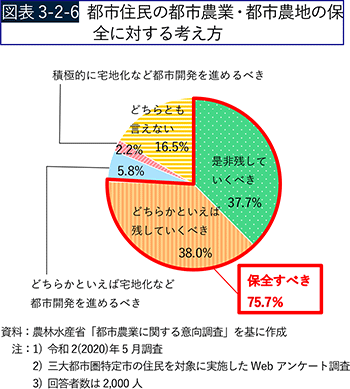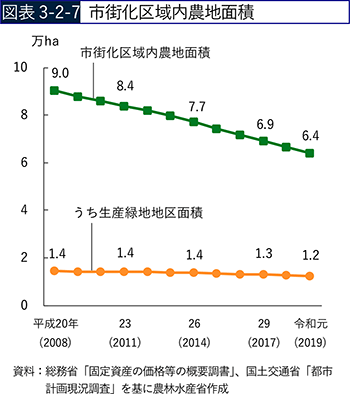第2節 地域の特性を活かした複合経営等の多様な農業経営等の推進
農村、特に中山間地域(*1)では、米、野菜、果樹作等のほか、畜産、林業にも取り組む複合経営を進め、所得と雇用機会を確保する必要があります。一方で、都市農業は、農業体験等において重要な役割を担っています。本節では、地域の特性を活かした多様な農業経営等の取組について紹介します。
*1 用語の解説2(7)を参照
(1)中山間地域の農業の振興
(中山間地域の総農家数、農地面積、農業産出額は全国の約4割)
中山間地域は、総農家(*1)数、農地面積、農業産出額の約4割を占めるなど、食料生産を担うとともに、豊かな自然や景観の形成・保全といった多面的機能の発揮の面で重要な役割を担っています(図表3-2-1)。
*1 用語の解説2(3)を参照
(我が国の果実の4割以上、畜産の5割以上は中山間地域で生産)
農業産出額に占める中山間地域の割合を品目別にみると、平成27(2015)年は米や穀物・麦類の割合が2~3割程度の一方、果実では4割以上、畜産では5割以上を占め全品目の平均値である約4割より高くなっています(図表3-2-2)。これは、果樹や畜産は地形上の制約が比較的小さいためであると考えられます。
(中山間地域の1農業経営体当たりの農業所得は全国平均の8割程度で推移)
1農業経営体(*1)当たりの農業所得(*2)を農業地域類型別に比較すると、中山間地域の農業所得はおおむね全国平均の8割程度で推移しており、令和元(2019)年では134万円となっています(図表3-2-3)。中山間地域では、平地農業地域(*3)と比較して経営耕地面積が小さく、農業粗収益が低いことが原因の一つとして考えられます(図表3-2-4、図表3-2-5)。
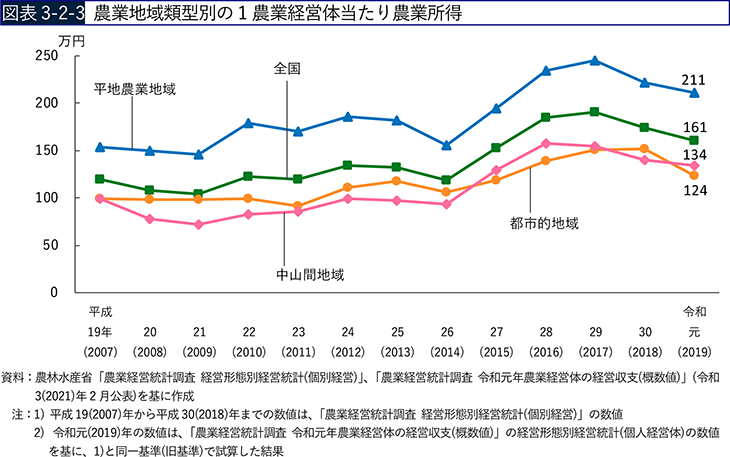
データ(エクセル:144KB / CSV:2KB)
*1 用語の解説1、2(1)を参照
*2 用語の解説2(4)を参照
*3 用語の解説2(7)を参照
(中山間地域等の特性を活かした複合経営の全国的な展開を推進)
中山間地域等を今後も安定的に維持していくためには、小規模農家を始めとした多様な経営体が、それぞれにふさわしい農業経営を実現する必要があります。
このため、農林水産省は、令和3(2021)年3月、地域特性を活かした農業、畜産、林業も含めた多様な経営の組合せにより所得を確保する複合経営モデルを提示しました。このモデルでは、近年、市場性があると考えられる新たな作物や最新の技術も加味しながら、新規就農者(*1)等の地域内外の新たな人材が取り組み得る「入門段階」の小規模経営(農業所得200万円程度)と、家族で暮らせる「複合経営のモデル」(農業所得400万円程度)を一体的に示すとともに、各モデルによる多様なライフスタイルを実現するための考え方を示しました。
今後、中山間地域における小規模農家を始めとした多様な経営体の所得確保や新たな人材の裾野の拡大に向け、優良事例の全国的な展開を推進していくこととしています。
*1 用語の解説2(6)を参照
(2)多様な機能を有する都市農業の推進
(都市農業・都市農地を残していくべきとの回答が増加)
都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、農業体験・学習の場や災害時の避難場所の提供、住民生活への安らぎの提供等の多様な機能を有しています。
都市農業が主に行われている市街化区域(*1)内の農地が我が国の農地全体に占める割合は2%と低いものの、農業経営体数と農業産出額ではそれぞれ全体の10%と7%を占めています(*2)。
都市農業に対する都市住民の評価が高まってきた中で、平成27(2015)年4月には都市農業振興基本法が施行され、同法に基づき策定された都市農業振興基本計画において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換されました。
農林水産省が令和2(2020)年5月に実施した都市住民を対象とした調査では、都市農業の多様な役割が評価され、都市農業・都市農地を残していくべきとの回答が前年と比べて4.7ポイント増加し75.7%となりました(図表3-2-6)。
*1 都市計画法に基づき、既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域
*2 農林水産省「2015農林業センサス」、総務省「固定資産の価格等の概要調書(平成30年)」等を基に農林水産省が作成
(都市農地の貸借が進展)
生産緑地制度は、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内の農地の計画的な保全を図るものです。市街化区域内の農地面積が一貫して減少する中、生産緑地地区の農地面積はほぼ横ばいで推移しています(図表3-2-7)。生産緑地地区内の農地の所有者は自らによる耕作を要件に税制上の軽減措置を受けることができましたが、農業者の減少や高齢化が進行する中、都市の農地の有効な活用に向けて、平成30(2018)年9月に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が施行され、都市農地の所有者が、意欲ある農業者等に安心して農地を貸付けすることができるようになりました。
また、これまでは、企業、NPO(*1)等が都市農地において市民農園を開設する場合には、地方公共団体等を経由して農地を借り受ける必要がありましたが、同法により都市農地所有者から直接農地を借り受けることができるようになりました。令和元(2019)年度末時点の制度の活用状況を見ると、貸借による耕作の事業に関する計画については、前年度から97件増加し、9都府県で計119件、22万2千m2の農地について認定が行われ、市民農園の開設については35件増加し、9都府県で計55件、8万4千m2の農地の承認が行われ、合わせて30万6千m2の農地について認定・承認されています。
*1 用語の解説3(2)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883