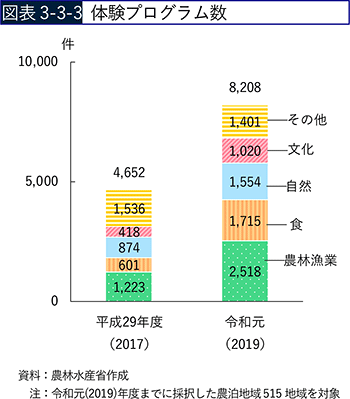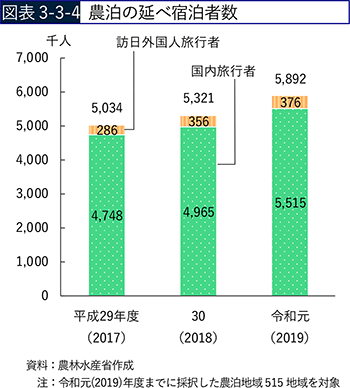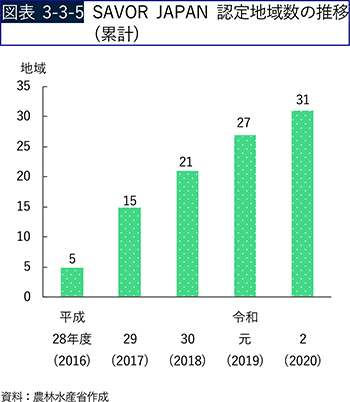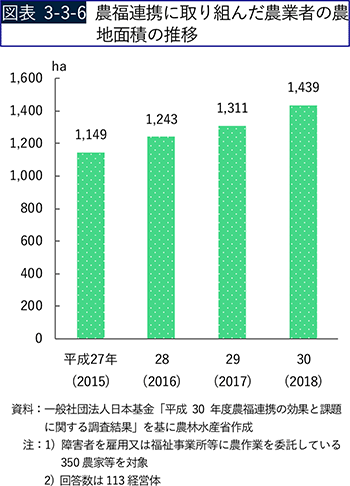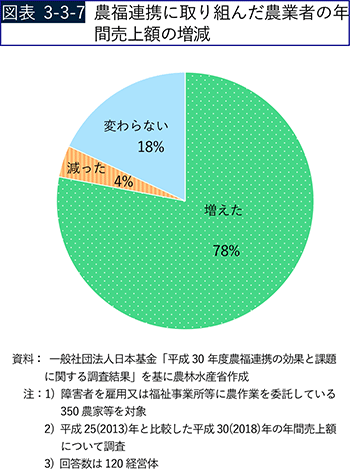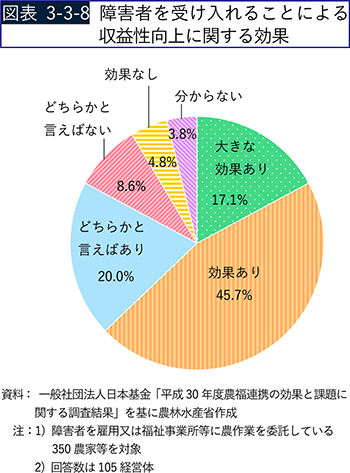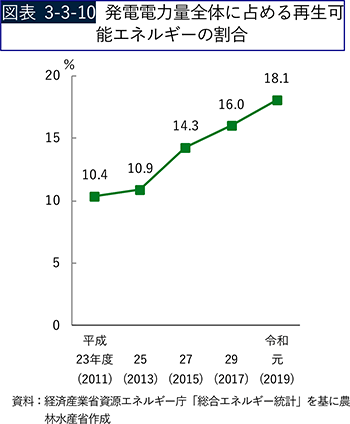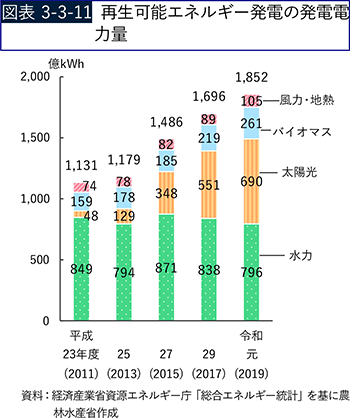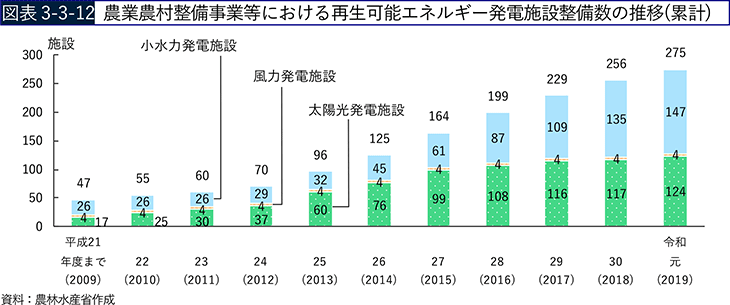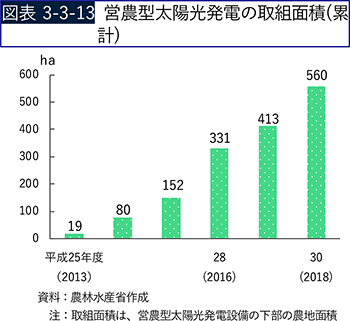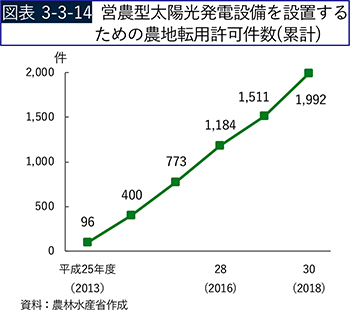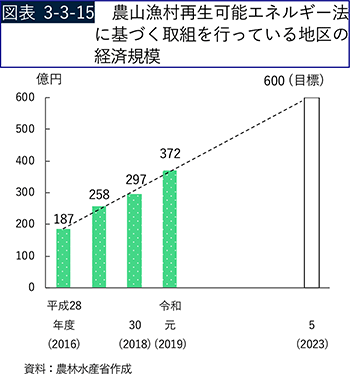第3節 農泊、農福連携、再生可能エネルギー等の農村発イノベーションの推進
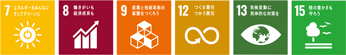
農村の地域資源を他分野と組み合わせ新たな価値を創出する取組「農村発イノベーション」が進みつつあり、地域資源を活用した食事や体験・交流プログラムを提供する農泊や障害者による農業分野での活躍を通じて社会参画を実現する農福連携、太陽光発電等の再生可能エネルギーの活用等の動きが広がっています。
本節では、このような地域資源を活用した農村の所得、雇用機会を確保するための様々な取組について紹介します。
(1)農村発イノベーションをはじめとした地域資源の高付加価値化の推進
(農村発イノベーションを推進)
所得と雇用機会を確保し、農村に人を呼び込むため、活用可能な地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる「農村発イノベーション」を実現し、新たなビジネス展開を促進することが必要です。このため、農林水産省は、令和2(2020)年5月から「新しい農村政策の在り方に関する検討会」を立ち上げ、農村発イノベーションの推進を通じた所得確保手段の多角化について検討を行っており、令和3(2021)年6月までに取りまとめることとしています。
検討会での議論を踏まえ、ポストコロナ時代を見据えて、農村で農業経営と農村発イノベーションに取り組む世帯や事業体を育成するのに不可欠な資金、情報等の支援を今後も充実させていくこととしています。
なお、令和元(2019)年度からの取組として、農山漁村で活動する起業者等が情報交換を通じてビジネスプランを磨き上げることができるプラットフォーム(INACOME(イナカム))の運営を実施しており、農村発イノベーションの取組を支援しています(図表3-3-1)。
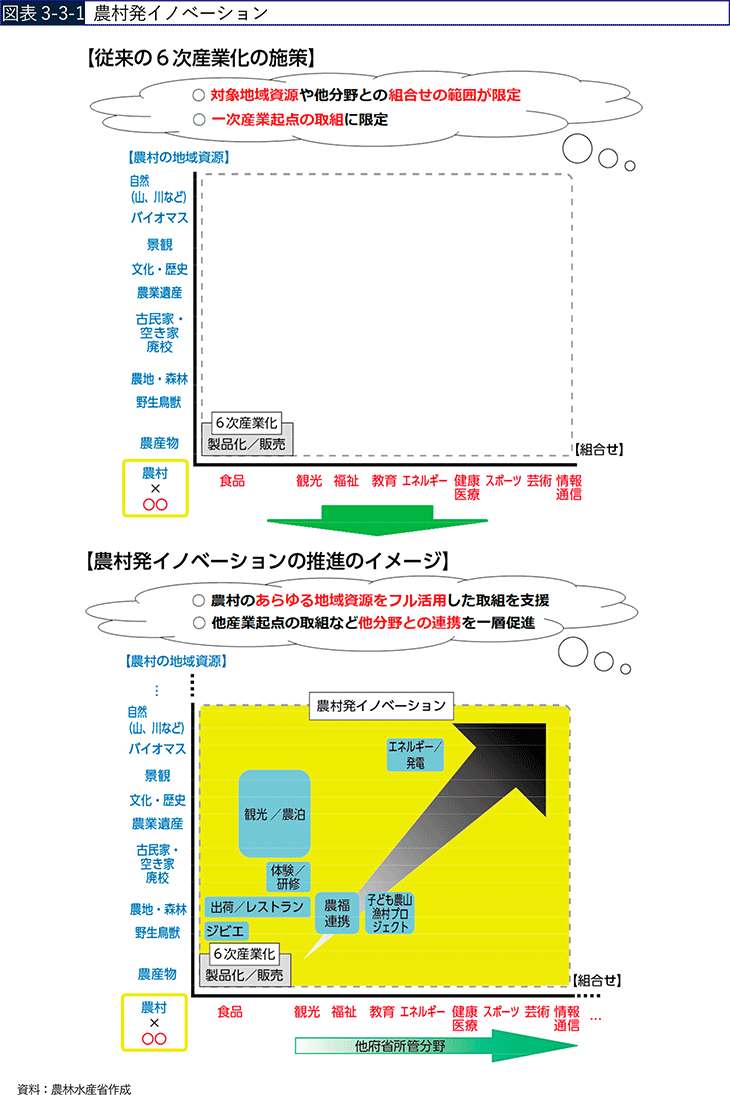
(山村地域の特性を活かした産業の育成による雇用と所得の増大)
農林水産省は、平成27(2015)年度から、振興山村(*1)の山菜やくり、ゆず、木工品等の特色ある地域資源を活かした新商品の開発や販路開拓等を支援し、地域の雇用と所得の増大を図っています。令和2(2020)年度は90地区で支援を行いました。
*1 山村振興法に基づき指定された地域
(事例)特用作物・紫草を活用し、化粧品を開発、販売(滋賀県)
振興山村に指定されている滋賀県東近江市奥永源寺(ひがしおうみしおくえいげんじ)地区では、古くから染料、生薬として用いられており、市の花にも選定されている絶滅危惧種「紫草(むらさき)」の根「紫根(しこん)」を活用した山村の活性化に取り組んでいます。
地域資源の活用に向けた取組として、紫草の栽培に適した風土や耕作放棄地の再生に着目し、平成27(2015)年度から山村活性化支援交付金事業により、耕作放棄地を利用して無農薬・有機栽培にこだわった紫草の栽培に取り組みました。さらに、栽培した紫草の商品化に取り組み、100%植物性由来の化粧品である、紫根を主原料としたオーガニックシコンコスメ「MURASAKIno ORGANIC」を開発しました。
平成29(2017)年には、同市の地域おこし協力隊が中心となって地元住民や市民から出資金を募り、「株式会社みんなの奥永源寺(おくえいげんじ)」を設立し、平成31(2019)年2月に東京ビッグサイトで開催された「山の恵みマッチング商談会」でミニブースを出展するなど、シコンコスメの販路拡大に取り組んだ結果、無農薬・有機栽培等の商品特性が評価され、バイヤーとの商談が成立しました。
シコンコスメの出荷量は2万本を超え、販売額は山の恵みマッチング商談会の前と比べ、令和2(2020)年9月時点で約10倍に増加しました。
(2)農泊の推進
(ビジネスとして実施できる体制を持った農泊地域)
農泊は、農山漁村において農家民宿や古民家等に滞在し、我が国ならではの伝統的な生活体験や農村の人々との交流を通じて、その土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行のことです。
農林水産省は、令和2(2020)年度末時点で、全国554地域を農泊推進対策地域として採択し、宿泊、食事、体験に関するコンテンツ開発等、農泊をビジネスとして実施できる体制構築等の取組を支援しています(図表3-3-2)。
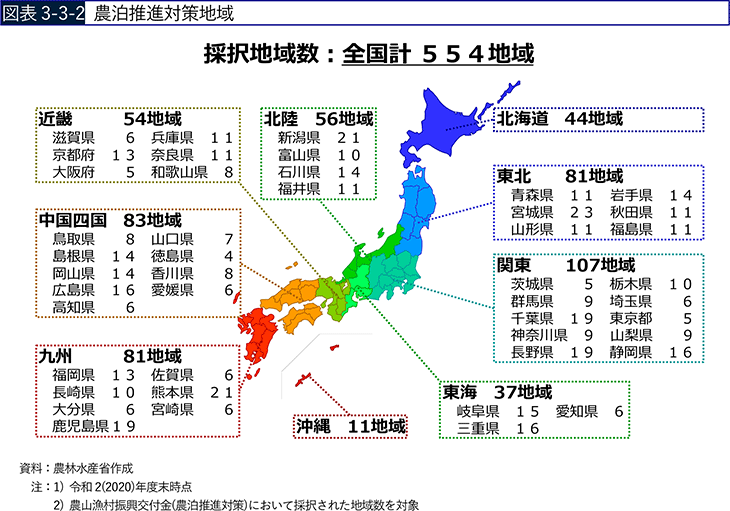
(農泊の体制整備は進みつつあるものの、一層の環境整備が必要)
農林水産省は、平成29(2017)年度から、宿泊、食事、農林漁業体験等のプログラム(以下「体験プログラム」という。)を提供する、地域の多様な関係者を構成員とする協議会や、農泊実施の中心となる役割を担う法人の設立等の体制整備を進めています。
その結果、令和元(2019)年度までに採択された515地域では、平成29(2017)年度末では約4,700件だった体験プログラム数が、令和元(2019)年度末時点で、約8,200件に増加しました(図表3-3-3)。また、延べ宿泊者数は平成29(2017)年度の約503万人から約589万人へと増加し、そのうち、訪日外国人旅行者の延べ宿泊者数は約38万人に増加しました(図表3-3-4)。
農泊地域における利用者ニーズに更にきめ細かく対応するため、農泊地域に対して、ジビエ料理等の食事メニューや農業、文化、自然等を体験するプログラムの開発、古民家等を活用した宿泊施設等の整備を支援するほか、訪日外国人旅行者の受入れに向けた環境整備のため、無線LANの整備や外国語Webサイト等の多言語対応等の支援を引き続き行っています。
(事例)地域資源を活用した農泊の取組(北海道)
北海道余市町(よいちちょう)は札幌市(さっぽろし)から日帰り圏にあり、平成27(2015)年に北海道版構造改革・地域再生特区に認定されたことをきっかけに、農家民宿事業への取組を本格的に開始しました。
余市町は、北海道における果樹の主要生産地であるとともに、ウイスキーやワイン産業も盛んであり、ニセコ積丹小樽(しゃこたんおたる)海岸国定公園の景観や遺跡等も豊富であるなど宿泊事業に取り組む好条件を備えています。
農家民宿事業では、消費者がリンゴ農家による民宿に宿泊し、果樹栽培の歴史を学ぶことができるとともに、スノーシューを使っての果樹園散策等を行うことができるほか、北海道産の木材や古材を使った一棟貸の宿泊施設で地元住民との交流を楽しむことができるなど、個性豊かな宿泊プランを販売しています。また、農業も題材に盛り込んだ忍者エンターテイナー「嵐嶄(らんざん)」と手裏剣や忍者刀を使った体験は、訪日外国人旅行者に人気のコンテンツです。
一般社団法人余市(よいち)観光協会では、町内の宿泊施設の予約状況をオンラインで一元的に管理するなど、効率的に事業に取り組んでいます。
(「SAVOR JAPAN」認定地域に4地域を追加)
農林水産省は、平成28(2016)年度から地域の食・食文化や農林水産業を核に訪日外国人旅行者を中心とした観光客を誘致する重点地域を「農泊 食文化海外発信地域(SAVOR JAPAN(セイバージャパン))」に認定する取組を行っています。令和2(2020)年度に認定された地域は、前年度から4地域増え、全国で31地域となりました(図表3-3-5)。
農林水産省では、認定地域を対象に、専門家の派遣による地域の食・食文化体験のコンテンツ造成と磨き上げを行うとともにオールジャパンでのブランド化と一元的な情報発信を行い、訪日外国人の誘客の強化に取り組んでいます。
(3)農福連携の推進
(農福連携により収益が向上)
障害者の農業分野での雇用・就労を推進する農福連携は、農業、福祉両分野にとって利点があるものとして各地で取組が進んでいます。
一般社団法人日本基金(にっぽんききん)の調査によれば、農福連携の取組について、農地面積ベースでみると平成27(2015)年から平成30(2018)年までの3年間で25%増加しています(図表3-3-6)。また、農福連携に取り組んだ農業者の78%が、平成25(2013)年と比較し、平成30(2018)年には年間売上額が増加したと回答しています(図表3-3-7)。障害者を受け入れた農業者の83%が収益性向上に「効果がある」と回答しており、農福連携に取り組む多くの農業者が農業分野へのメリットを実感しています(図表3-3-8)。
(多様な関係者による国民的運動を展開するとともに専門人材を育成)
令和元(2019)年6月に政府の農福連携等推進会議にて決定した農福連携等推進ビジョンに基づき、令和2(2020)年3月、農林水産省は、関係省、関係団体等と共に、農福連携等応援コンソーシアムを設立しました。本コンソーシアムでは、農福連携に関する優良事例の表彰と全国的な展開、普及啓発のためのイベントの開催、連携・交流の促進、情報提供等を行うこととしています。その取組の一環として、令和3(2021)年3月、農福連携に取り組む団体、企業、個人等の優良事例16団体を「ノウフク・アワード」として表彰しました(図表3-3-9)。
また、農業者、障害者、障害者就労施設の指導員の間に立ち、障害者の農業分野での定着を支援する専門人材を育成するため、農林水産省は、令和2(2020)年度には、障害特性に対応した農作業の流れ・農作業方法や農作業における作業の細分化、割当ての方法等を学ぶ育成研修を農林水産研修所つくば館水戸ほ場で実施しました。
(事例)農業と福祉で地域を活性化(北海道)
北海道月形町(つきがたちょう)の社会福祉法人雪(ゆき)の聖母園(せいぼえん)(以下、「雪の聖母園」という。)は、昭和39(1964)年、障害のある子供の入所施設として開設し、敷地内で自分たちの食料とするために農産物を生産、平成7(1995)年に成人の施設へ移行するとともに、徐々に生産量の拡大を行いながら、販売への道筋を模索してきました。
平成18(2006)年からは、町内の農業者と連携し、都市部への出荷を開始しました。また、平成25(2013)年から、離農した町内の農業者を農福連携の専属支援員として雇用し、収量の増加に向けて、障害者へ作業手順の説明等を行っています。
現在は、雪の聖母園が所有する1haの農地で、10名程度の障害者がジャガイモ、大根、カボチャ、ミニトマト等の生産に取り組み、播種、施肥、除草、収穫、出荷準備等のほぼ全ての工程を、障害者の得意不得意に応じて役割分担を決め、作業を行っています。
農産物の月平均の売上高は、平成25(2013)年は17万円でしたが、農福連携の取組を進めるにつれ年々増加し、令和2(2020)年では25万円となりました。この結果、障害者の月平均の工賃は平成25(2013)年度の約4千円から令和元(2019)年度には約1万3千円に増加しました。
また、地域や近郊で催事が開かれる際には、障害者自ら農産品を販売しており、顧客の反応を感じ取ることにより、作業へのモチベーションにつながっています。
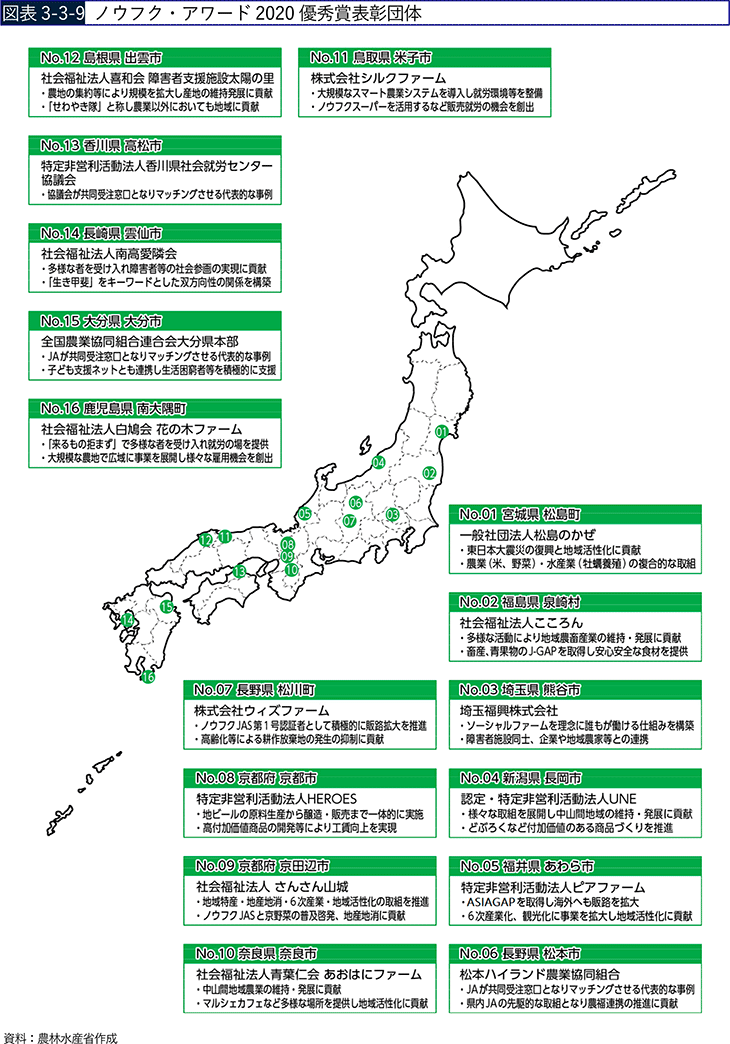
(4)再生可能エネルギーの活用
(再生可能エネルギー発電の割合は18%に上昇)
長期エネルギー需給見通しにおいては、総発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合を令和12(2030)年度に22~24%にする見通しが示されています。令和元(2019)年度の再生可能エネルギーの割合は18.1%となり、その内訳は、水力発電が796億kWh、太陽光発電が690億kWh、バイオマス(*1)発電が261億kWh、風力・地熱発電が105億kWhとなっています(図表3-3-10、図表3-3-11)。特に太陽光が占める割合は平成23(2011)年度は発電全体の0.4%でしたが、令和元(2019)年度では6.7%へ大きく増加しました。
*1 用語の解説3(1)を参照
(農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成した市町村は68に増加)
再生可能エネルギーの導入に当たっては、農山漁村が持つ食料供給機能や国土保全機能の発揮に支障を来さないよう、農林地等の利用調整を適切に行い、地域の農林漁業の健全な発展や地域の活性化につながる取組とする必要があります。
こうしたことから、農林水産省では、市町村、発電事業者、農業者等の地域の関係者が主体となって協議会を設立し、地域主導で農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を行う農山漁村再生可能エネルギー法(*1)に基づく取組を促進するとともに、営農を適切に継続しながら上部で太陽光発電を行う営農型太陽光発電を推進しており、令和2(2020)年度には、このうち営農型太陽光発電について、荒廃農地を再生利用する場合の要件緩和を講ずることとしたところです。
令和元(2019)年度末時点で、農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成し、再生可能エネルギーの導入に取り組む市町村は、前年度に比べ7市町増加の68市町村となりました。
*1 正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
(農業水利施設等を活用した発電により農業者の負担軽減を推進)
農業用ダムや水路を活用した小水力発電施設、農業水利施設(*1)の敷地等を活用した太陽光発電施設及び風力発電施設については、昭和58(1983)年度から農業農村整備事業等により、国、地方公共団体、土地改良区が実施主体となって整備を進めています。令和元(2019)年度末時点で、小水力発電施設は147施設、太陽光発電施設は124施設、風力発電施設は4施設を整備しました(図表3-3-12)。これらの発電により得られた電気を自らの農業水利施設等で利用することで、施設の運転に要する電気代が節約でき、農業者の負担軽減にもつながっています。
*1 用語の解説3(1)を参照
(営農型太陽光発電の導入が進展)
農地に支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う営農型太陽光発電の取組は年々増加しています。平成30(2018)年度の営農型太陽光発電の取組面積は前年度と比べて147ha増の560haとなり、設備を設置するための農地転用許可件数(累計)は前年度と比べて481件増の1,992件となりました(図表3-3-13、図表3-3-14)。
(農山漁村再生可能エネルギー法に基づく取組を行っている地区の経済規模は増加)
令和元(2019)年7月に見直した、農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本方針では、再生可能エネルギーを活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を行っている地区の経済規模を令和5(2023)年度に600億円とする目標を設定しています。令和元(2019)年度末時点の経済規模は、前年度と比べて75億円増の372億円となっています(図表3-3-15)。
(バイオマス産業都市を新たに選定)
農山漁村における再生可能エネルギーの導入の拡大を図り、地域に存在するバイオマスを有効活用していくため、関係府省では、バイオマス産業都市の構築を推進しています。バイオマス産業都市では、原料生産から収集・運搬、製造・利用まで、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とする環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指しています。
令和2(2020)年度に北海道湧別町(ゆうべつちょう)、秋田県大潟村(おおがたむら)、三重県多気町(たきちょう)、南伊勢町(みなみいせちょう)の4町村を選定し、バイオガスプラントの整備、稲わら・籾殻の有効活用、食品廃棄物や生活排水汚泥を主原料としたメタン発酵によるエネルギー利用等、地域の特色を活かしたバイオマスの有効利用を推進しています。
このほか、畜産経営の規模拡大の進展に伴い、増大する家畜排せつ物の利用の高度化を進めるため、令和元(2019)年度補正予算において、7地区で自家消費を含めたエネルギー地産地消(*1)型のバイオガスプラントの導入を進めているほか、副産物の消化液の利用を推進しています。
*1 用語の解説3(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883