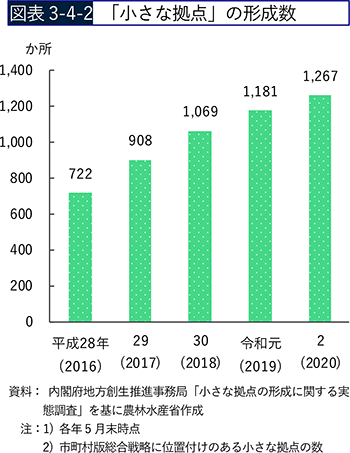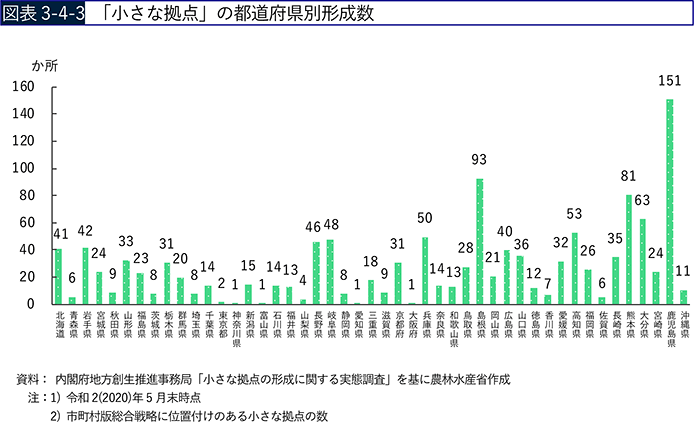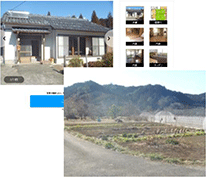第4節 中山間地域をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備
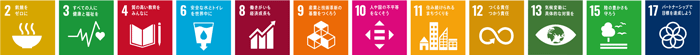
中山間地域(*1)を始めとする農村は、多様な地域住民が生活する場ですが、人口減少や少子高齢化が都市に先駆けて進行しています。このような中で農村を維持し、次の世代に継承していくためには、地域コミュニティの維持を目的とする「小さな拠点」の形成や多面的機能の発揮を促進するための日本型直接支払等により、農村に人が安心して住み続けるための条件が整備されることが必要です。
本節では、これらの取組に係る動向について紹介します。
*1 用語の解説2(7)を参照
(1)地域コミュニティ機能の維持や強化
ア 地域コミュニティ機能の形成のための場と世代を超えた人々による地域のビジョンづくり
(地域の将来像についての話合い等を促進)
農林水産省は地域コミュニティの形成や交流のための場づくりを推進するため、平成12(2000)年度から中山間地域等直接支払制度の活用により、地域コミュニティによる農用地や集落の将来像の明確化、農地、水路等の機能の維持・増進を図る共同活動等を支援しています。
また、これに加えて、地域住民がいきいきと暮らしていける環境の創出を行うため、地域住民団体等からなる地域協議会に対して、ワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定や地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築、実証活動等を支援しています。平成27(2015)年度から支援を開始し、これまで全国で164地区の地域協議会が様々な活動に取り組んでおり、令和2(2020)年度は、全国で98地区の活動計画を支援しました。
イ 「小さな拠点」の形成の推進
(「小さな拠点」の形成数が増加)
地域住民が地方公共団体や事業者、各種団体と協力・役割分担をしながら、行政施設や学校、郵便局等の各種生活支援機能を集約し、地域コミュニティを維持する「小さな拠点」づくりの取組が平成23(2011)年から行われており、令和2(2020)年5月末時点で、全国で1,267か所の「小さな拠点」が形成されています(図表3-4-1、図表3-4-2、図表3-4-3)。
関係府省庁が連携し、遊休施設の再編・集約に係る改修や、廃校施設の活用等に取り組む中、農林水産省は、農産物加工・販売施設や地域間交流拠点等のほか、「小さな拠点」間や「小さな拠点」と周辺集落の間を結ぶ農道を始めとしたインフラの整備を行っています。
(コラム)中山間地域では集落機能が低下傾向
集落は、資源管理機能(水田や山林等の地域資源の維持保全に係る集落機能)、生産補完機能(農林水産業等の生産に際しての草刈り、道普請(みちぶしん)等の相互扶助機能)、生活扶助機能(冠婚葬祭等日常生活における相互扶助機能)を有していますが、中山間地域ではこれらの集落機能の低下傾向が見られます。
総務省、国土交通省の条件不利地域を対象とした調査によると、平成22(2010)年から令和元(2019)年にかけ、集落機能の維持状況について「機能低下」又は「維持困難」と回答した割合は、中間農業地域では6.3ポイント増加し19.5%、山間農業地域では7.9ポイント増加し37.6%となっています。
(2)多面的機能の発揮の促進
(多面的機能支払制度を着実に推進)
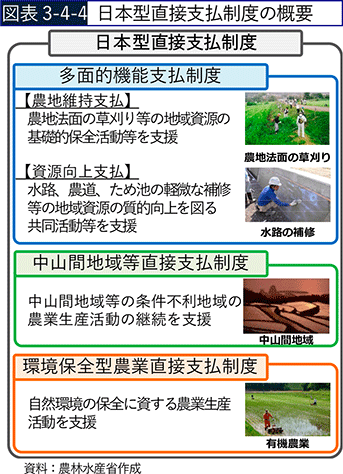

農業・農村の多面的機能(*1)の維持・発揮を目的として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、平成26(2014)年度から日本型直接支払制度(*2)が実施されています(図表3-4-4)。
この日本型直接支払制度のうち、多面的機能支払制度は、農地維持支払と資源向上支払の二つから構成されています(図表3-4-5)。農地維持支払は、地域共同で行う農地法面(のりめん)の草刈りや水路の泥上げ等の地域資源の基礎的な保全活動等を対象としています。また、資源向上支払は、水路や農道等の軽微な補修等の地域資源の質的向上を図る共同活動等を対象としています。
農地維持支払については、令和元(2019)年度の取組面積が、農用地面積(*3)の55%にあたる227万haとなっています。また、活動組織のうち947の組織が広域活動組織として活動しており、前年度と比較すると48組織増加しています。
資源向上支払のうち地域資源の質的向上を図る共同活動については、令和元(2019)年度の取組面積が、農用地面積の48%にあたる201万haとなっています。また、資源向上支払のうち施設の長寿命化のための活動は、令和元(2019)年度の取組面積が、農用地面積の18%である74万haとなっています。
令和2(2020)年度からは、甚大な自然災害時に対象組織間で交付金を融通できるよう制度の見直しが行われました。例えば、異常気象時に災害復旧費が不足し自己負担をせざるを得ない場合に、同交付金を受ける他の活動組織の余剰金を災害復旧費に充当することができるようになり、早期の営農再開が可能となりました。また、資源向上支払の対象である多面的機能の増進を図る活動として、従来の医療・福祉との連携に加えて、やすらぎや教育の場としての機能増進を図る活動も対象となったほか、防災・減災力の強化として災害時における応急体制の整備も対象となりました。
*1 用語の解説4を参照
*2 多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度、環境保全型農業直接支払制度の三つの制度から構成
*3 農用地区域内の農地面積に農用地区域内の採草放牧地面積(ともに平成30(2018)年時点、農林水産省調べ)を加えた面積
(事例)多面的機能支払制度を活用した生態系保全等の取組(大分県)
大分県宇佐市岩崎(うさしいわさき)地区は、平成24(2012)年6月に多面的機能支払制度を活用して、「岩崎農地水環境保全組合」を設立しました。
同組合では、農村の混住化が進む中、非農業者等の参加者のアイデアを活用し、生態系保全活動や学校教育との連携等の様々な活動が行われています。
例えば、集落の外縁にある河川からの取水施設周辺に繁茂した特定外来生物のオオフサモについて、同組合が重機による大掛かりな駆除を行うことで、それ以降は日常的な管理作業の一環として手作業で容易に駆除することができるようになり、維持管理の負担の軽減にもつながるとともに、在来生物の保全が図られました。
また、個々の農家が行うには負担が大きいことから断念されていた子供の農業体験についても、同組合員が協力して、地元の小学校や地域の子供会で実施するなど、地域コミュニティの強化等の活性化にもつながっています。
(中山間地域等直接支払制度第5期対策により支援を強化)
中山間地域等直接支払制度は、平地に比べ自然的・経済的・社会的に不利な営農条件下にある中山間地域等での農業生産活動を継続することを目的として平成12(2000)年度に始まり、現在は日本型直接支払制度の一つとして実施されています。令和元(2019)年度の交付面積は、前年度からほぼ横ばいの66万5千haであり、対象農用地面積に対する交付面積の割合は84%となっています。
本制度は、施策の評価を第三者委員会において実施しつつ5年ごとに対策の見直しが行われており、令和2(2020)年度からは第5期対策が始まっています。第5期対策では、交付金の返還措置が見直されるとともに、農用地や集落の将来像の明確化を図る集落戦略の作成や集落の地域運営機能の強化、棚田の保全や地域の振興を図る活動等、将来に向けた前向きな取組への支援が強化されています。
(事例)中山間地域等直接支払制度を活用した6次産業化の実現(岡山県)
岡山県美咲町境(みさきちょうさかい)集落は過疎地域及び特定農山村地域に指定されており、近隣に棚田百選にも選出された「大垪和西(おおはがにし)の棚田」や「北庄(きたしょう)の棚田」のある棚田地域です。高齢化や人口減少による地域活力の低下への対策として、平成12(2000)年度から中山間地域等直接支払制度を活用し、赤そば「高嶺(たかね)ルビー」の栽培を行っています。
平成15(2003)年には、中山間地域等直接支払交付金等を活用して棚田のそば屋「紅(あか)そば亭(てい)」を開設し、地区内で生産されたそばやそば加工品、野菜等を販売しています。
また、中山間地域等直接支払交付金等により汎用型コンバインを生産組合法人に導入し、法人への農地の集積を進めてきました。法人が集積した農地面積は平成23(2011)年の1haから令和元(2019)年には10haに増加しており、生産拡大と耕作放棄地の発生の防止につながっています。
(環境保全型農業直接支払制度第2期対策では対象となる取組を拡大)
環境保全型農業直接支払制度は、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動の支援を目的として平成23(2011)年度に始まり、現在は日本型直接支払制度の一つとして実施されています。支援の対象となる取組には、カバークロップ(緑肥)の作付けや堆肥の施用、有機農業等の全国共通取組と、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で都道府県が申請を行い、 地域を限定して取り組むことができる地域特認取組があります。令和元(2019)年度の実施面積は、前年度からほぼ横ばいの8万haで、実施市町村数は全市町村の52%にあたる887市町村となっています。
令和2(2020)年度からは第2期対策が始まり、多くの農業者が取組を実施できるよう、全国共通取組にリビングマルチ(*1)や長期中干し(*2)等の五つの取組が追加されました。また、地域特認取組の運用も見直され、地球温暖化防止や生物多様性保全以外に、水質保全等の効果がある取組も支援の対象にすることができるようになるなど、都道府県の裁量が拡大しました。
*1 主作物の畝間に緑肥を作付けする取組
*2 水稲の生育中期に10a当たり1本以上の溝切りを実施した上で14日以上の中干しを実施する取組
(3)生活インフラ等の確保
(農地付き空き家等の契約数が増加)
農村への移住希望者にとって、住宅の確保は、収入の確保とともに重要な課題です。
国土交通省は、一部の地方公共団体が行う、空き家等の情報サイトを一元化したWebサイトを平成30(2018)年に開設し、「全国版空き家・空き地バンク」として運営しています。
同Webサイトに登録されている物件数は増加しており、令和2(2020)年10月末時点で1万1,048件となっています(図表3-4-6)。このうち495件が農地付き空き家となっています。また、同Webサイト開設以降、契約件数も増加しており、同年10月末時点で630件の農地付き空き家を含む約6千件が契約されています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883