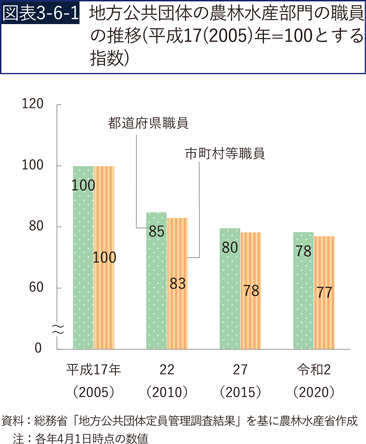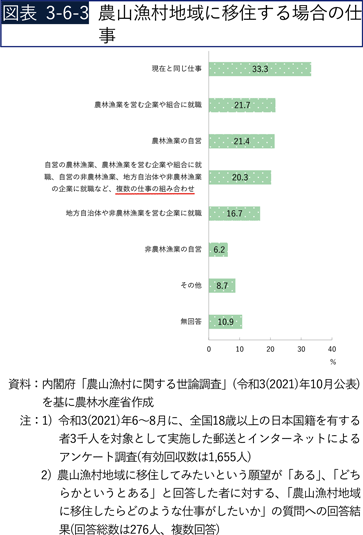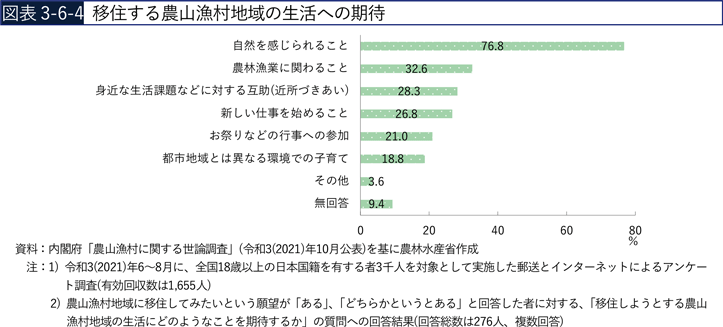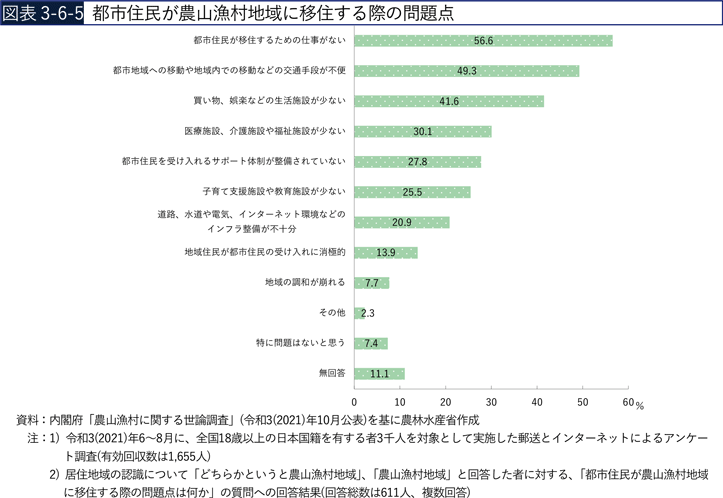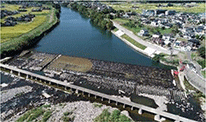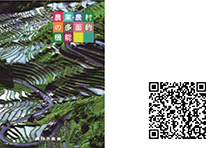第6節 農村を支える新たな動きや活力の創出
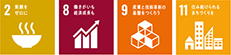
「田園回帰」による人の流れが全国的に広がりつつある中で、本節では、地域づくりに向けた人材育成や、棚田地域の振興、多面的機能(*1)に関する理解の促進等の様々な取組について紹介します。
1 用語の解説4を参照
(1)地域を支える人材づくり
ア 地域づくりに向けた人材育成等の取組
(地域に寄り添ってサポートする人材「農村プロデューサー」を養成)
近年、地方公共団体職員、特に農林水産部門の職員が減少しており、平成17(2005)年を100としたときに比べて令和2(2020)年では20ポイント以上低下しています(図表3-6-1)。このような中、各般の地域振興施策を使いこなし、新しい動きを生み出すことができる地域とそうでない地域との差が広がり、いわゆる「むら・むら格差」につながることが懸念されます。
こうしたことから、地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いをくみ取りながら、地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサポートする人材(農村プロデューサー)を育成するため、農林水産省は、令和3(2021)年度から「農村プロデューサー養成講座」の取組を開始しました。地方公共団体職員や地域おこし協力隊員等が受講しています。
(農山漁村地域づくりホットラインの活用)
農林水産省は、令和2(2020)年12月から、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等を対象に相談を受け付け、取組を後押しするための窓口「農山漁村地域づくりホットライン」を開設しています。開設以来、市町村を始め、地域協議会、社会福祉法人等からの相談が寄せられています。

農山漁村地域づくりホットラインについて
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/hotline/
これらのうち、活用可能な事業や事業制度に関する相談が全体の約7割を占めており、次いで交付金事業の公募や予算に関する相談が多くなっています。このほか、農山漁村で活用可能な様々な府省の施策を紹介する「地域づくり支援施策集」についても情報を随時更新し、窓口のWebサイト内で紹介しています。
(事例)行政と住民が協働した地域の課題解決への取組(高知県)
高知県梼原町(ゆすはらちょう)は、町の面積の91%を森林が占める山深い町です。住民の多くが「梼原で一生過ごしたい。」と思う一方、「飲み水や生活用水の質や量が不十分」、「交通の手段が不十分」、「野生動物による農業被害」、「雇用の不足」等の課題が浮き彫りとなっていました。
これらの課題を解決するために行政と住民が協働して平成22(2010)年に梼原町の振興計画を策定し、住民自身が解決していく仕組みである「集落活動センター」を、平成25(2013)年から順次、町内全域に6か所設置しました。
「できることから始めよう」を合い言葉に、課題に取り組んでおり、お金も物も地域内で循環する仕組みの構築による雇用創出や生産者の所得増につながり、更に住民の意識と行動が変わり始めています。
集落活動センターの仕組みは公共的な役割も担っており、その経営は、収益を得る活動だけではなく、その地域で生きる住民や地域の役に立ち、地域社会を支えることを目指して、引き続き取り組んでいくこととしています。
イ 関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じた地域の支えとなる人材の裾野の拡大
(農的関係人口の創出・拡大等を推進)
都市住民も含め、農村の支えとなる人材の裾野を拡大していくためには、都市農業、農泊等を通じ、多様な人材が農業・農村に関わることで、農村の関係人口である「農的関係人口」の創出・拡大や関係深化を図ることが効果的です。農的関係人口については、都市部に居住しながらの農産物の購入や、農山漁村での様々な活動への参画等により農村を支える場合、都市部の住民が短期間の農作業を手助けするなど農業に携わる場合、農村の地域づくりに関わる場合等、多様な関わり方があります(図表3-6-2)。
農林水産省は、これらの様々な形で農村への関わりを深め、農村の新たな担い手へと発展していくような取組に対して、発展段階に応じて支援を行っています。具体的には、都市部での農業体験や交流、農山漁村でのくらしを体験する取組等に対する支援を行っています。
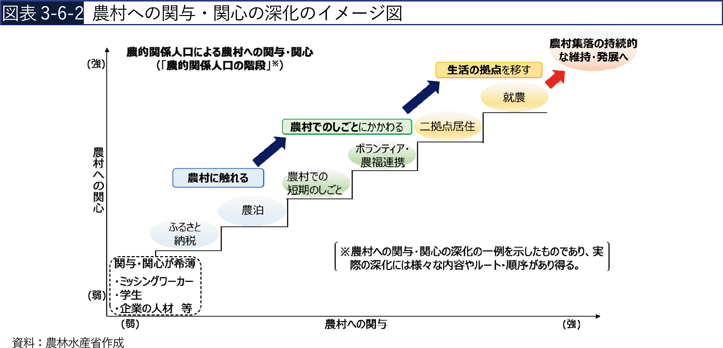
(事例)農業体験から移住へつながる活動(千葉県)
NPO法人(*)SOSA Project(そーさぷろじぇくと)は、平成23(2011)年から千葉県匝瑳市(そうさし)で都市部に住む人に向けた農業体験や希望者に対する移住のあっせん等を行う活動をしています。
参加者やその家族が食べるお米を田植から収穫、持ち帰りまで一貫して行う取組や、里山維持のための草刈り、小屋づくりや古民家のリノベーション、田舎暮らしのノウハウを伝授する取組等を継続して行っています。
こうした米・大豆づくりなどに加えて、DIYや伝統的土木、電気自給などのワークショップに参加するために、令和3(2021)年度は都市部から同市に100組、約300人が通っています。移住希望者には、空き家のあっせんも行い、同市を含め近隣市町村への移住者はこれまでに50組以上となっています。また、この取組への地域住民の参加者も増え、都市住民・移住者と地元住民の交流等が盛んになっています。
同法人理事の髙坂勝(こうさかまさる)さんは、「取組の規模を大きくし過ぎると運営側の負担が過大となり無理が生じるので、現状の取組規模を維持しつつ、田舎暮らしに必要なスキルや知恵、経験を得てもらい、関係人口にとどまらず、地方移住への流れを大きくしたい。」と話しています。
用語の解説3(2)を参照
(子供の農山漁村体験の推進)

子ども農山漁村交流プロジェクトについて
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kodomo/
農林水産省を含む関係府省は、平成20(2008)年度から、子供が農山漁村に宿泊し、農林漁業の体験や自然体験活動等を行うことで、子供たちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心等を育む「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進しています。この取組の中で、農林水産省は、都市と農山漁村の交流を促進するための取組や交流促進施設等の整備に対する支援等、受入側である農山漁村への支援を行っています。
ウ 多様な人材の活躍による地域課題の解決
(企業人材や地域おこし協力隊が活躍)
農山漁村地域でビジネス体制の構築やプロモーション等を行う専門的な人材を補うため、総務省は地域活性化に向けた幅広い活動に従事する企業人材を派遣する「地域活性化起業人」を実施しています。この取組は、企業から人材の派遣を受ける地方公共団体だけでなく、人材を派遣する企業側にも人材育成や社会貢献等のメリットがあるものです。農林水産省としては、農山漁村地域における人材ニーズの把握や活用の働き掛け、マッチング等を行っています。
さらに、「地域おこし協力隊」として都市地域から過疎地域等に生活の拠点を移した者が、全国の様々な場所で地域のブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援等の「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組を行っています。
(半農半Xを始めとした農業への関わり方の多様化が進展)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり、テレワーク等場所を問わない働き方が急速に進んだことで、地方への移住や二地域居住のような動きが注目されています。
半農半Xの「X」に当たる部分は多種多様で、半分農業をしながら、半会社員、半農泊運営、半レストラン経営等様々です。この場合、Uターンのような形で、本人又は配偶者の実家等で農地やノウハウを継承して半農に取り組む事例も見られます。また、季節ごとに繁忙期を迎える農業、食品加工業等、様々な仕事を組み合わせて通年勤務するような事例も見られるようになってきています。
令和3(2021)年6~8月に内閣府が行った世論調査で、農山漁村に移住願望があると回答した者に「農山漁村地域に移住したらどのような仕事がしたいか」と尋ねたところ、「現在と同じ仕事」と回答した者が33.3%と最も多いものの、「複数の仕事の組み合わせ」が2割程度となっており、生業(なりわい)についての考え方が多様化していることがうかがわれます(図表3-6-3)。また、「移住しようとする農山漁村地域の生活にどのようなことを期待するか」について尋ねたところ、「自然を感じられること」(76.8%)に続き、「農林漁業に関わること」が32.6%と多くなっています(図表3-6-4)。
一方、現在の住まいの地域が農山漁村地域と回答した者に「都市住民が農山漁村地域に移住する際の問題点は何か」と尋ねたところ、「都市住民が移住するための仕事がない」と回答した者が56.6%と最も多くなっており、就業の場の確保が重要な課題となっていることがうかがわれます(図表3-6-5)。
(事例)人手不足の解消と良質な雇用環境を確保(長崎県)
五島市地域(ごとうしちいき)づくり事業協同組合は、人口急減地域特定地域づくり推進法(*)に基づき、令和3(2021)年に長崎県五島市(ごとうし)で設立しました。組合で職員を雇用し、組合員である農業者等の事業者に派遣することにより、地域の担い手の確保に取り組んでいます。
同組合では、同年4月から2人の職員を採用し、季節によって繁忙期が異なる職場に職員を派遣しており、派遣された職員は通年で安定した収入を得られています。組合員の要望に応え、同年12月時点で8人の職員を雇用し、農業や食品加工業等の事業者に派遣しています。
職員の一人である、尾田遼斗(おだりょうと)さんは同年5月から農業生産法人「株式会社アグリ・コーポレーション」で畑作業をし、7月からは水産加工、冬からはだいこん等の収穫作業や切り干し加工をするなどの食品加工の仕事に就いています。尾田さんは、「様々な職場で働くことは、いろいろな人たちと触れ合えるし、良い経験になり、自分自身が成長するのを感じている。農作物を作る楽しみもあって今後も続けていきたい。」と話しています。
組合事務局長の野口敏明(のぐちとしあき)さんは、「当初予定より、職員のなり手が多く、有り難い状況となっている。引き続き、島内の若者の流出を食い止め、UIターン者の増加にもつなげたい。」と話しています。
正式名称は「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」
(事例)半農半Xを実践する企業(静岡県)
静岡県伊豆(いず)の国市(くにし)の土屋建設(つちやけんせつ)株式会社は、農村の高齢化・人口減少等による基盤整備需要の減少を受け、自ら農村の活性化と地域産業の振興を行うため、平成23(2011)年から農業に参入しています。
営農開始当初に借り入れた農地のうち、70aは耕作放棄地でしたが、自社の重機やそのオペレーター等、建設業の技術を活用して農地を耕し、栽培技術については、農協や地元農家等からの支援を得て、耕作を開始しました。
令和3(2021)年時点での経営面積は2.5ha、農業従事者7人、うち臨時雇用者4人となっています。地域の特産であるだいこんやすいかの栽培を始め、60種程度の露地野菜等、多種多様な品種を栽培し、自社ブランド「ろっぽう野菜」として販売をしています。
同社は、今後も近隣の農家の販売を請け負う体制を構築することにより、地域の活性化に取り組んでいきたいとしています。
(2)農村の魅力の発信
(棚田地域の振興を推進)
棚田を保全し、棚田地域の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的とした棚田地域振興法が令和元(2019)年に施行され、市町村や都道府県、農業者、地域住民等の多様な主体が参画する指定棚田地域振興協議会による棚田を核とした地域振興の取組を、関係府省横断で総合的に支援する枠組みが構築されています。農林水産大臣等の主務大臣(*1)は、令和3(2021)年度までに、同法に基づき累計698地域を指定棚田地域に指定しました。また、指定棚田地域において指定棚田地域振興協議会が策定した認定棚田地域振興活動計画を累計166計画認定しました。
また、棚田の保全と地域振興を図る観点から、同年度には、「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~」として、優良な棚田271か所を農林水産大臣が認定しました。
このほか、農林水産省は、都道府県に対して、棚田カードを作成し、都市住民に棚田の魅力を発信することを呼び掛けています。同年度末時点で累計108の棚田地域が参加する取組となっており、棚田地域を盛り上げ、棚田保全の取組の一助となることが期待されます。
1 主務大臣は、農林水産大臣のほか、総務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣及び環境大臣
(3)多面的機能に関する国民の理解の促進等
(新たに2施設が世界かんがい施設遺産に登録)
世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設をICID(国際かんがい排水委員会)が認定・登録する制度で、令和3(2021)年には我が国で新たに寺ケ池(てらがいけ)・寺ケ池水路(てらがいけすいろ)と宇佐(うさ)のかんがい用水群(ようすいぐん)の2施設が登録され、これまでの国内登録施設数は計44施設となりました。
(世界農業遺産国際会議2021を開催)
FAO(国際連合食糧農業機関)が認定する日本国内の世界農業遺産は、令和3(2021)年度末時点で、11地域となっています。令和3(2021)年は国内で初めて世界農業遺産が認定されてから10周年となることから、同年11月に石川県において世界農業遺産国際会議2021を開催し、各認定地域の取組や情報を共有するとともに世界農業遺産の更なる活用・保全について議論を行いました。
このほか、農林水産大臣が認定する日本農業遺産は令和3(2021)年度末時点で、22地域となっています。
(「ディスカバー農山漁村の宝」に34地区と4人を選定)

ディスカバー農山漁村の宝について
URL:https://www.discovermuranotakara.com/(外部リンク)
農林水産省と内閣官房は、平成26(2014)年度から、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことで地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、農村への国民の理解の促進や優良事例の横展開等に取り組んでいます。令和2(2020)年度までに211件選定しており、第8回目となる令和3(2021)年度は全国の34地区と4人を選定しました。選定を機に更なる地域の活性化や所得向上が期待されます。
(コラム)パンフレットやジュニア農林水産白書で多面的機能等の理解を促進
(1)パンフレット「農業・農村の多面的機能」
農林水産省では、農業が有する国土保全・水源涵養(かんよう)・景観保全等の多面的機能について国民の理解を促進するため、これらの機能を分かりやすく解説したパンフレット約2万8千部を道の駅やイベント等を通じて、国民の幅広い層に配布し、普及・啓発を行っています。
(2)ジュニア農林水産白書
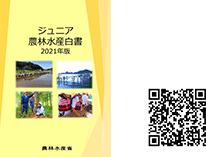
ジュニア農林水産白書
URL:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/
w_junior/index.html
農林水産省は、小学校高学年向けに、我が国の農林水産業、農山漁村、それらが有する多面的機能への理解を深めてもらうようジュニア農林水産白書を作成しています。令和3(2021)年9月に公表した2021年版ジュニア農林水産白書については、農林水産省のSNSで配信したことに加え、文部科学省の協力により同年10月に同省のメールマガジンとSNSで、全国の子供の保護者、教育関係者等に対し周知しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883