トピックス1 食料安全保障の強化に向け、構造転換対策や地域計画の策定を推進
食料や生産資材について過度な輸入依存度を低減していくため、小麦や大豆、飼料作物といった海外依存度の高い品目の生産拡大を推進するとともに、生産資材の国内代替転換を推進するなどの構造転換を進めていくことが重要です。
また、令和5(2023)年4月に改正農業経営基盤強化促進法(*1)が施行され、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」が法定化されています。
以下では、食料安全保障の強化に向けた構造転換対策や地域計画の策定に向けた取組等について紹介します。
*1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」
(世界の食料需給等をめぐるリスクが高まり)
昨今、気候変動等による世界的な食料生産の不安定化、世界的な食料需要の拡大に伴う調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化等も加わり、輸入する食品原材料や農業生産資材の価格高騰を招くとともに、産出国が偏り、食料以上に調達切替えが難しい化学肥料の輸出規制や、コロナ禍における国際物流の混乱等による供給の不安定化も経験するなど、世界の食料需給等をめぐるリスクが高まっています(図表 トピ1-1)。食をめぐる国内外の状況が刻々と変化する中、食料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題となっています。
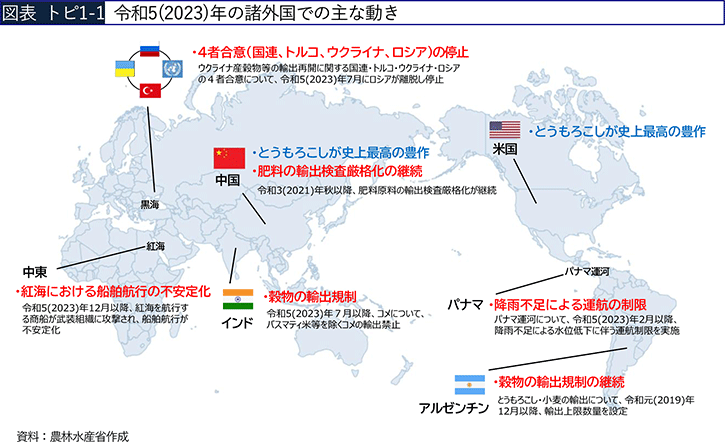
(食料安全保障の強化に向けた構造転換対策を推進)
食料安全保障については、国内の農業生産の振興を図りながら、安定的な輸入と適切な備蓄を組み合わせて強化していくこととしています。このような中、農林水産物・食品の過度な輸入依存は、原産国の不作等による穀物価格の急騰のほか、化学肥料の原料産出国の輸出規制による調達量の減少が生じた場合等には、国際情勢の変化により、思うような条件での輸入が困難となること等から、平時でも食料の安定供給を脅かすリスクを高めることとなります。
一方、小麦や大豆、米粉等の国産の農林水産物については、品質の向上が進む中で、海外調達の不安定化とあいまって、活用の拡大が期待されています。飼料については、牧草、稲わら等の粗飼料を中心に国内の生産を拡大する余地があり、生産者である耕種農家と利用者である畜産農家との連携や広域流通の仕組み、利用者の利便を考慮した提供の在り方等を実現することにより、活用の更なる拡大が期待されています。このほか、青刈りとうもろこしを始め、輸入に代わる国産飼料の生産拡大・普及等が期待されています。
また、肥料についても、国内には、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源等があり、これらの資源の有効活用が期待されるほか、主要な原料の大部分を輸入している化学肥料の使用量の低減や化学肥料原料の備蓄等の取組の重要性が高まっています。
このため、農林水産物・生産資材ともに、過度に輸入に依存する構造を改め、農業生産資材の国産化や備蓄、輸入食品原材料の国産転換等を進め、耕地利用率や農地集積率等も向上させつつ、更なる食料安全保障の強化を図ることとしています。
(事例)共同大型機械の導入や農地の高度利用等により、小麦の増産を推進(大分県)


大型機械による小麦の収穫
資料:農事組合法人おぶくろ営農
大分県中津市(なかつし)の集落営農法人である農事組合法人おぶくろ営農(えいのう)では、大型機械の活用や農地の高度利用等により、小麦の増産を推進しています。
同法人は、「地域の水田は地域で守る」を合言葉に、加入全戸の出資による共同大型機械の導入等により生産性の高い土地利用型農業を実践しています。
経営農地面積は45.3haで、集落内農地の89%を集積しており、団地化による効率の良い農業を実践しています。夏作では主食用米20.7ha、大豆21.0ha、冬作では麦41.9haを作付けしています。
同法人では、畦畔(けいはん)除去による区画拡大等の基盤整備により効率化を図るとともに、連作障害回避や団地化による効率的な管理作業を可能にするためブロックローテーションを徹底し、地域を二つのブロックに分けて、水稲と大豆を毎年交代しながら、冬作ではほとんどの農地で麦を作付けするなど、農地の高度利用を図っています。
同法人の小麦の作付面積については、令和4(2022)年産は36.2ha(はるみずき)となり、令和元(2019)年産(ミナミノカオリ)と比べて約3割増加しています。
大型機械を駆使した大規模経営に取り組みつつ、基本技術の励行に加え、作物の生育状況に応じた施肥管理や土壌の状態を見て麦踏み時期や回数を調整するなど、きめ細かな管理により、収量・品質の高位安定化とコスト低減を実現しています。
今後は、実需と結び付いた醤油(しょうゆ)用小麦の生産を推進するとともに、新品種小麦である「はるみずき」の品種特性を把握しながら、施肥時期や施肥量を研究し、実需者の求める製品づくりを追求していくこととしています。
(特定農産加工業者の経営改善と原材料の調達安定化を促進)
経済連携協定の締結等により農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化による影響が継続している状況を踏まえ、特定農産加工業者(*1)の経営の改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を5年間延長するとともに、輸入小麦・大豆の価格水準の上昇等によりその調達が困難となっている状況を踏まえ、原材料の調達の安定化を図るための措置に関する計画承認制度を設け、当該承認を受けた特定農産加工業者に対する公庫による貸付けの特例の措置等を講ずる「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案」を第213回通常国会に提出したところです。
*1 特定農産加工業者とは、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化の影響を受ける農産加工業であって農林水産省令で定める業種に属する事業を行う者のこと
(令和5(2023)年4月に改正農業経営基盤強化促進法が施行)
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。令和5(2023)年4月に施行した改正農業経営基盤強化促進法では、市街化区域を除き、基本構想を策定している市町村において、これまでの「人・農地プラン」を土台とし、農業者等による話合いを踏まえて、将来の地域農業の在り方や目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した目標地図を含めた「地域計画」を策定することとしています(図表 トピ1-2)。
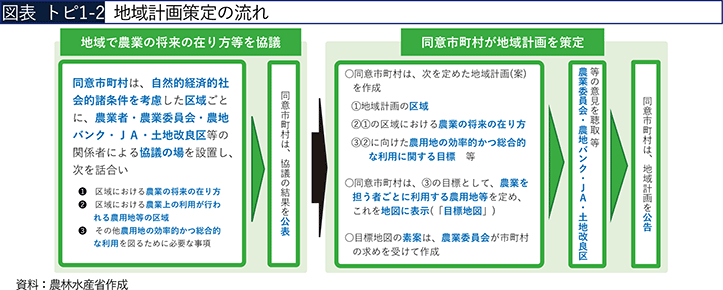
地域計画の策定は、食料安全保障の強化やスマート農業技術の導入による生産性の向上、環境と調和のとれた食料システムの確立等にも重要な意義を有することから、令和7(2025)年3月までに各市町村において策定が着実に進められるよう、関係機関・団体が一体となって計画的に取組を推進していく必要があります。
(「地域計画」の策定を推進)
地域計画は、地域農業の将来設計図となるものであり、若年者や女性を含む幅広い意見を取り入れながら、地域の農業関係者が一体となって話し合い、策定することが重要です。
市町村は、幅広い関係者に参加を呼び掛け、協議の場を設置するとともに、協議の場では、区域の現状や課題を踏まえ、米から輸入依存度の高い小麦・大豆等への転換、輸出向け農産物の生産、有機農業の導入、耕畜連携等による飼料の増産、水田の畑地化といった地域の実情を踏まえた目指すべき将来の地域農業について協議することが重要です。
また、地域の農地を次世代に着実に引き継いでいくため、農業上の利用が行われる農地は、農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)を活用した農地の集積・集約化を進めるとともに、農業上の利用が困難な農地は、計画的な土地利用を推進するなど、一体的に推進していくことによって地域の農地の利用・保全を計画的に進め、農地の適切な利用を確保することとしています。
農林水産省では、地域計画の策定に向け、市町村等による協議の実施・取りまとめ、地域計画案の取りまとめ等の取組を支援するほか、農業委員会による目標地図の素案作成の取組支援、都道府県による市町村等への説明会や研修会の開催等の取組を支援することとしています。
(事例)エリアごとでの話合いを進め、地域計画の策定を推進(島根県)
島根県江津市(ごうつし)では、コーディネーターを活用し、地域単位における将来の農業の方向性や、将来の農用地利用の姿である目標地図をまとめた地域計画の作成を進めています。
同市では、狭隘(きょうあい)な農地においても収益を上げるため、有機農業を中心に、付加価値を高めるための取組が進められてきました。一方で、人口減少や高齢化が進む中、農地の減少は住民の生活圏域の圧迫につながる課題であり、担い手への農地の集積を始めとした農地を維持するための取組が課題となっています。
このため、同市では、令和元(2019)年7月に、市や農業委員会、農地バンクを核とした推進体制を構築し、市全体の人・農地施策の方針調整を定期的に開催し、話合いを進めてきました。
令和3(2021)年度には、人・農地プランで実質化した市内45集落を9エリアに広域化するとともに、各エリアにエリア・ビジョン会議を設置し、コーディネーターを活用しながら、担い手の意向に重心を置いたエリア・ビジョンを作成しました。また、農地に対する担い手の意向を「見える化」し、農地利用の将来を描いた図表である「人・農地利用ゾーニング」を作成することにより、農地の集約を促進させる手法を整理しました。
さらに、令和5(2023)年9月には、担い手からの意向の聞き取りやエリア・ビジョン会議を経て作成した人・農地利用ゾーニングを「分析できる地図」として整理した上で、令和6(2024)年1月に、協議の場での意見を反映した地域計画と目標地図の素案を作成し、同年7月を目途に地域計画を取りまとめることとしています。
今後は、耕作者・地権者に対し、人・農地利用ゾーニングに係る説明を丁寧に行っていくほか、担い手が守ることが困難な農地に対しては、集落が主体となって打開策を考え、長期にわたって営農が続けられるようサポートをしていくこととしています。

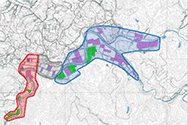
集落のゾーニング例
資料:島根県江津市

エリア・ビジョン会議
資料:島根県江津市
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




