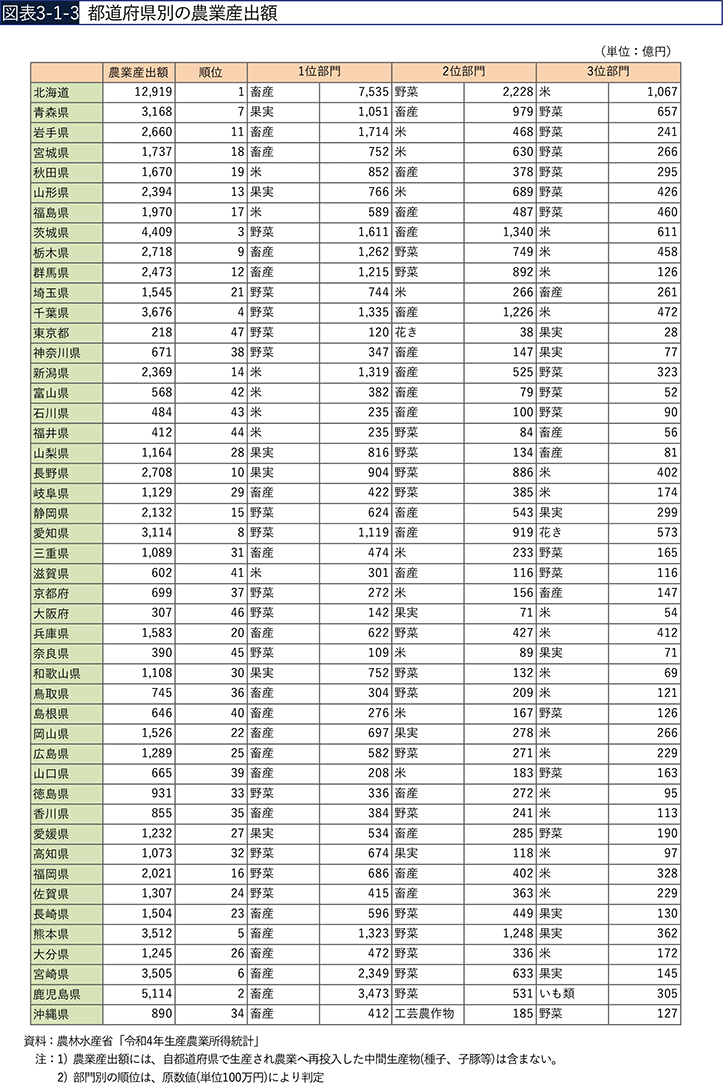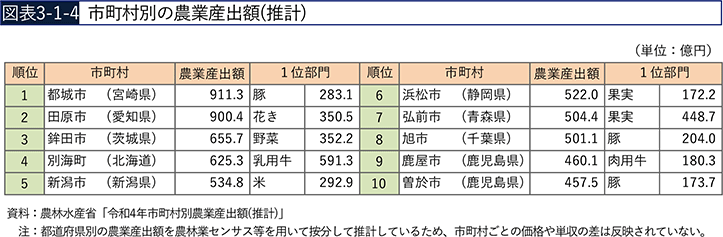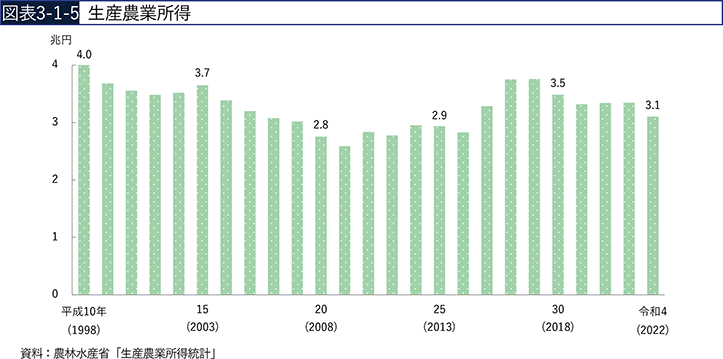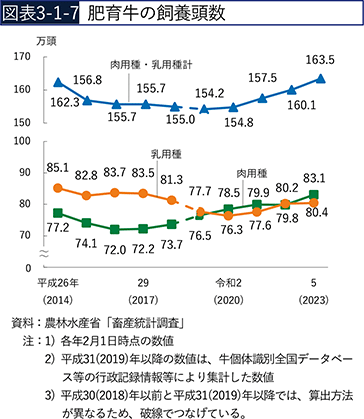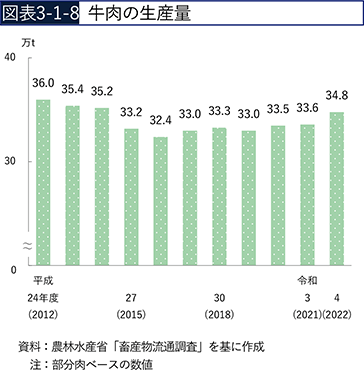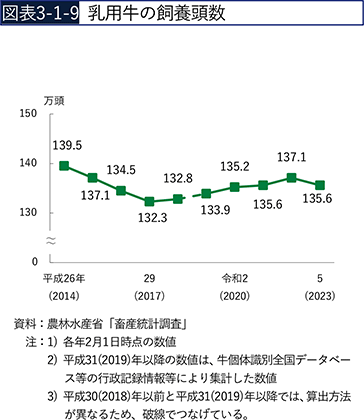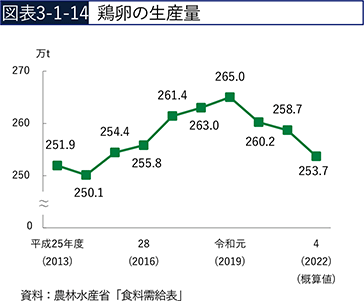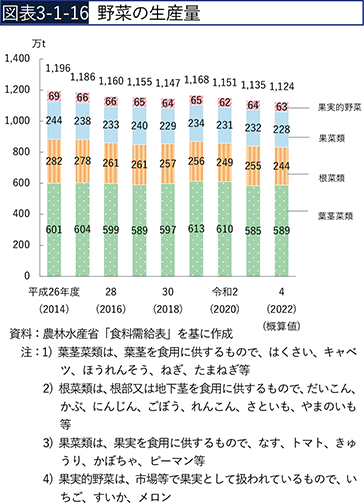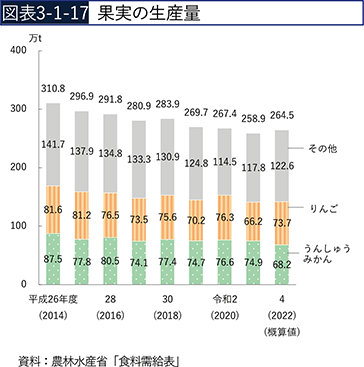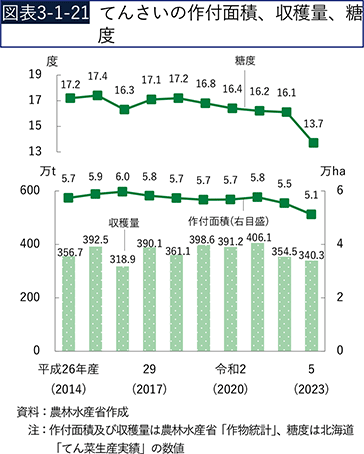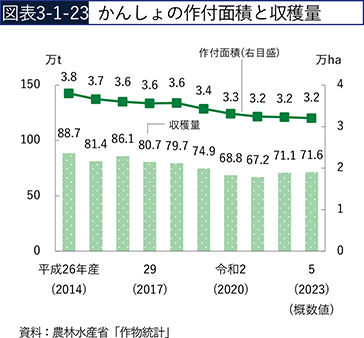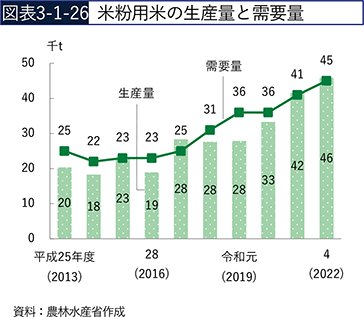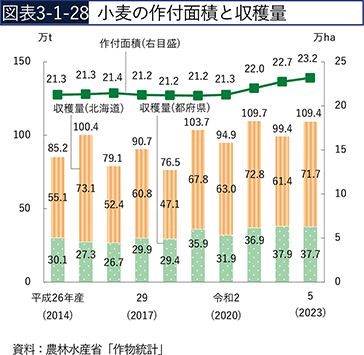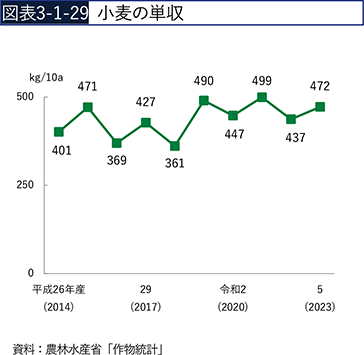第1節 農業生産の動向

我が国では、各地の気候や土壌等の条件に応じて、畜産、野菜、米、果実等の様々な農畜産物が生産されており、農業総産出額は、近年では9兆円前後で推移しています。品目ごとに需要に応じた生産の推進が求められる中、足下では原油価格・物価高騰の影響等により、我が国の農業生産にも変化が見られています。
本節では、このような農業生産の動向について紹介します。
(1)農業総産出額の動向
(農業総産出額は前年に比べ1.8%増加し9兆円)
農業総産出額は、近年、農畜産物における需要に応じた生産の取組が進められてきたこと等により9兆円前後で推移しており、令和4(2022)年は耕種において米や野菜、畜産において豚や鶏の価格が上昇したこと等から、前年に比べ1.8%増加し9兆15億円となりました(図表3-1-1)。
部門別の産出額を見ると、米の産出額は前年に比べ1.8%増加し1兆3,946億円となりました。これは、主食用米から他作物への転換といった産地や生産者が中心となった需要に応じた生産の進展により民間在庫量が減少し、主食用米の取引価格が前年から回復したこと等によるものと考えられます。
野菜の産出額は前年に比べ3.9%増加し2兆2,298億円となりました。これは、たまねぎにおいて前年からの価格高騰が継続したことや、トマトやにんじん等の品目で令和4(2022)年8月の北・東日本を中心とした天候不順等の影響により生産量が減少し、価格が前年産に比べて上昇したこと等が寄与したものと考えられます。
果実の産出額は前年に比べ0.8%増加し9,232億円となりました。これは、おうとうやもも等において生産時期の天候に恵まれ順調に生育したことにより、生産量が前年産を上回ったこと等が寄与したものと考えられます。
畜産の産出額は前年に比べ1.9%増加し3兆4,678億円となり、引き続き全ての部門の中で最も大きい数値となりました(図表3-1-2)。このうち肉用牛は、和牛肉の需要が軟調に推移し価格が低下した一方、生産基盤の強化に伴い、引き続き和牛の生産頭数が増加したことにより、産出額が増加したものと考えられます。生乳については、需給バランスの改善に向けて生産者団体が自主的に抑制的な生産に取り組んだことにより生産量が減少したものの、飲用等向けの取引価格が上昇したことにより、産出額が増加したものと考えられます。豚については、出荷頭数は前年を下回ったものの、高騰する輸入品の代替需要や節約志向の高まりによる需要増を背景に価格が上昇したこと等により、産出額が増加したものと考えられます。
(都道府県別の農業産出額は、北海道が1兆3千億円で1位)
令和4(2022)年の都道府県別の農業産出額を見ると、1位は北海道で1兆2,919億円、2位は鹿児島県で5,114億円、3位は茨城県で4,409億円、4位は千葉県で3,676億円、5位は熊本県で3,512億円となっています(図表3-1-3)。上位5位の道県で、産出額の1位の部門を見ると、北海道、鹿児島県、熊本県では畜産、茨城県、千葉県では野菜となっています。
令和4(2022)年の市町村別の農業産出額を見ると、1位は宮崎県都城市(みやこのじょうし)で911億3千万円、2位は愛知県田原市(たはらし)で900億4千万円、3位は茨城県鉾田市(ほこたし)で655億7千万円、4位は北海道別海町(べつかいちょう)で625億3千万円、5位は新潟県新潟市(にいがたし)で534億8千万円となっています(図表3-1-4)。
(生産農業所得は前年に比べ7.3%減少し3兆1千億円)
生産農業所得については、長期的には農業総産出額の減少や資材価格の上昇により減少傾向が続いてきましたが、農畜産物において需要に応じた生産の取組が進められてきたこと等から、平成27(2015)年以降は、農業総産出額の増減はあるものの、3兆円台で推移してきました(図表3-1-5)。
令和4(2022)年は、国際的な原料価格の上昇等により、肥料、飼料、光熱動力等の農業生産資材価格が上昇したこと等から、前年に比べ7.3%減少し3兆1,051億円となりました。
(2)主要畜産物の生産動向
(肥育牛の飼養頭数は前年に比べ増加、牛肉の生産量は前年度に比べ増加)
令和5(2023)年の繁殖雌牛の飼養頭数は、前年に比べ1.3%増加し64万5千頭となりました(図表3-1-6)。
また、令和5(2023)年の肥育牛(肉用種・乳用種)の飼養頭数は、前年に比べ2.1%増加し163万5千頭となりました(図表3-1-7)。
令和4(2022)年度の牛肉の生産量は、和牛や交雑種が増加したことから、前年度に比べ3.5%増加し34万8千tとなりました(図表3-1-8)。
(乳用牛の飼養頭数は前年に比べ減少、生乳の生産量は前年度に比べ減少)
令和5(2023)年の乳用牛の飼養頭数は、前年に比べ1.1%減少し135万6千頭となりました(図表3-1-9)。
また、令和4(2022)年度の生乳の生産量は、生乳需給の緩和等を背景として生産者団体が自主的に抑制的な生産に取り組んだこと等により、都府県では前年度に比べ1.7%減少し327万9千t、北海道では前年度に比べ1.3%減少し425万4千tとなりました(図表3-1-10)。その結果、全国では前年度に比べ1.5%減少し753万3千tとなりました。
(事例)ICTの活用や飼料給餌の自動化を通じた効率的な酪農経営を展開(鳥取県)


個体情報の把握のため
センサーを付けた乳牛
資料:有限会社岸田牧場
鳥取県琴浦町(ことうらちょう)の有限会社岸田牧場(きしだぼくじょう)は、ICTを活用した飼養管理や飼料給餌の自動化を通じた効率的な酪農経営を推進しています。
同社は、大山(だいせん)山麓の豊かな自然の中で、酪農と肥育の大規模複合経営を行っており、令和5(2023)年11月時点で乳用牛を約260頭、肉用牛を約800頭飼養しています。
同社では、乳用牛のデータをデジタルで管理するため、クラウド牛群管理システムを導入しています。牛の様々な個体情報をクラウド化することで、家畜の飼養状況や健康状況等を一元管理することが可能となっているほか、スタッフは現場にいなくても遠隔で作業状況が把握できるようになり、労働時間の短縮や休日の確保につながっています。
また、同社では、給餌作業の省力化や、多数回給餌による飼養管理の高度化を図るため、自動給餌機を導入しています。牛の発育状況によって給餌のタイミングを変更するなどのきめ細かな対応が可能となっています。
さらに、同社では、搾乳牛だけに特化せず、副産物である雄牛の肥育、堆肥の販売、自社堆肥を利用した小麦の栽培、自社ブランドである牛乳の販売等を進めることにより、酪農の可能性を最大限に生かした経営を行っています。
同社では、今後とも先進技術の追及や衛生管理の向上を図りながら、地域に根ざし、地域から誇りとされる農場を目指し、畜産事業を展開していくこととしています。
(豚の飼養頭数は前年に比べ増加、豚肉の生産量は前年度に比べ減少)
令和5(2023)年の豚の飼養頭数は、前年に比べ0.1%増加し895万6千頭となりました(図表3-1-11)。
一方、令和4(2022)年度の豚肉の生産量は、同年に飼養頭数が減少したこと等から、前年度に比べ2.4%減少し90万1千tとなりました(図表3-1-12)。
(鶏肉の生産量は前年度に比べ増加、鶏卵の生産量は前年度に比べ減少)
令和4(2022)年度の鶏肉の生産量は、安定した需要が継続していることを背景として、前年度に比べ0.2%増加し168万1千tとなりました(図表3-1-13)。
一方、令和4(2022)年度の鶏卵の生産量は、飼料価格等の生産コスト上昇により、ひなの導入が抑制されたことに加え、令和4(2022)年シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大規模発生の影響により、前年度に比べ1.9%減少し253万7千tとなりました(図表3-1-14)。
(飼料作物の収穫量は前年産に比べ増加)
飼料作物のTDN(*1)ベースの収穫量については、令和4(2022)年産は牧草の生育が順調であったことに加え、飼料用米や稲発酵粗飼料(WCS(*2)用稲)の作付けが拡大したことから、前年産に比べ5.9%増加し407万3千TDNtとなりました(図表3-1-15)。
また、令和5(2023)年産の飼料作物の作付面積は、前年産に比べ0.8%減少し101万8千haとなりました。

青刈りとうもろこし生産の推進
URL:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/
lin/l_siryo/aogari_corn.html
1 Total Digestible Nutrientsの略で、家畜が消化できる養分の総量
2 Whole Crop Silageの略で、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料のこと
(3)園芸作物等の生産動向
(野菜の生産量は前年度に比べ減少、果実の生産量は前年度に比べ増加)

かんきつを栽培する農業者
*写真の出典は、「農林水産省Webマガジン
aff(あふ) 2023年1月号」
令和4(2022)年度の野菜の生産量は、主要品目の多くが前年度並みとなった中で、一部の根菜類等において、令和4(2022)年8月の北・東日本を中心とした天候不順等の影響により生産量が減少したことから、前年度に比べ1.0%減少し1,124万tとなりました(図表3-1-16)。
令和4(2022)年度の果実の生産量は、多くの品目で生育期の天候に恵まれ、生産が順調であったことから、前年度に比べ2.2%増加し264万5千tとなりました(図表3-1-17)。
(事例)水田休耕期間の借地利用によりブロッコリーの作付けを拡大(石川県)


ブロッコリーの収穫
資料:有限会社安井ファーム
石川県白山市(はくさんし)の有限会社安井(やすい)ファームでは、期間借地による水田の高度利用を通じ、ブロッコリーを中心とした大規模な複合経営の取組を推進しています。
平成13(2001)年に設立した当初は水稲の単作を行っていましたが、水田複合経営へ転換を図ってきた結果、令和4(2022)年の栽培面積はブロッコリー84ha、水稲42ha、大豆17ha等となっています。
ブロッコリーの栽培では、水稲の裏作や近隣市町の水田の期間借地により規模拡大を実現しています。大麦を収穫してから水稲の作付けまでの期間、地域の未利用水田を期間借地し、貸し手と相互にメリットを享受しています。丁寧な仕事ぶりが地域で評価され、当初の地権者ごとの交渉から、地区生産組合との一括交渉による借地へと発展し、他地域にも展開しています。
また、選果場や冷蔵庫、ライスセンター、集出荷施設等を順次整備し、品質向上や数量の確保により、市場への出荷に加え、食品大手企業への長期安定出荷も拡大しています。
さらに、同社では、目標や成果、課題を従業員自らが設定する目標管理シートの導入のほか、課題に対して、他産業での職務経験で培った少人数での業務改善手法を取り入れることで従業員の主体性を育む人材育成を実践しています。また、各部門に責任者を配置し、意思決定権を移譲するとともに、スマートフォンの活用により、栽培履歴や生育状況、販売状況を全スタッフで共有しています。
同社では、今後とも水田の高度利用を図るため、水稲、麦、大豆にブロッコリーを組み合わせた2年3作体系を維持しながら、期間借地の更なる活用による水田農業の高収益化を推進していくこととしています。
(花きの産出額は前年産に比べ増加)
令和3(2021)年産の花きの産出額は、前年産に比べ6.8%増加し3,519億円となりました(図表3-1-18)。一方、作付面積は前年産に比べ2.4%減少し2万4千haとなりました。
農林水産省では、「物流の2024年問題」に対応した花き流通の効率化、需要のある品目の安定供給を図るための品目の転換や導入、病害虫被害の軽減等の産地の課題解決に必要な技術導入を支援するとともに、花き需要の回復に向けて、新たな需要開拓、花き利用の拡大に向けたPR活動等の前向きな取組を支援することとしています。
(茶の栽培面積は前年産に比べ減少)
令和5(2023)年産の茶の栽培面積は、前年産に比べ2.4%減少し3万6千haとなりました(図表3-1-19)。また、荒茶の生産量は、前年産に比べ2.6%減少し7万5千tとなりました。
農林水産省では、消費者ニーズへの対応や輸出の促進等に向け、茶樹の改植・新植等の支援を行うとともに、有機栽培への転換やスマート農業技術の実証等を支援しています。
(薬用作物の栽培面積は前年産に比べ増加)
漢方製剤等の原料となるミシマサイコやセンキュウ等の薬用作物の栽培面積については、令和3(2021)年産は、原料生薬の安定確保のための国産ニーズが高まっていることを背景として、前年産に比べ2.8%増加し508haとなりました(図表3-1-20)。
農林水産省では、産地と、漢方薬メーカー等の実需者が連携した栽培技術の確立のための実証圃(じっしょうほ)の設置等を支援するとともに、全国的な取組として、販路の確保・拡大に向けた地域相談会の開催等への取組を支援しています。
(てんさいの収穫量は前年産に比べ減少)
令和5(2023)年産のてんさいの作付面積は、前年産に比べ7.6%減少し5万1千haとなりました(図表3-1-21)。また、収穫量は前年産に比べ4.0%減少し340万3千tとなりました。このほか、糖度は高温多湿の影響で褐斑病(かっぱんびょう)が多発したことにより前年産に比べ2.4ポイント低下し13.7度となりました。
農林水産省では、直播(ちょくはん)栽培の拡大を始め、省力化や生産コスト低減、高温・病害対策等の取組を推進しています。
(さとうきびの収穫量は前年産に比べ減少)
令和4(2022)年産のさとうきびの収穫面積は、前年産並みの2万3千haとなりました(図表3-1-22)。一方、収穫量は前年産に比べ6.4%減少し127万2千tとなりました。このほか、糖度は前年産に比べ1.1ポイント低下し14.0度となりました。
農林水産省では、通年雇用による作業受託組織の強化を始め、地域における生産体制の強化、機械収穫や株出し栽培(*1)に適した新品種「はるのおうぎ」の普及等を推進しています。
1 さとうきび収穫後に萌芽する茎を肥培管理し、1年後のさとうきび収穫時期に再度収穫する栽培方法
(かんしょの収穫量は前年産に比べ増加)
令和5(2023)年産のかんしょの作付面積は、前年産並みの3万2千haとなりました(図表3-1-23)。一方、収穫量は前年産に比べ0.7%増加し71万6千tとなりました。
農林水産省では、共同利用施設の整備や省力化のための機械化体系確立等の取組を支援しています。また、サツマイモ基腐病(もとぐされびょう)の発生・まん延の防止を図るため、土壌消毒、健全な苗の調達等を支援するとともに、研究事業で得られた成果を踏まえつつ、防除技術の確立・普及に向けた取組を推進しています。
なお、令和5(2023)年産のかんしょ生産において、一部の圃場(ほじょう)でサツマイモ基腐病と異なる腐敗症状を呈するかんしょが確認されたことから、オープンイノベーション研究・実用化推進事業の緊急対応課題として、腐敗症状の発生原因の特定、効果的な防除対策の提案に向けて、農研機構が鹿児島県、宮崎県、鹿児島県(かごしまけん)経済農業協同組合連合会と連携して研究を行っています。
(ばれいしょの収穫量は前年産に比べ増加)
令和4(2022)年産のばれいしょの作付面積は、前年産並みの7万1千haとなりました(図表3-1-24)。一方、収穫量は前年産に比べ5.0%増加し228万3千tとなりました。
農林水産省では、省力化生産のための機械導入、収穫時の機上選別を倉庫前集中選別等に移行する取組を支援しています。また、ジャガイモシストセンチュウやジャガイモシロシストセンチュウの発生・まん延の防止を図るため、共同施設の整備等の推進や抵抗性品種への転換を推進しています。
(4)米の生産動向
(主食用米の生産量は前年産に比べ減少)
令和5(2023)年産の主食用米の生産量(*1)は、需要量の減少や他作物への転換等需要に応じた生産が進んだこと等から、前年産に比べ1.4%減少し661万tとなりました(図表3-1-25)。
1 農林水産省「作物統計」における主食用米の収穫量の数値
(米粉用米の生産量は前年度に比べ増加)
令和4(2022)年度の米粉用米の生産量は、主食用米からの作付転換が進んだことから前年度に比べ10.3%増加し4万6千tとなりました(図表3-1-26)。また、需要量は、消費者の米粉に対する関心の高まり等を背景として、前年度に比べ9.8%増加し4万5千tとなりました。

広がる!米粉の世界
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/
komeko/
(飼料用米の作付面積は前年産に比べ増加)
令和4(2022)年産の飼料用米の作付面積は、前年産に比べ22.7%増加し14万2千haとなりました(図表3-1-27)。また、生産量についても、前年産に比べ21.2%増加し令和12(2030)年度目標(70万t)を上回る80万3千tとなりました。
今後は、より定着性が高く、安定した供給につながる多収品種への切替えを進めていく観点から、令和6(2024)年産以降、一般品種に対する飼料用米の支援単価を段階的に引き下げていくこととしています。
(5)麦・大豆の生産動向
(小麦の作付面積は前年産に比べ増加)
令和5(2023)年産の小麦の作付面積は、前年産に比べ1.9%増加し23万2千haとなりました(図表3-1-28)。また、収穫量は、天候に恵まれ生育が良好に推移したこと等から、前年産に比べ10.1%増加し109万4千tとなりました。このほか、単収は前年産に比べ8.0%増加し472kg/10aとなりました(図表3-1-29)。
(大豆の作付面積は前年産に比べ増加)
令和5(2023)年産の大豆の作付面積は前年産に比べ2.0%増加し15万5千haとなりました(図表3-1-30)。また、収穫量は生育期間中において北海道や九州でおおむね天候に恵まれ、着さや数が多かったことから、前年産に比べ7.0%増加し26万tとなりました。このほか、単収は前年産に比べ5.0%増加し168kg/10aとなりました(図表3-1-31)。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883