第1節 農業の動向
我が国では、各地の気候や土壌等の条件に応じて、米、野菜、果実、畜産等の様々な農畜産物が生産されており、農業総産出額は、近年では9兆円前後で推移しています。品目ごとに需要に応じた生産の推進が求められる中、足下では原油価格・物価高騰の影響等により、我が国の農業生産や農業経営にも変化が見られています。
本節では、このような農業生産の動向、農業経営の動向、農業経営の安定化に向けた取組について紹介します。
(1)農業総産出額の動向
(農業総産出額は前年に比べ5.5%増加し9兆5千億円)
農業総産出額は、近年、農畜産物における需要に応じた生産の取組が進められてきたこと等により9兆円前後で推移しており、令和5(2023)年は耕種において米や野菜、畜産において鶏卵の価格が上昇したこと等から、前年に比べ5.5%増加し9兆4,987億円となりました(図表2-1-1)。

データ(エクセル:31KB)

データ(エクセル:26KB)
部門別の産出額を見ると、米の産出額は前年に比べ8.9%増加し1兆5,193億円となりました(図表2-1-2)。これは、令和5(2023)年産米の需要が堅調に推移したこと等により、民間在庫量が減少し、主食用米の取引価格が上昇したこと等によるものと考えられます。
野菜の産出額は前年に比べ4.3%増加し2兆3,243億円となりました。これは、きゅうり、ピーマン、ねぎ等の品目で令和5(2023)年8月から9月にかけて高温少雨の影響等により生産量が減少し、価格が上昇したこと等が寄与したものと考えられます。
果実の産出額は前年に比べ3.9%増加し9,590億円となりました。これは、国内外での高品質な果実の需要が堅調である一方、生産量の減少等により、みかん、りんご、ぶどうを始めとする果実の価格が前年産に比べ上昇したこと等が寄与したものと考えられます。
畜産の産出額は前年に比べ7.4%増加し3兆7,248億円となり、引き続き全ての部門の中で最も大きい数値となりました。このうち肉用牛は、和牛及び交雑種の出荷頭数が引き続き増加する中、和牛肉の需要が軟調に推移し価格が低下したこと等により産出額が減少したものと考えられます。一方、生乳については、夏場の猛暑に加え、需給バランスの改善に向けた生産抑制により生産量が減少したものの、飲用等向け及び乳製品向け乳価が引き上げられたこと等により、産出額が増加したものと考えられます。豚については、出荷頭数は前年を下回ったものの、枝肉重量の増加により生産量が増加したほか、引き続き需要が高く、価格が堅調に推移したこと等により、産出額が増加したものと考えられます。鶏卵については、令和4(2022)年10月以降の鳥インフルエンザの発生等に伴う生産量の減少等があったものの、価格が上昇したことで、産出額が増加したものと考えられます。
(都道府県別の農業産出額は、北海道が1兆3千億円で1位)
令和5(2023)年の都道府県別の農業産出額を見ると、1位は北海道で1兆3,478億円、2位は鹿児島県で5,438億円、3位は茨城県で4,571億円、4位は千葉県で4,029億円、5位は熊本県で3,757億円となっています(図表2-1-3)。上位5位の道県で、産出額の1位の部門を見ると、北海道、鹿児島県、千葉県、熊本県では畜産、茨城県では野菜となっています。令和5(2023)年の市町村別の農業産出額を見ると、1位は宮崎県都城市(みやこのじょうし)で981億円、2位は愛知県田原市(たはらし)で891億1千万円、3位は茨城県鉾田市(ほこたし)で677億1千万円、4位は北海道別海町(べつかいちょう)で639億3千万円、5位は千葉県旭市(あさひし)で559億4千万円となっています(図表2-1-4)。

データ(エクセル:36KB)

データ(エクセル:30KB)
耕種部門における品目別の都道府県別割合を見ると、米は新潟県、いも類、野菜及び工芸農作物は北海道、果実は青森県、花きは愛知県が最も大きくなっています(図表2-1-5)。
また、畜産部門における品目別の都道府県別割合を見ると、生乳及び肉用牛は北海道、豚及びブロイラーは鹿児島県、鶏卵は千葉県が最も大きくなっています。

データ(エクセル:32KB)
(生産農業所得は前年に比べ6.1%増加し3兆3千億円)
生産農業所得については、長期的には農業総産出額の減少や農業生産資材価格の上昇により減少傾向が続いてきましたが、農畜産物において需要に応じた生産の取組が進められてきたこと等から、平成27(2015)年以降は、農業総産出額の増減はあるものの、3兆円台で推移してきました(図表2-1-6)。
令和5(2023)年は、農産物の価格が上昇したこと等から、前年に比べ6.1%増加し3兆2,929億円となりました。

データ(エクセル:27KB)
(2)農業経営の動向
(1経営体当たりの農業所得は全農業経営体では114万円、主業経営体では404万円)
令和5(2023)年における全農業経営体1経営体当たりの農業粗収益は、作物収入や畜産収入が増加したこと等から、前年に比べ82万3千円増加し1,247万9千円となっています(図表2-1-7)。また、農業経営費(*1)は、肥料費や飼料費等が増加したことから、前年に比べ66万3千円増加し1,133万7千円となりました。この結果、農業粗収益から農業経営費を除いた農業所得は、前年に比べ16万円増加し114万2千円となっています。
一方、令和5(2023)年における主業経営体(*2)1経営体当たりの農業粗収益は、作物収入や畜産収入が増加したこと等から、前年に比べ148万9千円増加し2,184万8千円となっています(図表2-1-8)。また、農業経営費は、肥料費、飼料費等が増加したことから、前年に比べ107万6千円増加し1,780万6千円となりました。この結果、農業粗収益から農業経営費を除いた農業所得は、前年に比べ41万3千円増加し404万2千円となっています。
*1 雇人費、種苗費、肥料費、飼料費や農薬衛生費等の農業経営に要した一切の経費
*2 農業所得が主(世帯所得の50%以上が農業所得)で、1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体
(農業生産性の一層の向上が重要)
米、小麦、大豆の単位面積当たりの労働時間の推移を長期的に見ると、昭和35(1960)年産以降、圃場(ほじょう)整備や機械化の進展等により労働時間は大幅に減少しました。一方、平成12(2000)年産以降からは労働時間の減少率が小さくなってきています(図表2-1-9)。

データ(エクセル:36KB)
単位面積当たりの収量について、諸外国と比較すると、我が国においては近年米、小麦、大豆ともに大幅な単収の向上が見られないのに対し、米は米国、小麦は中国、大豆は米国とブラジルにおいて増加が目覚ましく我が国を大きく上回っています(図表2-1-10)。

データ(エクセル:37KB)
また、全農業経営体1経営体当たりの労働生産性についても近年顕著な上昇は見られず令和5(2023)年は63.9万円となっており、経営耕地面積10a当たりの土地生産性についても同様の傾向で令和5(2023)年は7.4万円となっています(図表2-1-11)。
このように、労働生産性、土地生産性ともに上昇率が停滞傾向にあり、基幹的農業従事者が減少していく中で農業生産を維持・拡大していくためには、労働生産性や土地生産性の向上が必要です。このため、担い手への農地の集積・集約化を進めるとともに、スマート農業を始めとした農業生産性向上のための設備投資や、省力化や多収化等に資する新品種の開発等を更に推進していくことが重要となっています。
(事例)直播栽培とスマート農業技術を駆使し、農業生産性を向上(岡山県)
(1)直播栽培とスマート農業技術を組み合わせて作業を省力化

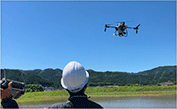
ドローンを活用した直播作業
資料:農事組合法人寄江原
水稲の直播(ちょくはん)栽培は種籾(たねもみ)を水田に直接播種(はしゅ)するため、育苗や移植作業が不要となり、特に春作業の省力化が期待できますが、一般的には出芽や苗立ちの不安定性等から直播方法に応じた適切な栽培管理が必要となります。
岡山県真庭市(まにわし)の農事組合法人寄江原(よりえばら)では中山間地域に適したスマート農業技術と直播栽培を組み合わせ、安定した栽培法の確立や栽培管理状況の可視化を通して省力化に取り組んでいます。
(2)スマート農業や蓄積データ活用で新規参入しやすい農業を目指す
同法人では、直播栽培においては農地がなるべく均平であることが望ましいため、ドローンで圃場の高低差を測定し、その結果を踏まえて代かきをすることで農地の均平度を高め、安定した生育環境を確保しています。
また、直播栽培では圃場の水管理が一層重要になるため、同法人では、約13haの水田の給水や排水をスマートフォンやパソコンを用いて遠隔操作することができる水管理システムにより、きめ細かな水管理を行っています。水管理システムによって水位や水温等のデータを取得し、そのデータを蓄積していくことで、栽培管理状況を可視化しています。さらに、直進アシスト田植機での条播(じょうは)のほか、令和5(2023)年からはドローンによる散播(さんぱ)も行っています。
同法人では、スマート農業機械等を活用することによって作業の省力化を実現しただけでなく、蓄積したデータを用いて作業を組合員に分かりやすく指示することにより、同法人に新たに加入した農業の経験がない組合員もスマート農業機械を活用して熟練者と同等の作業を行えるようになりました。このような人材が担い手となっていくことが期待されています。新規参入しやすい農業を目指し、今後は組合外からドローンによる防除や直播作業を受託することも視野に入れ、スマート農業技術の活用や直播栽培の取組を促進するとしています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883







