第2節 農地の確保と有効利用
農業者の減少・高齢化等の課題に直面している我が国の農業においては、荒廃農地(*1)が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このような中、食料安全保障の強化や農業の成長産業化を進めていくためには、生産基盤である農地が持続性をもって最大限利用されるよう取組を進めていく必要があります。
本節では、農地面積の動向や担い手への農地の集積・集約化の取組、地域計画の策定に向けた取組等について紹介します。
*1 現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地
(1)農地の動向
(農地面積は減少傾向で推移)
令和6(2024)年の農地面積(*1)は、荒廃農地からの再生等による増加があったものの、耕地の荒廃や転用等による減少を受け、前年に比べ2万5千ha減少し427万haとなりました(図表2-2-1)。作付(栽培)延べ面積も減少傾向が続いている中、令和5(2023)年の耕地利用率は前年に比べ0.3ポイント低下し91.0%となっています。

データ(エクセル:30KB)
*1 農林水産省「耕地及び作付面積統計」における耕地面積の数値
(新たに発生した荒廃農地面積は2.5万ha)
令和5(2023)年度に新たに発生した荒廃農地面積は2.5万haとなりました(図表2-2-2)。主な理由としては、農業者の高齢化・病気・死亡や、担い手・労働力不足が挙げられます。
一方、新たに再生利用された荒廃農地面積は1.0万haとなりました。これは、市町村・農業委員会の働き掛けや、農地所有者・地域住民による保全活動等によるものです。なお、令和6(2024)年3月末時点における荒廃農地面積は25.7万ha、うち再生利用が可能な荒廃農地面積は9.4万haとなっています。
今後とも、地域における積極的な話合いを通じて、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の活用、担い手への農地の集積・集約化、放牧等の農地の粗放的な利用等により荒廃農地の発生を防止するとともに、農業委員会による所有者等への利用の働き掛け等により荒廃農地の再生利用に取り組むこととしています。

データ(エクセル:34KB)
(事例)オリーブの生産拡大によって荒廃農地を再生(大分県)
(1)荒廃農地をオリーブ農園として再生


オリーブ農園に再生した
荒廃農地
資料:小関オリーブ農園
大分県豊後高田市(ぶんごたかだし)の香々地(かかぢ)地区では、元々かんきつ類等を主体とした農業が営まれていましたが、高齢化の進行や後継者不足から、耕作放棄された農地が増加していました。平成23(2011)年に、建設業を営んでいた小関直也(おぜきなおや)さんは、建設需要の減少に伴い、新たな業種への参入を検討していた中、オリーブ栽培による農業参入を決意しました。自己の建設機械活用や同業者の支援により荒廃農地を再生し、オリーブ苗を定植しました。このほか、肉用牛の放牧に取り組む就農者も入植し、オリーブ栽培への転換や荒廃農地での放牧をしながら、地域一体となって農地保全・管理を行ってきました。
(2)オリーブ産業を通して地域の雇用拡大に貢献
今後は、地域ぐるみの話合いを更に進め、樹園地の伐採・整地によって荒廃農地を再生して新規就農者や認定農業者への集積を行い、法人化も視野に入れています。また、加工や販売までの一貫したオリーブ産業として業態を拡大させ、農業の所得向上や地域の雇用拡大にも貢献しています。
(所有者不明農地への対応を推進)
相続未登記農地の面積は、令和4(2022)年3月末時点で52.0万ha、このうち遊休農地(*1)は2万9千haとなっています。また、相続未登記のおそれのある農地の面積は50万9千ha、このうち遊休農地は2万9千haとなっています。
通常、所有者不明農地であっても、農業委員会が行う探索・公示の手続により農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)経由で担い手へ貸付けできる仕組みを措置し、担い手への農地の集積・集約化を進めています。農地バンクに貸付けを行った所有者不明農地の面積は、令和6(2024)年3月末時点で220haとなっています。
所有者不明土地の解消に向けて、令和3(2021)年に民法等が改正され、令和6(2024)年4月から相続登記の申請が義務化されました。
*1 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する農地をいう。
(1)現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
(2)その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地((1)に掲げる農地を除く。)
(企業の農業参入を推進)
農地を借りて農業経営を行うリース法人数は、平成21(2009)年の農地法改正によりリース方式による参入を全面解禁して以降、増加傾向で推移してきましたが、令和5(2023)年1月時点では集計方法の変更もあったことから、初めて前年に比べ81法人減少し4,121法人となりました。一方、リース法人の借入面積の合計は1万5,295ha、1法人当たりの平均面積は3.7haとなり、それぞれ前年に比べ1,071ha、0.3ha増加しています。
農林水産省では、農地バンクを中心としてリース方式による企業の参入を促進することとしています。
(食品事業者等との連携を通じて農地所有適格法人の経営基盤を強化)
我が国においては、農地法上、基本的に、農地を所有できる法人は農地所有適格法人に限られており、その他の一般法人は賃借による農地の権利取得が認められています。
令和5(2023)年1月時点では、農地所有適格法人の経営面積の合計は約64万ha、1法人当たりの平均面積は30.3haとなっており、農地の受け皿として大きな役割を果たしています。
一般企業の農業参入については引き続きリース方式が基本です。一方、農地所有適格法人の一部に、取引企業との連携による経営発展を図るニーズがあることも踏まえ、令和6(2024)年6月に公布された改正農業経営基盤強化促進法(*1)により、農業経営発展計画制度を創設しました。本制度が施行される令和7(2025)年4月からは、認定農業者として一定の実績があること等の要件を満たす農地所有適格法人が、取引実績のある食品事業者等との出資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合、農林水産大臣の計画認定による議決権要件の特例を受けることができることとされています。
これにより、農地所有適格法人は農地の権利移転等の重要事項に関する農業関係者の拒否権を確保しつつ、最大3分の2未満まで食品事業者等から出資を受けることが可能となります。
取引企業の関与の増加等に対する農業現場の懸念への対応として、農林水産省では、本制度に基づく計画の実施状況や認定を受けた法人の農地の権利移転・転用を国が監督するなどの措置を講ずることとしています。
*1 正式名称は「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」
(外国法人等が議決権を有する日本法人等による農地取得は0.6ha)
令和5(2023)年に外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得はありませんでした(*1)。また、外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者について、これらが議決権を有する日本法人又は役員となっている日本法人による農地取得は1社、0.6haとなっています(*2)。
我が国において農地を取得する際には、農地法において、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと、必要な農作業に常時従事すること等の要件を満たす必要があります。このため、地域とのつながりを持って農業を継続的に営むことができない者は農地を取得することはできず、我が国に居住しない外国人等が農地を取得することは基本的に困難であると考えられます。
*1 居住地が海外にある外国人と思われる者について、平成29(2017)年から令和5(2023)年までの累計は1者、0.1ha
*2 平成29(2017)年から令和5(2023)年までの累計は6社、68.2ha(売渡面積5.3haを除く。)
(2)農地の集積・集約化の推進
(農地の総権利移動の面積は近年横ばい傾向で推移)

データ(エクセル:27KB)
農地の総権利移動の面積については、近年横ばい傾向で推移しており、令和4(2022)年は前年に比べ5.6%減少し28万2千haとなりました(図表2-2-3)。また、令和4(2022)年における農地の権利移動の件数は、前年に比べ3万6千件減少し50万3千件となりました。
(担い手への農地集積率は前年度に比べ0.9ポイント上昇)
農地中間管理事業を創設した平成26(2014)年4月以降、担い手への農地集積率については上昇傾向にあり、令和5(2023)年度は前年度に比べ0.9ポイント上昇し60.4%となりました(図表2-2-4)。

データ(エクセル:30KB)
農業者の減少が進行する中、農業の生産基盤を維持する観点から、農地の受け手となる農業経営体の役割が一層重要となっており、農地バンク等の活用や基盤整備の推進により、担い手等の目標地図(*1)に位置付けられた受け手への農地の集積・集約化を進めていく必要があります。
*1 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、地図に表示したもの
(農地バンクの借入面積は前年度から7,300ha増加)
農業現場においては、農地が分散している状況を改善し、農地を引き受けやすくしていくことが重要となっており、農地バンクにおいては、地域内に分散・錯綜(さくそう)する農地を借り受け、まとまった形で担い手へ再配分し、農地の集積・集約化を実現する農地中間管理事業を行っています。令和5(2023)年度の農地バンクの借入面積は前年度から7,300ha増加し5万2千haとなったほか、転貸面積は前年度から8,200ha増加し6万2千ha、そのうち新規集積面積は前年度から4,600ha増加し2万1千haとなっています。
農地の集積・集約化を進めることによって、(1)作業がしやすくなり、生産コストや手間を減らすことができる、(2)スマート農業等にも取り組みやすくなる、(3)遊休農地の発生防止を図れるなどの効果が期待できます。
農地バンクは、地域計画の中で、目指すべき将来の農地の利用を明確化した目標地図に位置付けられた受け手に対して、農地の集積・集約化を進めていくこととしています。
農林水産省では、農地バンクが分散した農地をまとめて借り受けた場合には、農業者の費用負担がない基盤整備、農地の集約化等に取り組む地域等への機構集積協力金の交付、出し手に対する固定資産税の軽減を支援措置として講じています。
(農業委員会が農地利用の最適化活動を通じて地域計画の策定を促進)
農業委員会は、農地法等の法令業務や農地利用の最適化業務を行う行政委員会で、全国の市町村に設置されています。農業委員は農地の権利移動の許可等を審議し、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は現場で農地の利用集積や遊休農地の解消、新規参入の促進等による農地利用の最適化活動を担っています。
農業委員会系統組織では、地域計画の策定に向けた、地域内における農地の出し手・受け手の意向把握、目標地図の素案作成、農地バンクへの農地貸付け等を積極的に促進することとしています。

データ(エクセル:28KB)
また、農業委員の任命には、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮し、青年・女性の積極的な登用に努めることとしています。
令和6(2024)年の農業委員会数は、1,696委員会となっています(図表2-2-5)。また、農業委員数は23,016人、推進委員数は17,513人で、合わせて40,529人となっています。
(事例)農業委員が地域における話合いを活性化(長崎県)
(1)地域計画策定に向けた話合いを開始

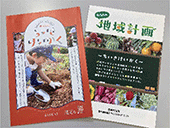
西海市独自のパンフレット
資料:長崎県西海市
長崎県西海市(さいかいし)は、県内有数のうんしゅうみかんの産地です。同市では、「人・農地プラン」と同様、地域計画についても旧小学校区単位で策定することとしています。
同市は、地域計画の策定に向け、令和5(2023)年度に関係機関で協議を行い、令和6(2024)年2月から地域での話合いを開始しました。4コマ漫画で地域計画を分かりやすく解説した独自のパンフレットを作成し、全戸に配布するなど、理解促進に取り組んでいます。
この結果、県内で初めて樹園地の基盤整備を行った地区では、農地バンクを活用した農地の集積・集約化が進み、話合いがスムーズに進んでいます。
他方、条件の悪い農地では、イノシシによる農作物への被害が多発して離農する者もおり、荒廃農地が増えて、今後の営農の在り方が課題になっていました。
(2)農業委員が地域の話合いを活性化
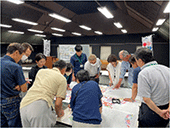
地域計画策定の協議の場
資料:長崎県西海市
同市の農業委員は、日頃から農地の見回りを行い、作付品目等の農地の状況について経年変化を含めて把握しているため、話合いの場に多くの農業者が参加するよう、推進委員とともに声掛けを行っています。農業委員や推進委員が、参加できなかった農業者の実態や意向を補足することで、話合いを円滑に進めています。
(3)地域計画策定によって見えてきた地域の課題を迅速に共有
地域計画の策定に向けた話合いの場を持つことによって、離農の事前情報や基盤整備の意向といった今後の営農の意向を的確に把握することができ、関係機関で情報共有が迅速に行われるようになりました。
(3)地域計画の策定の推進
(ウェブ意見交換会等の実施により、地域計画の策定を支援)
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。令和5(2023)年4月に施行された改正農業経営基盤強化促進法(*1)では、市街化区域を除き、基本構想を策定している市町村において、これまでの「人・農地プラン」を土台とし、農業者等による話合いを踏まえて、将来の地域農業の在り方や目指すべき将来の農地の利用を明確化した目標地図を含めた「地域計画」を策定することとされました。
地域計画は、地域農業の将来設計図となるものであり、若年者、女性、新規就農者や法人等の地域の幅広い意見を取り入れながら、地域の農業関係者が一体となって話し合い、策定することが重要です。
市町村は、幅広い関係者に参加を呼び掛け、協議の場を設置するとともに、協議の場では、区域の現状や課題を踏まえ、輸入依存度の高い小麦・大豆等の生産拡大、輸出向け農産物の生産、有機農業の導入、耕畜連携等による飼料の生産・利用の拡大、水田の畑地化といった地域の実情を踏まえた目指すべき将来の地域農業について協議することが重要です。地域計画の策定は、食料安全保障の強化やスマート農業技術の導入による生産性の向上、環境と調和のとれた食料システムの確立等にも重要な意義を有するものです。
農林水産省では、令和7(2025)年3月末の策定期限に向けて、地域での話合いをコーディネートする専門家の活用を始め、市町村による地域計画の策定に必要な取組や農業委員会の活動経費を支援しました。また、地域計画の策定の参考となる地域計画策定マニュアルや飼料生産も含めた地域計画策定のポイントの作成、地域計画の策定に向けて参考となる事例の紹介、先進的な地域とのウェブ意見交換会の実施、現場での意見交換やパンフレットの配布等により策定を呼び掛けました。
*1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」
(策定された地域計画を踏まえた着実な取組が重要)
地域計画の策定を通じて、地域の課題が可視化され、担い手の不在や基盤整備が必要になることといった地域の実情が浮き彫りとなります。
このため、地域計画は一度策定して終わりではなく、市町村を始めとする関係機関や地域の農業者の話合いによる見直しを毎年行い、協議を進めていくことが重要です。
農林水産省では、地域計画の実現に向け、地域計画変更マニュアルの作成や、多様な関係者の参画により話合いが活性化した事例の横展開、現場との意見交換等により市町村の取組等をサポートしていきます。
また、地域計画により明らかとなった地域の課題を解決し、地域計画の実現を後押しするため、現場の状況に応じて、「将来像が明確化された地域計画の実現に向けた支援」や「課題が見える化された地域計画の解決に向けた支援」として、担い手への農業用機械・施設の導入、受け手不在の農地の解消に向けた支援等を着実に行っていくこととしています。
(事例)話合いを通じて農地の集積・集約化を推進(岩手県)
(1)営農の組織化から地域農業の在り方を議論


湯本地区での話合いの様子
資料:岩手県花巻市
岩手県花巻市(はなまきし)の花巻(はなまき)農業協同組合では、集落における農業関係等の自主的な活動組織である「農家組合」を同農協の重要な組合員組織として位置付け、平成11(1999)年に全ての農家組合が「集落営農振興計画」を策定して以降、継続して地域の話合いが行われています。同市では、同市役所、同農協や同市農業振興公社等の農業関係機関がチームとなって農家組合を訪問し、農地バンクを活用した農地の集積・集約化に取り組み、担い手への農地集積率は令和5(2023)年3月時点で62.7%となっていました。他方、オペレーターの高齢化等が課題で集落営農が解散する事例も発生しています。このため、同市湯本(ゆもと)地区では、令和3(2021)年度から、農家組合の単位からエリアを広げて、農地の集約化に向けた話合いを本格化し、令和6(2024)年4月に地域計画を策定しました。
(2)標準賃料の設定により、地域内でサポートをし合える体制を整備
話合いを進めていく中で、農地の賃料や耕作条件について議論を行い、条件ごとの標準賃料を設定することで、農地の交換の円滑化や担い手の急なリタイアに備える体制整備にもつながりました。同地区では、このような話合いを通じて、農業用ドローン、自動操舵(そうだ)システム、水管理システム等のスマート農業技術の導入といった技術的事項や、人材の活用等についても話合いを行っており、今後も地域での話合いを継続し、問題意識の共有と課題解決に向けた意思統一を図っていくこととしています。
(事例)地域の課題を共有して地域計画を策定(富山県)
(1)地域計画策定のために、地域の課題の共有が必要


中田地区での協議の場
資料:富山県高岡市
富山県高岡市(たかおかし)では、計画的に地域の課題を話し合う場を設け、地域計画策定につなげています。
このうち、同市中田(なかだ)地区では、「人・農地プラン」の取組以前から定期的な話合いの場を設けており、次世代に農地を継承していくために、担い手への農地の集積に積極的に取り組み、地域の課題も話合いの場で共有していました。そのため、地域計画の協議開始時から農地集積率も90%を超えており、同地区では令和6(2024)年3月までに地域計画を策定、公表することができました。今後は新たに地域に入ってきた担い手との交流や、スマート農業技術の導入のための講習会といった、担い手一人一人が感じている課題を解決するための取組を行うとしています。
(2)課題を抱える地域での話合いを実施
一方、同市内の全ての地区で中田地区と同様に協議がスムーズに進んでいるわけではありません。同市では主に平野で水田作を中心とした農業が営まれていますが、担い手が高齢化する一方、農地の区画が小さく、畦畔(けいはん)や用排水の維持管理が困難なことも多いため、今後の農地の受け手も見つからない地区も少なくありません。同市ではそのような地区を含め、将来の地図を思い描くことが難しい地区については、まずは地域の課題を共有し、将来の地域農業の在り方について話合いを続けていくとしています。
(4)農業振興地域制度による農用地の確保
(農業振興地域制度に基づき農用地の確保を推進)
農林水産省では、農業上の利用を図るべき土地の区域を設定する農業振興地域制度と個々の農地の転用等を規制する農地転用許可制度等により農地の確保とその有効利用を図っています。農業振興地域制度では、都道府県知事が、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域を農業振興地域として指定することとしており、さらに市町村において、同地域内の土地について農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)を定めることとしています。この農用地区域内の土地については、開発行為が制限されるほか農地転用許可制度において転用が不許可とされるなどの措置がとられています(図表2-2-6)。

(農振法を改正し、農地の総量確保のための措置を強化)
令和5(2023)年の農地全体の面積(*1)は、耕地の荒廃や転用等により平成27(2015)年に比べ約20万ha減少しており、年平均2.5万haで減少しています(図表2-2-7)。一方、農用地区域内農地面積は年平均0.8万haの減少にとどまっており、農地転用について、優良農地以外の農地への誘導に一定の効果が見られています。
食料安全保障の根幹は、人と農地の確保であり、世界の食料事情が不安定化する中で、我が国の食料安全保障を確保するため、食料生産の基盤である農地の総量確保と、その適正利用のための措置を強化することが必要です。このため、「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」が令和6(2024)年6月に成立しました。

データ(エクセル:29KB)
同法では、農業振興地域の整備に関する法律の目的規定に食料の安定供給の確保及びそのために必要な農用地等を確保する旨を明記するとともに、国と地方公共団体の責務を明確化することとしています。また、農用地区域からの除外に係る都道府県の同意基準として都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないことを規定するとともに、国の関与に係る手続を整備し、農地の総量確保のための措置の強化を図ることとしています(図表2-2-8)。

*1 農林水産省「耕地及び作付面積統計」における耕地面積の数値
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




