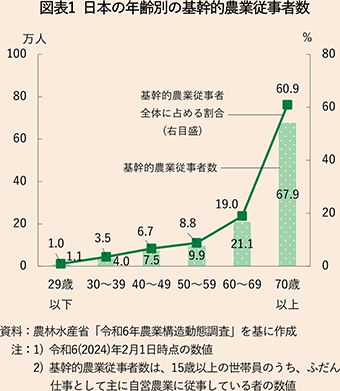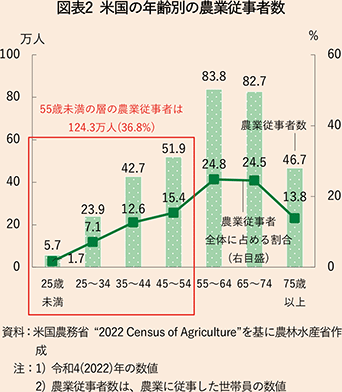第3節 担い手の育成・確保と多様な農業者による農業生産活動
農業者の減少・高齢化等に直面している我が国の農業が、成長産業として持続的に発展していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を目指す担い手の育成・確保が必要です。また、地域農業を維持し、持続可能なものとしていくためには、担い手の育成・確保の取組と併せて、地域の話合いを基に、農業を副業的に営む経営体等の多様な農業者による農業生産活動等を通じた農地の確保が図られることも重要です。
本節では、農業経営体の動向、経営継承・新規就農、多様な農業者による農業生産活動等の取組について紹介します。
(1)農業経営体の動向等
(農業経営体数は減少傾向で推移)
農業経営体数については減少傾向で推移しており、令和6(2024)年は前年に比べ5.0%減少し88万3千経営体となりました(図表2-3-1)。
このうち個人経営体は前年に比べ5.2%減少し84万2千経営体(全体の95.4%)となった一方、団体経営体は前年に比べ0.7%増加し4万1千経営体(全体の4.6%)となっています。
なお、個人経営体のうち、主業経営体は17万7千経営体、準主業経営体は10万2千経営体、副業的経営体は56万4千経営体となっています。

データ(エクセル:28KB)
(基幹的農業従事者数は約20年間で半減)
基幹的農業従事者(*1)数は約20年間で半減しており、平成12(2000)年の240万人から令和6(2024)年は111万4千人にまで減少しています(図表2-3-2)。このうち49歳以下の基幹的農業従事者数は12万5千人と全体の11.2%を占めている一方、65歳以上は79万9千人と全体の71.7%を占めています。また、令和6(2024)年の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳となっており、高齢化が進行しています。

データ(エクセル:29KB)
*1 トピックス3を参照
(基幹的農業従事者の年齢割合は部門別に見ると異なる状況)
販売金額1位の部門別に基幹的農業従事者の年齢割合を見ると、稲作や果樹類では70歳以上の高齢者層が半数以上を占めているものの、施設野菜・酪農・養豚・養鶏では49歳以下の若年層が2割を超えており、他の品目に比べ割合が高くなっています(図表2-3-3)。農業の中でも扱う品目によって働き方は異なっており、年齢割合の違いに影響していることがうかがわれます。
一方、法人その他団体経営体の農業就業者は、各部門でバランスの取れた年齢割合となっており、若年層の割合も多くなっています。法人その他団体経営体では、若年層の雇用が進んでいることがうかがわれます。

データ(エクセル:30KB)
(コラム)米国でも高齢化の傾向が続くものの、日米では農業従事者の年齢構成に差
我が国では、農業者の減少・高齢化が大きな課題となっており、基幹的農業従事者数は、令和6(2024)年には111万4千人、うち70歳以上の層が60.9%を占め、平均年齢は69.2歳となっています(図表1)。
令和6(2024)年2月に米国農務省が公表した調査では、米国でも引き続き農業従事者の高齢化傾向が続いていると分析しています(図表2)。
同調査によると、米国の農業従事者の平均年齢は、令和4(2022)年は58.1歳と前回調査時の平成29(2017)年に比べ0.6歳上昇しました。また、農業従事者数を年齢別に見ると、55歳未満の層が全体の約4割を占めているものの、年齢構成のピークは55~64歳と65~74歳の二つの層となっています。
我が国と米国では、全人口の年齢構成が異なり、農業を取り巻く環境も異なるため、一概に比較することはできませんが、我が国では米国よりも高齢の農業従事者が全体に占める割合が多いことがうかがわれます。
(農業者年金の被保険者数は減少傾向で推移)
農業者年金は、農業従事者のうち厚生年金に加入していない自営農業に従事する個人が任意で加入できる年金制度です。同制度においては農業者の減少・高齢化等に対応した積立方式・確定拠出型が採用されており、農林水産省では、青色申告を行っている認定農業者等やその者と家族経営協定を結び経営参画している配偶者・後継者等一定の要件を満たす対象者の保険料負担を軽減するための政策支援を実施し、農業者の老後生活の安定と農業者の確保を図っています。

データ(エクセル:26KB)
農業者年金の被保険者数については減少傾向で推移しており、令和5(2023)年度は前年度に比べ667人減少し4万3,909人となっています(図表2-3-4)。一方、受給権者数については増加傾向で推移しており、令和5(2023)年度は前年度に比べ2,037人増加し5万7,413人となっています。
年金等を給付する事業を実施している独立行政法人農業者年金基金(のうぎょうしゃねんきんききん)では、農業者年金事業の業務の一部を担う農業委員会系統組織及び農協系統組織と連携して、若者や女性の加入拡大に向け、推進活動を実施しています。
(2)経営継承や新規就農、人材育成・確保等
(規模の小さな経営体における後継者の確保は深刻な状況)

データ(エクセル:23KB)
5年以内に農業経営を引き継ぐ後継者を確保している経営体の割合は全体で3割未満であり、経営耕地面積規模別に見ると、平地農業地域では規模が大きい経営体ほど後継者の確保割合は高まっています(図表2-3-5)。一方で、50ha以上の層においてもその割合は6割以下にとどまっており、規模の小さな1ha未満の層においては、2割程度になっています。
他の農業地域類型区分でも同様の傾向が見られており、農業経営の後継者が十分に確保されていない状況です。農業生産基盤を維持していくためには、農地はもとより、農地以外の施設等の経営資源や、技術・ノウハウ等を次世代の経営者に引き継ぎ、計画的な経営継承を促進することが必要となっています。
農林水産省は、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、地域の担い手から経営を継承した後継者が行う経営発展に向けた取組を市町村と一体となって支援するとともに、都道府県が整備している農業経営・就農支援センターにおいて相談対応や専門家による経営継承計画の策定支援、就農希望者と経営移譲希望者とのマッチングへの支援を行うなど、円滑な経営継承を進めています。
(新規就農者数が前年に比べ減少)
令和5(2023)年の新規就農者数は、前年に比べ5.2%減少し4万3,460人となりました(図表2-3-6)。就農形態別で見ると、令和5(2023)年の新規自営農業就農者は前年に比べ3.4%減少し3万330人、新規雇用就農者は前年に比べ12.0%減少し9,300人、新規参入者は前年に比べ1.0%減少し3,830人となりました。特に新規雇用就農者数については、他産業との雇用労働者の採用競争や、厳しい経営環境が求人数に影響した可能性等が考えられます。
年齢階層別では、60~64歳の新規就農者数は、前年に比べ20.7%減少し5,350人となりました。また、将来の担い手として期待される49歳以下の新規就農者数は、平成27(2015)年をピークに減少傾向で推移しており、令和5(2023)年は前年に比べ5.8%減少し1万5,890人となりました。さらに、49歳以下の新規就農者数のうち新規雇用就農者の割合は、令和5(2023)年には新規自営農業就農者(40.4%)を上回る43.3%を占めており、新規就農者の受け皿としても法人経営体の役割が大きくなっています。

データ(エクセル:30KB)
農業者の減少・高齢化が進む中、地域農業を持続的に発展させていくためには、農業の内外から若年層の新規就農を促進する必要があります。
このため、農林水産省では、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、就農相談会の開催や、職業としての農業の魅力の発信等について支援を行っています。また、就農準備段階や就農直後の経営確立を支援する資金や雇用就農を促進するための資金の交付に加え、経営発展のための機械・施設等の導入を地方と連携して親元就農も含めて支援するとともに、伴走機関等による研修向け農場の整備、新規就農者への技術サポート等の取組を支援しています。
このほか、農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画を作成し市町村から計画の認定を受けた認定新規就農者は、令和4(2022)年度は前年度に比べ2.3%増加し1万806人となりました。農林水産省では、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新規就農施策を重点的に支援しています。
(事例)新規就農の育成支援を受け、安定した農業経営を実現(福岡県)
(1)ライフステージの変化に合わせて、新規就農に挑戦


立石宜丈さん
資料:立石宜丈さん
福岡県大木町(おおきまち)の立石宜丈(たていしよしひろ)さんは、令和2(2020)年から新規就農して、同県の名産品である「あまおう」の栽培に取り組んでいます。
立石さんは、元々大阪府で会社員をしていましたが、実家が食品加工業を営んでおり、独立して農業経営に取り組みたいと考えていました。そのような中、子供が小学校に入学したタイミングをきっかけに、農業の収支計画や長期的な貯蓄計画を作成し、家族の理解を得て、妻の出身地である福岡県で農業を始めました。
(2)新規就農の支援を受け、就農1年目から福岡県平均以上の単収を達成
まず、就農に当たっては、公益財団法人福岡県(ふくおかけん)農業振興推進機構(のうぎょうしんこうすいしんきこう)に相談し、大木町新規就農育成支援協議会(おおきまちしんきしゅうのういくせいしえんきょうぎかい)を通じて、研修機関である株式会社NJ(エヌジェイ)アグリサポートで1年間研修を受けて、いちごの栽培技術を学びました。
農業を開始する際には、農地を確保することが課題となりましたが、地域行事で知り合った近隣の住民から情報を得て、農地を確保することが出来ました。
また、いちごの栽培に当たっては、ハウスを建設しますが、栽培を開始できるタイミングが9月であり、8月中旬までに必要な床づくり等の作業を行う必要があります。その際には、研修機関の卒業生が集まって手伝ってくれたため、短い期間で床づくりを終えることができ、スムーズに栽培を始めることが出来ました。
このように、研修機関の卒業生や近隣の住民の助力があり、就農1年目から福岡県平均以上の単収を達成しています。
さらに、資金面では農業次世代人材投資資金(経営開始型)(*)や無利子の融資である青年等就農資金を活用して、トラクター等の必要な機材を揃えており、就農3年目には、中古ハウスや農地を借りて44aまで規模拡大を実現させ、安定した農業経営を行っています。
(3)地域や人とのつながりを大切にして、安定した農業経営を継続
立石さんは、自らを受け入れてくれた産地に感謝しており、地域や人とのつながりを大切にしています。今後は、産地の維持を図るため、雇用確保に向けた従業員の募集・育成の強化、就業体制の整備を検討しながら、安定した農業経営を続けていくこととしています。
* 令和6(2024)年度における名称は、経営開始資金
(農業高校・農業大学校による教育の高度化が進展)

データ(エクセル:26KB)
農業経営の担い手を養成する教育機関のうち、農業高校は全ての都道府県、農業大学校(*1)は41道府県において設置されています。
このうち農業大学校の卒業生数については、令和元(2019)年度以降はほぼ横ばいで推移しており、令和5(2023)年度の卒業生数は1,698人、卒業後に就農した者は897人(卒業生全体の52.8%)となっています(図表2-3-7)。このほか、同年度の卒業生全体に占める自営就農の割合は13.8%、雇用就農の割合は33.0%となりました。
また、近年、GAP(*2)(農業生産工程管理)に取り組む農業高校・農業大学校も増加しており、令和6(2024)年3月末時点で97の農業高校、28の農業大学校等が第三者機関によるGAP認証を取得しています。GAPの学習・実践を通じて、農業生産技術の習得に加えて、経営感覚・国際感覚を兼ね備えた人材の育成に資することが期待されています。
農林水産省では、若年層に農業の魅力を伝え、将来的に農業を職業として選択する人材を育成するため、スマート農業や有機農業等の教育カリキュラムの強化のほか、地域の先進的な農業経営者による出前授業等の活動を支援しています。
*1 就農を目指す人や、経営発展のためにスキルアップを図りたい農業従事者を対象とした研修教育施設。三つの教育課程があり、中心となる「養成課程」の標準的な履修時間は2年間2,400時間(80単位)以上
*2 第2章第4節を参照
(3)多様な農業者による農業生産活動等を通じた農地の確保
(農業経営体に占める担い手以外の割合は75.3%)

データ(エクセル:23KB)
令和6(2024)年の農業経営体に占める個人経営体の割合は95.4%、準主業経営体と副業的経営体の占める割合は75.3%となっており、農業を副業的に営む経営体等の担い手以外の経営体が大きな割合を占めています(図表2-3-8)。
生産現場では農業を副業的に営む経営体等が、地域社会の維持に重要な役割を果たしている実態がうかがわれます。
(農業経営体のうち担い手以外が占める経営耕地面積の割合は33.5%)
令和2(2020)年の農業経営体のうち個人経営体が占める経営耕地面積の割合は76.6%、農業経営体のうち担い手以外の準主業経営体と副業的経営体が占める経営耕地面積の割合は33.5%となっています(図表2-3-9)。
地域農業の担い手となる法人経営体や主業経営体が、離農する経営体の農地を引き受けて食料生産や供給を支えていますが、農業経営体のうち担い手以外が占める経営耕地面積も依然として大きな割合となっています。このほか、自給的農家が保有している農地もあり、食料安全保障の確保に向けて、担い手に限らず、担い手以外の多様な農業者による農業生産活動が行われるとともに、農業者、地域住民等による地域共同の農地の保全管理活動が重要になっています。
また、令和2(2020)年の農家数と土地持ち非農家数は、平成27(2015)年に比べ8.9%減少し324万9千戸となりました(図表2-3-10)。販売農家数と自給的農家数の減少に比べ、土地持ち非農家数の増加は相対的に抑えられており、このことから地域に在住していない土地持ち非農家の増加が懸念されています。地域に在住していない場合、地域の農業委員会が通常の活動で土地持ち非農家に接触することが困難であり、地域の農地を適切に利用していくためには、実態の把握を進めていく必要があります。
(多様な農業者の取組を促進)
農地を保全し、集落の機能を維持するためには、地域の話合いを基に、担い手への農地の集積・集約化を進めるとともに、農業を副業的に営む経営体等の担い手以外の多様な農業者が重要な役割を果たしていることも踏まえ、これらの者が農地の保全管理を適正に行うことによって、地域において持続的に農業生産が行われるようにすることが必要です。
農林水産省では、地域の実情に応じた生産体制の強化を支援するとともに、専門的に経営・技術等をサポートする農業支援サービス事業体の育成・活動、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るために地域共同で行う農地・水路等の保全活動の推進等の取組を支援しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883