第4節 消費者の需要に即した農業生産の推進と農業経営の安定
我が国の農業生産においては、消費者ニーズや海外市場、加工・業務用等の新たな需要に対応し、国内外の市場を獲得していくため、需要構造等の変化に対応した生産供給体制の構築を図ることが重要です。また、効率的かつ安定的な農業経営の育成に向け、収入保険や金融面での支援等を図り、自然災害等の様々なリスクに対応していくことが必要です。
本節では、各品目の需要に応じた生産や農業経営の安定に向けた取組、労働安全性の向上等の取組について紹介します。
(1)需要に応じた生産の推進と流通・加工の合理化
(品目ごとの需要に応じた生産を推進)

データ(エクセル:24KB)
食の外部化・簡便化が進展し、農畜産物の加工・業務用需要の比率が高まる一方、生産サイドではその需要に合わせた対応が必ずしも十分にできていません。
品目別食料支出割合の今後の推移をみると、内食から中食への食の外部化が一層進展し、生鮮食品から加工食品や調理食品へのシフトが加速化する見込みです(図表2-4-1)。このような食料消費形態の変化に応じた需給ギャップの解消を図り、加工・業務用需要を取り込んでいくことが必要です。
一方、主食用米の需要が減少する中、食料安全保障の観点から農地を最大限活用していくため、主食用米から輸入依存度の高い小麦や加工・業務用野菜等の需要のある作物への本格的な転換を一層進めることも重要です。
また、持続可能な農業や海外市場も見据えた農業に転換していく観点においても、需要に応じた生産は不可欠であることから、今後も品目ごとに需要に応じた生産を推進していくことが重要になります。
このため、農林水産省では、国産農産物に対する消費者ニーズが堅調であることも踏まえ、輸入品から国産への転換が求められる小麦、大豆、加工・業務用野菜、飼料作物等について、水田の汎用化・畑地化を行うなど、総合的な推進を通じて、国内生産の増大を積極的かつ効率的に図っていくこととしています。また、米粉用、業務用向けの米といった今後の需要の高まりが見込まれる作物についても、生産拡大やその定着を図っていくこととしています。
(共同利用施設の再編集約・合理化を促進)
農畜産物の調製保管や、加工、流通を支える共同利用施設の耐用年数は、一般的に約30~50年である中、JA全中(*1)が令和6(2024)年11月に公表した調査では稼働している共同利用施設のうち、約7割が30年以上前に設置された施設となっています(図表2-4-2)。また、農業者の減少に伴い、施設利用者の減少による施設稼働率の低下や、経年劣化、旧式化に伴う、施設・設備の稼働経費の負担拡大及び利用者の負担の増加が発生しており、施設利用率の向上や計画的な修繕・更新等を行いつつ、共同利用施設の再編集約・合理化を進めていくことが必要です。
このような中、農林水産省では、産地の実態を踏まえた、既存施設の役割の見直しに係る協議の実施や修繕・更新に係る計画の策定及びその実施体制の構築等を行った上で、地域計画に基づく産地の将来像の実現に向け、老朽化した共同利用施設の再編集約・合理化を促進することとしています。

*1 正式名称は「一般社団法人全国農業協同組合中央会」
(農協系統組織は農業者の所得向上等に向けた取組を推進)
農協は協同組合の一つで、農業協同組合法に基づいて設立されています。農業者等の組合員により自主的に設立される相互扶助組織であり、農産物の販売や農業生産資材の供給、資金の貸付けや貯金の受入れ、共済、医療等の事業を行っています。
農協系統組織においては、農業者の所得向上等に向け、農産物の有利販売や農業生産資材の価格引下げ等に主体的に取り組む自己改革に取り組んでいます。

データ(エクセル:35KB)
このような中、令和6(2024)年10月、農協系統組織の今後の取組方向を決定・発信する第30回JA全国大会が開催され、農協が不断の自己改革の更なる進化を図ること等が決議されました。
また、全国農業協同組合連合会(以下「JA全農」という。)では、食農バリューチェーンの構築に向け、他業種企業との業務提携等により、物流の合理化、国産農畜産物の高付加価値化、多様な販売チャネルによる消費拡大等に取り組んでいます。
総合農協の組合数、組合員数については減少傾向で推移しており、令和5(2023)年度はそれぞれ537組合、1,021万人となっています(図表2-4-3)。
(コラム)2025国際協同組合年を通じた協同組合活動の推進

「2025国際協同組合年」の
ロゴマーク
令和7(2025)年は国連が定めた国際協同組合年(International Year of Cooperatives:IYC2025)であり、平成24(2012)年に続き2回目となります。国連は今回のIYC2025を通じて、協同組合のSDGsの実現への貢献に対する認知を高めることや、協同組合の振興の取組を講ずることを、各国政府や関係機関に対して求めています。
IYC2025のロゴマークは、「協同組合はよりよい世界を築きます」というテーマのとおり、よりよい世界を築くために世界中の人々が互いに結び付く様子を表しています。
我が国では、平成24(2012)年の1回目の国際協同組合年を契機に、異なる協同組合同士が連携して社会課題の解決に取り組む協同組合間連携の機運が高まり、平成30(2018)年に、農協を始めとする構成員により日本協同組合連携機構(にほんきょうどうくみあいれんけいきこう)(JCA(*1))が設立されました。IYC2025には、国際協同組合デー記念中央集会といった、協同組合を中心に結成された全国実行委員会による記念イベントが開催される予定です。
また、JAグループでは、農産物の販売や資材の供給等に加え、買物困難者に対する移動購買車の導入、体験型農園の設置やこども食堂への食材提供、高齢者への福祉事業等の社会貢献活動を通じて、SDGs(*2)(持続可能な開発目標)の実現に向けた取組を行っており、IYC2025により、このような取組がより活性化することが期待されます。
くわえて、農林水産省としても協同組合の認知を高める広報活動を行うこととしています。
*1 Japan Co-operative Allianceの略
*2 Sustainable Development Goalsの略
(2)畜産・酪農の経営安定を通じた生産基盤の強化
(酪農経営の改善に向けた取組を支援)

データ(エクセル:34KB)
我が国の酪農経営は、ロシアによるウクライナ侵略や為替相場等の影響による飼料費等の生産コストの高止まりに加え、脱脂粉乳の需給が緩和したこと等により、厳しい状況にあります。このため、農林水産省では、令和6(2024)年度において、酪農経営に対して、コスト低減に資する長命連産性に優れた牛群への転換や脱脂粉乳の在庫低減対策の支援、農林漁業セーフティネット資金等の特例措置等による金融支援等により、生産者への影響を緩和しています。特に脱脂粉乳の需給状況については、ヨーグルト需要の減少等により、需要低迷が課題となっています。農林水産省では、民間事業者が協調して行う脱脂粉乳の在庫の低減を図るための取組等を支援しています。こうした取組により、メーカーが乳価を引き上げやすくなり、累次の引上げが行われ、酪農経営の安定に寄与しています。
このほか、農林水産省では、酪農乳業界の枠を超えた取組である「牛乳でスマイルプロジェクト(*1)」等の消費拡大や販路開拓の取組等を推進しています。
一般社団法人中央酪農会議(ちゅうおうらくのうかいぎ)が令和7(2025)年3月に公表した調査によると、指定生乳生産者団体の受託農家戸数の減少率は、令和5(2023)年8月以降鈍化しつつあるものの、令和7(2025)年2月には前年同月比で5.8%の減少となっています(図表2-4-4)。
農林水産省では、経営安定対策や金融支援、就農支援等各種施策を総合的に活用しながら、経営安定を図っています。
*1 第4章第4節を参照
(子牛価格の下落に対する支援を実施)

データ(エクセル:26KB)
黒毛和種の子牛の取引価格は、物価高騰に伴う牛肉の消費減退等を背景として、肥育農家の子牛の導入意欲が低下したこと等から、令和4(2022)年5月以降大幅に下落し、令和6(2024)年9月には1頭当たり50万円まで下落しました(図表2-4-5)。
その結果、令和6(2024)年度の第1四半期から第3四半期において、黒毛和種の子牛の全国平均売買価格が保証基準価格を下回り、肉用子牛生産者補給金が3期連続で発動しました。
農林水産省では、同補給金に加え、令和6(2024)年4月から措置した優良和子牛生産推進緊急支援事業で繁殖経営を下支えするとともに、より高く取引される優良な肉用子牛の生産に向けて、成長が良く肉質に優れた若い繁殖雌牛への牛群の転換を支援しています。
(地域における畜産の収益性向上を図る取組を推進)
畜産・酪農については、農業者の減少や高齢化、飼料価格の高止まりといった厳しい状況にあります。これらへの対応のほか、畜産物の国内需要への対応と輸出拡大に向け、生産基盤の強化を図ることが重要となっています。
このため、農林水産省では、地域における畜産の収益性向上等に必要な施設整備や機械導入等を支援するとともに、経営資源を継承する取組や農業生産資材の価格高騰等を踏まえた肉用牛繁殖経営、酪農経営における牛群構成の転換を支援しています。
また、酪農・肉用牛経営の省力化に資するロボット・AI・IoT等の先端技術の導入や、それらの機器等により得られる生産情報等を畜産経営の改善のために集約し、活用するための体制整備等を支援しています。
さらに、これまで推進してきた肉用牛・乳用牛・豚・鶏の改良に加え、肉用牛の肥育期間の短縮・出荷時期の早期化等の取組を支援することにより、生産基盤の強化と持続可能な畜産物生産の推進を図っています。
なお、令和4(2022)年4月に施行された畜舎特例法(*1)について、令和6(2024)年度においても、令和5(2023)年度に引き続き事業者等との意見交換会を実施し、緩和された構造等の技術基準により農業者や建築士の創意工夫で畜舎等の建築費が抑えられるよう、その活用を推進しています。
*1 正式名称は「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」
(事例)持続可能な畜産物生産に向け、国産飼料の活用を推進(山形県)
(1)国産原料100%飼料を給与した牛肉の生産・販売に挑戦

山形県天童市(てんどうし)の株式会社なごみ農産(のうさん)では、生産費の大きな割合を飼料費が占める中、飼料原料のほとんどが輸入であり、生産国の作柄や為替等による価格変動の影響を受けやすいことが経営上の課題となっていました。そのため、同社では、持続可能な畜産物生産に向け、国産原料100%飼料にこだわり、牛肉の生産に取り組みました。
(2)国産飼料原料の安定調達に向け、地域の農家等と連携

自社ブランド牛肉
資料:株式会社なごみ農産

直営精肉店「eat M eat」
資料:株式会社なごみ農産
同社では、国産原料100%の飼料の給与に向け、平成26(2014)年から原料価格が安い飼料用米をメインとした籾米(もみまい)サイレージの製造を開始しました。一方、ルーメンアシドーシス(*)の防止が必要であったため、地域の企業等が製造した圧ぺん籾米や圧ぺん玄米を利用し、飼料用米の多給(47%)を実現しました。
また、国産飼料原料の安定調達及び低コスト化に向け、地域の農家や企業と連携した生産・供給体制の構築が重要であると考え、平成27(2015)年に地域内外の耕種農家や企業とともに天童地区国産飼料(てんどうちくこくさんしりょう)クラスター協議会(きょうぎかい)を設立し、国産飼料原料の調達、加工、流通及び保管体制を整備しました。
このような取組の結果、同社は令和6(2024)年6月時点で約900頭の肉牛に対して国産原料100%飼料の給与を実現しています。
(3)地域の活性化を目指し、国産原料100%飼料を給与した牛肉の生産・販売を推進
同社は、関係者との信頼関係の構築を重視しており、イベント等による地域住民等の交流の場の提供や耕作放棄地の有効活用を通じて地域の活性化にも取り組んでいます。また、平成28(2016)年から自社ブランド牛肉の販売を直営精肉店やインターネットで開始し、こだわりの牛肉を消費者に直接届け、食べてほしいという思いから、販売強化に取り組んでいます。
今後とも、「安心で安全な餌で育てたおいしい牛肉を届けたい」という理念のもと、地域の理解と共生を図り、規模拡大と持続可能な畜産物生産に向けた取組を推進していくこととしています。
* ルーメン(第1胃)内が急激に酸性化し、正常な消化・吸収ができなくなる障害
(持続可能な畜産物生産のための取組を推進)
持続可能な畜産物生産に向け、世界的な気候変動に伴う飼料生産の不安定化や人口増加に伴う穀物需要の高まりを見据え、輸入飼料への過度な依存から脱却し、飼料の国際価格動向に左右されない国内の飼料生産基盤に立脚した足腰の強い畜産経営の育成を図ることが重要です。
一方、近年、農林水産分野における環境負荷低減の取組が加速する中で、我が国の温室効果ガス排出量の約1%を占める畜産でも排出削減の取組が求められています。今後も安定的に国産畜産物の生産・供給拡大を図るためには、国際的な潮流も踏まえ、地球温暖化対策を始めとした、持続的な食料システムの構築に向けた取組を関係者に促すとともに、消費者への情報発信等を図っていくことが重要です。
農林水産省では、家畜生産に係る環境負荷低減に向けた取組の展開、耕種農家のニーズに適した高品質堆肥の生産や堆肥の広域流通・資源循環の拡大、国産飼料の生産・利用の拡大や有機畜産業の取組、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理の普及、畜産GAP認証の推進、消費者の理解醸成等に取り組み、持続的な畜産物の生産を図ることとしています。
(アニマルウェルフェアに関する取組を推進)
家畜を快適な環境下で飼養することにより、家畜のストレスや疾病を減らし、家畜の本来持つ能力を発揮させる取組であるアニマルウェルフェアの推進が求められています。

アニマルウェルフェアに関する
飼養管理指針
URL:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/
sinko/230726.html#guidelines
農林水産省では、アニマルウェルフェアに対する相互の理解を深めるため、幅広い関係者による「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」を定期的に開催しています。また、令和5(2023)年7月に策定した「アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針」の周知やアニマルウェルフェアに関する理解醸成に引き続き取り組むとともに、令和6(2024)年度より、生産現場における取組状況の本格調査を開始しています。今後はその調査結果を踏まえ、同指針における「実施が推奨される事項」の達成目標年を設定するなど、同指針の更なる普及・定着を図ることとしています。
さらに、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理を重視しつつ、ブランド化に取り組む事例(*1)も見られています。
*1 「農業・農村の活性化を目指して-令和6(2024)年度農林水産祭天皇杯等受賞者事例紹介-」を参照
(3)新たな需要に応える園芸作物等の生産体制の強化
(加工・業務用野菜の国産切替えを推進)
家計消費用野菜については、ほぼ全量が国産となっており、国内生産は生鮮野菜を重視する傾向が見られています。一方、需要量の約6割を占める加工・業務用野菜は、食品製造事業者等の実需者からの国産需要が多い一方、国産割合が約7割程度となっており、国産品の出回らない時期がある品目等を中心に輸入が約3割を占めています。
令和5(2023)年産の指定野菜(*1)(ばれいしょを除く。)の加工・業務用向け出荷量は、前年産に比べ0.4%減少し101万3千tとなりました(図表2-4-6)。

データ(エクセル:26KB)

国産野菜シェア奪還プロジェクト
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/
engei/kokusan_shea_dakkan.html
食の外部化を背景に、需要は家計消費用から加工・業務用にシフトしており、今後もその傾向は継続する見込みです。また、昨今の国際情勢から、輸入野菜の価格も上昇しており、特に需要増加が見込まれる冷凍野菜やカット野菜、総菜原料等を視野に入れ、加工・業務用の戦略的な国産切替えの取組を進めていく必要があります。
このため、加工・業務用を中心とした国産野菜の生産、供給に関わる事業者の経営安定化等を通じ、国産野菜の活用拡大を図る「国産野菜シェア奪還プロジェクト」を令和6(2024)年4月に立ち上げるとともに、同プロジェクトの推進に向け、同年同月に「国産野菜シェア奪還プロジェクト推進協議会」を設立し、生産や供給に関わる事業者が結びついたサプライチェーンの構築を図るなど、全国各地において国産野菜の周年安定供給体制を確立するための取組の展開を加速化することとしています。
さらに、加工・業務用野菜の国産シェア奪還に向けた産地リレーによる周年安定供給体制の構築等のため、加工・業務用野菜の新規産地、物流合理化に取り組む産地等の実需者ニーズに対応した多様な産地の形成に資する取組等を支援することとしています。
近年、需要の高まりが見られるブロッコリーについて、国民への安定供給体制の確保に向け、計画的な生産・出荷の推進が必要です。そのため、農林水産省では、令和8(2026)年度からの指定野菜への追加に向け、準備を進めていくこととしています。
*1 野菜生産出荷安定法において、消費量が相対的に多い又は多くなることが見込まれる14品目(キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス)をいう。産地・生産者は国によって示される全国の需要及び供給の見通しや需給ガイドラインを参考に、自らの販売実績や見通しに基づく供給計画を策定する。
(果樹農業における生産基盤強化を推進)
国産果実については、「食味が良い」、「機能性が高い」等の消費者ニーズに対応した優良品目・品種への転換が進んでいます。他方で、生産量の減少が消費量の減少を上回る状況にあること等を背景として、卸売価格は上昇傾向で推移しており、近年では、国内の果実の産出額は増加傾向にあります。令和5(2023)年における品目別の果実産出額は、ぶどうが2,068億円で最も多く、次いで、みかんが1,733億円、りんごが1,730億円となっています(図表2-4-7)。
一方、果樹農業は、整枝・剪定(せんてい)等の高度な技術を要する作業や、摘果、収穫等の機械化の困難な作業が多く、急傾斜地等の条件の厳しい園地が中心で機械化が遅れていることや、収穫等の季節的な労働ピークが存在するため年間を通じた雇用が困難で臨時雇用等の外部労働力に頼っているなどの果樹特有の課題があります。

データ(エクセル:26KB)
このため、農地の集積・集約化と規模拡大が進まず、生産者の減少・高齢化等により栽培面積が減少するなど生産基盤が脆弱(ぜいじゃく)化しており、国内外の需要に応えきれていない状況にあります。
果樹の生産拡大に向けて、農林水産省は、地域計画を活用した園地の集積・集約化や基盤整備、省力樹形等の導入、スマート農業技術・省力化品種の開発・導入による労働生産性の向上とともに、担い手や労働力の確保に向けた取組等を通じ、果樹農業の生産基盤の強化を推進しています。さらに、令和6(2024)年度より、スマート農業技術等の導入を前提とした樹園地の環境整備や流通事業者等との連携等による、生産性を飛躍的に向上させるための産地構造の転換に向けた実証等の取組を新たに支援しています。
(4)米政策の着実な推進
(米の需要に応じた生産を推進)
米については、米価が上昇すると生産減が進まず、その結果として在庫量が増加して価格が下がり、生産量が減少するというサイクルを繰り返しつつ、中長期的には生産量も需要量に合わせて減少しています。
主食用米の需要量が年間10万t程度減少する中、米の生産においても、主食用だけでなく、麦や大豆、加工・業務用野菜といった需要のある作物への転換を進めていく必要があります。
また、需要のウェイトが高まっている業務用向けのほか、新たな需要としての米粉・新市場開拓用米等の需要にきめ細かく対応した米生産を進める必要があります。
このため、農林水産省では、水田活用の直接支払交付金等による作付転換への支援のほか、実需者との結び付きの下、新市場開拓用米、加工用米、米粉用米の低コスト生産等に取り組む生産者の支援を実施しています。
(米の事前契約を推進)
主食用米の需要量が減少している中、消費者・実需者が求める様々な需要に対応するとともに米の安定供給を図るためには、豊凶変動や価格変動リスクに対応しつつ、生産者が事前に販売先や販売数量等を見通すことが可能となる事前契約の拡大を図っていくことが重要です。
事前契約のうち、主食用米の播種(はしゅ)前契約(複数年契約を含む。)の比率は、令和6(2024)年産は31%となっていますが、需要に応じた生産・販売の推進を通じて農業経営の安定化等を図るためには、各産地において安定取引のための取組を更に推進していく必要があります(図表2-4-8)。

データ(エクセル:26KB)
農林水産省では、産地・生産者と卸売業者・実需者が結び付いた事前契約や複数年契約による安定的な取引を推進しているほか、都道府県別の販売進捗、在庫・価格等のきめ細かな情報発信等により需要に応じた生産・販売が進展するよう取り組んでいます。
(米の指数先物取引が認可され、令和6(2024)年8月から取引を開始)
価格形成の公平性・透明性を確保しつつ、米の需給実態を表す価格指標を示す現物市場として、令和5(2023)年10月にみらい米市場(こめいちば)(*1)が創設されました。
農林水産省は、現物取引を補完する観点から、相対取引を始めとする現物取引と併せて先物取引を活用して将来価格を把握することによるリスク抑制について検討してきました。令和6(2024)年6月には、株式会社堂島取引所(どうじまとりひきじょ)の米の指数先物取引(*2)の本上場申請が認可され、同年8月から取引が開始されました。
現物取引と先物取引を組み合わせて活用することにより、将来の価格変動に対しリスク抑制を行う場合の選択肢が広がることに加え、米の将来価格の動向把握が可能となることから、先を見通した経営や需要に応じた生産の推進を通じ、米の需給と価格の安定に寄与することが期待されています。
*1 公益財団法人流通経済研究所等が出資し設立したみらい米市場株式会社が開設
*2 「主食用米の平均価格」を対象とした先物取引
(令和6(2024)年産米においても引き続き需要に応じた生産を推進)
需要に応じた生産が行われた結果、令和6(2024)年産の主食用米の作付面積は、前年産に比べ1万7千ha増加し125万9千haとなりました(図表2-4-9)。

データ(エクセル:29KB)
水田活用の直接支払交付金を活用した水田における主食用米以外の作物への作付転換は、近年、飼料用米を始めとする主食用米以外の米を中心に増加していますが、主食用米以外の米については、主食用米の価格動向によっては主食用米の作付けに回帰しやすい性格を有しています。このため、主食用米の価格動向に左右されずに、当該品目の作付けを定着・拡大させていく産地づくりや流通・販売等の体制づくりが重要になっています。
また、農林水産省では、食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色を活かした魅力的な産地づくり、産地と実需者との連携に基づいた低コスト生産の取組、畑地化による高収益作物等の定着等を支援することとしています。
今後の水田政策については、令和9(2027)年度から根本的に見直す検討を本格的に開始しました。
(コラム)令和6(2024)年夏の米の品薄と米の円滑な流通の確保のための対応
主食用米の需給は、令和5(2023)年産米の需要が堅調に推移していました。
その中で、新米が出回る前の、令和6(2024)年8月の端境期において、南海(なんかい)トラフ地震臨時情報が発表され、また、同時期に地震や台風等もあり、スーパーでの米の購買量が前年の約1.5倍まで増加したことから、小売店等において、米の品薄状況が発生しました。
このため、農林水産省では、米の集荷業者・卸売業者の方々に対して米の円滑な流通の確保に向けた対応の要請などを行うとともに、同年9月から新米が本格的に供給されることから、新米の集荷量や、販売量の週次調査等の情報発信を行いました。
米の生産コストについては、近年、令和2(2020)年に比べ肥料費が4割増加するなどにより、上昇が続いていました。こうしたコストの上昇に加え、流通状況を踏まえた集荷の動きなどにより、農家に支払われる概算金が4~5割上昇し、令和6(2024)年産米の令和7(2025)年2月までの相対取引価格も前年産に比べ59.2%上昇しています。
また、米の流通については、令和6(2024)年産米の収穫量は、前年産より18万t増加しましたが、大手の集荷業者の集荷量は、前年と比べて大きく減少(同年12月時点で21万t減少)する状況となりました。このため、大手の集荷業者と取引をしていた卸売業者や中食・外食・小売事業者は、必要な量を調達するため、例年とは異なる調達ルートからも補完的に比較的高値で仕入れざるを得なくなるという状況となり、スーパー等の小売店での価格上昇につながりました。
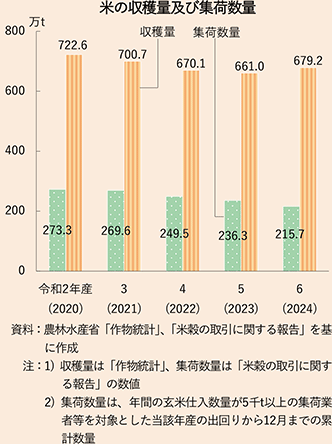
データ(エクセル:27KB)

政府備蓄米の引渡しの様子
こうした米の流通の滞りを解消するため、令和7(2025)年1月に、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」において、米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるときは、政府備蓄米の売渡しを一定期間後に買い戻すことを条件に行うことができる仕組みを設けました。
その後、同年2月に今回設けた規定に基づき、集荷業者の集荷の減少分に相当する21万tの政府備蓄米の売渡しを決定し、同年3月に2回の入札を実施しました。このうち、14万t分については3月中旬に引渡しが開始され、同年3月下旬時点で店頭に並び始め、残る7万tは4月中旬から引渡しされる予定です。
また、政府備蓄米の売渡しと併せて、令和7(2025)年1月末時点の生産者や小規模な集荷業者、卸売業者等の在庫数量や、生産者の出荷の状況等の調査を実施しました。調査結果では、まず、調査対象となった生産者の収穫量が、前年産よりも増加したこと、生産者の出荷量は前年より14万t増加したこと、生産者から集荷業者への出荷量が前年に比べて31万t減少する一方、生産者の直接販売や集荷業者以外への販売等が前年に比べて44万t増加したこと、生産者、卸売業者、中食・外食・小売業者等の各段階で在庫が増加したこと等が明らかになりました。
さらに、第3回として10万t分の入札を4月に行うとともに、夏まで毎月、政府備蓄米の売渡しを行うこととしています。
(水田の汎用化・畑地化等による水田農業の高収益化を推進)
主食用米の需要量が毎年減少傾向にある中、水田農業の高収益化を図っていくためには、野菜や果樹等の高収益作物を適切に組み合わせて経営を行っていくことが重要です。
農林水産省では、高収益作物の導入・定着を図るため、水田農業高収益化推進計画に基づき、国のみならず地方公共団体等の関係部局が連携し、水田における高収益作物への転換、水田の汎用化・畑地化に向けた農業生産基盤整備、栽培技術や機械・施設の導入、販路確保等の取組を計画的かつ一体的に支援しています。水田農業における高収益作物等の産地については、令和6(2024)年12月末時点では538産地まで増加しています。
(事例)水田農業高収益化推進計画により、収益や作業効率の向上を実現(茨城県)
(1)産地としての規模拡大を目指し、水田かられんこん畑に転換

茨城県稲敷市(いなしきし)は、低湿地帯の農地が多く、販売先も安定しており、れんこんの面積当たりの収益性は高くなっています。
同市では、産地としての更なる規模拡大や収量向上を目指し、令和2(2020)年6月に同県が策定した水田農業高収益化推進計画に基づき、県や市の地域農業再生協議会、稲敷市東地区(いなしきしあずまちく)れんこん生産者団体(せいさんしゃだんたい)等が連携して水田におけるれんこんの導入・定着に取り組んでいます。
(2)積極的な販路開拓と生産面積の拡大を推進

畑地化した圃場での収穫作業
資料:株式会社れんこん三兄弟
同市でれんこんを生産・販売する株式会社れんこん三兄弟(さんきょうだい)は、積極的に販路開拓を行い、約300店舗の小売店や飲食店等と直接取引をしています。また、販路開拓とともに生産面積の拡大に取り組み、離農者から借り受けた水田等の畦(あぜ)の高さや作土深の調整、畦シートや防鳥ネット等を設置し、れんこん生産に適した圃場(ほじょう)整備を行っています。さらに、収穫用の機械や洗浄機等を導入し、作業を効率化しています。
同社の圃場や施設の整備に関しては、同計画に基づく、畑地化の取組の支援やれんこんの導入・定着に応じた支援等が行われており、地域における高収益作物の生産拡大に貢献しています。
(3)高収益化に向け、産地で一体となり収量向上や規模拡大を推進
このような取組の結果、同社の令和5(2023)年の作付面積は令和元(2019)年の約1.6倍の約26haに、令和5(2023)年の販売額は令和元(2019)年の約1.8倍の約1億7千万円となり、規模を拡大しています。
同社では、同計画に基づき、産地一体で生産基盤の強化や収量向上、規模拡大を図るとともに、需要拡大に向けたレシピ開発や出荷場の新設等に取り組み、今後も消費者が食べたいと思うれんこんの生産を目指していくこととしています。
(米の生産コスト低減に向けた取組を推進)

データ(エクセル:28KB)
業務用や輸出用、パックご飯需要等の様々な需要に対応する上で、米の生産コストを大幅に低減していく必要があります。米の生産コストについては、認定農業者のいる15ha以上の個別経営体の生産コストで見ると、令和5(2023)年産は肥料費等が高騰したことから、前年産に比べ543円/60kg増加し11,350円/60kgとなっています(図表2-4-10)。
農林水産省では、米の生産コスト削減に向けて、農地の集積・集約化、大区画化を加速化するとともに、大規模経営に適合した直播(ちょくはん)栽培やスマート農業技術等の省力栽培技術・多収品種の開発・導入を進め、農業生産資材費の低減を推進しています。
(グルテンフリー市場も踏まえた米粉等の利用拡大が重要)
異常気象等による食料の安定供給をめぐるリスクが顕在化する中、国内で自給可能な穀物である米を原料とした米粉の活用は重要な課題となっています。
また、小麦粉に由来するアレルギーに対応するグルテンフリー食品としても、米粉や米粉製品の利用拡大を進めていくことが重要です。
農林水産省では、米粉の需要拡大や需要に応じた生産を図るため、生産段階では用途ごとに適した米粉専用品種の開発・生産拡大、製粉段階では製造に適した製粉施設の導入、流通・消費段階では米粉の特徴を活かした新商品開発やパン・麺類等の製造機械・設備の導入等を後押しすることにより、川上から川下まで総合的な取組を進めています。
(5)麦・大豆の需要に応じた生産の更なる拡大
(畑作物の本作化を推進)
需要に応じた生産が進められる中、令和5(2023)年産には約3万ha、令和6(2024)年産には約1万8千haの水田で畑地化促進事業が採択されました。農林水産省では、畑作物の本作化をより一層推進するため、畑作物の定着までの一定期間を支援する畑地化促進事業、低コスト生産等の技術導入や畑作物の導入・定着に向けた取組を支援する畑作物産地形成促進事業を引き続き措置しています。
(国産小麦の需要に対応するため、安定した生産供給体制の構築・強化が必要)
我が国における小麦の需要は、輸入が8割以上を占めている一方、生産量については、収穫期における降雨等の天候の影響を受けやすいことに起因して単収の年次変動が大きく、量の観点から需要と供給に差が生じています。
また、品質については外国産と比べ遜色がない程度まで向上している品種も増えていますが、生産年や生産地によって品質の振れ幅が大きく、安定化が課題となっています。
国産小麦の実需者の需要に対応するためには、需要の高い品種の導入や効果的な営農技術の導入、ストック機能の強化等による、品質・供給量の安定化に向けた対策を総合的に進めることが重要です。
農林水産省では、国産小麦の生産拡大に向け、排水対策等の営農技術の導入、大区画化や汎用化等の基盤整備、多収品種の開発・普及、スマート農業技術等を活用した効率的な栽培体系による適期作業等を推進しています。
(国産大豆の需要拡大に向け、安定した生産供給体制の構築・強化が必要)
食用大豆の需要見込みは増加しており、国産大豆の需要も堅調に推移する見込みである一方、国内生産量はほぼ横ばいであり、また、主な水田地帯において生産性も低下傾向にあるなど、生産体制の抜本的な強化が必要となっています。
また、国産大豆の更なるシェア拡大に向け、用途に応じて大豆に求められる品質が違うことに加え、均等化、大ロット化といった食品製造事業者の目線に立った、食品加工原料としての安定化を図ることや生産量を安定させ、安心して使えるように確実に供給できるようにすることが必要です。
農林水産省では、国産原料を使用した大豆製品の需要拡大に向け、実需者の求める安定した生産量・品質・価格といったニーズに応えるため、極多収品種の普及推進と更なる開発の加速化、集約化やブロックローテーションの導入、畑地化等を推進しています。
(6)GAP(農業生産工程管理)の推進
(国際水準GAPの取組拡大を推進)

データ(エクセル:27KB)
GAP(*1)は、農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動です。
農林水産省では、「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」、「人権保護」、「農場経営管理」の5分野を含むGAPを国際水準GAPと呼称しています。令和4(2022)年3月に「我が国における国際水準GAPの推進方策」を策定するとともに、国際水準GAPの我が国共通の取組基準として「国際水準GAPガイドライン」を策定し、その普及を推進しています。
また、都道府県では、農業者へのGAPの普及に関して、国際水準GAPガイドラインや独自のGAP基準(都道府県GAP)に基づく指導、GAP認証取得を目指した指導等を行っています。このような中、農林水産省では、国際水準GAPの推進方策を受け、都道府県GAPを存続する都道府県に対し、令和6(2024)年度末を目途として、都道府県GAPを国際水準に引き上げるよう求めています。
我が国では、主にGLOBALG.A.P.(*2)、ASIAGAP(*3)、JGAP(*4)の3種類のGAP認証が普及しています。令和5(2023)年度のGAP認証取得経営体数は、7,738経営体と、近年はおおむね横ばいで推移しています(図表2-4-11)。
令和7(2025)年に開催される2025年日本国際博覧会(にっぽんこくさいはくらんかい)(以下「大阪(おおさか)・関西万博(かんさいばんぱく)」という。)や令和8(2026)年の愛知(あいち)・名古屋(なごや) 2026 アジア競技大会(きょうぎたいかい)(*5)、令和9(2027)年の国際園芸博覧会(こくさいえんげいはくらんかい)(*6)の持続可能性に配慮した農産物の調達基準において、GAP認証農産物や国際水準GAPガイドラインに準拠したGAPに基づき生産された農産物が、調達基準の要件への適合度が高い農産物として位置付けられました。農林水産省では、これらの国際的なイベントの開催を契機として、国際水準GAPの取組を更に推進していくこととしています。
*1 Good Agricultural Practicesの略
*2 ドイツのFoodPLUS GmbHが策定した第三者認証のGAP
*3 一般財団法人日本GAP協会が策定した第三者認証のGAP。対象は青果物、穀物、茶
*4 一般財団法人日本GAP協会が策定した第三者認証のGAP。対象は青果物、穀物、茶、家畜・畜産物
*5 正式名称は「第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)」
*6 正式名称は「2027年国際園芸博覧会」
(7)効果的な農作業安全対策の展開
(農作業中の事故による死亡者数は、農業機械作業に係る事故が約6割)

データ(エクセル:27KB)
令和5(2023)年には、就業者10万人当たりの死亡事故者数が11.6人と増加傾向にあります。農作業中の事故による死亡者数については、令和5(2023)年は236人となりました。要因別に見ると、農業機械作業に係るものが147人(62.3%)で最も多くなっており、このうち乗用型トラクターに係るものが61人(25.8%)と最多となっています(図表2-4-12)。
死亡事故要因の6~7割が農業機械作業となっている状態が続いていることに加え、熱中症等の機械事故以外の死亡者数も減少していない現状を踏まえ、農作業事故死亡者数を令和4(2022)年の238人から令和8(2026)年までに半減(119人)することを新たな目標としました。
この実現に向け、農林水産省では、令和3(2021)年に取りまとめた「農作業安全対策の強化に向けて(中間とりまとめ)」に基づく対応を引き続き進めていくこととしています。このうち農作業環境の安全対策については、農研機構が農業機械メーカーからの依頼に基づいて農業機械の安全性を確認する安全性検査制度を見直し、新たな検査制度・検査基準による運用を開始できるよう、より安全な農業機械の普及促進に向けた取組を進めました。
また、農業者の安全意識の向上については、農業者が正しい安全知識を習得できるよう、「農作業安全研修実施強化期間」等を設定し、農作業安全に関する指導者が中心となり、各地域で農業者に向けた研修の実施を推進しており、令和6(2024)年度は全国で4,437回、約15万7千人が農作業安全研修を受講しています。
厚生労働省においても令和6(2024)年2月から、農業における労働災害の減少を図るため、「農業機械の安全対策に関する検討会」を開催しています。同検討会では、労働安全衛生法令における、車両系農業機械の規制の必要性や具体的な安全対策等について検討されており、農林水産省においても農業機械事故の減少に向け、厚生労働省と連携して安全対策を推進することとしています。
(雇用時の安全教育の実施)

データ(エクセル:26KB)
令和5(2023)年の労働者死傷病報告によると、農業においては経験期間が3年以下の未熟練労働者の農作業事故の発生割合が、全体の51.9%と半数以上を占めています。(図表2-4-13)。
雇入れ時教育について、厚生労働省の労働安全衛生法では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」旨が規定されていたものの、農業については、機械の取扱い方法等の一部項目を省略できることとされていました。
このため、令和6(2024)年4月より、同法の規則改正に伴い、「雇入れ時教育」の義務が拡充され、農業等では省略可能とされていた(1)機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法、安全装置、(2)有害物抑制装置、保護具の性能・取扱い方法、(3)作業手順、(4)作業開始時の点検を含む8項目について、全業種で教育が義務化されています。
こうした雇入れ時教育の徹底により、労働災害の発生件数の減少が期待されており、農林水産省では、雇入れ側農家(事業者)向けの教育資材と雇われ農家(労働者)向けのリーフレットを作成し、農業現場への周知を図っています。
また、農業分野で働く技能実習生や特定技能実習生等に向けて、英語版、中国語簡体字版、ベトナム語版、インドネシア語版の労働者向けリーフレットを作成し、周知しています。

労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!
URL:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/
s_kikaika/anzen/roudouanzenkyouiku.html
(農作業中の熱中症による死亡者数は増加傾向)

データ(エクセル:26KB)
令和5(2023)年における農作業中の熱中症による死亡者数は37人となっており、「農業機械・施設以外の作業」での死亡事故要因としては最も多くなっています。また、農作業事故死亡者数のうち、熱中症による死亡者数は、令和3(2021)年以降増加傾向で推移しており、令和5(2023)年は前年に比べ8人増加しています(図表2-4-14)。さらに、農作業中の熱中症による死亡事故は、過去10年間の累計では280人に上り、その過半が80歳以上となっていることから、高齢者への対策は特に重要となっています。
農作業中の熱中症による救急搬送は、暑さに慣れていない5月頃から発生しています(図表2-4-15)。

データ(エクセル:31KB)
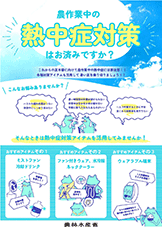
熱中症対策を呼び掛けるポスター
そのため、農林水産省では、暑さが本格化する前の5月から7月を「熱中症対策研修実施強化期間」に設定し、熱中症の予防策の研修・講習等を行うことを重点的に推進しています。
さらに、熱中症対策に関するオンライン研修の実施や啓発資料の充実を図るとともに、農林水産省が運営する「MAFF(マフ)アプリ」等を活用し、熱中症警戒アラートや熱中症による救急搬送者数の状況等を農業者等に対してきめ細かく情報提供するなど、現場での注意喚起を強化しています。
(8)農業経営の安定化に向けた取組の推進
(経営所得安定対策の加入申請件数は、前年度に比べ減少)
経営所得安定対策は、農業経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正するための畑作物の直接支払交付金(以下「ゲタ対策」という。)や農業収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するための米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(以下「ナラシ対策」という。)を交付するものです。
令和6(2024)年度におけるゲタ対策については、加入申請件数は前年度に比べ1,230件減少し3万9,291件となった一方、作付計画面積は前年度に比べ8千ha増加し53万6千haとなりました(図表2-4-16)。
また、ナラシ対策については、収入保険への移行や高齢化に伴う脱退のほか、継続加入者の作付転換等により、加入申請件数は前年産に比べ5,197件減少し4万8,964件、申請面積は前年産に比べ3万5千ha減少し56万1千haとなっています。

データ(エクセル:28KB)
(収入保険の加入者は着実に拡大)
収入保険は、農業者の自由な経営判断に基づき収益性の高い作物の導入や新たな販路の開拓にチャレンジする取組等に対する総合的なセーフティネットであり、品目の枠にとらわれず、自然災害だけでなく価格低下等の様々なリスクによる収入の減少を補償しています。

データ(エクセル:26KB)
令和6(2024)年の加入経営体数は、前年に比べ8,484経営体増加し99,128経営体となりました(図表2-4-17)。これは青色申告を行っている農業経営体数(35万3千経営体)の28.1%に当たります。
品目別に見ると、同年の加入経営体数は、米が60,363経営体で最も多く、次いで野菜、果樹の順となっています(図表2-4-18)。
自然災害による損害を補償する農業共済と合わせた農業保険全体で見た場合、令和5(2023)年産における水稲の作付面積の79%、麦の作付面積の99%、大豆の作付面積の95%が加入していることになります。

データ(エクセル:26KB)
また、令和4(2022)年12月に、農業保険法の施行後4年を迎えた収入保険の今後の取組方針として決定した、(1)甚大な気象災害による影響を緩和する特例、(2)青色申告1年分のみでの加入、(3)保険方式のみで9割まで補償する新たな補償タイプについて、令和6(2024)年に保険期間が始まる収入保険の加入者から実施しています。
(農業共済事業を着実に実施)
農業共済制度は、農業保険法に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補塡することを目的としています。同制度は、被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補塡しており、農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払うこととしています。

データ(エクセル:27KB)
また、農業共済団体は、農業保険制度の実施主体として同法に基づき設立されており、農業共済組合及び農業共済事業を実施する市町村(以下「農業共済組合等」という。)、都道府県単位の農業共済組合連合会、国の3段階で運営されてきました。
近年、農業共済団体においては、業務効率化のため、農業共済組合等の合併により都道府県単位の農業共済組合を設立するとともに、農業共済組合連合会の機能を都道府県単位の農業共済組合が担うことにより、農業共済組合と国との2段階で運営できるよう、1県1組合化を推進しています。
農業経営のセーフティネットへの関心が高まる中、農業共済団体では、農業の生産現場での農業保険の普及・利用拡大に向けた取組を推進しています。
令和5(2023)年度における農業共済組合数は49組合、農業共済組合員数は197万人となっています(図表2-4-19)。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883





