第4節 食料消費の動向と食・農のつながり
我が国においては、食料品の価格上昇が食料消費に大きな影響を及ぼすことが懸念されているほか、ライフスタイルの変化に伴い、食の外部化・簡便化が進展しています。また、国産農林水産物の積極的な選択のためには、消費者が農業者・食品関連事業者等との交流を進め、食や農を知り、それらに触れる機会を拡大することが必要です。
本節では、食料消費や農産物・食品価格の動向、国産農林水産物の消費拡大、食育や地産地消の推進等の食・農のつながりに関する取組について紹介します。
(1)食料消費の動向
(1人1日当たりのエネルギー摂取量は平成12(2000)年に比べ減少)
食料消費の動向を見る前に栄養摂取状況を見ると、令和5(2023)年の1人1日当たりのエネルギー摂取量は平成12(2000)年に比べ71kcal減少し、1,877kcalとなっています(図表4-4-1)。
また、栄養素別に令和5(2023)年の1人1日当たりの摂取量の平均値を見ると、平成12(2000)年に比べ、たんぱく質は7.3g減少し70.4g、脂質は3.5g増加し60.9g、炭水化物は21.3g減少し244.9gとなっています。

データ(エクセル:32KB)
(食料の消費者物価指数は上昇傾向で推移)

データ(エクセル:26KB)
消費者物価指数は上昇傾向で推移しており、総合の消費者物価指数は令和7(2025)年1月に111.2となっています(図表4-4-2)。また、生鮮食品を除く食料の消費者物価指数は、同年2月に121.6となり、前年同月比で5.6%上昇しました。
また、家計の消費支出に占める食料消費支出の割合であるエンゲル係数は、前年に比べ0.5ポイント上昇し、令和6(2024)年には平成12(2000)年以降最も高い28.3%となっています(図表4-4-3)。中長期的な上昇の主な要因としては、円安による輸入価格の上昇の影響で多くの食品価格の値上げが実施されたため食料消費支出が増加していることや単価の高い調理食品や外食の支出が増加したこと、一般的に食料への支出割合が高い高齢層が増加したこと等が考えられます。

データ(エクセル:27KB)
(消費者世帯の食料消費支出は名目で増加、実質で微増)

データ(エクセル:29KB)
消費者世帯(二人以上の世帯)における1人当たり1か月間の「食料」の支出額(以下「食料消費支出」という。)について、令和6(2024)年の平均値(*1)は、名目で約3万円となり、前年に比べ4.5%増加しました。一方、物価変動の影響を除いた実質(*2)では約2万5千円となり、前年に比べ0.1%増加しました。
また、同年における食料消費支出を前年同月比で見ると、実質でも前年を上回る月が5か月あるほか、名目では前年を上回る状況が続きました(図表4-4-4)。食料価格の上昇により、食料消費支出が増加し、家計の負担感の増加につながっていることがうかがわれます。
*1 各月ごとに算出した1人当たり1か月間の食料消費支出を基に、年間の平均値を算出したもの
*2 令和6(2024)年各月の食料消費支出について、消費者物価指数(令和2(2020)年基準)を用いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた上で、年間の平均値を算出したもの
(令和6(2024)年の外食支出は、前年に比べ増加傾向で推移)
家計における令和6(2024)年の食料支出を前年同月比で見ると、外食支出は増加傾向で推移しています(図表4-4-5)。その要因として、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ外食支出の回復や原材料費高騰等の影響を受けた客単価の上昇が挙げられます。また、米の支出は、南海(なんかい)トラフ地震臨時情報の発表やその後の地震、台風等による消費者の買込み需要が発生したこと等(*1)により、8月は3割程度増加しています。その後は、11月までは前年を下回る水準で推移し、12月以降は前年とほぼ同水準で推移しています。

データ(エクセル:29KB)
*1 第2章第4節を参照
(食品類のEC市場は年々拡大)

データ(エクセル:25KB)
食品類のEC市場は年々拡大しており、スマートフォン等の身近なIT端末の普及や共働き世帯の増加といった社会構造の変化と共に、多くの人々にとって日常的な取引形態となっています。
経済産業省の調査によると、令和5(2023)年の「食品、飲料、酒類」(以下「食品類」という。)のEC(*1)市場規模(BtoC(*2))は、前年に比べ約6.5%増加し2兆9,299億円となりました(図表4-4-6)。この結果、同年の食品類のEC化率は、前年に比べ0.1ポイント上昇し約4.3%となりました。また、同調査によると、健康食品分野においては、メインユーザーである高齢者がテレビ通販やカタログ販売等から徐々にECでの購入に移行しつつあるといった点に加え、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として生活習慣病予防、ダイエット、健康増進といった消費者のニーズを捉えた商品が注目されたことが売上拡大の主要因とも推察しています。
令和6(2024)年6月に公表した調査によると、食材や食品・飲料の買物場所については、約2割がインターネットで購入すると回答しました(図表4-4-7)。また、インターネットで食材や食品・飲料を購入する人の割合は、男女ともに65~74歳が最も高くなっています(図表4-4-8)。
*1 Electronic Commerceの略で、電子商取引のこと
*2 Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のこと
(食の外部化・簡便化が進展)
我が国においては、少子高齢化の進展による単身世帯の増加や、ライフスタイルの変化による共働き世帯の増加等により、食に関して外部化・簡便化の進展が見られています。
一般社団法人日本惣菜協会(にほんそうざいきょうかい)の調査によると、中食(惣菜)市場の売上高については近年増加傾向で推移しており、令和5(2023)年は平成26(2014)年比で118.6%の11兆円となっています(図表4-4-9)。

データ(エクセル:25KB)

データ(エクセル:25KB)
また、カテゴリー別に見ると、令和5(2023)年は、米飯類の割合が43.9%で最も高くなっており、次いで一般惣菜が34.9%、調理麺が9.2%となっています(図表4-4-10)。
農林水産省では、食の外部化・簡便化の進展に合わせ、外食・中食における国産農産物の需要拡大を図ることとしています。
(冷凍食品の国内生産額が過去最高を更新)
一般社団法人日本冷凍食品協会(にほんれいとうしょくひんきょうかい)の調査によると、令和5(2023)年の冷凍食品の国内生産額は、前年に比べ160億円増加し7,799億円となり、過去最高を更新しました(図表4-4-11)。国内生産額のうち、業務用は前年に比べ226億円増加となり、家庭用は66億円減少となりましたが、令和2(2020)年から家庭用が業務用を上回る状況が続いています。また、品目別で見ると、上昇幅が最も大きかった畜産物は前年に比べ55.4%増加しています。
国内生産額の上昇は、冷凍食品の値上げも要因と見られますが、コロナ禍以前に比べ高い水準で推移しています。食の簡便化の進展により、冷凍食品市場は今後も拡大することが見込まれます。

データ(エクセル:26KB)
(2)農産物・食品価格の動向
(米の相対取引価格は前年産に比べ上昇)
令和6(2024)年産米の令和7(2025)年2月までの相対取引価格は、昨今の資材費等の生産コストの上昇等により産地の集荷価格が上昇したことに加え、流通状況を踏まえた集荷の動き等により、年産平均で玄米60kg当たり2万4,383円となり、前年産に比べ59.2%上昇しました(図表4-4-12)。
また、小売価格について、令和7(2025)年3月のコシヒカリは前年同月比で89.4%上昇しました(図表4-4-13)。
(野菜の小売価格は夏季の高温の影響により多くの品目が平年を上回って推移)
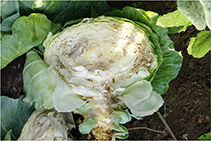
高温等によるキャベツの生理障害
野菜は天候によって作柄が変動しやすく、短期的に価格が大幅に変動する傾向があります。令和6(2024)年は、キャベツ、はくさい、トマト等の多くの品目において、夏季の高温の影響により生育不良等が発生したため、夏季・秋季の出荷量が減少し、小売価格は平年に比べ大きく上昇しました(図表4-4-14)。さらに、キャベツは10月の天候不順や12月以降の少雨の影響等により、引き続き出荷量が少なくなり、小売価格は12月以降も平年を上回って推移しました。

データ(エクセル:27KB)
(牛肉・豚肉・鶏肉の小売価格はやや上昇、鶏卵の小売価格は上昇傾向で推移)
令和6(2024)年度における国産牛肉の小売価格は、流通コストの上昇等に伴い、やや上昇傾向で推移しました(図表4-4-15)。また、豚肉の小売価格は、輸入豚肉価格の上昇等により、やや上昇傾向で推移しました。さらに、鶏肉の小売価格は、輸入鶏肉価格の上昇や堅調な需要等により、やや上昇傾向で推移しました。
鶏卵の小売価格は、夏季の暑熱による供給減や、令和7(2025)年1月に高病原性鳥インフルエンザの発生が急増したことを受け、上昇傾向で推移しました。

データ(エクセル:25KB)
(食パンの小売価格は上昇傾向で推移)

データ(エクセル:24KB)
穀物等の国際価格の上昇により、輸入原料を用いた加工食品の小売価格は上昇傾向で推移しています。
食パンの小売価格は、原料小麦や包材、燃料等の価格上昇を受けて、令和7(2025)年3月には578円/kgとなり、令和6(2024)年4月に比べ8.2%上昇しました(図表4-4-16)。また、食用油(サラダ油)の小売価格は、令和6(2024)年4月の477円/kg以降、下降傾向で推移しています。

食品の価格動向
URL:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/
(3)国産農産物の消費拡大に向けた対応
(50歳代と60歳代の年齢層の米の消費が急減)

データ(エクセル:29KB)
米・米加工品の1人1日当たり摂取量は減少傾向にあり、令和5(2023)年は平成13(2001)年に比べ、特に60歳代で25.4%減少するなど、若年層よりも高齢層で急減している状況となっています(図表4-4-17)。また、ほとんど毎食ごはんを食べる頻度を年代別で見ると、50歳代と60歳代で低くなっています(図表4-4-18)。
消費量が減少している背景には、人口減少に加えて、少子高齢化、ライフスタイルの変化に伴う食の多様化・簡便化、炭水化物の摂取を控えた食生活の広がりが挙げられます。

データ(エクセル:28KB)
(「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」を展開)

データ(エクセル:27KB)
米(*1)の1人当たりの年間消費量については、食生活の変化等により減少傾向で推移していますが、令和5(2023)年度は前年度に比べ0.2kg増加し51.1kgとなりました(図表4-4-19)。
農林水産省では、米の消費を喚起する取組として「やっぱりごはんでしょ!」運動を展開しており、「BUZZ MAFF(ばず まふ)」での動画投稿やSNS・ウェブサイトでの情報発信等を実施しています。
令和6(2024)年度は、「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」において米粉情報サイトやSNSを活用し、米粉の認知、利用方法等について情報発信をするとともに、全国の外食事業者や飲食店、食品流通事業者等と連携した取組を実施しました。また、同年6月からは、米作りの工程を取り扱っているテレビアニメーション「天穂(てんすい)のサクナヒメ」とコラボレーションし、「お米の魅力」を伝える企画を実施しました。テレビアニメーションをきっかけとして、食や農林水産業について興味・関心を持ってもらうことを目的としています。

テレビアニメーション「天穂のサクナヒメ」
とのコラボビジュアル
資料:©えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会

「消費者の部屋」における展示の様子
*写真内のポスターの出典は、©えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会
*1 主食用米のほか、菓子用・米粉用の米を含む。
(「野菜を食べようプロジェクト」を展開)

データ(エクセル:26KB)
野菜の1人当たりの年間消費量については、食生活の変化等により減少傾向で推移しており、令和5(2023)年度は前年度に比べ3.2kg減少し84.6kgとなりました(図表4-4-20)。また、厚生労働省の調査によると、1人1日当たりの野菜摂取量は、男女ともに20歳代で最も少なく、年齢階級が高い層で多い傾向が見られています。
農林水産省では、1人1日当たりの野菜摂取量を、目標値の350gに近づけることを目的として、「野菜を食べようプロジェクト」を実施しています。令和6(2024)年度は、同プロジェクトの一環として、食の簡便化志向の高まり等により需要が増加している「冷凍野菜」をテーマにシンポジウムを開催しました。また、8月31日の「野菜の日」に合わせ、日頃の野菜摂取状況が把握できる測定機器を農林水産省内に設置し、来庁者や職員に対して、食生活に十分な量の野菜を取り入れることが習慣となるよう、野菜の消費拡大を図りました。
(茶の消費拡大に向け「お茶の可能性は無限!~お茶×(かける)キャンペーン~」を展開)

データ(エクセル:26KB)
緑茶(*1)の1世帯当たりの年間購入数量については近年減少傾向で推移しており、令和6(2024)年は前年に比べ5g減少し671gとなりました(図表4-4-21)。
農林水産省では、令和3(2021)年3月から「日本茶と暮らそうプロジェクト」を実施しており、その一環として、毎年新茶シーズンの本格化に併せて、産地や事業者等と連携してお茶の消費拡大に向けたキャンペーンに取り組んでいます。令和6(2024)年4月からは「お茶の可能性は無限!~お茶×(かける)キャンペーン~」を開始し、日本茶の多様な楽しみ方を発信しています。
*1 緑茶には、茶飲料を含まない。
(砂糖の需要拡大に向け「ありが糖運動」を展開)

データ(エクセル:26KB)
砂糖の年間消費量については、人口減少や消費者の低甘味嗜好(しこう)等に伴い、近年減少傾向で推移しています。直近では新型コロナウイルス感染症の影響緩和に伴う経済活動の回復等により、緩やかに回復基調ですが、令和5(2023)砂糖年度は物価高の影響等により前砂糖年度に比べ6千t減少し174万2千tとなりました(図表4-4-22)。
農林水産省では、砂糖に関する知識や砂糖・甘味に由来する食文化の魅力等について広く情報発信する「ありが糖運動」を展開しています。砂糖関連業界等と連携し、SNS等を活用しながら、砂糖の効能や、砂糖を使った郷土料理や郷土菓子、スイーツ情報等の発信に取り組んでいます。
(「花いっぱいプロジェクト」を展開)

データ(エクセル:26KB)
切り花の1世帯当たりの年間購入額については長期的に見ると減少傾向で推移しており、令和6(2024)年は前年に比べ350円減少し7,684円となりました(図表4-4-23)。
農林水産省では、令和9(2027)年に神奈川県横浜市(よこはまし)で開催される「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」を契機とした需要拡大を図るため、「花いっぱいプロジェクト」を展開しています。花きをより身近に感じてもらうため、花き業界と協力し、バレンタイン等のイベントに合わせた花贈りの提案や花きの暮らしへの取り入れ方等について、情報発信を行っています。
(「牛乳でスマイルプロジェクト」を展開)

データ(エクセル:26KB)
牛乳乳製品の1人当たりの年間消費量については、令和5(2023)年度はヨーグルト等の原料となる脱脂粉乳の需要低迷等により前年度に比べ3.8kg減少し90.1kgとなりました(図表4-4-24)。
農林水産省では、酪農・乳業関係者のみならず、企業・団体や地方公共団体等の幅広い参加者と共に、共通ロゴマークにより一体感を持って、更なる牛乳乳製品の消費拡大に取り組むため、一般社団法人Jミルクと共に、「牛乳でスマイルプロジェクト」を展開しています。令和6(2024)年度は、6月1日の「牛乳の日」、6月の「牛乳月間」に併せて、消費者の部屋において展示を行うなど、牛乳乳製品の消費拡大に向けた取組を実施しました。
(コラム)国産チーズの競争力強化に向けた取組を推進
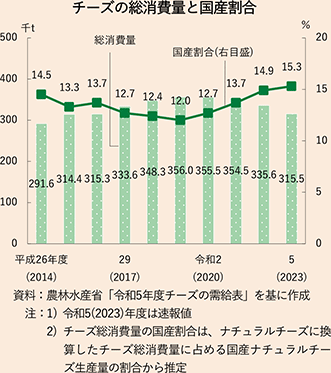
データ(エクセル:26KB)

令和6(2024)年のJapan Cheese Awardsの様子
資料:特定非営利活動法人チーズプロフェッショナル協会
令和5(2023)年度の国内のチーズ総消費量は、食料品を始めとした物価上昇により、消費者の節約志向が高まり、嗜好品であるチーズの買い控えがあったことから前年度に比べ約6%減少し、31万5千tとなりました。しかしながら、円安による輸入価格の上昇で輸入品は減少しており、総消費量のうち国産品が占める割合は前年度に比べ0.4ポイント上昇し15.3%となり、過去10年間で最も高い割合となりました。
特定非営利活動法人チーズプロフェッショナル協会は、平成26(2014)年から隔年で国内最大級のコンテストである「Japan Cheese Awards」を開催しており、令和6(2024)年は前回に比べ出品数は61品増え372品、出品工房数は11工房増え120工房となり、年々着実に増加しています。同時に開催されるイベントでは、実際に消費者が生産者と交流することを通じ、消費者が国産チーズの魅力を知るきっかけとなっています。また、欧州では毎年「World Cheese Awards」が開催されており、同年は世界中から4,786品が出品され、我が国のチーズは21品入賞する結果となり、海外でも高く評価されていることがうかがわれます。同協会では、今後とも我が国の食卓、そして日本人の様々な生活シーンにチーズを定着させるために活動していくこととしています。
(4)食育の推進
(「第4次食育推進基本計画」の実現に向けた取組を推進)

「ワクワクEXPO with 第19回食育推進全国大会」の
周知ポスター
食育の推進に当たっては、国民一人一人が自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することが重要です。令和3(2021)年度からおおむね5年間を計画期間とする「第4次食育推進基本計画」では、基本的な方針や目標値を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等を定めています。
農林水産省、大阪府、大阪市(おおさかし)と第19回食育推進全国大会大阪府実行委員会は、令和6(2024)年6月に「ワクワクEXPO with 第19回食育推進全国大会」を開催しました。令和7(2025)年に大阪・関西万博が開催されることから、同大会においては、万博をインパクトとした健康寿命の延伸、万博開催機運の醸成、「食」で始める大阪の成長を目指すことを目的としました。また、農林水産省では、第8回食育活動表彰を実施し、ボランティア活動や教育活動、農林漁業、食品製造・販売等の事業活動を通じて、食育の推進に取り組む者(以下「食育関係者」という。)による優れた取組を表彰しました。
また、農林水産省では、最新の食育活動の方法や知見を食育関係者間で情報共有するとともに、異業種間のマッチングによる新たな食育活動の創出、食育の推進に向けた研修を実施できる人材の育成等に取り組むため、全国食育推進ネットワークを活用した取組を推進しています。
さらに、食育を推進していく上では、国、地方公共団体による取組のほか、地域において、学校、保育所、農林漁業者、食品関連事業者等の様々な関係者の緊密な連携・協働の下で取組を進めていく必要があります。このため、農林水産省では、地域の関係者が連携して取り組む食育活動を支援しています。
(事例)料理教室を通して子供たちに対する食育を展開(福井県)
(1)全国で初めて食をテーマにした条例を制定し、「生涯食育」、「義務食育」を展開
福井県小浜市(おばまし)は、平成13(2001)年に全国で初めて食をテーマにした「小浜市食のまちづくり条例」を制定し、全市民を対象とした「生涯食育」を掲げ、特に重要な子供の食育については、誰ひとり取り残さない「義務食育」体制を整備しています。
(2)食育を伴う「キッズ・キッチン」と「ジュニア・キッチン」を実施
様々な食育事業の中で、特にユニークなのが、幼児の料理教室「キッズ・キッチン」です。同市内の年長児全員が参加する基礎編と、希望者が参加する拡大編の両輪で実施しており、基礎編では、かまどでごはんを炊くほか、だしを引いた具沢山みそ汁といった和食の一汁一菜を作ります。拡大編では、魚さばきや行事食といったかなり高度な内容が盛り込まれています。料理の際には、本物の包丁を使い、火の管理等も含めたプロセス全般を子供たちが主体的に取り組む中で、食への関心の高まりや料理技術の習得のほか、料理を作りあげることの達成感や満足感、友達と協力することや命ある食材への感謝の気持ちといった心の成長が期待できます。

このような「キッズ・キッチン」の運営は、20~50歳代の仕事と子育てを両立させながら活動している「キッズ☆サポーター」が行っており、令和7(2025)年1月時点で19人が所属しています。
さらに、同団体は市内の小学校六年生全員が授業の一環として参加する「ジュニア・キッチン」も担当しており、郷土料理に加え、同市の御食国(みけつくに)や鯖街道(さばかいどう)といった大切な食の歴史を子供たちに伝えています。
(3)地域外へ食育事業を広域展開

「キッズ・キッチン」の様子
資料:福井県小浜市
このような同市の特徴ある食育事業は、これまで20年以上継続しています。近年では、幼い頃に「キッズ・キッチン」等に参加した方が成人し、指導者として活躍する姿も見られます。このように、地域に定着したこのような食育事業を今後も継続するとともに、地域外の方々も「食育ツーリズム」として積極的に受け入れることで、食育の広域展開を図ります。
(5)地産地消の推進
(消費者の取組として約4割が「地産地消に取り組む」と回答)
我が国の食の未来を確かなものにするための消費者の取組として、令和6(2024)年6月に公表した調査によると、「地産地消に取り組む」が39.4%、「買物や外食時に、国産食材を積極的に選ぶ」が28.7%となっています(図表4-4-25)。
地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する「地産地消」の取組は、国産農林水産物の消費拡大につながるほか、地域活性化や農林水産物の流通経費の削減等にもつながります。少子・高齢化やライフスタイルの変化等により国内マーケットの構造が変化する中、消費者の視点を重視し、地産地消等を通じた新規需要の掘り起こしを行うことが重要となっています。
特に地域の農産物を直接消費者に販売する直売所は、販売金額における地場産物商品の割合が約9割を占め、地産地消の核となるものであり、消費者にとっては、生産者との顔の見える関係が築け、安心して地域の新鮮な農林水産物を消費できるほか、生産者にとっては、消費者ニーズに対応した生産が展開できるなどの利点があります。農林水産省では、直売所における新商品の開発や直売所の施設等の整備を支援しています。
このほか、JA全中を始めとしたJAグループは、「私たちの『国』で『消』費する食べ物は、できるだけこの『国』で生『産』する」という考え方である「国消国産」の実践を推進しています。

データ(エクセル:26KB)

「国消国産」を呼び掛けるポスター
資料:JA全中
(学校給食における地場産物の使用を推進)
学校給食は、栄養バランスの取れた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を図ること等を目的に、学校の設置者により実施されています。文部科学省の調査によると、令和5(2023)年5月時点で、小学校では18,584校(全小学校数の99.1%)、中学校では8,990校(全中学校数の91.5%)、特別支援学校等も含めた全体で29,204校において実施されており、約920万人の子供を対象に給食が提供されています。
学校給食において地場産の農林水産物を使用することは、地産地消を推進するに当たって有効な手段であり、地域の関係者の協力の下、未来を担う子供たちが持続可能な食生活を実践することにつながる取組となっています。また、食に関する指導の教材として活用することで、地域の自然、文化、産業等に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や食に関する感謝の念を育む上で重要となっています。
文部科学省が令和5(2023)年6月及び11月に実施した調査によると、学校給食における地場産物、国産食材の使用割合を都道府県別に見ると、地場産物の使用割合にばらつきが見られる一方、国産食材の使用割合はほとんどの都道府県で80%以上となっており、全国的に使用割合が高い状況となっています(図表4-4-26)。都道府県ごとに農業生産の条件が異なる中、学校給食における地場産物や国産食材の活用に向けた取組が全国各地で進められています。
地場産物の利用に当たっては、一定の規格等を満たし、数量面で不足なく安定的に納入する必要があるなど、多くの課題が見られるため、農林水産省では、地産地消コーディネーターの派遣による給食現場と生産現場の間の課題解決に向けた指導、助言等の支援を行っています。また、食育の推進の観点から、地域で学校給食に地場産物を供給・使用する連携体制づくりや献立の開発等の活動を支援しています。

データ(エクセル:28KB)
(6)和食文化の保護・継承
(和食文化の保護・継承に向けた取組を推進)
食の嗜好やライフスタイルの変化等を背景に、和食(*1)や地域の郷土料理、伝統料理に触れる機会が少なくなってきており、和食文化の保護・継承に向けて、郷土料理等を受け継ぎ、次世代に伝えていくことが課題となっています。このため、農林水産省では、子供たちや子育て世代に対して和食文化の普及活動を行う中核的な人材である「和食文化継承リーダー」を育成する取組を実施しています。
また、地域固有の多様な食文化の保護・継承を図るため、各地域で選定された郷土料理の歴史やレシピ、郷土料理を生んだ地域の背景等を紹介するウェブサイト「うちの郷土料理」と、その英語サイト「Our Regional Cuisines」にて情報発信しているほか、令和4(2022)年度にウェブサイト「にっぽん伝統食図鑑」を開設し、伝統的な加工食品の歴史や製造方法等の情報を発信しています(図表4-4-27)。
さらに、身近で手軽に健康的な和食を食べる機会を増やしてもらい、将来にわたって和食文化を受け継いでいくことを目指した、官民協働の取組である「Let’s!和ごはんプロジェクト」を実施しています。
このほか、文化庁では、我が国の豊かな風土や人々の精神性、歴史に根差した多様な食文化を次の世代へ継承するために、文化財保護法に基づく文化財の登録等を進めるとともに、各地の食文化振興の取組に対する支援、食文化振興の機運醸成に向けた情報発信等を行っています。

*1 「和食」は、「自然を尊重する」というこころに基づいた日本人の食慣習。「和食;日本人の伝統的な食文化」として平成25(2013)年12月にユネスコ無形文化遺産に登録
(7)消費者と生産者の関係強化
(消費者と生産者の交流の促進に向けた取組を推進)

データ(エクセル:27KB)
消費者と生産者の交流を促進することにより、農村の活性化や農業・農村に対する消費者の理解増進が図られるなどの効果が期待されています。しかしながら、消費者は、食や農との関係が消費のみにとどまることが多いことから、食や農に関する体験活動に参加する機会を持つことも重要です。家族の中で農林漁業体験に参加したことのある人の割合は6割前後で推移しています(図表4-4-28)。さらに、体験後「自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった」と回答した人は約6割となっており、農林漁業体験は消費者の行動変容につながることがうかがわれます。このようなことから、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を深めるために、農業者が生産現場に消費者を招き、教育ファーム等の農業体験の機会を提供する取組等も行われています。
農林水産省では、これらの取組を広く普及するため、教育ファーム等による農林漁業体験を始めとする消費者と生産者の交流の促進に対する機会の提供への支援のほか、どこでどのような体験ができるか等についての情報発信を行っています。
くわえて、消費者にとって生産者との顔の見える関係づくりを目指した消費者と生産者を結びつける取組も見られつつあります。
(事例)消費者と生産者が直接つながるプラットフォームを実現(東京都)
(1)生産者と消費者が直接つながる産直通販サイトを立上げ

東京都港区(みなとく)の株式会社ビビッドガーデンでは、「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」をビジョンに掲げ、生産者が、個人や法人に「直接」商品を販売し、消費者と直接つながるオンライン直売所を運営しています。
実家の農地が荒廃しているのを見た代表取締役の秋元里奈(あきもとりな)さんが、「1次産業に関わる仕事がしたい」という気持ちから、平成28(2016)年に同社を創業しました。
(2)充実したサポート体制による生産者支援が強み

スタートアップ大賞を受賞
資料:株式会社ビビッドガーデン
令和7(2025)年2月時点でオンライン直売所の登録生産者数は約1万軒、登録消費者数は110万人を突破しました。同社の強みは、カスタマーサポートの代行やインターネットに不慣れな生産者のサポート等の手厚い生産者支援と、生産者と消費者のお互いの声を直接届ける仕組みにあります。
また、インターネット通販に苦手意識を持つ生産者のため、近所の生産者と一緒に出品できるサービスや地方公共団体との連携も行っており、取組件数は100を超えました。
(3)事業規模の拡大・新たな事業への挑戦

野菜セット
資料:株式会社ビビッドガーデン
今後同社は、オンライン直売所の更なる登録生産者数の拡大を目指して、地方公共団体や企業との連携に力を入れていくこととしています。また、令和6(2024)年11月にサービス開始から7年で培った全国1万軒の生産者ネットワークを基盤に3つのサービスを新たにリリースし、今後はより幅広い消費者の課題を解消できるように事業領域を拡大していきます。
長期的な視点では、生産者に対しては販売に関する支援だけでなく、生産者の抱える多様な課題の解決に貢献していく考えです。
(国民運動「ニッポンフードシフト」を通じ、食と農の魅力を発信)
食料の持続的な確保が世界的な共通課題となる中で、我が国においては食と農の距離が拡大し、農業や農村に対する国民の意識・関心が薄れています。このような中、農林水産省は、食と農のつながりの深化に着目した、官民協働で行う国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」(以下「ニッポンフードシフト」という。)を展開しています。
ニッポンフードシフトは、未来を担う1990年代後半から2000年代生まれの「Z世代」を重点ターゲットとして、食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解と共感・支持を得つつ、国産農林水産物の積極的な選択といった行動変容につなげるために、全国各地の農林漁業者の取組や地域の食、農山漁村の魅力を発信しています。
令和6(2024)年度は、10月から11月を「食から日本を考える。月間」と位置付け、情報発信を強化しました。その取組として、ニッポンフードシフト公式ウェブサイト内で、「食」関連の体験やイベント情報を発信しました。また、ニッポンフードシフトの趣旨に賛同した「推進パートナー」企業と連携し、消費者に向けて農作物等の生産から消費までの裏側について、SNSを通じて発信しました。さらに、令和5(2023)年度に引き続き、東京都及び大阪府で、日本の「食」や「農」をめぐる事情や課題を共に考えるイベントを開催しました。くわえて、一般社団法人日本新聞協会(にほんしんぶんきょうかい)による第44回新聞広告賞において優秀賞を、株式会社日本経済新聞社(にほんけいざいしんぶんしゃ)による第73回日経広告賞において大賞を受賞し、「食」に関する国民の理解醸成につなげています。

47都道府県合同企画
「ニッポンは、ずっとおいしいか?」
*左上と左下の広告は令和6(2024)年1月8日に日本経済新聞に、右上の広告は令和6(2024)年2月29日に日本経済新聞に掲載
(消費者と農林水産業関係者等を結ぶ広報を推進)
デジタル技術の活用を始めとした生活様式の変化により、消費者はSNS等のインターネット上の情報を基に購買行動を決定し、生産者もこれに合わせて積極的にSNS上で情報発信をするようになってきたことを踏まえ、農林水産省は、農林水産業関連の情報や施策を消費者目線で発信する省公式X(旧Twitter)、食卓や消費の現状、暮らしに役立つ情報等を毎週発信するウェブマガジン「aff(あふ)」等を通じて、消費者と農林水産業関係者、農林水産省を結ぶための情報発信を強化しています。
また、我が国の農林水産物や農山漁村の魅力等を動画で伝えるため、令和元(2019)年度から開設した、職員自らがYouTuberとなって発信する省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF」は5周年を迎え、令和6(2024)年度末時点で、チャンネル登録者数は17万人を数え、1日1本以上のペースで投稿を続け、総投稿本数は1,920本、総再生回数は4,800万回を超えています。
さらに、令和6(2024)年度の「こども霞が関見学デー」の一環として、農林水産省では5年ぶりに予約せずに参加できる会場プログラムも復活し、ワークショップ等を開催したほか、食や農林水産業について学べる夏の特設ウェブサイト「マフ塾~遊ぶ!学ぶ!食べる!~」を開設し、小学生から大人まで楽しめるクイズを始め、全国どこからでも農業・林業・水産業を学べるコンテンツを公開しました。

BUZZ MAFF5周年記念の動画

省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF」
URL:https://www.youtube.com/channel/
UCk2ryX95GgVFSTcVCH2HS2g

aff(あふ)
URL:https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








