第3節 食品の安全確保と消費者の信頼の確保
食品の安全性を向上させるためには、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼすおそれのある有害化学物質・有害微生物について、科学的根拠に基づいたリスク管理(*1)等に取り組むとともに、農畜水産物・食品に関する適正な情報提供を通じて消費者の食品に対する信頼確保を図ることが重要です。
本節では、国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保に向けた取組について紹介します。
*1 全ての関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措置について技術的な実行可能性、費用対効果等を検討し、適切な政策・措置の決定、実施、検証、見直しを行うこと
(1)科学的知見等を踏まえた食品の安全確保の取組の強化
(リスク評価機関とリスク管理機関が相互に連携し、食品の安全を確保)
食品安全基本法は、「国民の健康保護が最も重要」、「農場から食卓まで」、「科学的知見に基づき、後始末より未然防止」といった考え方に基づき、国や食品事業者等の関係者の責務・役割、施策策定の基本的な方針等を規定しています。
この基本理念は、食品安全行政に関する世界的な考え方であり、食品安全に関する国際基準の策定機関であるコーデックス委員会(*1)のリスク分析の原則とも整合するものです。
食品安全を守る仕組みは、「リスク評価」、「リスク管理」、「リスクコミュニケーション」の3要素から構成されており、我が国では、リスク評価機関(食品安全委員会)とリスク管理機関(厚生労働省、農林水産省、消費者庁等)が、相互に連携しつつ、食品安全を確保するための取組を推進しています(図表4-3-1)。

令和6(2024)年4月から、食品安全行政の総合調整機能を担う消費者庁に、厚生労働省が所管している食品衛生に関する規格基準の策定等が移管されました。これにより食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図ることとしています。
*1 消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、昭和38(1963)年にFAO及びWHO(世界保健機関)により設置された国際的な政府間組織
(食中毒発生件数は前年と同程度)

データ(エクセル:27KB)
食中毒の発生は、消費者に健康被害が生じるばかりでなく、原因と疑われる食品の消費の減少にもつながることから、農林水産業や食品産業にも経済的な影響が及ぶおそれがあります。このため、農林水産省は、食品の安全や消費者の信頼を確保するため、科学的根拠に基づき、生産から消費に至るまでの必要な段階で有害化学物質・有害微生物の汚染の防止や低減を図る措置の策定・普及に取り組んでいます。
令和6(2024)年の食中毒の発生件数は、前年と同程度の1,037件となりました(図表4-3-2)。
(最新の科学的知見・動向を踏まえリスク管理を実施)
農林水産省は、食中毒の患者数等の最新の科学的知見、消費者・食品関連事業者等関係者の関心、国際的な動向を考慮して、食品の安全確保に取り組んでいます。
農林水産省では、優先的にリスク管理の対象とする有害化学物質・有害微生物を選定した上で、5年間の中期計画及び年度ごとの年次計画を策定し、サーベイランス(*1)やモニタリング(*2)を実施しています。また、汚染低減のための指針等の導入・普及や衛生管理の推進等の安全性向上対策を食品関連事業者と連携して実施し、その効果の検証のための調査を行い、最新の情報に基づいて指針等を更新しています。さらに、食品安全に関する国際基準・国内基準や規範の策定、リスク評価に貢献するため、これらの取組により得た科学的知見やデータをコーデックス委員会や関連する国際機関、関係府省へ提供しています。
令和6(2024)年度は、有害化学物質40件、有害微生物12件の調査を実施しました。これまでの調査の評価・解析の結果はウェブサイトに掲載しており、それらの結果を活用し、有害化学物質・有害微生物の汚染の防止・低減のための措置の必要性や効果について検証・評価し、科学的な根拠に基づき、食品の安全性の向上のための取組を推進しています。
また、近年、人の健康や動植物の生育への影響が指摘されている「PFAS(ピーファス)(*3)」について、農林水産省では農地土壌等の環境からの農産物等への移行に関する研究を更に進めるとともに、令和6(2024)年度から国産農畜水産物の含有実態調査を開始し、科学的知見の集積に取り組んでいます。
さらに、食品事業者等による食品の安全性向上に係る取組について、事業者等の取組状況や消費者意識等を踏まえた情報発信手法により「見える化」し、国民理解の増進を図っています。

こども霞が関見学デー
手洗い教室の様子
このほか、消費者向けの食品安全に関する情報の発信にも積極的に取り組んでおり、ノロウイルスや有毒植物、毒きのこ等による食中毒の防止について、ウェブサイトに掲載するとともに、SNS、動画等を活用して注意喚起を行っています。令和6(2024)年度は、「こども霞が関見学デー」において手洗い教室を開催し、食中毒予防の取組を推進しました。同教室では親子でハンドソープを作るイベントを行い、子育て世代を含む幅広い世代を対象に親しみやすい内容としました。
*1 問題の程度又は実態を知るための調査のこと
*2 矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査のこと
*3 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称
(コラム)食品業界では、製品中のトランス脂肪酸を継続的に低減
健康を保つためには、食品からエネルギーや栄養素をバランス良く摂ることが最重要です。エネルギー産生栄養素の一つである脂質は、食品から摂る量が少な過ぎると健康リスクを高めることがある一方、摂り過ぎた場合は肥満等による生活習慣病のリスクを高めることも知られています。そのため、WHOは飽和脂肪酸及びトランス脂肪酸(*)の摂取に関するガイドラインを令和5(2023)年7月に公表し、トランス脂肪酸の摂取量を総摂取エネルギーの1%に相当する量まで減らすことを強く勧告しました。また、1%未満に減らすことや、より健康的な脂肪酸への置換えも推奨しています。我が国においては、これまで食品メーカーや事業者団体による食品中のトランス脂肪酸濃度の低減に向けた自主的な取組等が実施されてきました。
例えば日本(にほん)マーガリン工業会(こうぎょうかい)の会員企業では、油脂の加工段階でトランス脂肪酸の生成を防ぐ取組を実施しています。マーガリンやファットスプレッドの製造には、常温で液体の油脂を半固体又は固体に変える必要があり、かつてはトランス脂肪酸が生成されやすい水素添加という方法がよく用いられていました。しかし、水素添加の代わりにトランス脂肪酸が生成されにくい方法へと移行したことにより、製品の品質を保ちつつトランス脂肪酸の濃度を低減することに成功しています。
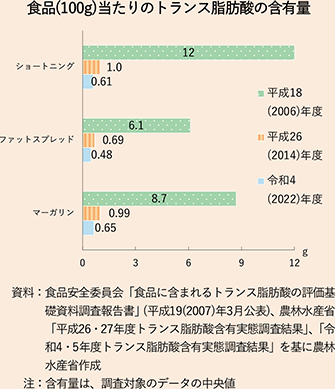
データ(エクセル:25KB)
様々な食品でこのような取組が継続された結果、食品中のトランス脂肪酸濃度は引き続き低い状態となっています。例えば令和4(2022)年度に農林水産省が実施した調査では、マーガリン100g当たりのトランス脂肪酸は0.65gとなっており、試料の採取方法等が異なるものの、平成26(2014)年度の0.99gより約34%低い結果となりました。食パン1食当たりのマーガリンを塗る量を10gとすると0.065gで、総摂取エネルギーに占める割合は約0.03%となっています。
また、農林水産省では、行政施策・措置の決定に必要な科学的知見を得るため、様々な研究を実施しています。その一環として、植物油の精製工程で生成される、トランス脂肪酸以外の化学物質についても低減方法の研究が行われています。食品安全の問題発生の未然防止や発生後の被害拡大防止のため、引き続き取組が進められています。
* 植物油を高温にして脱臭する工程や植物油等をマーガリンやショートニング等に加工する際に生じる不飽和脂肪酸の一種。反すう動物の肉や乳製品等にも微量に含まれる場合がある。

安全で健やかな食生活を送るために
URL:https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html

トランス脂肪酸に関する情報
URL:https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/
trans_fat/index.html
(農業生産資材の安全確保の取組を推進)
農薬や肥料、動物用医薬品、飼料等の農業生産資材については、農畜水産物の安全を確保するため、これまでも科学的知見や国際基準に基づき、使用基準や安全基準の設定・見直し等を実施しています。
農薬については、安全性の一層の向上を図るため、農薬取締法に基づき、再評価を進めています。再評価は、最新の科学的知見に基づき、全ての農薬についておおむね15年ごとに、国内での使用量が多い農薬を優先して順次実施しています。
また、肥料については、国内資源の利用拡大が重要となる中、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、令和5(2023)年度に汚泥資源の利用拡大に向け、公定規格「菌体りん酸肥料」(*1)を創設し、肥料生産業者等に対して同規格の周知を進めています。
動物用医薬品及び飼料についても、それぞれの関連法令に基づき、畜産物の安全の確保を前提としつつ、最新の科学的知見等を踏まえ、リスク管理措置の見直し等を進めています。また、動物用ワクチンについては、家畜疾病の発生予防・まん延防止に重要な農業生産資材であることから、開発促進及び安定的な確保・供給を図るため、動物用ワクチン戦略を策定しました。
食料生産・供給のグローバル化を踏まえ、農林水産省では、国際的なリスク評価との調和を始め、農業生産資材の更なる安全性向上を進めていくこととしています。
*1 第2章第5節を参照
(薬剤耐性菌の増加を防ぐ対策を推進)
近年、抗微生物剤の不適切な使用を背景とした薬剤耐性(AMR(*1))の拡大により、人や動物の健康への影響が懸念されています。このような中、薬剤耐性の発生をできる限り抑制するとともに、薬剤耐性微生物による感染症のまん延を防止するため、令和5(2023)年に策定された「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)」では、令和9(2027)年における畜産分野の動物用抗菌薬の全使用量を対令和2(2020)年比で15%削減すること等を目標値として掲げています。
農林水産省では、動物用抗菌薬の農場単位での使用実態を把握できる仕組みの検討やワクチンの開発・実用化の支援等を行っています。令和6(2024)年度においては、動物用抗菌薬の使用実態の把握に資するため、電子指示書システムの構築を行ったほか、関係者の薬剤耐性対策への理解を深めるためのオンラインセミナーを開催しました。
*1 Antimicrobial Resistanceの略
(2)食品に対する消費者の信頼の確保
(消費者の信頼確保に関する事項への懸念が一定程度存在)
公庫が令和7(2025)年1月に実施した調査によると、保存料、甘味料、着色料、香料といった食品の製造過程又は食品の加工・保存の目的で使用される「食品添加物」のほか、「残留農薬」や「食品表示の偽装」、「食中毒」といった消費者の信頼に関わる懸念事項が一定程度見られており、消費者の信頼確保に取り組む必要性がうかがわれます(図表4-3-3)。

データ(エクセル:28KB)
(コラム)食品安全に関する正しい知識を伝える取組を開始

ワークショップの様子
資料:大阪いずみ市民生活協同組合
食品の安全や消費者の信頼確保に関する事項への懸念も一定程度見られる中、科学的根拠に基づいた情報を正しく理解することが重要です。大阪府南部をエリアとする大阪(おおさか)いずみ市民(しみん)生活協同組合と、和歌山県のわかやま市民(しみん)生活協同組合では、令和6(2024)年7月から、食品の安全に関する正しい情報を伝えることができる「食品安全コミュニケーター」を育成する講座を開始しました。
講座では、専門家による食品安全に関するハザード(危害要因)とリスク(食品中にハザードが存在する結果として生じる健康への悪影響が起きる可能性とその程度)や、食品表示に関する講義と、コミュニケーターとして消費者にどのように伝えるかについて参加者同士で議論するグループワークを実施しています。
近隣の生活協同組合からも関心が寄せられており、両組合では、令和7(2025)年度以降も継続し、内容を更に充実させていくこととしています。
(機能性表示食品の健康被害情報の報告を義務化)
機能性表示食品制度は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる制度です。
令和6(2024)年3月に紅麹(べにこうじ)関連製品による健康被害が報告されました。同年5月に開催された紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において取りまとめられた「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」を踏まえ、消費者庁及び厚生労働省は、同年8月に「食品表示基準」及び「食品衛生法施行規則」を改正し、同制度の見直しを行いました。具体的には、健康被害と疑われる情報の収集と都道府県等や消費者庁長官への提供を義務付け、情報提供期限等の明確な基準を示したほか、錠剤、カプセル剤等食品の適正製造規範(GMP(*1))に基づく製造・品質管理等も規定したところです。その他、表示方法の見直し及び届出に関する事項等の見直しを行いました。
*1 Good Manufacturing Practiceの略
(時代に即した食品表示の見直しを推進)
消費者庁では、令和5(2023)年度に改定した消費者基本計画工程表等に基づき、有識者からなる「令和5年度食品表示懇談会」を開催し、今後の食品表示が目指していく方向性を取りまとめ、それに基づき、個別品目ごとの表示ルールの見直し、食品表示へのデジタルツールの活用等を検討する必要があるとされました。これを受けて令和6(2024)年度は、食品表示懇談会に分科会を立ち上げ、これらの具体的な議論を進めています。
また、容器包装の見やすい箇所に食品表示を行う日本版包装前面栄養表示については、消費者の健康の維持・増進のために食品関連事業者が自主的に取り組むものであり、消費者庁では、令和6(2024)年7月から「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」を開催し、日本版包装前面栄養表示ガイドライン等の作成に向けた検討を行っています。
(不適正な食品表示への注意喚起を推進)
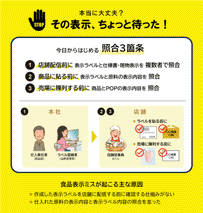
食品表示ミス防止に向けた啓発チラシ
食品の表示やトレーサビリティに関連する法律においては、原料の原産地等に関する情報の伝達や商品の性能を示すための表示を商品の包装等に付すこと等を規定しています。食品表示の適正化や的確な情報伝達を図るため、食品表示法等に基づく監視を実施しており、表示の外形的な的確性や保存された記録から表示の真正性を確認しています。令和6(2024)年10月には、食品関連事業者に対して、不適正表示が起こる主な原因や対策をチラシで周知し、食品表示ミスの防止に取り組んでいます。
(食品リコールの届出件数について、回収理由別ではアレルゲンが最多)
食品衛生法及び食品表示法の改正を踏まえ、令和3(2021)年6月から、食品リコールの届出が義務化されています。
令和6(2024)年9月末時点での食品表示法に基づく自主回収の届出件数(公開件数)は5,584件となっています。回収理由別では、アレルゲンが2,821件で最多となっているほか、品目別では、調理食品が2,203件で最多となっています(図表4-3-4)。

データ(エクセル:27KB)
(食品トレーサビリティの普及啓発を推進)
食品トレーサビリティは、食品の移動を把握できることを意味しています。各事業者が食品を取り扱った際の記録を作成・保存しておくことで、食中毒等の健康に影響を与える事故等が発生した際に、問題のある食品がどこから来たのかを遡及(そきゅう)して調べ、どこに行ったかを追跡することができます。
一方、食品の製造工程における内部トレーサビリティは、人手が不足していること、入出荷を優先していること等の理由から、特に中小零細企業での取組率が低いことが課題となっています。
このため、農林水産省では、食品トレーサビリティに取り組むためのポイントを記載したマニュアルや、QRコード等を活用したトレーサビリティの優良事例集等を作成し、セミナー等を開催して更なる取組の普及啓発を推進しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




