第2節 円滑な食品アクセスの確保に向けた対応
我が国においては、全ての国民が健康的な生活を送るために必要な食品を入手できない、いわゆる「食品アクセス」の問題への対応が重要な課題となっています。平時から食料を確保し、全ての国民が食料を入手できるようにするため、関係省庁・地方公共団体等が連携して円滑な食品アクセスの確保に向けた対応を推進していく必要があります。
本節では、食品アクセスの状況と円滑な食品アクセスの確保に向けた対応について紹介します。
(1)食品アクセスの状況
(経済的アクセスと物理的アクセスの確保に向けた対応が必要)
内閣府が令和3(2021)年2~3月に実施した調査によると、過去1年間でお金が足りなくて食料困窮を経験したことのあるひとり親世帯の割合は、30.0%となっています(図表4-2-1)。ふたり親世帯の8.4%に比べ21.6ポイント高くなっており、ひとり親世帯では、ふたり親世帯に比べ厳しい生活状況がうかがわれます。経済的に困窮している者の食品アクセス(経済的アクセス)の確保に向けた対応が必要となっています。
また、国内市場の縮小化等を背景として、高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる人、いわゆる「買物困難者」が増加しています。令和6(2024)年2月に農林水産政策研究所が公表した調査によると、令和2(2020)年の食料品アクセス困難人口は全国で904万3千人と推計され、平成27(2015)年に比べ9.7%増加しました(図表4-2-2)。このような課題に対し、買物困難者の食品アクセス(物理的アクセス)の確保に向けた対応が必要になっています。
(食品へのアクセスが十分でない者が一定数存在)
公庫が令和7(2025)年1月に実施した調査によると、食料品店舗へのアクセスについて、「公共交通手段の利用又は徒歩により、15分以内で食料品店舗にアクセスすることができる」と回答した人は62.2%となっている一方、「15分以内ではできない」と回答した人は37.8%となっています(図表4-2-3)。
また、同調査によると、健康的な食事のための食料品の購入が手頃な価格でできているかどうかについて、「できている」と回答した人は54.6%となっている一方、「できていない」と回答した人は45.4%となっています(図表4-2-4)。このような調査結果からも、我が国においては、平時から円滑な食品アクセスの確保に課題があることがうかがわれます。
(2)円滑な食品アクセスの確保に向けた対応
(「食品アクセスの確保に関する支援策パッケージ」に基づき地域の取組を促進)
経済的理由により十分な食料を入手できない者や買物困難者が増加していると考えられ、経済的にも、物理的にも、食品アクセスの問題が顕在化している中、平時から国民一人一人が食料にアクセスでき、健全な食生活を実践できるようにすることが重要です。そのためには、地域の関係者が連携して取り組む体制づくりや、フードバンクやこども食堂等の機能強化、食品流通業者等の流通サービスへの支援が必要になっています。
農林水産省では、食品アクセスの確保に資する関係省庁の支援策を組み合わせて活用してもらえるよう、「食品アクセスの確保に関する支援策パッケージ」を取りまとめており、その周知を通じて、地方公共団体や民間事業者等による地域における食品アクセスの確保に向けた取組を促進しています。
また、令和6(2024)年9月、令和7(2025)年1月には、関係省庁と連携して「食品アクセス全国キャラバン」を開催し、各地域の関係者や団体等に対し、食品アクセスの確保に関する関係省庁の支援策の説明や、食品アクセスの確保に取り組む先進的な事例の紹介を実施しています。
(地域の関係者が連携する体制づくり等を促進)
農林水産省では、円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域の関係者が連携して組織する協議会の設置、関係者間の調整役の配置、地域における食品アクセスの現状・課題の調査、課題解決に向けた計画の策定を支援しています。
また、相談窓口の設置等により食品アクセスに関する諸課題の解決のための取組を支援するとともに、先進的な事例を収集・活用等することで、取組の全国展開を図っています。
(フードバンク活動の支援を強化)

データ(エクセル:25KB)
フードバンクは、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることのできる食品の提供を受けて、貧困や災害等により必要な食品を十分に入手できない者にこれを提供するための活動を行う団体のことを言います。その性質上、フードバンク活動は、食品ロスの削減に直結するとともに、経済的に困窮している者への支援にもつながるものであり、令和7(2025)年3月末時点で、全国で287団体(農林水産省ウェブサイトに掲載の希望があった団体に限る。)と、その数とともにその役割も拡大しています(図表4-2-5)。
このような役割を踏まえ、農林水産省では、未利用食品の提供等を通じた食品ロスの削減を推進するため、その受け皿となる大規模かつ先進的な取組を行うフードバンク等を支援しているほか、円滑な食品アクセスの確保の観点から、経済的に困窮している者への食料提供の充実を図るため、フードバンク等の立上げ等を支援しています。
一方、特定非営利活動法人フードバンク仙台(せんだい)が令和6(2024)年7月に公表したアンケート調査によると、物価高騰を背景としてフードバンクへの寄附が減少しているといった回答も見られました。全国のフードバンク活動を行っている団体のうち66団体による回答であることに留意する必要がありますが、フードバンク活動を取り巻く情勢が厳しくなっていることがうかがわれます。
農林水産省では、フードバンクやこども食堂等への食品の寄附が進むよう、企業とフードバンクとのマッチングや、企業による寄附の内容の見える化を推進することで、経済的に困窮している者への食料支援にもつなげていくことを目指しています。
(事例)食品ロスの削減と貧困の解消に向け、フードバンク事業を実施(山梨県)
(1)支援を必要とする世帯や施設に食料を提供する取組を展開
山梨県南(みなみ)アルプス市(し)の認定特定非営利活動法人フードバンク山梨(やまなし)は、食品ロス削減と貧困の解消につなげるため、企業から余剰在庫等の食品の寄贈を受け、行政を始めとした様々な主体と連携しながら、支援を必要としている世帯や施設に無償で提供するフードバンク事業を実施しています。
(2)様々な主体との連携による支援体制の構築や県内フードバンク設立支援を実施
平成20(2008)年に設立された同法人は、食品ロス削減を目的とした活動に取り組む中、「食べるものがない」という目に見えない課題があることを知り、平成22(2010)年から、行政と連携して食料支援に取り組む「食のセーフティネット事業」を開始しました。同事業は、行政等の要請をもとに、対象世帯に毎月2回食料等を届けるシステムで、令和5(2023)年度は5,327世帯に約51tの食料支援を実施しました。
また、平成27(2015)年からは、給食のない夏休み・冬休みに食料支援を行う「フードバンクこども支援プロジェクト」を全国に先駆けて実施しています。同プロジェクトは、連携協定を締結した市町村の学校を通じて支援対象世帯児童に申請書を配布し、支援を希望する家庭は学校を介さずに申請書を送付できるように工夫されており、令和5(2023)年度は1,789人の子供に支援しました。
このほか、地域の中核的フードバンクとして、同県内フードバンクの設立や品質管理を始めとしたノウハウ支援等を通じ、同県内全域での支援体制の構築に取り組んでいます。
(3)子供たちの未来につなげる活動を推進
同法人は、安定的に食料支援を行うために、企業からの大量寄贈の受入れや、一般家庭から寄附された食品を提供する取組であるフードドライブに取り組んでいます。また、フードバンク活動に関心のある団体・企業向けの説明会も定期的に実施しており、活動の輪を広げています。
さらに、同法人においては、子供の貧困を我が国の大きな課題と捉え、今後は、食料支援を行っている世帯を対象とした学習支援やシングルマザー支援といった貧困の連鎖を断ち切り困窮世帯の子供たちの未来につなげるための活動にも注力することとしています。


提供される食料等
資料:認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

活動を行う学生
資料:認定特定非営利活動法人フードバンク山梨
(こども食堂等による食料提供の取組を推進)
こども食堂は、子供たちを中心に、無料又は安価でバランスの良い食事や温かな団らん、共食の場を提供する、地域住民等による自主的な取組です。認定特定非営利活動法人全国(ぜんこく)こども食堂支援(しょくどうしえん)センター・むすびえが令和6(2024)年8~10月に実施した調査によると、こども食堂の数は全国で10,867か所となっています。
こども食堂は、共食の場の提供のほか、子供の居場所づくりや、経済的に困窮している者の食品アクセスの確保の観点からも重要な取組です。
農林水産省では、食育の推進という観点から、こども食堂等の地域での様々な共食の場を提供する取組を支援しており、令和2(2020)年度からは、政府備蓄米の無償交付を行っています。また、令和6(2024)年9月からは、こども食堂等向けの政府備蓄米無償交付の申請窓口を、農林水産省本省と9か所の地方農政局等に加えて、地域拠点等がある51か所にも新規開設しました。さらに、受付時期が年4回に限定されていた交付申請の受付を、通年で行うこととしました。令和7(2025)年3月からは、食育活動を支援するフードバンクも交付対象としました。その結果、令和6(2024)年度の交付数量は、こども食堂・こども宅食及びフードバンク向けを合わせて約1,199tとなっています。
くわえて、経済的に困窮している者への食料提供の充実を図るため、こども食堂等の立上げ等の支援を進めています。
(事例)スポーツの力を活かして「こども食堂」の取組を推進(千葉県)
(1)「地域愛着」をモットーとして社会貢献活動を推進
「千葉(ちば)ジェッツ」は、平成27(2015)年に創立されたB.LEAGUE(ビー リーグ)に所属するプロバスケットボールチームです。「地域愛着」をモットーとする同チームでは、「JETS ASSIST(ジェッツ アシスト)」という社会貢献活動を行っています。その活動の一つとして、令和2(2020)年からフードドライブを実践しており、選手がSNSを通じて試合の観客に食料品の寄贈を呼び掛け、一回に100kgを超える食料品が集まることもありました。
その結果、令和3(2021)年12月には同リーグに所属するチームとして初の「HEROs AWARD(ヒーローズ アワード)」を受賞しました。同賞は、スポーツの力を活用して社会貢献活動を行うアスリートやチーム、企業を表彰するものであり、同チームでは、この受賞をきっかけに更なる社会貢献活動として、こども食堂の取組を開始しました。
(2)試合の映像を見ながら食事ができるこども食堂を開設し、累計2,500食以上を提供
こども食堂は、令和4(2022)年9月から令和5(2023)年6月にかけて10回開催しており、令和6(2024)年9月からは月1回のペースで開催しています。開催に当たっては、地方公共団体と連携して優先的にひとり親世帯への参加を呼び掛けました。会場では、同チームの試合映像を放映しており、参加した家庭からは、「子供が大喜びだった」といった声が聞かれています。また、提供する食事には、地産地消につながる地元の食材を優先的に使い、令和7(2025)年3月時点の累計では2,500食以上を無償で提供しました。
(3)こども食堂の場で食育に関する出前授業を開催して、学びの場としても展開
令和6(2024)年度においては、こども食堂を開催する際に新たに地方公共団体と連携して食育に関する出前授業を併せて行っています。今後は、参加者にとって食事だけでなく学びの場にもなるような工夫を行っていくこととしています。


千葉ジェッツふなばしが
プロデュースしたこども食堂の会場
資料:株式会社千葉ジェッツふなばし

こども食堂で提供された食事
資料:株式会社千葉ジェッツふなばし
(買物困難者対策を促進)
農林水産省では、買物困難者の食品アクセスの確保に向けた対応として、移動販売車や無人型店舗の設置等の地域に応じたラストワンマイル物流の強化に向けた取組を支援しています。
また、平成23(2011)年度以降、毎年、全国の市町村を対象として食料品の購入に困難を感じている住民への対策に関するアンケート調査を実施しており、その結果については、食品アクセス(買物困難者等)問題ポータルサイトを通じて情報発信しているところです。

食品アクセス(買物困難者等)問題ポータルサイト
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html
(事例)移動販売と高齢者見守りを組み合わせて高齢者の生活を支援(鳥取県)
(1)鳥取県日野町では、高齢者の生活を守るため「ささえ愛コンビニ・プロジェクト」を開始
鳥取県日野町(ひのちょう)では、高齢化が進行する中、地域で生活する高齢者にとって移動販売が必要不可欠なものとなっています。このような中、同町では、令和4(2022)年10月から合同会社ひまわりと「ささえ愛コンビニ・プロジェクト」を開始しました。同プロジェクトでは、移動販売事業と高齢者見守り事業等を組み合わせて、買物困難者の支援や高齢者が中山間地域で安心して暮らせる環境づくりを進めています。
(2)移動販売と高齢者見守りを組み合わせて地域の高齢者を支援
同プロジェクトでは、同町を中心とした約1,200人を対象として、移動販売車3台・販売員5人の体制により、週二回の移動販売が行われています。毎日市場から仕入れる鮮度の高い魚介類等の生鮮食品や飲料、調味料、弁当、日用品等が販売されており、買物に行くことが困難な高齢者に、食料品が届けられています。
また、巡回販売時には、高齢者の見守りとして、独居の高齢者世帯の訪問を月一回行っています。その際には、困っていることがないかどうかを確認して、買物代行や電球交換等といった生活面の支援にも取り組んでいます。
(3)地域の高齢者が安心して暮らせる環境づくりを推進
同プロジェクトによって、移動販売の利用者やドライバー、見守り活動のスタッフの間に交流が生まれ、地域の高齢者が安心して暮らせるコミュニティが形成されています。同町では、今後とも、同プロジェクトを継続していくこととしており、地域の高齢者が安心して暮らせる環境づくりを推進することとしています。
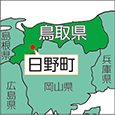

移動販売車
資料:鳥取県日野町

移動販売を利用する消費者
資料:鳥取県日野町
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883









