第1節 食品産業の健全な発展
食品産業は、農業と消費者の間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、国産農林水産物の主要な仕向先として、消費者ニーズを生産者に伝達する役割を担っています。また、多くの雇用・付加価値を生み出すとともに、環境負荷の低減等にも重要な役割を果たしています。
本節では、食品産業の動向や、JAS(*1)を始めとした規格・認証の活用等について紹介します。
*1 Japanese Agricultural Standardsの略で、日本農林規格のこと
(1)食品産業の競争力の強化
(食品産業の国内生産額は105兆8千億円)

データ(エクセル:27KB)
食品産業の国内生産額については、近年おおむね横ばい傾向で推移しており、令和5(2023)年は新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ外食支出が回復しつつあること等から、前年に比べ8.7%増加し105兆8千億円となりました(図表4-1-1)。このうち、食品製造業については、菓子類や清涼飲料の生産額が増加したこと等から、全体として4.4%増加となり、関連流通業は前年に比べ6.9%増加し38兆9千億円となりました。
(食料品製造業の労働生産性は前年度に比べ向上)

データ(エクセル:27KB)
令和5(2023)年度における食料品製造業の労働生産性は、設備投資により必要な生産体制の確保が進んだほか、新型コロナウイルス感染症からの経済回復が続いていること等から、前年度に比べ7.7%向上し7,105千円/人となっています(図表4-1-2)。
他方、食品製造業の人手不足・人材不足が引き続き課題となる中、生産性の向上が急務となっています。
このため、農林水産省では経済産業省等と連携し、生産性の向上に資するAI、ロボット等の先端技術の研究開発、実証・改良から普及までを総合的に支援することとしています。
具体的には、令和6(2024)年4月に策定したロボット等の先端技術を食品製造の現場にHACCP(*1)に基づく衛生管理に沿って導入するためのガイドラインの普及のほか、製造ラインの自動化等の省人化や生産性向上に資する機械設備等の新技術の導入を支援しています。
また、食品製造業における生産性向上等に向けた取組について、中堅・中小企業を対象としたアンケート調査やヒアリングを実施し、優良事例の横展開を進めるなど、食品産業全体の生産性向上を促進しています。
*1 Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、危害要因分析及び重要管理点のこと。我が国においては、令和3(2021)年6月から、原則全ての食品等事業者についてHACCPに沿った衛生管理が義務化されている。
(経営者の高齢化により事業承継の課題を抱える企業が多数存在)
中小企業が大半を占める食品産業では、経営者の高齢化により事業承継の課題を抱える企業が多くなっています(図表4-1-3)。
国内市場を対象としてきた食品事業者の中には、国内市場が縮小傾向にあること等を背景として、自身の世代での廃業を考え、将来に向けた生産拡大や設備の更新等の追加投資を控えるなど、撤退を視野に入れている事業者も見られています。
食料には食品製造業による加工を経て消費者に届くものが多いほか、地域の農林水産業と密接に関係し地域の食文化を反映する加工食品も多いことから、食品製造業を次世代につなげていくことが重要であり、事業の円滑な引継ぎや引継ぎ後の経営革新に向けた取組等を通じ、食品製造業の事業承継の円滑化や食品産業の体質強化を図っていく必要があります。

データ(エクセル:28KB)
(食品産業と農業の連携を推進)
持続的な食料システムの実現には、費用を考慮した価格形成だけでなく、食品産業における国産原材料の利用促進や生産性の向上等を推進し、その体質強化・事業継続を図ることによって、消費者に食品や豊かな食文化を提供するとともに、原材料調達や製造工程等において持続性に配慮した食品産業への移行を一層推進していくことが重要となっています。
このため、農林水産省では、国産原材料への切替えによる新商品開発や産地との連携強化等を支援しています。
また、持続的な食料システムの確立に向けて、地域を先導する食品企業や農林漁業者等が参画するプラットフォームを構築し、地域の多様な関係者の連携を強化し、新たなビジネスの創出等を促す取組を推進しています。
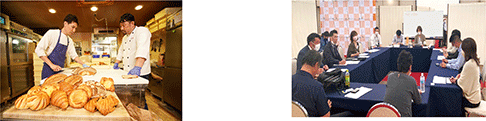
みやざき小麦粉・米粉プロジェクト
資料:公益財団法人宮崎県産業振興機構
(特定農産加工業者の経営改善と原材料の調達安定化を推進)
国際情勢の影響を受け、輸入原材料の価格水準の上昇・高止まりが生じている中、農産加工業者の経営環境は厳しさを増している状況にあります(図表4-1-4)。このため、令和6(2024)年7月に施行された特定農産加工業経営改善等臨時措置法(*1)に基づき、原材料価格の上昇が大きかったパン、製麺、菓子、大豆加工といった分野で、原材料の調達安定化に向けた取組に対する支援措置を新たに追加し、国産切替を推進しています。

データ(エクセル:31KB)
*1 正式名称は「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律」
(フードテック推進ビジョンに基づき、新市場創出のための環境整備を推進)
世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給のほか、個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活や食品産業の生産性の向上の実現が求められている中、フードテック(*1)を活用した新たなビジネスの創出への関心が世界的に高まっています。
このような中、食品企業、ベンチャー企業、研究機関、関係省庁等に所属する者で構成される「フードテック官民協議会」では、令和5(2023)年2月に「フードテック推進ビジョン」を策定し、今後のフードテックの推進に当たり、目指す姿や必要な取組等を整理し、フードテックの6分野(*2)について、具体的な課題を工程表として整理しています。
農林水産省では、これらに沿って、オープンイノベーションとスタートアップの創業を促進するとともに、新たな市場を作り出すための環境整備を進め、フードテックの積極的な推進に取り組んでいくこととしています。また、令和7(2025)年に開催される大阪・関西万博では、農林水産・食品分野で実装が期待される先端技術の展示を通じて、世界に我が国の技術力を発信していくこととしています。
*1 生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルのこと
*2 6分野は、植物由来の代替たんぱく質源、昆虫食・昆虫飼料、スマート育種のうちゲノム編集、細胞性食品、食品産業の自動化・省力化、情報技術による人の健康実現
(コラム)大阪・関西万博を食で盛り上げるプロジェクトを展開
大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、人類共通の課題解決に向け、先端技術等の世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場にすることをコンセプトに、令和7(2025)年4月から10月にかけて開催されます。
大阪商工会議所(おおさかしょうこうかいぎしょ)、公益財団法人大阪観光局(おおさかかんこうきょく)、一般社団法人大阪外食産業協会(おおさかがいしょくさんぎょうきょうかい)では、大阪・関西万博をきっかけに、食で万博を盛り上げると同時に、大阪の食の魅力を発信するプロジェクトを展開しています。
このうち、「万博メニューでおもてなし」プロジェクトでは、いのち、未来、SDGs、世界や日本の食文化といった、大阪・関西万博を表現した特別メニューを開発し、大阪府を訪れる方々へ提供・販売するよう呼び掛けており、大阪府内の飲食・食品事業者が生産者等と連携して、独自のメニュー等を考案しています。こうした万博メニューは、SNSから「#2025万博メニュー」で検索することができます。
農林水産省では、同年6月の「食と暮らしの未来ウィーク」期間中に、日本の食文化や農泊といった我が国の農林水産業や食の有する魅力のほか、スマート農業技術や、環境と調和した持続可能な食料システムの姿を発信することとしています。

メキシコ料理のトルティーヤと
たこ焼きを掛け合わせたメニュー
資料:株式会社エイチ・ツー・オー商業開発

大阪・関西万博公式キャラクター
がデザインされた菓子
資料:みどり製菓株式会社

規格外の食材とヴィーガン対応
食材による串カツ体験教室
資料:有限会社ラパン
(2)食品流通の合理化
(農林水産物・食品分野で流通合理化に取り組む事業者数は増加傾向)
農林水産物・食品を消費者に届ける役割を担う食品流通業は、売上高に占める売上原価及び経費(販売費及び一般管理費)の割合が高く、営業利益率が低い状態にあります。また、食品流通はトラック輸送に大きく依存していますが、長距離輸送が多い、手積み、手降ろし等の手荷役作業が多いといった課題があり、令和6(2024)年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限が適用され、何も対策を講じなければ物流が停滞しかねない「物流の2024年問題」の影響が懸念されています。このような中、食品の流通を確保していくためには、物流の生産性向上が不可欠です。
令和6(2024)年5月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、荷主、物流事業者等に対して、物流効率化の努力義務を課すなど新たな規制が定められることになりました。
こうした我が国の物流をめぐる情勢の中で、引き続き食品の流通を確保していくために、農林水産省では、「物流革新に向けた政策パッケージ」(令和5(2023)年6月閣議決定)に基づき、業界・分野ごとの自主行動計画の着実な実施を促すとともに、パレットの導入・標準化、ICTやロボット技術を活用した業務の省力化・自動化、コールドチェーンの整備による流通の高度化等の取組を支援しています。具体的には、青果物、花き、水産物それぞれの流通標準化ガイドラインの現場への普及、産地と卸売業者の間で出荷情報を共有するデータ連携システムの構築、物流効率化に資する卸売市場や中継共同物流拠点の整備等を行っています。

データ(エクセル:26KB)

青果物の標準仕様パレットでの出荷
また、令和5(2023)年12月に設置された農林水産大臣を本部長とする「農林水産省物流対策本部」の下に、農林水産省と民間の関係団体等で構成される「農林水産品・食品の物流に関する官民合同タスクフォース」を設置し、必要に応じメンバーの現地派遣を行い、物流の確保に不安や課題を抱える産地等に対し具体的な改善策を提案するなどの取組を行っているところです。同タスクフォースは令和6(2024)年5月、10月、令和7(2025)年3月に全体会合を開催し、各地域での物流改善の取組状況や課題について情報交換、意見交換するとともに、同年1月及び2月には、中長期的な物流の改善の方向性を見据え、食品流通のデジタル化に取り組む事業者からヒアリングを行ったところです。
このような中、農林水産物・食品等の流通合理化に取り組む事業者数(*1)については、令和6(2024)年度は前年度に比べ80件増加し296件となりました(図表4-1-5)。
他方、農林水産物・食品の物流の現場での取組も進展しており、例えば九州・四国では、熊本・愛媛のかんきつ産地が共同で標準仕様パレットに対応した新たな段ボール規格の開発に着手したところであり、また、東北・北陸では、生産者団体が鉄道事業者と連携し、青森県から北陸を経由して大阪府へ米等を輸送する貨物列車の定期運行を行っているところです。
さらに、ハム、チーズ、生麺等のチルド食品の食品製造業者が共同で、納品条件の緩和、輸配送効率化等について協議するため「チルド物流研究会」を立ち上げるなどの取組も見られています。
*1 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画又は「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づく食品等流通合理化計画の認定件数
(コラム)「ゆとり配送」による物流効率化
(1)「ゆとり配送」の概要
北海道・東北・北関東で食品スーパーを展開するアークスグループでは、物流効率化の一環として、グループ企業間の物流倉庫の共同利用や、リードタイムの延長、トラックドライバーの負担軽減等を行い、配送の最適化を目的とした「ゆとり配送」に取り組んでいます。
(2)「ゆとり配送」導入前の課題と運用方法
「ゆとり配送」を導入するまでは、日替わり特売品や酒類等の仕入れ量が大幅に変動しやすい商品については、1日に運ぶ商品が多い場合、トラックを追加で確保することにより、当日配送に応じるなど、可能な限り早く店頭へ配送していました。
この運用を改めて、トラック数の削減と荷物の平準化を目的に、原則として、前日までに輸送量を確定し、1日の商品量を明確にするとともに、店舗への到着時間にもゆとりを設け、翌日以降に販売する商品は急ぐ必要がない場合、夕方までに配送するという新たなルールを定めて運用しています。

物流センターの様子
資料:株式会社アークス
また、トラックドライバーの作業負担を減らすことを目的に、トラックドライバーが店舗のバックヤードまで入り、納品作業をこなす場合もあったところ、商品の搬入作業を搬入口での受渡しに限定することで店舗での荷下ろし作業を30分以内に短縮しています。このほか、車両の一部を大型化することや、札幌市内の配送についても高速道路の利用を認めること等を通じて、運転時間の短縮・ドライバー不足への対応を行っています。
(3)取組の効果と今後の展開
「ゆとり配送」の取組によって、1日12時間ほどだったトラックドライバーの労働時間が、10時間程度に短縮される効果が出ています。今後、このような取組をまだ実施していないグループ企業にも展開していくこととしています。
(卸売市場の物流機能を強化)
卸売市場は、野菜、果物、魚、肉、花き等日々の食卓に欠かすことのできない生鮮食料品等を、国民に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラであり、多種・大量の物品の効率的・継続的な集分荷、公正で透明性の高い価格形成等の重要な機能を担っています。
食料安全保障の強化が求められる中、持続的に生鮮食料品等の安定供給を確保していくため、単に老朽化に伴う施設の更新のみならず、物流施策全体の方向性と調和し、標準化・デジタル化に対応した卸売市場の物流機能を強化することが必要となっています。
農林水産省では、物流機能を強化するために、コールドチェーンの確保等に資する施設や、中継共同物流に必要な施設の整備等を支援することとしています。
(3)規格・認証の活用
(JAS普及推進月間に新たな取組を展開)
近年、輸出の拡大や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林水産省では、JAS法(*1)に基づき、農林水産物・食品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱方法、生産方法、試験方法等について認証する新たなJAS制度を推進しています。令和6(2024)年度は新たに食品成分に関する試験方法のJASを2規格制定したほか、規格の更なる活用を視野に、既存のJASの見直しを行いました。また、令和6(2024)年11月のJAS普及推進月間を中心に、JASの認知を高めるため、イベントへの出展等の周知活動を行いました。事業者や産地の創意工夫により生み出された多様な価値・特色が戦略的に活用され、我が国の食品・農林水産分野の競争力の強化につながることが期待されています。
さらに、米国、カナダ、EU等既に同等性を相互承認している国・地域に対しては、この仕組みを活用し、茶やしょうゆ等の有機食品の輸出が行われています。
このほか、農林水産省では、輸出促進に向け海外との取引を円滑に進めるための環境整備として、産官学の連携により、ISO(*2)規格等の国際規格の制定・活用を進めています。

NIPPON FOOD SHIFT FES.出展時の様子
*1 正式名称は「日本農林規格等に関する法律」
*2 International Organization for Standardizationの略で、国際標準化機構のこと
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




