第1節 農産物輸出の概況
輸出の促進については、国内の農業生産基盤や食品産業の事業基盤等の食料供給能力を確保するために不可欠なものです。そのため、新たな基本計画では、「海外から稼ぐ力」の強化として輸出の拡大を位置付けるとともに、令和12(2030)年を目標年とする農林水産物・食品の輸出額の目標を設定しました。
本節では、我が国の輸出額の動向、主な輸出重点品目の取組状況について紹介します。
(1)農林水産物・食品の輸出額
(農林水産物・食品の輸出額が1兆5,071億円に拡大し、初の1.5兆円超え)

データ(エクセル:27KB)
令和6(2024)年の農林水産物・食品の輸出額は、前年に比べ3.6%増加し、初の1.5兆円超えとなる1兆5,071億円となりました(図表3-1-1)。中国等による日本水産物の輸入規制が継続しているため、中国等向け輸出が前年に引き続き減少したものの、日本食レストランの増加やインバウンドによる日本食人気の高まり等を背景とした、外食需要が好調だったほか、事業者の販路拡大の取組等の進展により、その他の国・地域向けの輸出が大きく増加したことが背景として挙げられます。
(品目別の輸出額では加工食品が最多)

データ(エクセル:28KB)
令和6(2024)年の農林水産物・食品の品目別の輸出額では、加工食品が最多で5,340億円となりました(図表3-1-2)。
加工食品の品目別の輸出額では、主に、ソース混合調味料や清涼飲料水、菓子で大きく増加しました。
(コラム)JASの有機酒類追加により、酒類の更なる輸出拡大を推進
近年、米国・EU等の海外市場においては、有機食品の人気が高く、野菜、果実等の生鮮食品に加えて、加工食品でも有機製品が高値で販売されるなど、その市場が拡大しています。このような背景を踏まえ、令和4(2022)年10月に改正JAS法(*1)が施行され、有機加工食品のJASの対象に有機酒類が追加されました。令和7(2025)年2月時点で、国内では約60件の事業者が有機酒類の有機JAS認証を取得しており、今後も認証取得に取り組む事業者が増えていくことが予想されます。
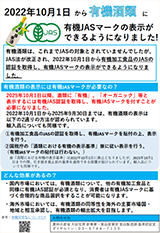
有機酒類が追加されたことを
周知するチラシ
多くの国・地域では、「有機」の名称表示を規制しており、有機農産物等を輸出する場合、我が国の農業者は、その国・地域の有機認証を受けなければ「有機」と表示できません。一方、我が国の有機の認証体制等について「同等性」が認められると、我が国で有機JAS認証を取得することで、輸出先国の有機認証を別途取得せずに有機表示を付して輸出することが可能となります。農産物及び農産物加工品については、これまで米国、カナダ、EU等と有機同等性の相互承認を行っており、有機酒類についても令和5(2023)年8月にカナダ、令和6(2024)年1月に台湾と相互承認を行い、有機表示を付した酒類を輸出できるようになりました。
我が国のアルコール飲料の輸出額は、令和3(2021)年に大きく伸び、初めて1千億円を超えるなど飛躍的に拡大する一方、直近3年間は横ばい状態が続いており、海外市場に訴求力のある有機酒類による更なる輸出の拡大が期待されています。農林水産省では、財務省と連携しながら、海外の主要市場国・地域との間で有機酒類の同等性の相互承認に取り組み、有機酒類を含む酒類の輸出拡大を図ることとしています。また、我が国の「伝統的酒造り」について、令和6(2024)年12月にユネスコ(*2)無形文化遺産に登録されたことも今後の追い風になっていくことが期待されます。
*1 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出に関する法律等の一部を改正する法律」
*2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationの略で、国際連合教育科学文化機関のこと
(国・地域別の輸出額では米国向けが最多)

データ(エクセル:26KB)
令和6(2024)年の農林水産物・食品の国・地域別では、米国向けが最も多く、次いで香港、台湾、中国、韓国の順となっています(図表3-1-3)。
また、輸出品目を各国・地域別に見ると、米国ではホタテ貝や牛肉、日本酒の輸出額が、第3位となった台湾ではりんごやホタテ貝、牛肉の輸出額が前年に比べ増加しています。
(2)主な輸出重点品目の取組状況
(コメ・コメ加工品の輸出額は前年に比べ増加)

データ(エクセル:29KB)
商業用のコメの輸出額は、日本食レストランやおにぎり店等の需要開拓により、近年増加傾向にあります。令和6(2024)年は、前年に比べ27.8%増加し120億3千万円となりました(図表3-1-4)。また、パックご飯や米粉・米粉製品を含めた輸出額は、前年に比べ29.4%増加し135億7千万円となりました。
主食用米の国内需要が減少する中で、輸出拡大によって新たな需要を生み出していくことは、食料自給力の強化を図る上でも重要です。農林水産省では、農地の集積・集約化による分散錯圃(さくほ)の解消や農地の大区画化、スマート技術の活用や品種改良、多収量品種の作付け拡大等により低コストで生産できる輸出産地を育成していくとともに、日本食のプロモーションや商流構築、国内外一貫してつなぐサプライチェーンのモデル構築、日系外食企業の海外進出、インバウンドと輸出の好循環の形成等の海外における需要拡大を進めていくこととしています。
(牛肉の輸出額は前年に比べ増加)

データ(エクセル:27KB)
牛肉の輸出額は、我が国が誇る和牛肉の品質の高さやおいしさが世界中で認められていることを背景として、近年増加傾向で推移しています。令和6(2024)年は、米国、台湾におけるレストラン等への販路拡大により、前年に比べ12.1%増加し648億円となりました(図表3-1-5)。
農林水産省では、畜産農家、食肉処理施設、輸出事業者等が連携して産地主導で取り組む新たな商流構築等を支援するとともに、輸出認定食肉処理施設の増加に向けた施設整備を支援しています。
(事例)和牛の更なる輸出拡大に向けた食肉処理・加工技術を普及(群馬県)
(1)和牛の輸出拡大には調理方法やカット技術の普及が課題

近年、我が国の牛肉輸出が増加しています。今後更に輸出を増やすためには、欧米で特に人気のあるステーキに適したロインに加え、他の部位もバランス良く輸出していくことが必要です。また、国内の加工場で和牛等の良さを引き出すスライスやカットをして輸出していますが、輸出先国・地域でカットできる人材を育成し、現地のニーズに合った調理方法により市場を拡大することも課題です。
このような状況を踏まえ、群馬県玉村町(たまむらまち)の公益社団法人全国食肉学校(ぜんこくしょくにくがっこう)では、海外における和食文化と日本式食肉処理・加工技術の普及に取り組んでいます。
(2)海外シェフ等を対象としたセミナーの開催により、多様な部位の需要拡大を推進

セミナーでのカット
技術の実演の様子
資料:公益社団法人全国食肉学校
同法人が食肉処理・加工技術の普及のために行っている取組の一つが、海外のシェフや卸売・精肉加工従事者等を対象とするセミナーです。令和6(2024)年度に国内で行ったセミナーでは、24か国・地域252人に対し、和牛の特性等の説明や講師によるカット技術の実演を行いました。また、参加国・地域に応じてメニューを変えた和牛の調理実演も併せて行い、現地での新メニュー開発のきっかけづくりにつながっています。このほかにも、海外の食肉学校への講師派遣等も行っており、これらの取組を通じて和牛の多様な部位の需要拡大に貢献しています。
(牛乳乳製品の輸出額は前年に比べ減少)

データ(エクセル:27KB)
牛乳乳製品の輸出額は、令和4(2022)年まで増加してきており、令和4(2022)年以降は300億円以上で推移しています。直近ではアジア向けの脱脂粉乳の輸出が減少しており、令和6(2024)年は、前年に比べ0.8%減少し305億円となりました(図表3-1-6)。
農林水産省では、更なる牛乳乳製品全般の輸出拡大に向けて、オールジャパンでのプロモーション、市場等の調査・分析を行うとともに、指定団体、産地の地方公共団体、乳業者等が一体となった更なる取組や新たな商流の構築を図ることとしています。
このような取組を通じて、今後、牛乳乳製品の中でも、国産生乳の使用割合の高い、ロングライフ牛乳やチルド牛乳について、アジアを中心に輸出を推進していくこととしています。
(緑茶の輸出額は前年に比べ増加)

データ(エクセル:28KB)
緑茶の輸出額は、健康志向や日本食への関心の高まり等を背景に、抹茶を含む粉末茶の需要が拡大し、近年増加傾向で推移しています。令和6(2024)年は、前年に比べ24.6%増加し364億円となり、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(以下「実行戦略」という。)で設定した、令和7(2025)年の茶の輸出額目標312億円を達成しました(図表3-1-7)。
また、有機栽培茶は海外でのニーズも高く、有機同等性の仕組みを利用した輸出量は増加傾向にあります。令和5(2023)年は前年に比べ18.1%増加し過去最高の1,585tとなりました。特にEUや米国が大きな割合を占めています。
農林水産省では、輸出拡大に向けた環境整備のため、相手国・地域の残留農薬基準をクリアする防除体系の確立に向けて、主要産地での現地実証を通じた防除体系の確立等を推進しています。
(果実の輸出額は前年に比べ増加)

データ(エクセル:31KB)
果実の輸出額は、我が国の高品質な果実が諸外国・地域で評価され、りんご、ぶどうを中心に近年増加傾向で推移しています。令和6(2024)年は、夏季の高温の影響等により収量が減少した品目が多かったものの食味に対する継続的な引合いがあるなど、特にりんごの輸出が堅調だったこと等から、前年に比べ14.8%増加し333億円となりました(図表3-1-8)。
農林水産省では、りんご等の果樹について、防除暦の見直し等の規制やニーズに対応する産地育成の推進とともに、プロモーション等による更なる海外需要開拓を図っていくこととしています。
(ホタテ貝の輸出額は、輸出先の転換・多角化の推進により、前年に比べ増加)
ホタテ貝等については、中国等による輸入規制の影響を受ける中、輸出先の転換・多角化が進んだことにより、米国、タイ、ベトナム等の中国以外の国・地域に対する輸出が大きく増加し、令和6(2024)年のホタテ貝(生鮮等)の輸出額は、前年に比べ0.9%増加の695億円となりました。
農林水産省では、JETRO、日本食品海外(にほんしょくひんかいがい)プロモーションセンター(以下「JFOODO(ジェイフードー)」という。)、認定農林水産物・食品輸出促進団体(以下「認定品目団体」という。)が連携して行う、海外バイヤーの国内産地への招聘(しょうへい)、ホタテ貝の加工業者等の海外派遣、非日系のスーパー・レストランや地方都市等でのプロモーションや商流構築等を通じた、輸出先の転換・多角化を支援しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




