第2節 輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化
人口減少や高齢化により農林水産物・食品の国内消費の減少が見込まれる中、農業の生産基盤を維持していくには、これまでの国内市場のみに依存する農林水産業・食品産業の構造から、成長する海外市場で稼ぐ方向に転換することが不可欠です。そのため、政府は令和2(2020)年11月に実行戦略を策定し、その後も改訂を行い、取組を進めてきました。
本節では、実行戦略に基づく施策や取組のほか、輸出拡大とともに、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費の拡大を図ることによる「海外から稼ぐ力」の強化に向けた取組を紹介します。
(1)実行戦略の基本的な考え方
(マーケットインの発想で輸出拡大を推進)

データ(エクセル:27KB)
我が国の農林水産物・食品の輸出拡大については、海外市場が要求する量や価格、品質、規格等のスペックで継続的に提供することが必要であること、輸出先国・地域の衛生検疫規制や規格基準に合わない産品は輸出ができないなどの課題があります。
また、令和元(2019)年の我が国の農林水産物・食品の輸出割合は2%となっており、他国と比較しても低い水準です(図表3-2-1)。一方、我が国の農林水産物・食品には潜在的なニーズがあり、輸出割合増加のポテンシャルは比較的高いことから、輸出拡大に向けた取組が重要となっています。
このような中、我が国の農林水産物・食品の輸出を拡大させるためには、生産から現地販売までのバリューチェーン全体を、「プロダクトアウト」から「マーケットイン」に転換する必要があります。
実行戦略では、我が国の強みを最大限に発揮すること、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しすること、省庁の垣根を超え政府一体として輸出の障害を克服することを基本的な考え方としています。
(2)我が国の強みを最大限に発揮するための取組
(輸出重点品目と輸出目標を設定)
今後の輸出拡大に向け、海外で評価される我が国の強みがある品目を中心に輸出を加速させ、その波及効果として、全体の輸出を伸ばすことが重要です。そのため、海外で評価される我が国の強みがあり、輸出拡大の余地が大きく、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的な品目として、29品目を輸出重点品目に選定しています(図表3-2-2)。
また、輸出重点品目以外についても、輸出目標とその実行のための課題と対策を明確化する産地・事業者には引き続き適切な支援を行っていくこととしています。

(輸出重点品目に係るターゲット国・地域、輸出目標、手段を明確化)
輸出重点品目ごとに、海外の市場動向や輸出環境等を踏まえ、輸出拡大を重点的に目指す主なターゲット国・地域ごとの輸出目標を設定し、現地での販売を伸ばすための課題とその克服のための取組を明確化しています(図表3-2-3)。
なお、輸出目標の設定に当たっては、市場のニーズを踏まえつつ、今後の輸出増のポテンシャルが高い国・地域についても、新たなターゲット国・地域として位置付け、輸出先国・地域の多角化を図っていくこととしています。

(認定品目団体によるオールジャパンでの輸出力強化の取組を推進)
輸出促進法(*1)に基づき、輸出重点品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請により、認定品目団体として認定しており、令和7(2025)年3月末時点では、合計15団体(27品目)となっています(図表3-2-4)。認定品目団体は、市場調査やジャパンブランドによる共同プロモーションといった個々の産地・事業者では取り組み難い非競争分野の輸出促進活動を行い、業界全体での輸出拡大に取り組んでいます。
また、ほかの認定品目団体やJETRO、JFOODO等と連携し、輸出先国・地域におけるマーケティングやプロモーション活動等を行っています。
くわえて、輸出量の増加に伴い拡大する輸送リスク等への対応や、将来的に自己財源を増加させ、国では行えない細かな業界支援を行うことも期待されています。

*1 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」
(JETRO・JFOODOによる海外での販路開拓支援を実施)
JETROでは、セミナーやウェブサイト等を通じた輸出関連制度やマーケット情報の提供、相談対応等の輸出事業者等へのサポートを行っています。また、海外見本市への出展支援、国内外での商談会の開催、サンプル展示ショールームの設置等によるビジネスマッチング支援等により、輸出に取り組む国内事業者への総合的な支援を実施しています。
また、JFOODOでは、「日本産が欲しい」という現地の需要を作り出すため、現地での消費者向けプロモーション等を戦略的に実施しています。具体的には、SNS、デジタル広告等による情報発信、小売・外食店等と連携したPRイベントの開催といった活動を認定品目団体等とも連携しながら行っています。
今後は、認定品目団体、JETRO、JFOODOが連携を強化し、海外の関係機関とも協力しながら、海外の主要都市や日本食レストラン、日系スーパー等の日系市場の拡大だけではなく、特に未開拓の有望エリアや非日系市場等の新市場の開拓に重点を置いた取組を一体的に実施していくこととしています。
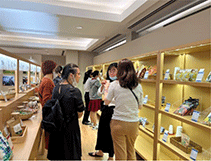
食品サンプルショールーム
資料:独立行政法人日本貿易振興機構

米国の有力メディアを活用した
ホタテのCM画像
資料:日本食品海外プロモーションセンター
(海外の日本食レストラン等と連携したプロモーションを実施)

令和5(2023)年の海外における日本食レストラン数(概数)は、特にアジアでの伸びが大きかったことにより、令和3(2021)年の15万9千店から約2割増加し18万7千店となりました(図表3-2-5)。
また、日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を⺠間団体等が主体となって認定する「日本産食材サポーター店」は、令和7(2025)年3月末時点で約6千店が認定されています。JFOODOでは、世界各地の日本産食材サポーター店等と連携して、日本産食材等の魅力を訴求するプロモーションを実施しています。
さらに、農林水産省では、日本料理の調理技能試験制度の普及、外国人を対象とした日本食料理人育成のための招聘(しょうへい)研修や日本料理コンテストの実施、海外料理学校等での日本食講座開設等を通じた外国人料理人の育成等により、海外における日本食・食文化発信の担い手を育成するとともに、日本食・食文化の魅力を外国人目線に立って紹介した映像・記事の制作・発信等を通じ、日本食・食文化の普及を図ることで、農林水産物・食品の輸出拡大を推進しています。
(輸出先国・地域における専門的・継続的な支援体制を強化)

主要な輸出先国・地域において、農林水産物・食品の輸出を行う事業者を包括的・専門的・継続的に支援するため、在外公館、JETRO海外事務所、JFOODO海外駐在員を主な構成員とし、現地発の情報提供や新たな商流の開拓支援等を行う輸出支援プラットフォームを設置しています。
令和6(2024)年度は、新たにマレーシア(クアラルンプール)、アラブ首長国連邦(ドバイ)において輸出支援プラットフォームの拠点を設立し、設置国・地域は合計で10か国・地域となっています(*1)(図表3-2-6)。
また、同プラットフォームでは、現地展開している食品事業者や日本食レストラン等のネットワークを構築するとともに、輸出を目指す事業者に必要な情報の提供やオールジャパンでのプロモーション戦略の立案等を協力して行っています。
さらに、現地商流に入り込んでいくため、日系市場への過度の偏重や既存の商流の奪い合いを避け、日系以外の商流への新規のアプローチを強化することに留意しながら取り組むこととしています。
*1 ( )内は事務局設置都市
(3)マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押し
(リスクを取って輸出に取り組む事業者への投資を支援)
「プロダクトアウト」から「マーケットイン」に発想を転換するには、リスクを取って輸出向け産品の生産・輸出にチャレンジする事業者が不可欠です。
そのため、農林水産省では、輸出向けの生産を行う輸出産地の育成・展開や、自らリスクを取り、輸出先国・地域の規制やニーズに対応したマーケットイン輸出に取り組む産地・事業者等に対し、重点的な支援・環境整備を行うこととしています。
また、輸出先国・地域の規制に対応した施設整備等の投資を行ってから収益化するまでに一定期間を有することから、輸出促進法に基づく公庫の融資(農林水産物・食品輸出基盤強化資金(*1))や税制特例(輸出事業用資産の割増償却)の積極的な活用により、輸出に取り組む事業者を強力に後押しすることとしています。
さらに、投資円滑化法(*2)に基づき、輸出に取り組む事業者に投資する民間の投資主体への資金供給の促進に取り組むこととしています。
*1 沖縄振興開発金融公庫でも貸付が行われている。
*2 第2章第9節を参照
(マーケットインの発想に基づく輸出産地・事業者の育成・展開を推進)
輸出先国・地域のニーズや規制に対応した産品を、求められるスペックで継続的に提供し、農林水産事業者の利益につなげるため、輸出促進法に基づく輸出事業計画を踏まえた輸出産地の形成に必要な施設整備等を重点的に支援することとしています。また、水田を転換した園地や畑地を活用し、果樹や野菜等高収益作物の輸出産地の育成・展開を図ることも必要です。
畜産物については、生産者、食肉処理施設等の、輸出事業者等が連携して生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る体制(コンソーシアム)の育成・設立等を進めるとともに、コンソーシアムが取り組む産地の特色を活かした商流の構築や拡大、ブランディング、輸出促進等を支援することとしています。
また、輸出産地・事業者をサポートするため、専門的な知見を持つ外部人材を「輸出産地サポーター」として地方農政局等に配置し、マーケットイン輸出に向けた産地の育成を支援することとしています。
さらに、輸出産地・事業者の育成や支援を行う農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP(*1))は、令和7(2025)年2月時点で会員数が10,184となっていますが、輸出の熟度・規模が多様化しており、輸出事業者のレベルに応じたサポートを行う必要があります。また、新たに輸出に取り組む輸出スタートアップを増やしていく必要があり、地方農政局等や都道府県段階で、現場に密着したサポート体制の強化に取り組んでいます。くわえて、輸出産地の形成に向け、GFPを活用した輸出産地向けのセミナーや交流会の開催等の取組を一層進めていくこととしています。

GFPの海外イベントに出展した米のブース
資料:株式会社百笑市場

GFPビジネスパートナーを活用し、
英語版プロモーションツールを作成
資料:村商株式会社
一方、農協系統は取扱量が多いものの、継続的かつ安定的な出荷の困難さや輸出に向けた物流に十分対応できないなどのマーケットインの輸出に対する課題が多く、輸出産地の課題解決に向け、農協系統と国の連携が重要となっています。
このような中、農林水産省では、今後の更なる輸出拡大に向けた取組を加速化するため、令和6(2024)年1月に、JAグループと「輸出関係連絡協議会」を設立し、輸出産地の形成を後押しする支援、フラッグシップ輸出産地の認定・公表や輸出人材の育成・確保等に関する国の取組について紹介しました。また、同協議会の下に、ワーキンググループを設置し、農協を核とした輸出産地の形成、効率的な輸出物流の構築、輸出人材の育成等の具体的な課題について協議を進めています。
また、農林水産省では、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系への転換を通じた輸出産地の形成を促進するため、令和6(2024)年6月から、JAグループ、JETRO、一般社団法人日本青果物輸出促進協議会(にほんせいかぶつゆしゅつそくしんきょうぎかい)と連携し、「園芸作物の輸出産地形成支援に係る全国キャラバン」を開催しました。同キャラバンでは、輸出拡大に向けた施策や支援策等の周知に加え、輸出に取り組む事業者や海外市場ニーズの紹介、輸出に向けた相談会を行いました。
さらに、輸出産地の形成支援に向けた取組と海外販路の開拓・拡大に向けた取組を有機的に連携させ、日本産農畜産物輸出の一層の拡大を図ることを目的として、JA全農、JETRO及びJFOODOの3者で「日本産農畜産物の輸出促進に向けた連携協定」を締結し、同年7月に調印式を開催しました。同協定により、輸出産地の形成や輸出の実現に向けた総合的なサポートや海外市場での販売力の向上、産地が有する魅力を最大限に活かした農畜産物の価値訴求力・ブランド力の向上等といった効果が期待されています。
*1 Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food Manufactures Projectの略
(コラム)輸出拡大に向け、多様な人材の参画を促進
日本食の需要が高まり、海外への輸出事業者が増える中、海外展開に向けた多様な業務に対応できる人材の不足が大きな課題となっており、このような課題の解決には、ITやマーケティング、デザイン等の多様な領域の知見や異なる視点を持った人々との共創が不可欠となっています。
このような状況の中、多様な業種の力を結集し、我が国の食を世界に広めることを目的に、GFPと内閣府プロフェッショナル人材事業との連携の下、輸出に取り組む事業者の経営課題の解決に向けた人材マッチング等を進めており、海外販路開拓人材や規制対応に係る書類作成を担う人材等のマッチングが実現しています。
例えば静岡県掛川市(かけがわし)の有限会社栄醤油醸造(さかえしょうゆじょうぞう)は、主に欧州と北米をターゲットとしており、課題となっていたマーケティングの知見を有する人材を確保することができました。また、鹿児島県指宿市(いぶすきし)の株式会社大吉農園(だいきちのうえん)は、キャベツに加えてかぼちゃを新たな輸出品目として更なる輸出拡大を図るため、貿易知見を有し、大ロットな販路開拓を担える人材とマッチングすることができました。
また、このような取組を一層推進するため、令和6(2024)年3月に「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクトを立ち上げたところであり、これらの取組を通じて我が国の食の輸出拡大に向けた多様な人材の参画促進、裾野拡大に取り組んでいくこととしています。

昔ながらの「木桶仕込み」にこだわった醤油造り
資料:有限会社栄醤油醸造

既存輸出品目のキャベツの圃場
資料:株式会社大吉農園
(輸出人材の育成・確保を推進)
輸出に取り組む事業者にとって、輸出先国・地域のニーズや検疫条件等の規制に精通し、輸出向けの生産や販路開拓等の関連業務に対応できる人材の不足が大きな課題となっています。
一方、現状は輸出先国・地域のニーズや規制、輸出実務等のノウハウを効率的かつ体系的に体得する学習環境が乏しいことから、教育機関と連携した輸出人材の育成の展開やGFPの支援の下で輸出実務経験者等の専門人材と輸出事業者のマッチングを進め、輸出事業者のニーズに合った輸出人材の確保を推進することとしています。
(生産から流通・販売に至る関係者が一体となったサプライチェーンの強化を推進)
輸出の促進に当たっては、生産から流通・販売に至る関係者が一体となったサプライチェーンを強化して取り組むことが不可欠です。
そのため、農林水産省では、国内の生産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等で構成されるコンソーシアムが行う、生産から現地販売までの一気通貫した新たなサプライチェーンモデルの構築に向けた取組を支援することとしています。
(大ロット・高品質・効率的な輸出等に対応可能な輸出物流の構築を推進)
輸出を拡大するためには、大ロットで経済的な輸出を実践するなど、輸出に向けた効率的な物流の構築が重要です。
そのため、農林水産省では、基幹的な輸出物流ルートにおける国内各地からの最適輸送ルートの構築や集荷・保管体制の構築に向けた取組を支援するとともに、地方港湾・空港等を活用した輸出物流の構築に向けた調査・実証等を支援することとしています。
(4)省庁の垣根を超え政府一体として輸出の障害を克服
(政府一体での戦略的な協議の実施)
マーケットイン輸出への転換に向け、海外現地での情報収集や売込み、輸入規制等に関する政府間協議、食品安全管理、知的財産管理、流通・物流整備、研究開発等の様々な関連分野において、政府による環境整備が不可欠です。
農林水産省では、輸出重点品目を中心に、規制導入に関する情報を現地で早期に収集し、国内に提供する体制を整えるとともに、輸出の障害となる輸出先国・地域の規制の撤廃・緩和に向け、農林水産物・食品輸出本部の下で政府一体となり、実行計画(*1)を策定し、戦略的に協議を行っています。
*1 正式名称は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画」(輸出促進法に基づき策定)
(東京電力福島第一原子力発電所の事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う輸入規制の撤廃を働き掛け)
東京電力福島第一(とうきょうでんりょくふくしまだいいち)原子力発電所の事故に伴い、55か国・地域において、日本産農林水産物・食品の輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求、検査の強化といった輸入規制措置が講じられてきました。これらの国・地域に対し、政府一体となってあらゆる機会を捉えて規制の撤廃に向けた粘り強い働き掛けを行ってきた結果、令和6(2024)年度においては、輸入規制措置が仏領ポリネシアで撤廃、台湾で緩和され、規制を維持する国・地域は6まで減少しました。
また、東京電力(とうきょうでんりょく)ホールディングス株式会社では、多核種除去設備(ALPS(アルプス)(*1))等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準を確実に下回るまで浄化処理した水(以下「ALPS処理水」という。)を、トリチウムについても1,500Bq/L未満になるまで海水で大幅に希釈した上で、令和5(2023)年8月から海洋への放出を開始しました。
これに伴い、従来の原発事故に伴う輸入規制に加えて、中国、香港、マカオ及びロシアは日本産水産物等の輸入停止を行いました。しかし、ALPS処理水の海洋放出については、IAEA(*2)(国際原子力機関)の包括報告書に明記されているとおり、人及び環境に与える放射線影響は無視できるほどであり、我が国としては、こうした点や水産物等の放射性物質検査結果を国内外に向け、透明性高く発信してきました。中国との間では、令和6(2024)年9月に、ALPS処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入規制について日中間の「共有された認識」を発表し、中国は、IAEAの枠組みの下での追加的なモニタリングを実施後、日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手し、日本産水産物の輸入を着実に回復させることになりました。令和7(2025)年3月の日中ハイレベル経済対話でこの認識が着実に履行されていることを両者が評価し、モニタリング結果に異常がないことを前提に、輸入再開に向けて関連の協議を推進することで一致しました。
引き続き、日本産農林水産物・食品の輸入規制を維持している国・地域に対して、規制の撤廃が早期に実施されるよう働き掛けを行っていきます。
*1 Advanced Liquid Processing Systemの略
*2 International Atomic Energy Agencyの略
(動植物検疫協議を引き続き推進)
動植物検疫協議については、農林水産業・食品産業の持続的な発展に寄与する可能性が高い輸出先国・地域や品目から優先的に協議を進めています。令和6(2024)年度は、フィリピン向けいちご、タイ向けゆず及びきんかんの輸出が解禁されました。鳥インフルエンザについては、令和6(2024)年シーズンは令和7(2025)年3月末時点で14道県51事例が確認されています。これらの道県については、道県単位で輸出を停止しており、防疫措置完了から28日が経過した時点で、輸出再開に向けた検疫協議を実施しています。
(輸出加速を支える政府一体としての体制整備を推進)
農林水産省では、電子媒体で輸出証明書の発行が可能となるよう、輸出先国・地域へ働き掛けています。また、手数料のオンライン納付機能を整備し、令和6(2024)年10月から一部の国による施設認定の手数料について、オンライン納付を開始しています。
さらに、植物検疫における輸出検査について、令和5(2023)年4月に施行された改正植物防疫法(*1)に基づき、同年同月から、第三者機関による輸出検査が可能となったことから、第三者機関の登録及び検査を実施しています。
*1 正式名称は「植物防疫法の一部を改正する法律」
(輸出先国・地域の規制やニーズに対応した加工食品等への支援を推進)
輸出先国・地域の規制に対応するためのHACCP対応施設等の整備目標達成に向け、計画的な施設整備に対する支援を行うとともに、厚生労働省と連携し、輸出促進法に基づく適合施設の認定を迅速に行うこととしています。
また、単独では輸出先の発掘や大ロットの輸出、海外小売店の売場の確保等を行うことが困難である、地域の中小食品製造事業者等については、関係者が連携して取り組む海外市場調査や販路開拓、輸出用商品開発等の支援が重要です。
(5)食品産業の海外展開とインバウンドによる食関連消費の拡大
(輸出の後押しにもつながる事業者の海外展開を支援)
我が国の食品事業者の海外事業展開は、日本産原材料を用いた現地加工、日本食の普及、食文化の理解促進等を通じた農林水産物・食品の輸出との相乗効果を含む、食産業の持続的発展に寄与することが期待されます。
農林水産省では、食品製造業等の海外展開に向けた環境整備を図るため、官民間及び企業間の情報交換の場である「グローバル・フードバリューチェーン(GFVC)推進官民協議会」の下でのセミナーの開催等を通じた事業者への情報提供や海外展開の際の実務的な留意事項等をまとめたガイドラインの策定・普及に加え、海外現地での物流・商流構築に係る設備投資等を行う場合の案件形成支援等に取り組んでいます。
食品産業の海外展開による収益額が近年拡大傾向にある中、今後は、現地におけるサポート体制の充実や、海外拠点の設置に対する制度融資の活用の推進等により、更なる海外展開の推進を図ることとしています。

食品産業の海外展開の促進に関する検討会
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/kaigai_tenkai.html
(訪日外国人旅行者に日本食の理解・普及を推進)

データ(エクセル:28KB)
日本政府観光局(にほんせいふかんこうきょく)(*1)(JNTO)の調査によると、令和6(2024)年の訪日外客数は、前年から増加し3,687万人にまで拡大しています(図表3-2-7)。
また、インバウンドによる食関連消費額も増加傾向にあり、今後も増加が見込まれます(図表3-2-8)。インバウンドによる食関連消費は、我が国の食に対する海外からの需要という点で、輸出と同様に農林水産業・食品産業の収益確保に資するという考えの下、その拡大に向けて取り組むこととしています。
農林水産省を始めとする関係省庁は、海外の消費者に対して我が国の食品の調理方法、食べ方、食体験等を通じた地域の文化とのつながりの発信等を行うとともに、訪日外国人旅行者の更なる増加と農林水産物・食品の輸出増大につながるといった好循環を構築するため、訪日外国人旅行者を日本の食・食文化の「本場」である農山漁村に呼び込む取組を推進しています。農林水産省は、地域の食や食文化等によりインバウンド誘致を図る地域を「SAVOR JAPAN(セイバージャパン)」に認定することで、オールジャパンのブランドとして、海外への一元的な情報発信を推進しています。令和6(2024)年度は新たに2地域(*2)を認定し、認定地域は令和6(2024)年12月時点で43地域となりました。
さらに、JFOODOでは、JNTO等と連携し、インバウンドによる消費額も多く人気も高い食品をターゲットとしたSNS等を活用した情報発信や、訪日外客数の多い地域におけるプロモーション活動に取り組んでいます。

データ(エクセル:29KB)
*1 正式名称は「独立行政法人国際観光振興機構」
*2 令和6(2024)年度に認定された地域は、長野県松川町(五平餅)、山梨県みのぶ農泊地域(あけぼの大豆)の2地域。( )内は、その地域の食
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




