第9節 農林水産・食品分野を支える技術の開発・推進
高齢化や労働力不足等の我が国の農業現場が直面している課題の解決に向けて、イノベーションを創出していくことが重要です。
本節では、産学官連携による研究開発の動向、農業施策の展開におけるデジタル変革に向けた取組等について紹介します。
(1)イノベーションの創出・技術開発の推進
(農林水産・食品分野における技術の開発を推進)
農林水産省では、食料安全保障の強化やみどり戦略の実現に向け、スマート農業技術にも対応した品種開発の加速化や、農林漁業者のニーズを踏まえた現場では解決が困難な技術的問題に対する研究開発を推進しています。
最近の研究の例では、水田輪作の高収益化に向け、茎葉等の残さも有機物として活用可能な子実用とうもろこしをブロックローテーションに組み込み、生産性向上と地力維持を両立できる技術や、ブリ類の輸出拡大に向け、冷凍ブリの血合筋が褐変するのを防止するため、解凍後の色調保持時間を延長する技術等を開発しました(図表2-9-1)。

(スタートアップの取組を支援)
我が国における経済成長を実現するため、牽引(けんいん)役として新しい技術やアイデアを有するスタートアップに大きな期待が寄せられています。農林水産業・食品産業の現場は、担い手不足の解消や環境と調和した食料生産への転換等の様々な課題を抱えており、これらの課題を乗り越えるためには、スマート農業技術や、廃棄物から資源を生み出すアップサイクル技術等の先端技術を速やかに社会実装させる必要があります。
スタートアップは、このような先端技術を有し、それを起点に新たなビジネスを起こす潜在力を持っており、農林水産・食品分野の発展にはスタートアップの存在は不可欠となっています。
しかしながら、スタートアップの成長過程には、いわゆる「死の谷(*1)」等の幾つもの壁があり、どんなに優れた技術を有していても、社会に成果を還元できないスタートアップも多数存在します。
また、農林水産・食品分野では、IT系等の分野に比べて、研究開発後、サービスを展開して、利益を回収するまでに相対的に長い期間を要するケースが多いため、成長資金の流入が少ない状況にあります。
このため、SBIR(*2)制度に基づき、農林水産・食品分野において新たな技術・サービスの事業化を目指すスタートアップ・中小企業等が行う研究開発等を発想段階から事業化準備段階まで切れ目なく支援しています。
また、スタートアップによる先端技術の社会実装を促進するため、事業化に向けて実際の使用環境下において大規模に実証する取組に対する支援を行っています。
このほか、投資円滑化法(*3)に基づき、スマート農業技術やフードテックのスタートアップ等に投資する民間の投資主体への資金供給を促進することとしています。
*1 製品開発~事業化における難所。製品開発から事業として収益を得るまでに要する時間が長く、事業化体制構築には相当な資金調達が必要となるため、経営判断の難しさ等から失敗するケースも多い。
*2 Small/Startup Business Innovation Researchの略で、中小企業者による研究技術開発と、その成果の事業化を一貫して支援する制度のこと
*3 正式名称は「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」
(事例)衛星データとAIを活用し、新たなサービスを創出(兵庫県)
(1)衛星データとAIを活用し、多様なサービスを展開


衛星データを活用した土壌分析
資料:サグリ株式会社
兵庫県丹波市(たんばし)のサグリ株式会社は、衛星データとAIを組み合わせた技術で農業分野の課題解決に取り組むスタートアップです。同社では、衛星データから耕作放棄地を検出し、農地のチェック業務を効率化できるアプリや、作付けされている作物を衛星データから推定し、画面上で一目で確認できるアプリの提供を行っています。また、生育・土壌の状態を見える化する営農アプリを提供しているほか、衛星データ解析とGIS(*1)技術を用いて、点在する農地を検出し、農地を提供可能な農地所有者と利用したい作り手・担い手をつなげる農地マッチングサービスの展開を行っています。
(2)カーボン・クレジットの創出に向けて
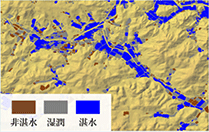
数理統計モデルによる湛水状況診断
(中山間地域への適用例)
資料:サグリ株式会社
令和5(2023)年度には農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業において採択され、土壌分析や水田の湛水(たんすい)状況の検知技術を用いて、農業分野における温室効果ガス削減の促進とカーボン・クレジット創出量の最大化を目指す取組を進めています。また、令和32(2050)年に目標とされているネット・ゼロ(*2)社会への貢献や農地の価値の向上を目指しています。
*1 Geographic Information Systemの略で、地理情報システムのこと
*2 カーボンニュートラルや脱炭素と同義
(SIP/BRIDGEを通じて府省連携による研究開発を推進)
このような農林水産省の取組と合わせて、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI(システィ)(*1))の下、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP(*2))や、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE(*3))の研究プロジェクトを通じて、府省連携による研究開発を推進しています。
SIPでは、「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」として、食料安全保障の強化等に向けた研究開発に取り組んでいます。このうち大豆の課題では、過去60年の日本国内の育種データを蓄積し、交配前に子孫の収量・品質等をシミュレーションすることにより、多収・高品質の新品種開発を効率化させるプラットフォームの開発を行っています(図表2-9-2)。また、生産現場の環境等に応じて、品種選択、作業時期等を最適化するAIの開発や、同AIからスマート農業機械への作業指示、データ取得等を行う、スマート農業技術と連携するシステムの開発を行い、これらの取組を通じ、大豆の地域単収1.6倍以上を目指しています。また、BRIDGEでは、農林水産分野での生成AIの活用に関する研究に取り組んでおり、農研機構に蓄積された研究データを始め、我が国農業に関する大量のデータを学習させた農業用基本AIモデルを構築し、そこにさらに地域に特化したデータを追加学習させた農業特化型生成AIを開発しました。これにより、農業者や普及指導員が栽培技術に悩んだ際に質問をすると、本生成AIが正確なデータに基づくアドバイスを行い、迅速に課題解決が図られることが期待されており、令和6(2024)年10月から、農研機構が本生成AIの実証実験を三重県で開始しています。このほか、農地や河川等の広域に被害が広がるナガエツルノゲイトウ等の侵略的外来種の効果的な防除技術の開発について、環境省、地方公共団体等と連携した取組を進めるなど、農林水産・食品分野の社会課題解決につなげる様々な研究開発を推進しています。

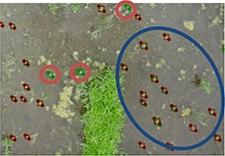
ナガエツルノゲイトウの画像識別AIを構築
資料:農研機構
注:青色の丸はナガエツルノゲイトウを識別したもの。
赤色の丸は近縁種を識別したもの
*1 Council for Science, Technology and Innovationの略
*2 Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Programの略
*3 programs for Bridging the gap between R&d and the IDeal society (society 5.0) and Generating Economic and social valueの略
(ムーンショット型研究開発を推進)
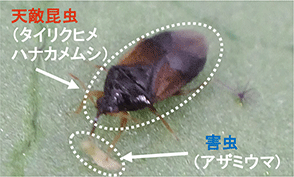
害虫を食べる天敵昆虫
タイリクヒメハナカメムシ
資料:農研機構
CSTIでは、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象とした目標を設定し、関係府省はこの目標を実現するため、挑戦的な研究開発(ムーンショット型研究開発)を推進しています。
農林水産・食品分野においては、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」することを目標として掲げ、食料の生産と消費の両面から八つの研究開発プロジェクトに取り組んでいます。これまでに、化学農薬に依存しない害虫被害ゼロ農業の実現に向け、不規則に飛翔する害虫の0.03秒後の位置をAIで予測し、青色レーザーで狙撃する防除技術が開発され、室内実験で、実際に飛翔する蛾(が)類を狙撃できることが確認されました。また、選抜育種により「餌(害虫)探しをすぐにあきらめず、同じ場所に長くとどまる性質を有する天敵昆虫」の作出に成功しました。定着性が向上した「すぐにあきらめない」天敵による害虫防除効果の検証がナス等の施設栽培において開始されています。これらの研究開発を進め、得られた研究成果を社会に還元することによって、本目標が掲げる持続可能な食料システムの構築の実現を目指します。
(「知」の集積と活用の場によるイノベーションを創出)
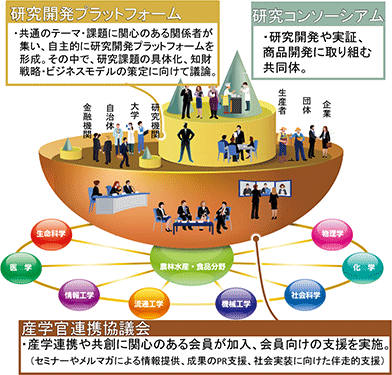
「知」の集積と活用の場
我が国における農林水産・食品分野の研究開発力を強化するためには、産学官による多様な分野の連携を推進していく必要があります。
このため、農林水産省では、農林水産・食品分野におけるオープンイノベーションの促進を目的としたプラットフォーム『「知」の集積と活用の場』を設置し、基礎から実用化段階までの研究開発やその成果の社会実装・事業化等を推進しています。令和7(2025)年3月末時点で、多様な分野から5,000以上の企業・大学等が参画しており、振動発生装置を用いて、トマトのハウス栽培におけるコナジラミ等の害虫防除や、ウナギ養殖の飼料に大豆イソフラボンを添加することによる、雄より食味の良い雌ウナギの増産化等の創意工夫による新たな技術の開発や社会実装等が進められています。さらに、このような優れた研究成果の速やかな社会実装や事業化を推進するため、アグリビジネス創出フェア等を通じて幅広く情報発信を行っています。

トマト栽培施設での
振動発生装置を用いた害虫防除(丸印)
資料:東北特殊鋼株式会社

大豆イソフラボンを添加した
飼料で養殖した雌ウナギ(上)
資料:愛知県水産試験場

「知」の集積と活用の場
URL:https://www.knowledge.maff.go.jp/
(2)農業の展開におけるデジタル化の推進
(農業データ連携基盤「WAGRI」を通じた農業現場でのデータ活用の取組が拡大)
農業現場における生産性向上のためには、データをフル活用できる環境を整備することが不可欠です。
このため、データを連携・共有・提供する機能を有する農業データ連携基盤「WAGRI(*1)」を構築し、平成31(2019)年から農研機構が運用しています。WAGRIを通じ、気象や市況情報、生育予測や病害虫診断プログラム等の多様なAPI(*2)が提供され、民間事業者による農業者向けサービスの開発が進展しています。また、これらのサービスを利用して、栽培管理や農業経営において、データを活用する取組が拡大しています。今後も、WAGRIの活用促進を通じ、データを活用した農業が一層展開されるよう、ニーズの高いデータやプログラム等をWAGRIに実装し、コンテンツの充実化を進めていきます。
*1 特集3を参照
*2 特集3を参照
(行政手続の効率化及び利便性の向上に向けたデジタル技術の高度活用)
我が国の人口構造の変化に伴い、多くの業界・分野で業務従事者数の減少・高齢化が進行しており、地方公共団体を含む行政においても、この傾向は顕著に表れています。これまでの人手に頼るやり方を抜本的に改め、デジタル技術を高度活用し、業務効率化に取り組むことが重要です。
令和6(2024)年6月に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においては、「デジタルの可能性を最大限引き出し、社会課題の解決を図りつつ、我が国全体のデジタル競争力が底上げされ、成長していく持続可能な社会を目指す」とされており、そのために、「制度・業務・システムの最適化されたあるべき姿を構想し、三位一体で改革を進めていく」こととされています。
農林水産省においては、これまで「農林水産省共通申請サービス(eMAFF(イーマフ))」「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF(イーマフ)地図)」といったシステムを構築し、行政手続のオンライン化、利便性の向上に取り組んできました。eMAFFについては、費用対効果の観点、利用者視点での利便性向上や行政運営効率化の観点からより適したシステムとなるよう、見直しに取り組んでいるところです。また、eMAFF地図についても、現地確認業務の効率化等に向けて利活用の向上に取り組んでいます。
(農林水産行政が保有するデータの活用に向けた環境整備等を推進)
農林水産業の生産・経営やそれらを取り巻く社会情勢の変化・多様化が加速する中、行政においてもデータを活用してその変化を的確に捉え、政策運営に活かしていくことの重要性が高まっています。農林水産省では、令和5(2023)年10月に策定した、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書」に基づき、データの集約・適切な管理を効率的に進めるデータマネジメント推進施策とデータ活用人材の育成等を行うデータ活用推進施策を両輪の取組として実施することとしています。
令和7(2025)年3月には、データマネジメント推進施策として、「データ活用基盤」を構築しました。引き続き、データ可視化・分析におけるデータ準備作業等の効率化に向けて、農林水産行政が保有するデータの「データ活用基盤」への集約・蓄積に取り組んでいきます。
今後も、様々なデータと連携した高度な分析が可能となるよう、分析しやすい形式でのデータの集約・蓄積を進めるとともに、その組織的活用に向けたBIツール(*1)等の研修を行うことで農林水産省におけるデータマネジメント及びデータ活用を進めていくこととしています。
*1 BIは、Business Intelligenceの略で、様々なデータを基に分析・可視化し、業務等における意思決定に役立てるソフトウェア・ツール
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




