第8節 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備と保全
我が国の農業を成長産業にするとともに、食料安全保障の確保を図るためには、令和3(2021)年に閣議決定した土地改良長期計画を踏まえ、農地を大区画化するなど、農業生産基盤を整備し良好な営農条件を整えるとともに、大規模災害時にも機能不全に陥ることのないよう、国土強靱(きょうじん)化の観点から農業水利施設の長寿命化や農業用ため池の適正な管理・保全・改廃を含む防災・減災対策を効果的に行うことが重要です。
本節では、水田の大区画化、汎用化・畑地化等の状況、農業水利施設の保全管理、流域治水の取組等による防災・減災対策の実施状況等について紹介します。
(1)農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
(50a以上に区画整備済みの水田は12%)
農地等の農業生産基盤は、食料安全保障の確保や農業の生産性向上を図っていく上で極めて重要であり、今後も効率的な整備を行っていくことが不可欠です。
令和5(2023)年の水田の整備状況を見ると、水田面積全体(234万ha)に対して、30a程度以上の区画に整備済みの面積は68.7%(160万ha)、担い手への農地の集積・集約化や生産コストの削減に特に資する50a以上の区画に整備済みの面積は12.3%(29万ha)、更に1ha以上の大区画に整備済みの面積は6.3%(15万ha)、暗渠(あんきょ)排水の設置等により汎用化が行われた面積は47.7%(111万ha)となっています(図表2-8-1、図表2-8-2)。
また、令和5(2023)年の畑の整備状況については、畑面積全体(196万ha)に対して、畑地かんがい施設整備済み面積は25.9%(51万ha)、区画整備済み面積は65.7%(129万ha)となっています。
農林水産省では、農業の競争力や産地の収益力を強化するため、農地の大区画化、水田の汎用化・畑地化、畑地かんがい施設の整備等の農業生産基盤整備を実施し、担い手への農地の集積・集約化、畑作物・園芸作物への転換、産地形成等に引き続き取り組んでいきます。
(事例)基盤整備により地域の明るい未来を目指して(宮城県)
(1)地域農業の存続をかけて基盤整備に挑戦

宮城県美里町(みさとまち)では長年、個々の農家による水稲主体の農業生産が展開されていましたが、圃場(ほじょう)が10a区画と狭く、水路は用排水兼用の土水路であったことから、維持管理に多大な労力を要していました。また、地下水の高い区域等では湿田状態となり、水田の汎用化が困難となっていたこと等から、同県が中心となって平成16(2004)年度から平成29(2017)年度にかけて、経営体育成基盤整備事業による暗渠の設置や用排水路の整備、圃場の大区画化等を実施しました。
(2)個々の経営から集落営農組織へ、そして法人化へ

圃場に設置された
地下水位制御システム
資料:農事組合法人みらいす青生

一面に広がる大豆の圃場
資料:農事組合法人みらいす青生
同事業を契機に、集落営農組合を経て平成26(2014)年に設立された農事組合法人みらいす青生(あおう)は、農地約110haにおいて水稲、麦、大豆等を生産しています。
同法人では、事業により水田の汎用化と圃場の集積・集約化が図られたことから、水稲単作から水稲、小麦、大豆の2年3作のブロックローテーションへの転換を実現しています。
また、圃場の1ha区画への大区画化や農道の整備による大型機械の導入に加え、他の地域に先駆けて導入した地下水位制御システムにより水管理作業等の省力化が図られたことから、特に乾田直播(ちょくはん)栽培を導入した圃場においては、基盤整備前に比べ水稲の生産コストの約4割の削減に成功しました。
さらに、地下かんがいにより、土壌水分を適切に調整することが可能となり、大豆と麦については同県平均を大きく上回る収量を達成し、品質も向上しています。
(3)地域農業の担い手として、今後は会社法人化も視野
同法人は、地域コミュニティの活性化にも貢献しています。新たに立ち上げた園芸部門では、女性が中心となりとうもろこしやねぎ等の収益性の高い作物を生産しています。また、地域農業の担い手として人材育成に取り組んでおり、同県の農業大学校の研修等の受入協力等も行っています。
同法人では、将来の会社法人化も視野に入れつつ、新技術の積極的な導入や働きやすい環境づくりに取り組み、同法人名の由来である「農業を基盤に地域の未来を明るくする」ことを目標に、今後も地域農業を守っていく考えです。
(スマート農業に適した農業生産基盤整備の取組が進展)

自動給水栓
資料:秋田県
農業分野においては、担い手不足や高齢化の進展、耕作者の経営規模拡大に伴い、農作業の効率化・省力化が求められています。農業を取り巻く情勢が変化している中、自動走行農機やICT水管理等のスマート農業技術の活用は、地域農業の継続に有用であると考えられます。このため、農林水産省は、農地の大区画化、情報通信基盤の整備を始めとしたスマート農業技術の実装を促進するための農業生産基盤整備を推進しており、自動走行農機等の効率的な作業に適した農地整備、ICT水管理施設の整備、パイプライン化等に取り組んでいます。
(国内の需要等を踏まえた農業生産基盤整備を推進)
食料安全保障を確保する観点で、持続可能な食料供給ができる農業生産基盤を確保していくことは重要です。世界の食料需給等をめぐるリスクの顕在化を踏まえ、麦や大豆、飼料等の海外依存度の高い品目の生産を拡大していく必要があります。また、農業者が減少する中、持続的な食料供給を確保するためには、これらに対応可能な生産基盤に転換していく必要があります。

データ(エクセル:28KB)
我が国においては、これまで麦・大豆等の生産拡大や生産性向上に向けて整備が進められてきていますが、農地整備率の高い市町村ほど麦や大豆の作付けが高い割合となっており、農業生産基盤の整備が畑作物の生産拡大に向けて重要な要素となっていることがうかがわれます(図表2-8-3)。
農林水産省では、農業生産基盤整備においても、食料安全保障の確保を図る観点から、農地の大区画化、排水改良等による水田の汎用化・畑地化、畑地かんがい施設の整備による畑地の高機能化、草地整備のほか、情報通信基盤の整備、農業水利施設の省力化、省エネルギー化、集約・再編等を推進しています。
(事例)水田の汎用化を契機として、大豆の契約栽培を開始(滋賀県)
(1)畑作物の導入に向けて土壌の水はけ改善に挑戦
滋賀県東近江市(ひがしおうみし)の蒲生南部(がもうなんぶ)地区では、水稲を主体に麦、大豆等のブロックローテーションが行われてきました。一方、地区内の土壌は粘土質で水はけの悪い圃場条件であることに加え、約40年前に整備された暗渠排水施設の機能低下が生じていたことから、排水不良により収益の高い畑作物の導入等を始めとした営農の新たな展開に支障が生じていました。そのため、「滋賀蒲生町(しががもうちょう)農業協同組合」(以下「JA滋賀蒲生町」という。)が中心となって、地域の中で話合いを進め排水改良による水田の汎用化に取り組みました。
(2)JA滋賀蒲生町が主導して、暗渠排水の導入による水田の汎用化を推進
JA滋賀蒲生町では、平成27(2015)年度から令和4(2022)年度にかけて、管内の生産者に圃場整備事業の実施を呼び掛け、圃場整備を希望する法人の取りまとめ作業、その他の事務作業の支援等を行い、約300haの圃場に暗渠排水を整備し、営農の省力化を図りました。また、暗渠排水の施工による圃場の排水改良等に取り組み、水田の汎用化を推進してきました。
(3)水田の汎用化によって大手豆乳メーカーとの契約栽培を呼び込み、生産者の所得向上に寄与
同地区では、水田の汎用化を契機として、豆乳メーカーであるマルサンアイ株式会社と地域の農家等との間で、豆乳用の新品種大豆である「すみさやか」の契約栽培が進められています。多収性のある新品種の産地を探していた企業側と農業所得の向上につながる品種選定を行っていた農業者側との間で意向が合致した結果、同地区全体のすみさやか等の出荷量は54,390㎏と、契約栽培の開始前に比べ47,310㎏増加しており、生産者の所得向上につながっています。同地区では、継続的な基盤整備の実施に取り組むとともに、研修会等を通じた営農組織間連携を促進し、市場ニーズを捉えた生産体制の拡大・強化による地域農業の発展を目指していくこととしています。


暗渠排水管を敷設した圃場
資料:滋賀蒲生町農業協同組合

契約栽培の品種を作付けした圃場
資料:滋賀蒲生町農業協同組合
(農業生産基盤整備の事業効果の発現を通じた農村地域の振興が展開)

土地改良事業を契機とした農村地域の振興事例集
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/kousyueki-zirei.html
農業生産基盤整備を実施した地域では、事業による効果の発現を通じ、施設の管理、農作業の効率化等が図られています。農林水産省では、優良事例について、ウェブサイトを通じて紹介を行い、全国への横展開を図ることとしています。
(みどり戦略の実現に向け、農業水利施設の省エネ化・再エネ利用を推進)
みどり戦略では、食料システムを支える持続可能な農山漁村の創造に向けて、環境との調和に配慮しつつ、農業水利施設の省エネルギー化・再生可能エネルギー利用の推進を図ることとしています。
農業水利施設等を活用した再生可能エネルギー発電施設については、令和6(2024)年3月末時点で、農業用ダムや水路を活用した小水力発電施設は177施設、農業水利施設の敷地等を活用した太陽光発電施設、風力発電施設はそれぞれ124施設、4施設の計305施設を農業農村整備事業等により整備しました(図表2-8-4)。これにより、土地改良施設の使用電力量に対する小水力発電等再生可能エネルギーの割合は、同年3月末時点で31.5%となりました。
農林水産省では、みどり戦略の実現を後押しするため、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の推進に向けて、農業用水を活用した小水力発電等の再生可能エネルギーの導入や電力消費の大きなポンプ場等の農業水利施設の省エネルギー化に引き続き取り組んでいきます。

データ(エクセル:29KB)
(2)農業水利施設の戦略的な保全管理
(農業水利施設の機能保全に対する取組を推進)
農業が持続的に発展し、食料安全保障の確保及び多面的機能の発揮という役割を果たしていくためには、水源を確保して適切な時期に必要な量の農業用水を農作物に供給するとともに、その生育を阻害しないよう適切に排水する一連の農業水利システムが、全国各地の農業生産の現場で持続的に安定して機能していることが不可欠です。
農林水産省では、国民共有の資産である農業水利施設について、適時の補修・補強、更新、突発事故が発生した場合の速やかな復旧等により機能保全を図り、農業水利施設の安定的な機能の発揮による持続的な農業生産の確保に努めています。
(標準耐用年数を超過している基幹的施設は58%、基幹的水路は48%)
農業者の減少や高齢化、農業水利施設の老朽化等が進行する中、基幹から末端に至る一連の農業水利施設の機能を安定的に確保し、次世代に継承していくことが重要です。
基幹的農業水利施設の整備状況は、令和5(2023)年3月末時点で、基幹的施設の施設数が7,763か所、基幹的水路の延長が5万2,073kmとなっており、これらの施設は土地改良区等が管理しています(図表2-8-5)。
基幹的農業水利施設は、戦後から高度経済成長期にかけて整備されたものが多く、老朽化が進行しているものが相当数あり、標準耐用年数(*1)を超過している施設数・延長は、基幹的施設が4,535か所、基幹的水路が2万4,902kmで、それぞれ全体の58.4%、47.8%を占めています。
また、経年劣化やその他の原因による農業水利施設の漏水等の突発事故については、令和5(2023)年度は1,650件となっており、依然として高い頻度で発生しています(図表2-8-6)。
農林水産省では、農業水利施設を長寿命化し、ライフサイクルコスト(*2)の縮減を進めるとともに、突発事故の発生を防止するため、適期の更新整備を推進することとしています。
*1 所得税法等の減価償却資産の償却期間を定めた財務省令を基に農林水産省が定めたもの
*2 施設の建設に要する経費、供用期間中の維持保全コストや、廃棄に係る経費に至るまでの全ての経費の総額
(人口減少に対応した農業水利施設の維持管理の効率化・高度化を推進)
都市化の進展や集中豪雨の頻発化・激甚化等により、施設管理者は複雑かつ高度な維持管理を行うことが求められている一方、農村人口の減少等により、施設操作等に係る人員や、土地改良区の賦課金収入の確保が困難となりつつあり、この傾向は今後より一層深刻化するおそれがあります。
農業水利施設の維持管理の効率化・高度化や突発事故の発生防止に向け、基幹施設では、農地面積や営農の変化を踏まえた集約・再編等のストックの適正化といったハード面での対応のほか、ドローンやロボット等を活用した管理水準の向上、ICT導入等による施設の操作・運転の省力化・自動化、維持管理要員の確保・育成、土地改良区に対する専門家派遣等の技術的支援等といったソフト面での対応も併せた総合的な対策に取り組むことが重要です。
また、末端施設においては、開水路の管路化、畦畔(けいはん)拡幅、法面(のりめん)被覆といった圃場周りの管理作業の省力化に資する整備を推進していくとともに、末端施設の保全管理を行う地域の活動組織の体制強化を図っていくことが必要となっています。

農業水利施設の保全管理
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/sutomane/index.html

ドローンによる頭首工の点検
資料:大分県土地改良事業団体連合会
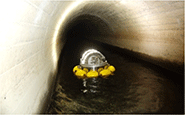
点検ロボットによる通水中の水路トンネルの点検
資料:農研機構
(コラム)農業水利施設の集約・再編により管理・更新にかかる負担を抑制
人口減少下において、農業生産基盤の保全を図るため、農業水利施設の管理・更新にかかる負担抑制を図ることが必要になっており、農業水利施設を集約・再編する取組が各地で見られています。
例えば山形県鶴岡市(つるおかし)、酒田市(さかたし)及び三川町(みかわまち)にまたがる赤川(あかがわ)地区では、昭和39(1964)~49(1974)年度にかけて造成された基幹水利施設が老朽化し、農業用水の安定供給に支障を来すとともに、施設の維持管理にも多大な労力と費用を要していたことから、平成22(2010)~令和3(2021)年度にかけて国営かんがい排水事業「赤川二期地区」を実施し、頭首工(とうしゅこう)や幹線用水路等の機能を維持するための改修等を行いました。
この事業では、施設の改修に加え、頭首工とは別に地区内への用水補給を行っていた下流の揚水機場を廃止し、上流の頭首工に取水機能を統合する用水系統の見直しにも取り組みました。営農形態の変化により稼働率が低下し、老朽化も相まって維持管理費が増大していた揚水機場を廃止・撤去することで、電気代や人件費といった維持管理費が削減されたほか、将来的な更新整備に係る費用も削減されることから、農業水利施設の効率的な運営・管理が実現されています。
標準耐用年数を超える農業水利施設が相当数ある中、営農形態の変化等に対応しつつ施設の機能を持続的に保全していくため、ストックの適正化等による戦略的な保全管理を進めていくことがますます重要となっています。
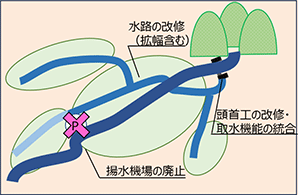
赤川二期地区の事業概要図
資料:農林水産省作成
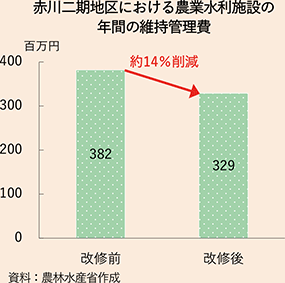
データ(エクセル:24KB)
(3)農業・農村の強靱化に向けた防災・減災対策
(農業水利施設、農業用ため池の防災・減災対策を推進)
近年、時間降水量50mm以上の大雨の発生回数は増加傾向にあり、湛水(たんすい)被害等が激化しています(*1)。また、南海(なんかい)トラフ地震の被害想定エリアには全国の基幹的水利施設の3割が含まれています。
頻発化・激甚化する豪雨・地震等の自然災害に適切に対応するためには、農業水利施設等の老朽化や豪雨・地震への対策、施設の集約・再編を含めた適切な更新、流域治水の取組を推進するための補修・更新等が重要です。
また、決壊した場合に人的被害を与えるおそれのある防災重点農業用ため池については、廃止工事を含む防災工事のハード対策と、劣化状況評価や地震・豪雨耐性評価の実施、ハザードマップ作成等のソフト対策を組み合わせながら防災・減災対策を推進することが重要です。
このような中、防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進するため、ため池工事特措法(*2)に基づき、都道府県知事は防災重点農業用ため池を指定するとともに、防災工事等推進計画を策定しています。令和6(2024)年3月末時点で指定された防災重点農業用ため池は約5万3千か所となっています。
さらに、農林水産省では、防災重点農業用ため池の監視・管理体制を強化するため、農業用ため池の管理者等へ技術的な支援を行う「ため池サポートセンター」等の活動を支援しており、令和7(2025)年1月末時点で40道府県において設立されています。あわせて、ハザードマップの作成、監視・管理体制の強化等の農業用ため池の防災・減災対策を推進しており、令和6(2024)年3月末時点でハザードマップ等を作成した防災重点農業用ため池の数は、全体の約9割となっています。

農業用ため池に設置された
遠隔監視機器
資料:長野県
くわえて、農業用ため池に水位計や監視カメラ等の遠隔監視機器を設置することにより、豪雨時の水位データや洪水吐(こうずいば)きの状況等を遠隔地からリアルタイムで把握することが可能となり、災害時における避難情報の発令等の判断材料となりうるものとして期待されています。流域治水の観点からも重要な取組であり、農林水産省では、引き続き遠隔監視機器の設置を支援していくこととしています。
*1 第5章第1節を参照
*2 正式名称は「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」
(農業用ため池の管理保全施策の点検・検証を実施)
ため池管理保全法(*1)では、法施行後5年を目途として、その施行状況の点検・検証を行うこととされており、農林水産省は、法施行後5年目に当たる令和6(2024)年に有識者による「農業用ため池の管理保全施策の施行状況の点検・検証に係る委員会」を設置し、農業用ため池の管理保全施策における施行状況の点検・検証を行いました。
同委員会では、同年9月に点検・検証の結果として、ため池管理保全法に規定されている制度等はおおむね適切に施行されており、ため池管理保全法は改正する必要がないとされた一方、農業用ため池の管理保全における課題への対応として、「農業用ため池の管理保全に係る持続的な体制整備」、「災害への備え、災害発生時の迅速かつ的確な対応」等の提言が示されました。これらの提言を踏まえ、引き続き、農業用ため池の管理保全施策を適切に推進していくこととしています。
*1 正式名称は「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」
(農地・農業水利施設を活用した流域治水の取組を推進)
「流域治水プロジェクト」は、国、地方公共団体、企業等が協働し、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像を取りまとめたものであり、令和7(2025)年3月末時点で全国109の一級水系における119のプロジェクトのうち110プロジェクトで農地・農業水利施設の活用が位置付けられています。
農林水産省は、流域全体で治水対策を進めていく中で、水田を活用した「田んぼダム」、農業用ダムや農業用ため池の事前放流、市街地や集落の湛水被害も防止・軽減させる排水施設の整備といった農地・農業水利施設の活用による流域治水の取組を関係省庁や地方公共団体、農業関係者等と連携して推進しています。

データ(エクセル:25KB)
このうち「田んぼダム」は、小さな穴の開いた調整板等の簡易な器具を水田の排水口に取り付けて流出量を抑えることにより、水田の雨水貯留機能の強化を図り、実施する地域の農地・集落や下流域の浸水被害リスクの低減を図る取組です。令和5(2023)年度の取組面積は、前年度に比べ1万3千ha増加し8万7千haとなりました(図表2-8-7)。
また、令和6(2024)年度の出水期においては、延べ208基の農業用ダムで事前放流等により洪水調節容量を確保し、洪水被害の軽減を図りました。
(4)農業生産基盤の整備・保全に向けた施策の推進
(土地改良区の運営基盤強化を推進)
土地改良区は、農業水利施設の整備・農地の大区画化等のほか、農業水利施設の保全管理を行っています。
土地改良区の数は合併の推進もあり減少傾向で推移しており、令和5(2023)年度においては4,095地区となっています。また、1土地改良区当たりの受益面積は拡大傾向にあり、同年度で595haとなっています(図表2-8-8)。
また、土地改良区の受益面積規模別の職員数と受益面積10a当たりの恒常的経費支出額を見ると、小規模な土地改良区では、1土地改良区当たりの平均職員数が一人を下回るなど職員が十分に確保されておらず、恒常的経費も割高となる傾向にあります(図表2-8-9)。
人口減少下において、組合員の減少や高齢化が課題となる中、持続的に土地改良区の組織を維持し、将来にわたって、農業水利施設等の保全管理といった土地改良区が求められる役割を十分に果たすためには、引き続き土地改良区の再編整備や多様な主体との連携等を促進することを通じて、その運営基盤の強化を図ることが重要です。
(農業生産基盤の整備・保全等に必要な制度の見直しを実施)
農林水産省では、農業生産基盤の保全等に向けて、災害等によるリスクが高まる中、老朽化が進む農業水利施設の計画的な更新や地域の農業水利施設の維持管理を将来にわたって継続していくため、必要な制度を見直しています。土地改良事業により造成された基幹的な施設については、その大半において老朽化が進行しており、今後、計画的な更新を進めていく必要があります。また、農村人口の減少下において、地域の施設等の適切かつ継続的な保全体制の確立が急務となっています。さらに、災害の激甚化・頻発化を踏まえ、施設の被害を未然に防止する対策と、被害が発生した際の対策の拡充が求められています。
このような背景の下、施設の老朽化の進行や農村人口の減少、気候変動による災害リスクの増大等に的確に対応できるよう、国や都道府県の発意によって基幹的な施設の更新を行う事業を創設し、地域の多様な関係者が連携し施設等の保全を行っていく計画を認定する制度を創設するとともに、手続を簡略化して迅速に実施できる急施の防災事業に損壊が生じるおそれがある施設の補強等の対策を追加、復旧事業に再度災害防止のための対策や突発事故と類似の被害を防止するための対策を追加し、また、農地中間管理機構関連事業の実施主体に市町村を追加するほか、土地改良区による地域の情報通信環境の整備を可能とするなど、農業生産基盤の整備・保全に必要な制度の見直しを行う「土地改良法等の一部を改正する法律」が第217回通常国会において成立し、令和7(2025)年3月に公布されました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883










