第10節 農産物の付加価値向上
農林水産物・食品の付加価値向上のためには、品種や技術、食文化等の優れた知的財産の創出とその保護・活用によるブランド化等の取組が重要です。しかしながら、我が国では、農業分野における知的財産の価値・保護・活用に係る認識等が十分ではなく、得られるべき利益を逸している事例が確認されています。また、今後、海外市場も視野に入れていく中で、知的財産を適切に保護・活用することが重要となっています。
このようなことから、新たな基本計画では、付加価値向上に向けた取組として、(1)高い品質を有する品種の開発・導入促進、(2)農産物を活用した新たな事業の創出の促進等(*1)、(3)知的財産の保護及び活用の推進、(4)付加価値の高い品目の輸出等(*2)の四つが位置付けられました。
本節では、このうち主に知的財産の保護・活用、新しい品種の導入促進の取組について紹介します。
*1 第6章第4節等を参照
*2 第3章第2節等を参照
(1)知的財産の保護・活用の推進
(我が国の農業・農産物の競争力強化に向けた知財サイクルの確立)
我が国の農林水産・食品分野は、優れた品種、高い技術やノウハウ、特有の食文化等の「知的財産」によって、諸外国に類を見ない特質・強みを有しています(図表2-10-1)。
改正基本法においては、このような知的財産の保護・活用が、農産物の輸出促進、付加価値向上・創出を図るための施策として明確に位置付けられました。
このような方向に即し、知的財産を戦略的に保護・活用し、農産物の付加価値を高めるとともに、知的財産を「稼ぎ」につなげ、得られた利益を新たな品種や技術等の開発へ投資し、農業・農産物の競争力強化につなげる知財サイクルの確立を図ることが重要となっています。

(過去に流出した品種の生産拡大により利益が逸失)

海外において販売が確認された
外国産シャインマスカット
果物や野菜を始めとした我が国の優れた品種は、世界的に高く評価され、輸出も増加しています。
しかしながら、過去には、農業分野における知的財産の価値に対する認識や保護・活用に関する知識が十分ではないことにより、我が国の開発した品種が海外へ流出し、得られるべき利益を逸している事例が複数確認されています。また、近年では、過去に流出した品種の流出先国における生産が拡大し、同国から品質が低く割安な生産物が輸出されることで、我が国からの輸出可能性が低下するといった状況につながっています。
(社会情勢の変化に対応した品種の開発・保護・活用を推進)
令和2(2020)年の種苗法改正により、登録品種の種苗の海外持ち出しや自家増殖に育成者権者の許諾を要することとなり、農業現場からの品種流出には一定の抑止が図られました。
他方、近年、オンライン取引の増大に伴う種苗の流通ルートの多様化が、新たな流出リスクとなっていることから、令和6(2024)年3月から、その対応方向について議論がなされ、同年6月に有識者により「デジタル化の進展等に対応した優良品種の保護・活用に向けた対応方向(提言)」が取りまとめられたところです。同提言では、権利者による管理や権利行使の実効性を高めるための支援の充実や環境・枠組みの整備を進め、費用対効果にも留意しつつ、総合的・複合的に侵害行為の未然防止に向けた対応、侵害行為に対する実効的な対応を講ずる必要があるとしています。
また、改正基本法や新たな基本計画の具体化に向け、優良品種の保護や管理を徹底しつつ、マーケットニーズに即した開発・普及を進めるとともに、権利者による優良品種の開発・普及に資する利用者に応じた戦略的な許諾料設定を通じ、新たな知的財産の創出につなげることで、国内産地の振興や農林水産物の輸出に寄与していく必要があります。
このような新たな基本計画の方向に則しながら、我が国農業の稼ぐ力の強化に向けた優良品種の戦略的な管理・活用等について、制度的枠組みの整備も含め同提言を踏まえた検討を行っています。
(コラム)新たな品種管理により、ブランド化に成功
登録品種の種苗の流出防止の実効性を高めるには、権利者が登録品種の種苗の厳格な管理を行い、無断での増殖・販売・輸出等の侵害行為の発生を未然に防ぐことが重要です。また、権利者による優良品種の種苗の管理の強化は、当該品種を利用する農業者・地域ぐるみのブランド化の取組にもつながります。このような背景を踏まえ、一部の地方公共団体では、海外・産地外への品種流出防止や優良品種を活用した産地ブランド化を推進するため、様々な取組が行われています。
例えば長野県では、平成31(2019)年に品種登録を行ったぶどうの新品種である「長果(ちょうか)G11」(商標名「クイーンルージュ」)について、種苗の購入者を、事前に同県との直接契約又は農協を通じて誓約書を提出した同県内の生産者に限定するとともに、苗木を予約販売とすることで、余剰苗木の発生を抑制しています。また、自家増殖の禁止や、購入した苗木本数の実績報告を求めるなど、販売後も徹底した管理を行っています。
また、山形県では、令和2(2020)年に品種登録を行ったおうとうの新品種である「山形(やまがた)C12号(ごう)」(商標名「やまがた紅王(べにおう)」)について、同県内の果樹で初めて生産者登録制度を導入し、登録された生産者のみに苗木の購入、栽培を認めています。登録要件には、剪定枝(せんていし)の処分や第三者への穂木・苗木の譲渡禁止といった、苗木の無断増殖を防ぐ内容に加えて、新規栽培には一定本数以上の苗木を導入することを義務化するなど、出荷量の早期安定確保によるブランド化に向けた内容も盛り込まれています。また、同品種では、大きさと色の品質基準を定めており、一定の基準を満たす果実にのみ商標を使用した販売が認められています。
優良でブランド価値の高い品種の種苗については、厳格な管理に当たって必要となる苗木業者や農業者等の負担・コストの増加にも留意しつつ、侵害・流出のリスクや国内・地域農業への影響、管理による費用対効果を踏まえ、新品種の生産性や市場性に応じた品種ごとの管理・活用を検討していく必要があります。
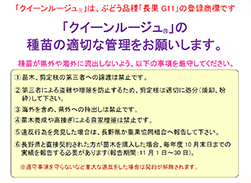
「長果G11」の種苗の適切な管理
を呼び掛けるチラシ
資料:長野県

ブランド化が進む「山形C12号」
資料:山形県
(育成者権管理機関の取組を推進)
優良品種の育成者権者である公的機関等が、海外現地で育成品種の無断栽培を監視し、侵害対応を実施することは難しい現状にあります。
このため、育成者権者に代わって海外での品種登録出願やライセンスを行うとともに、警告・差止等の侵害対応やこれらの助言・支援を行う育成者権管理機関の取組を、農研機構、JA全農、一般社団法人日本種苗協会(にほんしゅびょうきょうかい)、公益社団法人農林水産(のうりんすいさん)・食品産業技術振興協会(しょくひんさんぎょうぎじゅつしんこうきょうかい)(JATAFF)等が連携して、令和5(2023)年度から開始しました(図表2-10-2)。今後、この取組を通じ、海外現地のライセンス先が実効的な監視を行うことで、現地制度に基づく差止等の法的措置も講じやすくなっています。
育成者権管理機関の法人化に向けた業務基盤を整備するため、農林水産省では令和6(2024)年度において、優良品種の果樹の種苗について、適切な流通管理ができるシステムの開発や、海外ライセンス契約に向けた現地の種苗法や民法等の法令制度及びその運用実態や商慣習等の調査等の支援を行いました。
さらに、育成者権者が我が国の品種の無断栽培を実効的に抑止しつつ、国内農業の振興や輸出促進に寄与する戦略的な海外ライセンスを行うための指針として、令和5(2023)年12月に「海外ライセンス指針」を策定しました。
これを受けて同指針に則したライセンスの実現に向け、専門家の助言を受けて行う交渉加速化等の取組を支援することとしています。具体的には、品種保護制度の有無、ライセンスビジネスの成熟度等を考慮して生産国を選ぶとともに、我が国の輸出促進に理解のあるパートナーを選定します。また、契約に当たっては、収穫物の生産から販売までのルートの特定、収穫物の輸出競合市場への出荷制限、種苗の増殖・転売の制限や流出時のペナルティ措置等により保護・管理を徹底します。

(海外での我が国品種の登録迅速化のため、審査協力を推進)
我が国の植物品種の諸外国・地域における侵害に対処するためには、当該国・地域において品種登録が行われることが不可欠です。このため、我が国は、「植物の新品種の保護に関する国際条約」(UPOV(ユポフ)(*1)条約)の枠組みの下、加盟国・地域が、相手国・地域からの出願品種の審査に当たり、その相手国・地域における審査結果を活用する審査協力を進め、円滑な審査や迅速な登録を推進しています。
令和7(2025)年2月には、農林水産省と英国環境・食料・農村地域省との間で、「日英審査協力覚書」について署名を行いました。この結果、覚書に署名した国・地域は19となりました。このような取組により、我が国からの出願品種の審査に当たり、当該国・地域は我が国の品種登録審査結果を用いることが可能となりました。我が国からの輸出拡大に向け、当該国・地域での審査期間の短縮による我が国における優良品種の保護の迅速化が期待されています。
*1 Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétalesの略。英語表記は、International Union for the Protection of New Varieties of Plantsで、植物新品種保護国際同盟のこと
(和牛遺伝資源の管理・保護を推進)
和牛は関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であり、和牛の改良を継続的・効果的に促進し、国内の生産振興や和牛肉の輸出拡大を図るためには、精液等の遺伝資源の適正な流通管理を行い、知的財産としての価値を保護することが重要です。
農林水産省では、和牛遺伝資源の生産事業者と、その譲渡先との間で、使用者の範囲等について制限を付す契約を普及させることにより、知的財産としての保護を図り、和牛遺伝資源の管理・保護を推進しています。
また、令和5(2023)年度には、家畜改良増殖法に基づき、全国の家畜人工授精所1,049か所への立入検査を実施し、法令遵守の徹底を図りました。
(新たに16産品がGI登録)
地理的表示(GI(*1))保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。同制度は、国による登録によりそのGI産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅力や強みを「見える化」し、GIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして機能するものです。
国内のGI登録産品については、令和6(2024)年度は菓子類で初の登録となったちんすこうを含め新たに16産品が登録され、これまでに登録された国内産品は、令和7(2025)年3月末時点で計161産品となりました(図表2-10-3)。
また、日EU・EPAにより、日本側108産品、EU側121産品が相互に保護され、日英EPAにより、日本側109産品、英国側59産品が相互に保護されています(*2)。このほか、二国間の協力に基づき、タイとの間で日本側6産品、タイ側3産品、ベトナムとの間で日本側3産品、ベトナム側2産品が登録されています。
農林水産省では、農林水産物・食品の輸出拡大、所得、地域活力の向上に資するよう同制度の活用を推進しています。また、GI産品やその加工品へのGIマーク活用の働き掛けや、観光業を始めとするGI産品と他業種とのコラボレーションを通じて、GIやGIマークを露出する機会を増やし、実需者の認知・価値を向上させていくこととしています。
くわえて、海外ECサイトにおける国内GI登録名称等の不正使用調査を実施し、その結果を踏まえ、ECサイトに対して不正使用の削除を求めるなどの対策を実施しています。




知的財産・地域ブランド情報
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/
*1 Geographical Indicationの略
*2 日EU・EPA、日英EPAで相互に保護されている産品数については、いずれも酒類を除く。
(事例)GIを活用したPR活動による販売戦略を実施(和歌山県)
(1)長年の栽培の歴史と品質の高さが評価され「あら川の桃」がGI登録
和歌山県紀(き)の川市(かわし)桃山町(ももやまちょう)及び竹房(たけぶさ)では、江戸時代からの栽培技術の積重ねにより高品質なももを生産しています。また、ももの花の季節には桃源郷を思わせる絶景が地域の風物詩となっています。市内のもも生産農家や生産組合等で構成される「あら川(かわ)の桃振興協議会(ももしんこうきょうぎかい)」では、「あら川の桃」として全国的に高い知名度を持つ同地域のももについて、ブランド保護と認知度の更なる向上を図るため、GI登録の申請を行いました。そして、その生産の歴史と栽培技術の積重ねによる、美しい外観や良好な食味が評価され、令和5(2023)年7月にももでは初めて登録されました。
(2)GIマークを積極的に活用したPR活動の実施
GIには、地域と結び付いた産品の潜在的な魅力や強みが可視化されることで、その産品の価値が消費者に伝わり差別化され、ブランド価値の維持・向上につながるといった効果があります。
同協議会が、GI登録を販売促進につなげるために実施した、SNSへの写真投稿キャンペーンは、直売所で購入したももや、ももの花畑といった、多くの投稿で盛り上がりを見せました。また、大手小売と連携したスイーツの商品パッケージへのGIロゴマークの表示、直売所へのポスターの掲示等により、「あら川の桃」がGI産品であることを消費者に積極的に周知する取組を行っています。
また、「あら川の桃」は、東南アジア等を中心に海外への輸出が行われており、GI産品であることによる海外でのブランド価値向上や販路拡大が期待されています。


あら川の桃
(知的財産の戦略的な活用を推進)
農林水産・食品分野では、以前から、開発品種や栽培技術の普及が重視されてきたこと、国内市場を主なターゲットとしてきたこと等から、品種や技術等の知的財産を、財産や権利として捉え、戦略的に保護・活用することで、ブランド化や国際競争力の強化につなげるといった意識がいまだ十分に醸成されていない状況です。
このため、同分野への知的財産の保護・活用に関する意識の浸透に向け、令和6(2024)年度から関係者を対象とした農業分野の知的財産の基礎を学ぶオンライン講座を開設するとともに、農業現場に適した助言ができる専門人材の育成に取り組んでいます。また、農業分野の知的財産に明るい次世代人材の育成に向け、学生や農業現場等に対して農林水産・食品分野の知的財産の出張講座の拡大を図っています。
海外における我が国の農林水産物・食品の知的財産の保護に向けた対応も強化しています。農林水産省では、我が国の農林水産物・食品の海外での模倣品がジャパンブランドの毀損や輸出促進の阻害要因となることから、外務省、独立行政法人日本貿易振興機構(にほんぼうえきしんこうきこう)(以下「JETRO(ジェトロ)」という。)の関係省庁等と連携して、10か国・地域の輸出支援プラットフォーム(*1)内に模倣品疑義情報に関する相談窓口を設置しました。窓口では既に海外展開している又は海外展開を検討中の事業者・団体から広く情報提供や相談を受け付け、模倣品に対する侵害対策方法や模倣品を防ぐための知的財産の活用方法について専門家等による提案・助言を行っています。これらの情報を基に、現地での商標取得等の権利化を促進するとともに、模倣等の侵害が疑われる事案については現地当局に情報提供の上、適切な取締りを依頼することとしています。
*1 第3章第2節を参照
(2)新たな品種の導入促進
(高い品質や加工適性を維持しつつ多収化等に資する優良品種の育成を推進)
食料の安定供給を確保するためには、生産性向上を始めとした課題に対応した画期的な品種を開発していくことが不可欠であり、そのためには産学官連携による品種開発の強化が必要です。
農林水産省では、スマート技術向けの特性を持つ新品種や多収品種等の開発に取り組むとともに、品質の向上にも取り組んでいます。長期にわたる研究の結果、令和6(2024)年度は、機械化適性を持ちながら食味も良好なリンゴ「紅つるぎ」や多収でありながら豆腐加工適性も良い大豆「そらたかく」が開発されました。

既存品種(左)と
新品種「紅つるぎ」(右)
資料:農研機構
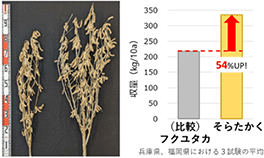
既存品種(左)と
新品種「そらたかく」(右)
資料:農研機構
また、気候変動等に対応し、食料安全保障に貢献する画期的な新品種の開発には育種素材となる多様な特性を有する植物遺伝資源の確保が不可欠です。耐乾性や耐病性等のこれまでにない特性を有する植物遺伝資源の確保のためには、海外における探索と収集が必要であり、東南アジアや中央アジア諸国等の新たな地域の国々と連携体制を構築し、海外の植物遺伝資源の収集・保存・提供を促進しています。
(スマート育種支援システムやゲノム編集技術の活用等を推進)
従来の交配による品種の開発には、多数の組合せによる交配を行い、子世代の多くの個体を栽培し、その中から優良な形質を持つ個体を選抜すること等から、10年以上の長い期間と多大な労力が必要です。
このため、農林水産省では、これまで、病害抵抗性等の優良な形質を持つ個体を早期に判別できる目印となる特定のDNA配列(DNAマーカー)の開発等により、品種開発の迅速化・効率化を図ってきました。
近年、食料安全保障や気候変動等に対応できる優良な品種の開発と普及の迅速化がますます重要となっていることから、ゲノム情報等のビッグデータとAI等を活用し、最適な交配組合せの予測や幼苗の葉のDNAを用いた将来の形質の予測等により、品種開発の迅速化・効率化を図るスマート育種支援システムの構築を推進しています(図表2-10-4)。

また、近年では天然毒素を低減したばれいしょを始め、ゲノム編集技術(*1)を活用した様々な研究が進んでいます。一方、ゲノム編集技術は新しい技術であるため、理解の促進が必要です。農林水産省では、ゲノム編集技術を活用した現場を体験できるオープンラボ交流会やシンポジウムの実施、ゲノム編集技術を分かりやすく解説した漫画等のコンテンツを作成したほか、大学や高校に専門家を派遣して出前講座等を行うなど、消費者に研究内容を分かりやすい言葉で伝えるアウトリーチ活動を実施しています。
*1 自然で起きるランダムな突然変異を狙った場所で起こすことで、ある生物がもともと持っている遺伝子を効率的に変化させる技術
(新たな品種導入に向けた現場での取組を促進)
病気に強い品種や多収品種等の新しい品種の導入に当たっては、現場での普及を推進していくことが必要です。
例えば高温耐性に加えて多収性やいもち病抵抗性も備えた水稲品種「にじのきらめき」は、開発段階から県と連携した実証圃(じっしょうほ)の設置や技術指導等を行うことにより、6県(*1)において奨励品種に採用されるなど、作付けが拡大しています。また、平成30(2018)年から発生が拡大したサツマイモ基腐病(もとぐされびょう)に対して抵抗性を持ち、焼酎加工適性が高く、でん粉の原料用としても適しているカンショ品種「みちしずく」は、鹿児島県及び宮崎県において、県、生産者、研究機関が連携して従来品種との置換えに取り組み、令和6(2024)年には1千haを超える普及につながりました。
*1 令和7(2025)年3月末時点で、茨城県、群馬県、山梨県、静岡県、和歌山県、佐賀県の合計6県
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




