第4節 地域資源を活用した事業活動の促進
農山漁村が将来にわたって維持・発展していくためには、6次産業化の取組に加え、他分野との組合せの下で農山漁村の地域資源をフル活用する地域資源活用価値創出(*1)の取組により、農村における所得の向上と雇用機会の確保を図るとともに、地域に豊富に存在するバイオマスや再生可能エネルギーを有効活用することが重要です。
本節では地域資源活用価値創出とバイオマス・再生可能エネルギーの活用を図る取組について紹介します。
*1 旧「農山漁村発イノベーション」
(1)地域資源活用価値創出の取組の推進
(6次産業化の取組を発展させた地域資源活用価値創出の取組を推進)

農山漁村において人口減少・高齢化が進む中、農林漁業関係者だけで地域の課題に対応することが困難になってきており、これまで農林漁業に携わっていなかった多様な主体を取り込み、農山漁村の活性化を図っていくことが重要となっています。
農山漁村における所得の向上に向けては、農林漁業所得と農林漁業以外の所得を合わせて一定の所得を確保できるよう、多様な就労機会を創出していくことが重要であることから、従来の6次産業化の取組を発展させ、農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、観光・旅行や福祉等の他分野と組み合わせて付加価値を創出する「地域資源活用価値創出」の取組を推進しています(図表6-4-1)。
農林水産省では、農林漁業者や地元企業等多様な主体の連携を促しつつ、商品・サービス開発等のソフト支援や施設整備等のハード支援を行うとともに、全国及び都道府県単位に設けた地域資源活用・地域連携都道府県サポートセンターを通じて、専門家派遣等の取組を支援しています。また、各地の優良事例を収集し、全国への横展開等を図ることとしています(図表6-4-2)。
さらに、地域資源を活用した多様なビジネスの創出を支援するため、起業促進プラットフォーム「INACOME(イナカム)」の運営を通じて、地域資源を活用したビジネスコンテストや起業支援セミナーの開催、地域課題の解決を望む地方公共団体と企業とのマッチングイベント等の取組を実施しています。

(事例)地域資源活用価値創出により、関係人口を創出(高知県)
(1)様々な分野で地域資源を活用

高知県黒潮町(くろしおちょう)の特定非営利活動法人NPO砂浜美術館(すなはまびじゅつかん)は、アート、スポーツ、防災といった様々な分野において、地域内の食材や資源を積極的に活用することにより、関係人口の創出に取り組んでいます。同法人の職員の約3割は町外出身となっており、同町の海や砂浜といった自然の魅力等に惹かれて活動を始めました。
(2)アート、スポーツ、防災といった様々な分野の取組を推進

Tシャツアート展
資料:特定非営利活動法人NPO砂浜美術館
アート分野では、長さ約4kmの砂浜を美術館に見立て、自然を活かした四季折々のイベントを開催しています。代表的なイベントである「Tシャツアート展」では、約1千枚のデザイン画や写真をTシャツに印刷して砂浜に展示しており、展示等の運営は、県外から参加するボランティアスタッフとともに行っています。
スポーツ分野では、砂浜に隣接している高知県立土佐西南大規模(とさせいなんだいきぼ)公園を活用した合宿やスポーツ大会を開催しています。このようなイベント時には、中山間地域の住民が運営する集落活動センターへ依頼し、地元の食材を使用した食事の提供や地域住民との交流等を行っています。令和5(2023)年度のスポーツツーリズムでの宿泊者数は1万5,043人となり、平成30(2018)年度から約3千人増加しました。
また、防災分野では、南海(なんかい)トラフ地震の津波予測をきっかけに「防災学習プログラム」を実施しており、併せて同プログラムには、ホエールウォッチングやかつおのたたき作りといった自然の恵みを感じることができる体験も組み入れ、自然の脅威と恵みの両面を理解し学習できる仕組みづくりや、中高生の教育旅行の受入れにも取り組んでいます。
(3)ふるさとに誇りを持ち、魅力を自慢できる事業を展開
同法人は、高齢化や地域の事業者が減少していく中、関係人口を創出しながら、地域の担い手をどのように確保していくかを課題と考えています。また、地域の子供たちがふるさとに誇りを持ち、同町の自然の美しさや住民の温かさといった魅力を自慢できるような町にする事業を展開していくこととしています。
(6次産業化による農業生産関連事業の年間総販売金額は2兆2,083億円)

データ(エクセル:27KB)
地域の農林漁業者が、農林水産物等の生産に加え、加工・販売等を行う6次産業化の取組も引き続き推進しています。6次産業化に取り組む農業者等による加工・直売等の販売金額は、近年横ばい傾向で推移しています。令和5(2023)年度の農業生産関連事業の年間総販売(売上)金額は、農産物直売所等の増加により前年度に比べ318億円増加し2兆2,083億円となっています(図表6-4-3)。
また、六次産業化・地産地消法(*1)に基づく総合化事業計画(*2)の認定件数は、令和7(2025)年3月末時点の累計で2,646件となっています。
*1 正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
*2 六次産業化・地産地消法に基づき、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林水産物や副産物(バイオマス等)の生産とその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画
(農村への産業の立地・導入を促進)
農林水産省では、農業と産業の均衡ある発展と雇用構造の高度化に向けて、農村地域への産業の立地・導入を促進するため、農村産業法(*1)に基づき、都道府県による導入基本計画、市町村による導入実施計画の策定を推進するとともに、税制等の支援措置の積極的な活用を促しています。
令和6(2024)年3月末時点の市町村による導入実施計画に位置付けられた計画面積は約1万8千haであり、同計画において、産業を導入すべき地区として定められた産業導入地区における企業立地面積は全国で約1万3,900ha、操業企業数は6,935社、雇用されている就業者は約46万人となっています。
*1 正式名称は「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」
(地域の稼ぐ力の向上を促進)
近年、特定の地域に拠点を置き、地域の特産品や観光資源を活用した商品・サービスの域外への販売を主たる事業とする「地域商社」と呼ばれる事業体が全国各地で見られており、地域経済の活性化や地域の稼ぐ力の向上に重要な役割を果たしています。
内閣官房及び内閣府では、地域資源の価値の向上等により、地方の社会的課題の解決に資する取組を行う者(地域商社を含む)を支援するため、ポータルサイトを開設し、経営課題の解決に向けた優良事例の普遍化や情報共有を支援しています。
また、農林水産省では、食品等の物流改革に向けた取組として、物流の標準化、デジタル化・データ連携等の支援や、GFP(*1)の活用による輸出に取り組む事業者支援、農林漁業者・食品事業者と地域商社の販路拡大支援や商材の紹介等を行っています。
*1 第3章第2節を参照
(2)バイオマスや再生可能エネルギーの利活用の推進
(農山漁村や都市部におけるバイオマスの総合的な利用を推進)
持続的に発展する経済社会の実現や循環型社会の形成には、みどり戦略に基づき、農林水産業から生じる家畜排せつ物や林地残材(りんちざんざい)、食品産業から生じる食品廃棄物等のバイオマスを製品やエネルギーとして活用するなど、地域資源の最大限の活用を図ることが重要であり、地域の未利用資源等を地域の農林漁業関連施設等で循環利用する「農林漁業循環経済地域」の取組を進めることとしています。
令和4(2022)年9月に閣議決定した「バイオマス活用推進基本計画」では、農山漁村だけでなく都市部も含め、新たな需要に対応した総合的なバイオマスの利用を推進することとしており、地域の様々な関係者間の連携により、地域主体でバイオマスの活用を推進し、持続可能な循環型社会の構築を目指しています。同計画では、全都道府県において、令和12(2030)年度までにバイオマス活用推進計画を策定し、全市町村においても、バイオマス関連計画を活用することとしています。このため、農山漁村や都市部に存在するバイオマスについて、種類ごとの利用率の目標を設定し、堆肥や飼料等の既存の利用に支障のないよう配慮しつつ、バイオガス等の高度エネルギー利用を始め、より経済的な価値を生み出す高度利用を推進しています。
また、地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築を図ることを目的として、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境に優しく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域を、関係府省が共同で「バイオマス産業都市」として選定しています。令和6(2024)年度においては新たに1市をバイオマス産業都市に選定し、選定された地域は、累計で104市町村となりました。バイオマス産業都市に選定された地域に対して、地域構想の実現に向けた各種施策の活用、制度・規制面での相談・助言等を含めた支援のほか、バイオマスの活用を促進する情報発信、技術開発・普及、人材の育成・確保等を行っています。
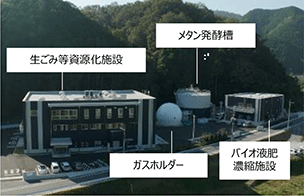
中山間地域で資源循環と農業の
持続的発展を図る施設
資料:岡山県真庭市

バイオマスの活用の推進
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/
(事例)もみ殻や稲わらを活用して、循環型社会の形成を目指す(秋田県)
(1)「自然エネルギー100%の村づくり」を目指す

秋田県大潟村(おおがたむら)では、基幹産業である稲作から生じるもみ殻や稲わらといったバイオマスを活用した循環型社会の形成に取り組み、「自然エネルギー100%の村づくり」を目指しています。
(2)バイオマス利用の効率化・高度化のために2つの事業を展開
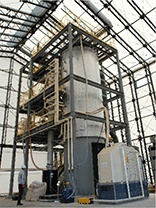
メタン発酵施設
資料:秋田県大潟村
同村で発生するバイオマスの大部分はもみ殻や稲わらです。これらは農地還元や暗渠(あんきょ)資材へ利用されていますが、バイオマス利用の更なる効率化・高度化を図るために2つの事業に取り組んでいます。
1つ目の「もみ殻燻炭(くんたん)プロジェクト」では、もみ殻をボイラーで燃焼させ、公共施設に熱供給して同村内の熱需要を賄うほか、燃焼後の燻炭は同村の農家向けに土壌改良剤として販売することを目指しています。
2つ目の「バイオガスプロジェクト」では、稲わら等をメタン発酵施設でバイオガスに変換するほか、バイオガス発生後に残った液肥は有機肥料として同村内の水田や畑で使用する予定です。水田へのすき込みによる温室効果ガス発生を避けることで地球温暖化対策に貢献できることに加え、液肥の利用を通じて循環型農業を実現することが期待されています。
今後は、実用化に向けてプロジェクトを展開していくとともに、生産者の収益向上やバイオマスを活用して栽培した米のブランド化に取り組み、稲作とその生産者を支える新たな仕組みづくりに貢献していくこととしています。
(バイオマスの利用率は76%)

データ(エクセル:26KB)
令和3(2021)年度のバイオマス利用率は76%となっています(図表6-4-4)。バイオマス活用推進基本計画では、対象とするバイオマスの種類を拡大し、令和12(2030)年には、バイオマスの年間産出量の約8割を利用することとしています。
(バイオマスを活用した技術開発が進展)
製品やエネルギーの各分野において、バイオマスを活用した技術開発が進められており、バイオマス活用推進基本計画では、これらの社会実装を見込むイノベーションを通じて、製品やエネルギーの産業化が進展することを前提とし、製品・エネルギー市場のうち、国産バイオマス関連産業の市場シェアを令和元(2019)年の約1%から令和12(2030)年に約2%に拡大することを目指すこととしています。
このうち、航空分野の脱炭素化に向けたSAF(*1)の導入促進については、令和12(2030)年時点の本邦航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換えるという目標の達成に向け、「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会」において議論が進められています。導入促進に当たっては、国際競争力のある価格の国産SAFの開発・製造や原料のサプライチェーンの構築等が課題となっており、それら課題の解決に向け、引き続き官民が連携していく必要があります。なお、足下の原料である廃食用油については、飲食店等から出る事業系のものはそのほとんどが回収され、配合飼料等の原料として再利用されていますが、近年では海外輸出も増加していることから、既存需要に配慮しつつ、できる限り国内で有効に再利用を図っていくことが重要です。他方、家庭から出る廃食用油は、SAFを始め、石けんや塗料、バイオディーゼル燃料等の様々な製品の原料として再利用することができますが、回収が進んでいない状況です。
農林水産省では、家庭から出る廃食用油の循環利用に向けた機運を高めるため、令和6(2024)年度に「廃食用油×MAFFチャレンジ」を実施し、廃食用油が再生資源として活用されるよう回収に向けた取組を呼び掛けるとともに、農林水産省本省に勤務する職員の家庭から出た廃食用油の回収に取り組みました。
さらに、バイオマス製品としてのマテリアル利用は加速しており、市場規模の成長が期待されています(図表6-4-5)。植物等のバイオマスを1割以上含む製品であることを示すバイオマスマークの認定商品数は令和5(2023)年12月時点で約1,900件にのぼり、包装資材や日用品といったバイオマス素材を使う製品は広がりを見せています。

データ(エクセル:27KB)
*1 Sustainable Aviation Fuelの略であり、持続可能な航空燃料のこと
(バイオマスの活用による農山漁村の活性化や所得向上に向けた取組を推進)
意欲ある農林漁業者を始め、地域の多様な事業者が、農山漁村に由来する資源と産業を結び付け、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す農山漁村の6次産業化は、我が国の農山漁村を再生させるための重要な取組です。
農林水産省では、みどり戦略に基づき、バイオマスの持続的な活用に向け、その供給基盤である食料・農林水産業の生産力向上と持続性を確保するとともに、重要な地域資源である農地において、荒廃農地の発生防止の観点から資源作物の栽培の可能性についても検討を進めることとしています。
また、更なるバイオマスの活用に向けた新たな取組を関係府省等と連携し推進することにより、地域の活性化や所得向上を推進することとしています。
(農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成した市町村数は99に増加)

データ(エクセル:27KB)
みどり戦略においては、温室効果ガス削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入に取り組むこととしています。それに伴い、農山漁村が持つ食料供給機能や国土保全機能の発揮に支障を来さないよう、農林水産省では、農山漁村再生可能エネルギー法(*1)に基づき、市町村、発電事業者、農業者等の地域の関係者から成る協議会を設立し、地域主導で農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を行う取組を促進しています。
農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成し、再生可能エネルギーの導入に取り組む市町村数については、令和5(2023)年度は前年度に比べ9市町村増加し99市町村となりました(図表6-4-6)。また、農山漁村再生可能エネルギー法を活用した再生可能エネルギー発電施設の設置数も年々増加しており、設備整備者が作成する設備整備計画の認定数は、令和5(2023)年度末時点で120となりました。
*1 正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」
(営農型太陽光発電の取組面積が拡大)
農地に支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う営農型太陽光発電は、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立し、適切に取り組めば、作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できる有用な取組です。その取組面積については年々増加しており、令和4(2022)年度は前年度に比べ222ha増加し1,209haとなりました(図表6-4-7)。
一方、太陽光パネル下部の農地において作物の生産がほとんど行われないなど、農地の管理が適切に行われず営農に支障が生じている事例も増えており、その件数は同年度末時点で存続している取組のうち約2割となっています(図表6-4-8)。
事業者に起因して支障が生じている取組に対しては、農業委員会又は農地転用許可権者により、事業者に対する営農状況の改善に向けた指導が行われていますが、指導に従わなかった結果、事業の継続に必要な農地転用の再許可が認められないようなケースも発生しています。
このため、太陽光パネルの下部の農地における営農が適切に行われるよう、農地法や再エネ特措法(*1)等の関係法令に違反する事例に対して、厳格に対処するなどの対応が必要であり、令和6(2024)年3月に一時転用の許可基準等の法令への位置付けのほか、ガイドラインの作成を行いました。営農型太陽光発電については、望ましい取組を整理するとともに、適切な営農の確保を前提に市町村等の関与の下、地域活性化に資する形で推進することとしています。
*1 正式名称は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






