特集3 スマート農業技術の活用と今後の展望
スマート農業技術の活用は農作業の効率化、農作業における身体の負担軽減、農業の経営管理の合理化等の効果が期待されるとともに化学肥料や化学農薬の使用低減等の環境負荷低減にも役立つものです。
農林水産省は、平成25(2013)年に「スマート農業の実現に向けた研究会」を設置し、スマート農業の将来像と実現に向けたロードマップを取りまとめ、これら技術の農業現場への速やかな導入に必要な施策を推進してきました。この十数年間で我が国のスマート農業は着実に進展しています。
一方、農業者の減少下においても生産水準が維持できる生産性の高い食料供給を確立するためには、スマート農業技術に適した生産方式への転換を図りながら、その現場導入の加速化と開発速度の引上げを図ることで生産性の向上を促進する必要があります。
本特集では、令和6(2024)年10月に施行された「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づく取組やスマート農業技術の将来の展望等について紹介します。
(1)スマート農業技術の活用の推進
(スマート農業の現状)
ロボット・AI(*1)・IoT(*2)等の情報通信技術を活用した「スマート農業技術」により、農業の生産性向上等を図る取組が農業の現場で広がりを見せています。例えばドローンによる農薬等の散布面積は、近年急速に拡大傾向で推移しており、令和5(2023)年度には、109万7千haとなっています。
また、圃場(ほじょう)内を自動走行するロボットトラクタやスマートフォンで遠隔地から水田の水管理を行うことが可能なシステム、位置情報と連動することで作付情報や営農計画等を電子化することが可能な営農管理システム等の農作業を自動化・省力化する取組や、ドローン等から得られたセンシングデータに基づき農作物の生育・病虫害予測を行い、可変施肥や防除、出荷管理等に活かすなど高度な農業経営を行う取組が各地で展開されています。これらの技術を活用することで、農業者が作業に取り組みやすく生産活動の主体になることも容易になります。

農業新技術_製品・サービス集
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/products.html
*1 Artificial Intelligenceの略
*2 Internet of Thingsの略で、モノのインターネットのこと
(事例)土壌消毒剤の使用低減に向け、AIを活用(香川県)
(1)環境にやさしい農業の推進のため土壌消毒剤の使用低減に向けた実証に挑戦
香川県高松市(たかまつし)の香川県(かがわけん)グリーン農業(のうぎょう)コンソーシアムでは、ブロッコリー等のアブラナ科野菜の土壌病害である根こぶ病に対し、AIを活用して発病リスクの評価を行うアプリ等の実証を令和4(2022)年から行っています。アプリは、同年4月から販売されており、全国での普及を目指しています。
(2)AIを活用し発病リスク評価を実施
根こぶ病の防除については、一般的に防除暦に基づく土壌消毒剤の使用等が行われていますが、同コンソーシアムでは環境への負荷低減や安定的な生産のために、土壌の実態に応じた効率的かつ、効果的な防除が必要な状況にありました。
土壌消毒剤の使用低減には、圃場単位で病害の発生のしやすさを診断し、対策手段を講ずる土壌病害管理法「HeSoDiM(*)(ヘソディム)」が有効です。一方、熟練指導者の下でないと取組が難しいなどの課題があったことから、同管理法の考え方に基づき、AIを活用してリスク評価を行う専用アプリ「HeSo+(ヘソプラス)」が国立研究開発法人農業(のうぎょう)・食品産業技術総合研究機構(しょくひんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうきこう)(以下「農研機構」という。)を代表研究機関とし、香川県等も参画する研究プロジェクトにおいて開発されました。
同アプリは、生産者が根こぶ病の菌密度、土壌pH、水中沈底(ちんてい)容積等の診断項目を入力するだけで、圃場ごとの発病リスクを判断し、発病リスクに応じた対策を提案することから、発病リスクが低い場合は防除対策のレベルを下げるなどの経営判断が可能となります。
(3)今後も適切な防除を推進
令和4(2022)年度の実証結果では、過剰防除が行われている圃場数が全体の13%程度あることが分かりました。また、令和5(2023)年度には発病リスクが高いと判断された圃場に対し、あらかじめ土壌改良等の対策を行い、収量に影響が生じない程度にまで根こぶ病の発生を抑えることに成功しています。
同コンソーシアムでは、適切な防除対策を選択する考え方を広めていくため、実証終了後も栽培体系マニュアルや講習会等を通じて生産者に対し「ヘソプラス」等を活用したヘソディムの普及啓発を行うこととしています。
* Health checkup based Soil-borne Disease Managementの略で、健康診断に基づく土壌病害管理のこと


ブロッコリー根こぶ病
資料:香川県グリーン農業コンソーシアム
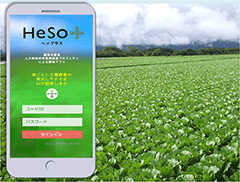
HeSo+(ヘソプラス)の画面
資料:農研機構
(事例)ICTを活用したきゅうりのデータ駆動一貫体系の実現(愛知県)
(1)環境・生育データを用いた高度な栽培を実施

きゅうり栽培では、日によって生産量が大きく変動するため、産地においては生産性や品質の向上に加え、安定した出荷量の確保が販売面における重要な課題となっています。
愛知県西尾市(にしおし)の西三河(にしみかわ)農業協同組合では、令和元(2019)年度から、関係機関と連携し、スマート農業実証プロジェクトに取り組み、環境データや植物生体データの収集・分析によるハウス環境の最適化、養液栽培データの土耕栽培への活用、きゅうりの生育予測に基づく栽培管理作業の効率化に向けた取組を実施しています。
(2)様々な取組を通じた生育の最適化・販売の強化

きゅうりの土耕栽培
資料:西三河農業協同組合
同組合では、ハウス内の温度や湿度、二酸化炭素濃度といった環境データを収集し、カーテンによる保温や遮光等を自動で制御することで生育とエネルギー使用量の最適化を図っています。
また、高騰する肥料価格に対応して土壌溶液の分析を行っています。以前は土壌分析に2~3週間を要していましたが、令和5(2023)年作から土壌溶液採取器と簡易分析器を導入し、土壌中の肥料濃度を短時間で確認できるようにしました。
さらに、個々の生産者の生育データを基に、同組合全体の合計出荷量を予測するモデルの構築にも取り組んでいます。産地として出荷量を予測することで納品に向けた出荷量の調整や新規の取引先の確保といった販売面での強化につながることが期待されます。
(3)データを活用して連携し、安定した産地として維持
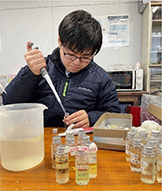
土壌溶液の分析
資料:西三河農業協同組合
データを利用した産地の維持・発展には、生産者と関係機関との勉強会も重要です。オンラインや対面での意見交換を繰り返すことで、栽培技術の向上や環境制御機器の高度利用を目指しています。また、生育状況が数値で可視化されることで、生産者同士や従業員との間でデータを使ったコミュニケーションが可能となり、生育状況等の詳細な認識や的確な栽培指導につながっています。
同組合では、これまで蓄積されたデータを更に活用して効率的な栽培体系を確立し、規模拡大を支援することで、安定した産地を維持していくこととしています。
(スマート農業実証プロジェクトにおいて、作業の省力化や負担軽減の効果を確認)
農林水産省は、実際の生産現場におけるスマート農業技術の効果を明らかにするため、令和元(2019)年度以降、全国217地区で生産性や経営改善に関する実証を行う「スマート農業実証プロジェクト」(以下「実証プロジェクト」という。)を展開してきました。
実証プロジェクトでは、水田作、畑作、露地野菜、施設園芸、花き、果樹、茶、畜産等の様々な品目でスマート農業の普及状況や政策課題に合わせた実証を行い、その結果、農業機械の自動運転や遠隔操作による労働時間の削減、栽培管理への環境・生産データの活用による収量・品質の向上、化学農薬・化学肥料の使用低減、スマート農業機械のシェアリングや農業支援サービス事業体の活用による導入コストの低減等の効果が様々な品目で確認されました。
また、スマート農業技術の活用により、重労働が軽減され、熟練農業者並みの速度・精度での作業が可能となることで農作業のハードルが下がり、活躍できる機会をもたらすことから、経営面積の拡大や女性、高齢者、新規就農者、学生アルバイトも含めた多様な人材が関わる経営の実現にもつながりました。

スマート農業実証プロジェクト
URL:https://www.affrc.maff.go.jp/docs/
smart_agri_pro/smart_agri_pro.htm
実証プロジェクトにおいて確認されたスマート農業技術の導入効果については、例えば水田作では総労働時間が平均で9%削減、単収が平均で9%増加したほか、慣行区との正確な比較が可能な実証地区の約3割において、10%以上の労働時間の削減効果が確認され、20%以上の削減効果が得られた事例も見られました。
また、技術別に見ると、平均作業時間が農薬散布用ドローンで61%、自動水管理システムで80%、直進アシスト田植機で18%、それぞれ短縮されたこと等が明らかになっています(図表 特3-1)。

データ(エクセル:25KB)
(スマート農業の実装に当たって生産方式の転換等も必要)
実証プロジェクト等を通じて、スマート農業技術の導入による効果が確認された一方、様々な課題も明らかになっています。
例えば果樹や野菜では、収穫等の人手に頼る作業が多くスマート農業技術の開発が不十分な領域があるため、開発の促進を図る必要があります。また、従来の栽培方式の下では、例えば狭い畝間(うねま)に機械が入らない、手作業の収穫を前提とした果樹の樹形にしているなど、このままではスマート農業技術の導入効果が十分に発揮されないことから、スマート農業技術に適した生産方式への転換を図ることも必要です。さらに、スマート農業機械等の導入にはコストが高いことやスマート農業機械等を扱える人材が不足していること等の課題も判明しました。
このような課題の解決には、技術開発・供給側と生産現場側の両方の歩み寄りが求められており、スマート農業技術に適した生産方式への転換を図りながら、開発ハードルを下げつつ、開発が特に必要な分野を明確化して多様なプレイヤーの参画を進めることが重要です。また、スマート農業技術を普及させるための環境整備を併せて進めていく必要があります。
(事例)スマート農業技術に適した生産方式への転換(静岡県)
(1)人手不足や輸入品に対抗するためスマート農業に取り組む
静岡県静岡市(しずおかし)の株式会社鈴生(すずなり)は、加工・業務用ブロッコリーの生産拡大を目指し、輸入品との競争や人手不足に対応するため、令和2(2020)年度からスマート農業機械を導入する実証プロジェクトに取り組みました。同プロジェクトでは、自動操舵(そうだ)トラクタやブロッコリー収穫機等の導入を通じ、全体の作業時間が55%削減されるなど大幅な省力化に成功しましたが、新たな課題に直面しました。
(2)スマート農業技術に適した品種の導入と作業の見直しにより収穫量向上へ
同プロジェクトで明らかとなった課題の一つが、従来の生産方式との適合性です。プロジェクトで導入した自動収穫機は、手作業で行っていた収穫作業の労働時間を50%以上削減することに成功しましたが、カット時に花蕾(からい)(*)を傷つけてしまうことや、大きさにばらつきのあるブロッコリーも収穫されることから、歩留りが低下しました。
同社では、この課題に対応するため、軸の部分が長く機械収穫に適した品種を選定するなどの工夫に取り組むとともに、生育が早い株については先に手作業で収穫するなど、作業方式の見直しも行い、令和4(2022)年度の10a当たりの収穫量は令和2(2020)年度と比較し大幅に改善しています。このほかにも、花蕾の切り分け方法を変えることで新たなニーズに応えるなど、スマート農業技術に適した生産方式への転換と販路の拡大を続けることとしています。
* ブロッコリーの大きなドーム状の部分


ブロッコリー収穫機
資料:株式会社鈴生

スマート農業機械をフル活用する
ために砕石作業を請け負う
コントラクター事業も開始
資料:株式会社鈴生
(2)スマート農業技術活用促進法に基づく取組
(スマート農業技術活用促進法が施行)

スマート農業技術活用促進法について
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo
/smart/houritsu.html
政府は、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」を第213回通常国会に提出し、同法案は令和6(2024)年6月14日に成立、同年10月1日に施行されました。スマート農業技術活用促進法は農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「生産方式革新実施計画」と「開発供給実施計画」の二つの計画認定制度を設けており、これらの認定を受けた農業者や事業者は税制特例措置や金融等の支援措置を受けることができます(図表 特3-2)。

(スマート農業技術に適した生産方式の転換を推進)
従来の生産方式のまま単にスマート農業技術を導入するだけでは、スマート農業技術の効果が十分に発揮されないという課題に対応するため、生産方式革新実施計画ではスマート農業技術の活用と新たな生産の方式の導入を併せて行う農業者の取組を後押しすることとしています。例えば野菜の自動収穫機の導入に併せて機械収穫の適性が高い野菜品種の導入や枕地(まくらじ)・畝間の確保を行うなどのスマート農業技術の効果を十分に引き出す生産現場の取組を認定することで、農業者の減少下でも生産水準が維持できる生産性の高い農業の実現を図っていくこととしています。
(スマート農業技術の重点開発目標を設定)
スマート農業技術活用促進法に基づき、農林水産省は、令和6(2024)年9月に「基本方針(*1)」を定め、この中で、水田作や畑作、野菜作、果樹・茶作、畜産・酪農等の営農類型ごとに省力化又は高度化の必要性が特に高いと認められるスマート農業技術等について「開発供給事業の促進の目標」(以下「重点開発目標」という。)として明示し、これらを令和12(2030)年度までに実用化することを目指しています。例えば「果樹・茶作」においては、自動収穫機や台車ロボット等により収穫及び運搬作業の労働時間を60%削減するという目標が掲げられています。また、重点開発目標の達成に資するスマート農業技術等の開発から供給までを行う事業者等の取組を、スマート農業技術活用促進法の計画認定制度を通じた税制特例措置や金融等の支援措置により後押しすることとしています。
*1 正式名称は「生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針」
(スマート農業技術の活用の促進に向けた関係者との連携強化)
スマート農業技術の開発及び普及の好循環を形成していくため、農業者、農業支援サービス事業者、スマート農業技術の開発を行う事業者、地方公共団体、農業関係団体、大学等が参加する、「スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA(イプサ)(*1))」を設置し、農業者とスタートアップやサービス事業者等のマッチング支援、国内外のスマート農業技術に係る研究開発や実用化の動向等の情報の収集・発信・共有、技術指導の研修等の活動を実施することとしています。
また、スマート農業技術の活用の促進に向けては、農村における情報通信環境の整備やスマート農業技術を使いこなせる人材の育成、サイバーセキュリティ対策等の関係府省庁との連携が重要です。令和6(2024)年6月に設置された「スマート農業技術の活用の促進に関する関係府省庁連絡会議」では、関係府省庁連携の下、スマート農業技術の活用の促進に関する取組を一体的に進める活動を行っており、例えば高度情報通信ネットワークの整備においては、総務省が中心となり運営する通信基盤整備推進のための地域協議会に農林水産省が参加し、地域におけるニーズを通信事業者等に伝えるなどの取組を行っています。
*1 Innovation Promotion Conference for Smart Agricultureの略
(3)スマート農業技術の活用の促進に係る現場での取組
(スマート農業の普及)
令和6(2024)年度にスマート農業技術活用促進法の認定を受けた取組については、生産方式革新実施計画が22件、開発供給実施計画が8件となりました。例えば生産方式革新実施計画の認定を受けた「しかりべつ高原(こうげん)野菜出荷組合加工キャベツ部会」では、加工・業務用キャベツの栽培において、「精密出荷予測システム」を通じて得られた収穫時期・収穫量等のデータを、サービス事業者や食品等事業者と共有することで、作業員の計画的な手配や集出荷における予冷庫等の計画的な手配に活用し、コストを削減するとともに、栽培履歴データの分析結果を産地全体の品質・収量の向上に向けた肥培管理に活用し、収益性の向上を図ることとしています(図表 特3-3)。
また、開発供給実施計画の認定を受けた株式会社NTT e-Drone Technologyは、傾斜地のかんきつ防除における労働時間の削減や、衛星やドローンで取得したセンシング結果に連動した可変施肥等による作業の効率化及び環境負荷低減に係る国産大型ドローンの供給を目指しており、計画認定の支援措置として、農研機構の施設等の供用を受け、令和7(2025)年1月から農研機構が供用する圃場においてドローンの飛行試験を開始しています。スマート農業技術の活用は、農業の生産性向上と化学肥料・化学農薬の使用低減の両立によりみどりの食料システム戦略(以下「みどり戦略」という。)の推進にも貢献します。例えば「第11回 ロボット大賞」において農林水産大臣賞を受賞した株式会社NEWGREEN、井関農機(いせきのうき)株式会社等によるアイガモロボットは、ブラシ型のパドルで自動で水田の泥をかき混ぜることにより、化学農薬を使わずに雑草の生長を抑制することができ、水稲の有機農業に役立ちます。ほかにも、障害者の作業をサポートする観点から農福連携の推進等の様々な取組に貢献しています。

(農業支援サービス事業体の育成を推進)
スマート農業技術を活用するには、スマート農業機械の導入コストの高さやスマート農業機械を扱える人材の不足等が課題となるため、専門作業の受注等を行う農業支援サービスの活用を通じて農業機械の「所有」から「利用」への転換を進めることにより、コスト低減を図りつつ、速やかに高度な技術導入を行うことが可能となります。近年、ドローンやIoT等の最新技術を活用して農薬散布作業を代行するサービス、スマート農業機械のレンタル・シェアリングやデータを駆使したコンサルティングといったスマート農業を支える農業支援サービスの取組が生産現場で広がっています(図表 特3-4)。

令和6(2024)年度に実施した調査によると、農業支援サービスを利用している農業の担い手が2,914人、農業支援サービスの利用を希望している農業の担い手が5,077人となっており、どちらも前年度より増加しています(図表 特3-5)。
より多くの農業者が農業支援サービスを利用できる環境を作るためには、事業参入者の更なる拡大に向けて、事業の立上げに当たって作業に必要な農業機械の導入や専門的な人材の育成を推進していく必要があります。また、農業支援サービスが地域で持続的に事業を継続できるものであることも重要です。このため、単一の産地や単一品目でのサービスを、作業時期の異なる複数産地や複数品目に拡大し、通年での需要を確保するなど、サービス事業の事業性の向上等への対応も進めていく必要があります。
このため、農林水産省では、農業支援サービス事業体が請け負う作業に必要な機械導入や機械の操作技術の習得といった人材育成等への支援に加え、事業ニーズの通年確保に向けて産地や品目間をまたいだサービスを展開するモデル的な取組への支援等を行っています。また、農業支援サービス事業体に対する農業者の認知度の向上、農業支援サービス事業体と農業者のマッチング機会の創出を図るため、「農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン」を示し、これに沿って情報表示を行う事業者のサービス内容等を農林水産省のウェブサイト上で公開しています。

データ(エクセル:28KB)
(事例)デジタル技術を駆使したデータ分析サービスを展開(宮崎県)
(1)経営判断をサポートする農業データ分析サービスを展開

宮崎県宮崎市(みやざきし)のスタートアップであるテラスマイル株式会社は、「アジアに競争力のある地域をたくさん創る」を志に、農業生産の盛んな宮崎県で創業しました。同社は、農業経営者の「右腕」になることを目指して自社で開発した農業経営管理クラウドを活用し、各種営農管理システムや各種センサー、農業機械等の点在する営農関連データを一元化・分析し、経営の意思決定に必要な情報を大規模農業法人等に提供しています。
(2)インプットで終わらない、重要なのはデータのアウトプット
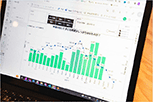
農業経営管理クラウド
資料:テラスマイル株式会社
同社のサービスの強みは、単にデータを集めるだけではなく、見える化できることです。見える化されたデータは、農業経営の的確な判断材料になります。同社のサービスを導入したあるピーマンの産地では、可視化した熟練生産者のノウハウを基にした生産の推進により、生産量が増加したほか、基本的な栽培に関してはパート従業員に任せられるようになったことで、平均単収が20%向上しました。
今後同社は、農業者と小売業者が出荷先・調達先を確保するために必要な互いの情報を提供し、物量・価格の最適化に資することで、両者がwin-winの関係になる仕組みを目指すこととしています。
(食品等事業者との連携による新たな流通・販売等方式の導入)
スマート農業技術による生産性向上には、新たな流通・販売等の方式を導入する食品等事業者との連携も重要です。例えば、農業者が自動収穫機等を用いて一斉収穫・収穫した農産物の圃場からの搬出と加工場までの輸送を一貫して行える鉄コンテナでの出荷を行い、連携する食品事業者が人手を要する選別・調製作業を代替する取組や、農業者が導入する出荷予測システムに併せて、食品事業者が消費者の需要予測システムを導入し、需給マッチングを図る取組等のスマート農業技術を契機に産地と食品事業者が連携する動きが広がっており、今後、フードチェーン全体での連携も期待されています。
生産方式革新実施計画では、新たな流通・販売等の方式を導入する食品等事業者の取組を計画認定とそれに伴う支援措置の対象とすることで、食品等事業者との連携を通じた生産性の向上を推進することとしています。
(スマート農業技術の研究開発の推進)
農林水産省では、実証プロジェクト等によって明らかになった課題を踏まえ、開発が必ずしも十分ではない品目や分野を対象に、生産現場で求められるスマート農業技術の研究開発を推進しており、令和6(2024)年度は、「戦略的スマート農業技術の開発・改良」において新たに13課題を採択しました。
さらに、スマート農業技術活用促進法に基づいて定めた重点開発目標の達成に向け、スマート農業技術活用促進法の開発供給実施計画の認定を受けた事業者等が取り組むスマート農業技術の研究開発等を推進するため、特に重要かつ高度な研究開発については、農研機構と民間事業者の役割分担の下、開発・供給期間の短縮とともにユーザー目線での技術改良を促進することとしています。くわえて、現場における生産性の高い農業を実現するため、スマート農業技術の導入効果を発揮させる栽培方式の確立や転換に向けた取組や、中山間地域等に対応したスマート農業技術の開発・実用化等について推進することとしています。
(スマート農業教育の充実)
農業現場においてスマート農業技術の活用が進む中、今後の我が国の農業の担い手を育成する農業大学校(*1)や農業高校等においても、スマート農業を学ぶ機会を充実させることが重要です。

農業大学校等におけるスマート農業教育について
URL:https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/
smart_kyoiku.html
農林水産省では、農業大学校や農業高校等におけるスマート農業の実践的な教育が行われるよう、無人田植機等を利用した栽培実証の実施やドローンの飛行訓練を通じた操作・活用方法の習得等のスマート農業のカリキュラム強化、GPSアシスト機能付きトラクタや自走式草刈機、ハウス内の環境測定機器等の、研修用農業機械・農業設備の導入、農場における無線LAN環境の整備、現場実習や出前授業の実施等に対する支援を行っています。また、授業や学生・生徒の自習等に活用できるオンライン教材や指導用の補助教材を作成し、教員等がスマート農業に関する知識や技術を習得できる研修を実施しています。
これらのスマート農業教育の取組を通じ、例えば「全国農業高校・農業大学校デジタルコンテスト」スマート農業部門で農林水産技術会議会長賞を受賞した大分県立大分東(おおいたひがし)高等学校では、いちごの品質をAIにより判定するシステムを開発するなど、学生によるスマート農業技術の活用に向けた取組が活発に展開されています。また、このような教育や研修を受けた人材が、スマート農業の現場で活躍するケースも見られています。
さらに、文部科学省と連携し、農業高校や大学農学部、高等専門学校等において、スマート農業技術に係る教育・実習等を推進することとしています。
*1 第2章第3節を参照
(4)今後の展望
(スマート農業の更なる進展・普及に向けて)
農業は、食料を安定供給する「国の基(もとい)」ですが、我が国の農業を取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少や高齢者の引退により農業者の急激な減少が避けられない中で、持続的な食料供給を図るためには、スマート農業技術の活用の促進による、生産性向上の加速化が不可欠です。
農林水産省では、スマート農業技術活用促進法に基づく計画認定に加え、同時にスタートアップも含めた多様なプレイヤーによる研究開発・実用化やスマート農業技術の効果を十分に引き出すことのできる生産・流通・販売方式への変革を後押ししています。また、経営、技術等で農業者をサポートする農業支援サービス事業体の育成・活動を促進し、スマート農業機械の導入コスト抑制を図るとともに、スマート農業技術の導入に資する農地の大区画化や、関係府省庁とも連携した情報通信環境の整備、スマート農業技術を活用する人材の育成、サイバーセキュリティ対策を図ることとしています。
さらに、農業者や研究者等の多様なプレイヤーが参画するIPCSAにおいて、経営に与える効果の分析や技術の客観的な評価手法の検討、成功・失敗事例の共有等の活動を推進し、スマート農業技術の開発及び普及の好循環を形成することとしています。
農業の生産性向上には、農業者がデータを活用し、自ら栽培管理や農業経営の簡易化・高度化に取り組むとともに、長年農業に従事されてきた方々の知識や経験、ノウハウを形式知化して継承していくことも不可欠です。農研機構が運用する農業データ連携基盤「WAGRI(ワグリ)(*1)」を通じて多くのAPI(*2)が民間事業者に提供され、農業者向けサービスの開発が進んでいますが、今後、農業者がそれぞれの経営形態に応じてこれらのサービスを選択できるよう、スタートアップ等によるサービスの拡大・強化を図るとともに、生成AIを用いたサービスの開発も推進することとしています。
このような取組を通じ、農業の関係者が、スマート農業技術を活用した、経営規模の拡大や後継者の確保・育成、環境負荷の低減といった、未来に向けた新たな農業のやり方に取り組んでみようと思える環境づくりを進めることとしています。
*1 農業データプラットフォームが、様々なデータやサービスを連環させる「輪」となり、様々なコミュニティの更なる調和を促す「和」となることで、農業分野にイノベーションを引き起こすことへの期待から生まれた言葉(WA+AGRI)
*2 Application Programming Interfaceの略。複数のアプリ等を接続(連携)するために必要な仕組みのこと
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883




