特集2 合理的な価格の形成のための取組を推進
食料の持続的な供給を実現するためには、生産だけでなく、加工、流通、小売等の各段階の持続性が確保される必要があり、また、このことを実現することは消費者の利益にもかなうものです。
生産や流通に係るコストが上昇する中、我が国の農業・食品産業において、そのコストを適切に価格へ転嫁し、食料の持続的な供給を実現するためには、食料システムの各段階でのコストを把握・明確化し、生産から消費に至る食料システム全体で合理的な費用が考慮される仕組みの構築が必要です。また、改正基本法においても、食料の価格形成に当たり持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう必要な施策を講ずること等が明記されています。
以下では、価格転嫁等の動向や、国民の理解と納得が得られる合理的な価格の形成のための取組について紹介します。
(1)農産物と農業生産資材の価格動向と課題
(令和6(2024)年度下半期の農業交易条件指数は基準年を上回る水準で推移)

データ(エクセル:33KB)
農業経営体が購入する農業生産資材価格に関する指数である農業生産資材価格指数については、令和3(2021)年以降、肥料や飼料等の価格高騰により上昇し、令和5(2023)年4月以降は横ばい傾向で推移しており、令和7(2025)年2月時点で123.0となっています(図表 特2-1)。一方、農業経営体が販売する農産物の生産者価格に関する指数である農産物価格指数については、令和3(2021)年以降、ほぼ横ばいで推移していましたが、令和6(2024)年8月以降、米や野菜等の価格が大きく上昇したことを受け、上昇基調で推移しており、令和7(2025)年2月時点では136.0となっています。また、農産物価格と農業生産資材価格の相対的な関係の変化を示す農業交易条件指数については、令和2(2020)年の平均値である100を下回る水準で推移していましたが、令和5(2023)年10月及び令和6(2024)年10月以降は100を上回る水準で推移しています。
(コスト高騰に伴う農産物・食品への価格転嫁が課題)
公益社団法人日本農業法人協会(にほんのうぎょうほうじんきょうかい)が令和5(2023)年9月~6(2024)年2月に実施した調査によると、農業法人の経営課題について、「資材コスト(肥料、飼料、農機等)」や「価格転嫁ができない」等のコストに係る項目が上位を占める結果となりました(図表 特2-2)。

データ(エクセル:28KB)
また、中小企業庁が令和6(2024)年9~11月に実施した調査によると、食品製造業(中小企業)における発注企業から見たコスト増に対する価格転嫁の割合は55.3%となっています(*1)。
農業生産資材や原材料の価格高騰は、農業者や食品企業の経営コストの増加に直結し、最終商品の販売価格まで適切に転嫁できなければ、食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。このため、農業者や製造事業者を始めとする売り手がコスト構造を把握し、買い手に説明できるようにすることで、コストの実態について消費者等の理解を得て、食料システム全体で合理的な費用を考慮した価格形成が行われるよう環境整備を進めていくことが必要です。
*1 中小企業庁「価格交渉促進月間(2024年9月)フォローアップ調査」(令和6(2024)年11月公表)
(円滑な価格転嫁や取引の適正化に係る取組を推進)
政府は、令和3(2021)年に決定した「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を価格に適切に転嫁できる環境整備に取り組んできました。
農林水産省では、食品製造業者と小売業者や、卸売市場の仲卸業者等と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例等を示した「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」及び「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」をそれぞれ策定し、これらを普及させることで、取引上の法令違反の未然防止に努めるとともに、事業者の経営努力が報われる適正な取引の推進を図っています。
(2)合理的な価格の形成に向けた取組が進展
(合理的な価格の形成に向けた仕組みづくり)
合理的な費用を考慮した価格形成の仕組みづくりに当たっては、まず品目ごとにコスト構造の実態を把握し、コストを明確化することが必要です。その上で、当事者間でコストについて協議を行い、価格を決定し、生産から消費に至る食料システム全体で費用を考慮した取引を行うことが重要です。さらに、政府全体として物価上昇を上回る賃金上昇の普及や定着を目指した取組を推進し、消費者の購買力を確保していくことが必要です。
農林水産省では、食料の持続的な供給の実現に向けて、食料システムの各段階でのコスト把握や、生産から消費に至る食料システム全体で合理的な費用が考慮される仕組みを検討することを目的として、令和5(2023)年8月に食料システムの各段階の関係者を構成員とする「適正な価格形成に関する協議会」を設立しました。
また、協議会の下に「飲用牛乳」、「豆腐・納豆」、「米」及び「野菜」の四つのワーキンググループを立ち上げ、実務に精通した取引担当者等による課題の分析等を行いました。
飲用牛乳の小売価格等の状況を見ると、令和4(2022)年春以降の生乳の生産コスト急増に伴う乳価の引上げを除き、小売価格はほぼ横ばいになっています(図表 特2-3)。また、納豆や豆腐については、製造コストが増加しているものの、小売価格は大幅な上昇はなくおおむね横ばいの状態が続いています(図表 特2-4)。
これらの状況等を踏まえて、「飲用牛乳」及び「豆腐・納豆」のワーキンググループでは、価格形成や取引における課題として、消費者の値頃感から納入価格が決定されやすいこと、原材料費や製造コストが上がっても価格交渉を機動的に行うことができないこと、取引上において生ずるリスク等を売り手側が負担していること等を挙げるとともに、消費者の値上げに対する理解醸成のため、各段階のコストの明確化や付加価値の向上を図っていくことが必要であることについて議論しました。
また、「米」及び「野菜」のワーキンググループでは、取引やコストの実態等についての議論を行いました。
同協議会では、生産者や製造事業者の立場から、コストデータの収集・提供方法については検討が必要であること、売り手側の取引上の立場が弱くなるという意見が出されました。他方、流通業者、小売業者及び消費者の立場からは、資材費上昇等の事情は理解しており、コストを指標化し、明確化することが必要であるという意見や、所得が増加しなければ消費行動の変容が困難であるといった意見が出されました。
農林水産省では、このような関係者からの意見を踏まえ、品目ごとのコスト構造や特徴を検証しながら、実効性のある制度を構築していくことになりました。
(持続的な食料システムの確立に向け、付加価値向上の取組を促進)
持続的な食料システムを確立するためには、費用を考慮した価格形成を促すだけでなく、生産と消費をつなぐ重要な役割を果たしている食品事業者による付加価値向上の取組を促進していくことが重要です。また、合理的な費用を考慮した価格形成の取組を消費者等に理解してもらう上でも、これらの取組を促進することが求められます。
農林水産省では、令和5(2023)年8月から、食料システムを構成する幅広い関係者が参加して議論し、将来にわたって持続的な食料システムの実現に向けた施策を検討することを目的として、「食品産業の持続的な発展に向けた検討会」を開催しています。
同検討会では、食品産業の持続的な発展を図るため、環境、人権、健康・栄養への配慮等の世界の潮流となっている取組、世界の食市場の確保、新たな需要の開拓、原材料の安定調達、食品産業の生産性向上、食品産業の事業継続・労働力確保、食品分野の物流効率化等について検討してきました。これまでの検討を踏まえ、令和6(2024)年8月に公表された「食品産業の持続的な発展に向けた対応方向(案)」では、農業と食品産業の連携強化、環境負荷低減等の促進、技術の開発・利用の推進等による食品の付加価値向上等の取組について、合理的な費用を考慮した価格形成の取組と一体として進めることとされました。
(食品産業の持続的な発展と合理的な費用を考慮した価格形成のための法案を国会提出)
農林水産省では、同協議会や同検討会での議論を踏まえ、合理的な費用を考慮した価格形成と持続的な食料システムの確立を一体の取組として検討しました(図表 特2-5)。

これを受けて、政府は食品等の持続的な供給を実現するため、食品産業の持続的な発展と合理的な費用を考慮した価格形成を内容とする「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案」(食料システム法案)を第217回通常国会に提出しました。
同法案では、目的規定に食料システムにおける食品等事業者の役割等を明記するとともに、食品産業の持続的な発展を促すため、農林水産業と食品産業との連携強化、流通の合理化、環境負荷の低減、消費者の選択支援等に計画的に取り組む食品等事業者の認定制度を創設し、認定を受けた計画に対して、株式会社日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)(以下「公庫」という。)による長期低利融資等の支援措置、中小企業等経営強化法等との連携による税制特例の措置を講ずることとしています。また、食品等の取引の適正化の強化を図るため、売り手と買い手双方に対する努力義務の措置と努力義務についての判断基準(行動規範)の策定を行い、取組が不十分な場合は農林水産大臣による指導・助言、勧告・公表、公正取引委員会への通知等の措置を講ずることとしています(図表 特2-6)。また、取引において、消費者の値頃感から、通常、費用について認識しにくい品目の指定や費用の指標を作成する団体の認定、卸売市場における指標の公表等の措置も講ずることとしています。

(3)消費者の理解醸成に向けて
(フェアプライスプロジェクトを引き続き展開)
持続的な食料システムの確立のためには、生産者等の売り手と小売業者等の買い手との間でコストを考慮した取引が行われることに加え、消費者からコストの実態への理解や支持を得ることが不可欠です。
このため農林水産省では、令和5(2023)年度に引き続き、令和6(2024)年度においても、農林水産業の現状や今後の我が国の未来について考え、生産等の現場の実情やコスト高騰の背景等を分かりやすく伝えるための情報発信を行う広報活動「フェアプライスプロジェクト」を継続して実施しています。同プロジェクトのウェブサイトでは、生産者のインタビューのほか、生産者と消費者の間をつなぐ食品スーパーで価格を決めることの難しさを描いた動画等を紹介しています。

フェアプライスプロジェクト
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fair-price-project/
(コラム)消費者の値上げに対する理解を得るため、付加価値の向上を促進(佐賀県)
合理的な費用を考慮した食品の価格形成に当たっては、コスト上昇による価格転嫁を促すとともに、消費者の値上げに対する理解を得るため、付加価値の向上も促進していく必要があります。
佐賀県鹿島市(かしまし)の合資会社光武酒造場(みつたけしゅぞうじょう)では、地域資源の活用や、他社との差別化を図った独創的な商品の提供を行うことで、付加価値の向上に取り組んでいます。例えば令和6(2024)年9月から販売を開始した商品では、購入者が熟成前のジンを樽(たる)ごと購入し、熟成度合いを楽しみながら消費できるといった商品自体の魅力に加え、町屋を活用した宿泊施設、酒蔵(さかぐら)ツアーやジン製造プロセス体験ができる蔵ツーリズム等の地域の魅力を活かした商品展開を行っています。また、幅広い世代に人気のある様々なゲームやアニメ等とのコラボ商品も定期的に販売しており、消費後も装飾品として楽しめるようボトルにも工夫を凝(こ)らすことで、商品の新たな価値の創出につながっています。
同社は、原材料である米、かんしょや人件費の上昇を受け、令和4(2022)年に約8割の商品について値上げを行いましたが、独自のブランディングが奏功(そうこう)し、値上げの影響を受けることなく、販売量は順調に増加しています。
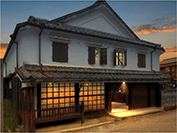
町屋を利用した宿泊施設
資料:合資会社光武酒造場

人気コンテンツとのコラボ商品
資料:© Cygames, Inc.
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883






