第1節 農村の動向
我が国の農村では、人口減少と高齢化が並行して著しく進行しており、その影響は地域の基礎的な社会集団である農業集落に強く表れています。
本節では、農村人口や農業集落の動向について紹介します。
(1)農村人口の動向
(農村における人口減少と高齢化が進行)
農村において人口減少と高齢化が並行して進行しています。総務省の国勢調査によると、令和2(2020)年の人口は、平成27(2015)年に比べ都市で142万人(1.6%)増加したのに対し、農村では237万人(5.9%)減少しています(図表6-1-1)。農村では生産年齢人口(15~64歳)、年少人口(14歳以下)が大きく減少しているほか、総人口に占める老年人口(65歳以上)の割合は、都市の25%に対し、農村では35%となっており、農村において高齢化が進んでいることがうかがわれます。
従来、農村を含む過疎地域の人口減少は、都市への人口流出による社会減が主な要因でしたが、平成21(2009)年度を境として、高齢化により自然減がそれを上回るようになりました(図表6-1-2)。今後、農村への移住等により、社会減が一定程度緩和されたとしても、それを上回る規模で自然減が進行することが予想されています。人口減少が特に著しい地域では、集落の存続が危ぶまれており、これまで集落の共同活動により支えられてきた、農業生産活動の継続が困難になることが懸念されます。
(農村・都市ともに、平均出生子ども数は減少傾向で推移)
国立社会保障(こくりつしゃかいほしょう)・人口問題研究所(じんこうもんだいけんきゅうじょ)が令和3(2021)年6月に実施した調査によると、令和3(2021)年の平均出生子ども数は、農村で1.97人、都市で1.74人となりました(図表6-1-3)。農村・都市ともに平均出生子ども数は減少傾向にある一方、農村が都市を上回っている状況にあります。
さらに、厚生労働省の令和5年人口動態統計によると、全国の合計特殊出生率は1.20であり、都道府県別では沖縄県が1.60、宮崎県・長崎県が1.49となる一方、東京都が0.99、北海道が1.06、宮城県が1.07となりました(図表6-1-4)。
出生率の動向には多様な要因が影響を及ぼすため、因果関係は必ずしも明らかではありませんが、令和3(2021)年3月に一般社団法人北海道総合研究調査会(ほっかいどうそうごうけんきゅうちょうさかい)が公表した「地域の出生率に影響を及ぼす要因の分析に関する調査研究報告書」によれば、人口規模の異なる全国10市町村を対象にした研究の結果、「第1次産業の割合の高さは、職住近接や家族・地域ぐるみの子育ての観点から出生率に望ましい効果を与えていることが示唆される」としています。
(農村では製造業や医療・福祉等の多様な産業が展開)
総務省の国勢調査によると、令和2(2020)年の農村の産業別就業者数は、「製造業」が348万人で最も多く、次いで「医療、福祉」となっています(図表6-1-5)。一方、「農業、林業」は156万人で全体の8.6%となっており、農村では第一次産業に限らず、多様な産業が展開されています。農村人口の減少・高齢化が進む中、人口減少に歯止めをかけ、農村での就業機会を確保するためには、農村における産業の振興や起業を促していくことが重要です。

データ(エクセル:29KB)
(2)農業集落の動向
(農業集落の小規模化や混住化が進行)

データ(エクセル:28KB)
我が国の農業集落は、地域に密着した水路・農道・ため池等の農業生産基盤や収穫期の共同作業・共同出荷といった農業生産面のほか、集落の寄り合い(*1)等の協働の取組や伝統・文化の継承といった生活面にまで、密接に結び付いた地域コミュニティとして機能しています。
しかしながら、農業集落では人口減少と高齢化の影響により小規模化が進んでおり、総戸数が9戸以下の農業集落の割合は、令和2(2020)年で7.8%となっています。
また、農業集落の総戸数に占める農家の割合を見ると、令和2(2020)年は5.8%にまで低下しており、混住化が大きく進んでいる様子がうかがわれます(図表6-1-6)。
小規模な集落では、単独で農業生産や生活支援に係る集落機能を維持することが困難になるとともに、集落機能の低下が更なる集落の人口減少につながり、集落の存続が困難になることが懸念されています。
老年人口割合が高い農業集落では、生活の利便性が低いと、更なる人口減少・高齢化につながり、集落の存続が危うくなってきます。このサイクルを断ち切るため、買物や医療、教育等へのアクセスのほか、高齢者を見守る福祉サービスといった、日々の生活を支える生活環境の改善が重要になってきます。
このため、広域的な範囲で支え合う組織づくりを進めるとともに、農業生産の継続と併せて生活環境の改善を図る必要があります。集落機能の維持はその地域の農地の保全や農業生産活動の継続にも影響することから、農村における労働人口の確保やコミュニティ機能の維持は重要な課題となっています。
*1 地域の諸課題への対応を随時検討する集会、会合等のこと
(農業集落の自立的な発展を目指す取組が各地で展開)
過疎化・高齢化等により、農村の活力低下が見られる一方、地域住民が主体となって農業集落の自立的な発展を目指す取組が各地で進められています。
地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う「地域運営組織(RMO)」や、各種生活サービス機能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された「小さな拠点」の数は全国的に増加傾向にあり、小さな拠点は地域の祭りや公的施設の運営等の様々な活動の場となっています。
農林水産省では、地域の創意工夫による活動の計画づくり、農業者を含む地域住民の就業の場の確保及び農山漁村における所得向上・雇用増大につながる取組に対して、総合的に支援することで、地域コミュニティの維持・強化に加え、農山漁村の活性化や自立的な発展を後押ししています。
(事例)「農村起業家」の育成により、農村の活性化を推進(広島県)
(1)「塾」開講で農村起業家を育成


「田万里家」の販売風景
資料:農ライファーズ株式会社
農村の発展には、地域資源を活用した魅力的な製品・サービスを提供する事業者の存在が欠かせません。広島県竹原市(たけはらし)の農(のう)ライファーズ株式会社は、農村の起業家を育成することを狙いとした「農村起業塾(のうそんきぎょうじゅく)」を令和6(2024)年4月から開講しました。
同社は、同市の中山間地域に所在する田万里(たまり)地区において、自社で栽培した水稲を原料とする米粉ドーナツの製造・販売に加え、公民館を改修した宿泊・飲食施設「田万里家(たまりや)」を運営しています。同施設には、令和5(2023)年度に周辺の都市部等から延べ約3万人が訪れており、地域の活性化に貢献しています。
同施設のように、農業生産に飲食や宿泊等を複合的に組み合わせた事業に取り組むことで、農業生産の規模拡大や効率化に限界のある中山間地域においても、収益性を向上させることが可能になります。農村起業塾では、同施設の事例をモデルケースの一つとしつつ、塾生が考案した事業内容等について指導やアドバイスを行っています。
(2)今後は地方公共団体や地域おこし協力隊等と提携
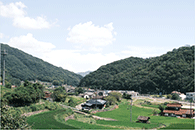
田万里地区の風景
資料:農ライファーズ株式会社
同社は今後、各地の地方公共団体、地域おこし協力隊や企業等との連携を強化するなど、受講者を増やしていく考えで、全国規模で農村起業家の育成を目指しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








