第2節 農村の総合的な振興
我が国の農村では、集落活動を担う人材が不足し、農地保全や水管理等の取組が低調となる地域が増加すること等が懸念されています。このような中、農山漁村における定住や交流促進、関係人口の創出・拡大に向け、所得の向上と雇用機会を生み出し、農村における付加価値を創出する「経済面」の取組と、生活の利便性を確保する「生活面」の取組を推進し、農村の総合的な振興を図っていくことが必要となっています。
本節では、農村の活性化に向けた取組や生活インフラ等の確保、地域コミュニティ機能の維持・強化に関する取組について紹介します。
(1)農村の活性化に向けた取組の推進
(農村の活性化に向けて「経済面」「生活面」の取組等を推進)
農村を活性化させるには、農村に人材を呼び込むことが必要です。農林水産省では多様な人材の呼び込みに必要な農村の「経済面」の取組を強化するため、6次産業化や農泊といった、地域資源を活用して付加価値を創出する取組を推進するとともに、関係人口も交えて地域に根差した経済活動が安定的に営まれるよう、地方公共団体と民間企業等が連携して、これらの取組への関わりを後押しすることとしています。
(事例)地域の課題を農業で解決するむらづくり事業を推進(愛媛県)
(1)「地域の課題を農業で解決する」をミッションに、ソーシャルビジネスを展開


運営する直売所
資料:百姓百品グループ
愛媛県西予市(せいよし)の百姓百品(ひゃくしょうひゃっぴん)グループは、「地域の課題を農業で解決する」をミッションに、地域の課題を持続可能な事業として位置付け、販売・生産・福祉に関わる三つの組織が連携する形で解決に取り組むソーシャルビジネスを展開しています。
同グループの百姓百品(ひゃくしょうひゃっぴん)株式会社は、直売所の運営や生活協同組合店舗でのインショップ事業等を行っており、地域の小規模農家の販売面における貴重な受け皿となっています。生産組織である株式会社ノムランドは、耕作の継続が困難となった農地を地域の農業者から借り受け、青ねぎを生産し、県内の食品事業者等との間で青ねぎの契約取引を行っており、今後、地域の中心的な経営体に成長することが期待されています。就労継続支援B型事業所を運営している株式会社野村福祉園(のむらふくしえん)は、農福連携に取り組んでおり、直売所の清掃や青ねぎの出荷調製といったグループ内での作業のほか、地域の他企業からの作業委託にも対応しており、地区平均を超える高い工賃を実現しています。
(2)農業から生まれる価値の提供を次の世代に引き継ぐ
同グループは、農家と非農家が一体となり、主体的に関わり合い運営に参加してきたことで、平成30(2018)年の「平成30年7月豪雨」からの復旧を含め、地域課題の解決に取り組む中心的な主体としてなくてはならない組織に成長してきました。また、近年では三つの株式会社それぞれの代表取締役に女性が就任するなど、多様な人材の参画と世代交代も進んでおり、今後も農業を軸とした持続的な地域づくりを通じ、中山間地域を守り育て、地域の「たからもの=田からもの」を社会に提供し続ける存在として、若い世代と共に活動を継続していくこととしています。
また、「生活面」の取組として、中山間地域等において複数の集落の機能を補完し、農用地の保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティ維持に資する取組を行う組織である「農村型地域運営組織」(以下「農村RMO」という。)の形成を推進しています。
さらに、棚田地域を含む中山間地域等において、棚田サポーター制度等を通じ、活力を創出するための社会貢献やビジネスの展開を図る企業の活動を後押しし、企業と地域との相互補完的なパートナーシップの構築を推進することとしています。
くわえて、土地利用に関し、地域ぐるみの話合いを通じ、農地の粗放的な利用を含めた計画的な活用のあり方を定め、それに即して景観作物等の導入やきめ細かな基盤整備などの支援を行うこととしています。
(コラム)地域特産品を活用した「まちづくり」の取組を展開
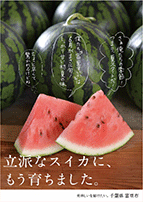
富里すいかの宣伝用ポスター
資料:千葉県富里市
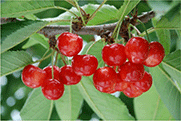
特産品である「さくらんぼ」
資料:山形県寒河江市
近年、地域を象徴する特産品を条例に位置付けることで、地域の良さを再認識するきっかけづくりや郷土への愛着形成を図り、地域一体で地域の活力創生に取り組む動きが広がっています。
千葉県富里市(とみさとし)では、特産品であるすいかを守ることを目的として、令和3(2021)年3月に「富里市すいか条例」を制定しました。同条例では、富里のすいかを地域の象徴する特産品と位置付け、市、生産者、事業者及び市民の役割や協力・連携、情報発信等を規定しています。条例の制定を受け、「富里すいか」のポスターを作成し、首都圏の電車内に掲示するなどのブランド強化への取組を行っています。
また、山形県寒河江市(さがえし)では、「さくらんぼ」にこだわった「まちづくり」を推進しており、令和6(2024)年6月に「さくらんぼのまち寒河江推進条例」を制定しました。同条例では、市の特産品である「さくらんぼ」を市民の誇りと位置付け、生産者、事業者、市民及び市がそれぞれの役割に応じた取組に努めるとともに、相互に連携・協力すること等を規定しています。同市では、条例を通じて「さくらんぼ」を核としたまちづくりを更に推進し、未来へ継承することとしています。
このような特色ある農林水産品等を地域資源として活かし、住民の理解・参加を得ながら地域全体で盛り上げるまちづくりの取組は、地域の振興につながるだけでなく、農業の持続的な発展を図る上でも重要な意義を有しています。
(デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づく農村の活性化を図る取組の広がり)
政府は「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定し、デジタル技術の活用によって地方創生を加速化・深化し、各地域における優良事例の横展開の加速化等を図ることとしています。例えば、農村における人口減少を補うため、積極的に都市から農村への移住を進めることとしており、DXを進めるための情報基盤の整備、デジタル技術を活用したサテライトオフィス等の整備を行い、地方公共団体間の連携を促進しつつ、移住を促進するための農村における環境整備を進めています。
また、農林水産省では、魅力ある豊かな「デジタル田園」の創出に向けて、関係府省と連携し、中山間地域等におけるデジタル技術の導入・定着を推進する取組を支援するとともに、デジタル技術の活用に係る専門人材の派遣や企業とのマッチング、スマート農業やインフラ管理等に必要な情報通信環境の整備等を支援することとしています。
(地方創生2.0に基づいた農山漁村の地方創生の推進)
令和6(2024)年12月、地方創生2.0の「基本的な考え方」が新しい地方経済・生活環境創生本部において策定されました。この中で、「基本的な考え方」の基本構想(令和7(2025)年夏に策定予定。)の5本柱として、<1>安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生、<2>東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散、<3>付加価値創出型の新しい地方経済の創生、<4>デジタル・新技術の徹底活用及び<5>「産官学金労言」の連携等、国民的な機運の向上が示されました。
農林水産省では、上記を踏まえ、令和7(2025)年2月、農山漁村における課題解決を図るため、「『農山漁村』経済・生活環境創生プロジェクト」を創設し、関係府省庁、地方公共団体、郵便局、民間企業、教育機関、金融機関等が参画して地域と企業のマッチングや連携の在り方を議論する「農山漁村」経済・生活環境創生プラットフォームを立ち上げました。
同年2月に、同プラットフォームの設立を記念したシンポジウムを開催し機運醸成を図るとともに、<1>通いによる農林水産業への参画・コミュニティ維持、<2>農山漁村を支える官民の副業促進、<3>市街地と農山漁村間における物流網の維持・確保及び<4>外部企業との案件形成に向けた民間資金・人材の確保といった四つのテーマごとに専門部会等を設け、現場での案件形成を進める上で参考となる事例の収集や手引の作成等に取り組んでいます。

官民共創による農業・農村の
課題解決のための取組について
URL:https://www.maff.go.jp/j/
nousin/kanmin_kyousou.html
また、テーマ<4>外部企業との案件形成に向けた民間資金・人材の確保に関連して、農林水産省では、官民共創の仕組みを試行的に実施するため、令和6(2024)年度においては、熊本県内市町村等における農業・農村の課題と、民間企業が有する解決策とのマッチングや案件形成に向けた地域と企業への伴走支援等に取り組みました。
あわせて、同事業の進捗や地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した地域課題の解決事例の発信等を行っていくこととしています。
(2)生活インフラ等の確保
(農村地域における交通・教育・医療・福祉等の充実を推進)
人口減少が進む農村においては、担い手の育成や農地の集積・集約化等の農業政策に加え、交通・教育・医療・福祉といった地域に定住するための諸条件の維持・確保が重要となっています。
このような中、生活の利便性向上や地域交流に必要な買物支援、ライドシェア等を推進するとともに、活力ある学校づくりに向けたきめ細かな取組を推進しています。また、へき地における医療の確保を図るとともに、住まい・医療・介護・予防・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

移動販売・宅配サービスの運営による買物支援
資料:特定非営利活動法人まち・ひと・みらい

巡回車による巡回特定健康診査
資料:鹿児島県厚生農業協同組合連合会鹿児島厚生連病院
(農業・農村における情報通信環境の整備を推進)
農業水利施設等の管理の省力化・高度化やスマート農業の実装、地域の活性化を図るため、ICT等の活用に向けた情報通信環境を整備することが重要な課題となっています。
令和5(2023)年度に農林水産省で行った推計によると、農地の一部又は全部で携帯電話等サービスを利用できない面積は約10万haで、全国の農地の約2.3%となっています。
農林水産省では、総務省と連携しつつ、農業・農村における情報通信環境の整備に取り組んでおり、行政、土地改良区、農協、民間企業等による官民連携の取組を通じて、普及・啓発・人材派遣等のサポートを行っています。また、令和6(2024)年度は、全国27地区において、光ファイバ、無線基地局等の情報通信環境整備に係る調査、計画策定、施設整備を実施しました。
(標準耐用年数を超過した農業集落排水施設は全体の約8割)

データ(エクセル:26KB)
農業集落排水施設は、農業用水の水質保全等を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水を処理するものであり、農村の重要な生活インフラとして稼働しています。
一方、機械類の標準耐用年数である20年を経過する農業集落排水施設の割合が令和7(2025)年3月末時点で84%となるなど、老朽化の進行や災害への脆弱性(ぜいじゃくせい)が顕在化するとともに、施設管理者である市町村の維持管理に係る負担が増加しています(図表6-2-1)。
このような状況を踏まえ、農林水産省では、農業集落排水施設が未整備の地域に関しては引き続き整備を進めるとともに、既存施設に関しては、地方公共団体による機能診断等の取組、更新整備等を支援し、広域化・共同化による維持管理の効率化、長寿命化・老朽化対策を進めています。
また、農業集落排水汚泥のうち、肥料等として再生利用されているものは、令和6(2024)年3月末時点で約7割となっています。みどり戦略の推進に向け、農業集落排水汚泥資源の再生利用を更に推進することが重要です。
(農道の適切な保全対策を推進)
農道は、圃場(ほじょう)への通作や営農資機材の搬入、産地から市場までの農産物の輸送等に利用され、農業の生産性向上等に資するほか、地域住民の日常的な通行に利用されるなど、農村の良好な生活環境を確保する重要なインフラです。令和6(2024)年8月時点で、農道の総延長距離は16万9,719kmとなっています。一方、農道を構成している構造物については、同年4月時点で供用開始後20年を経過するものの割合が、橋梁(きょうりょう)で84%、トンネルで68%となっています(図表6-2-2)。経年的な劣化の進行も見られる中、その機能を適切に維持していくためには、日常管理や定期点検、計画的・効率的な保全対策に取り組むことが重要です。
このため、農林水産省では、市町村や土地改良区等の職員向けに、非技術系の職員であっても容易に理解でき、直接点検等の実施にも役立つ手引案を作成し、保全対策の推進に取り組むとともに、農道の再編・強靱(きょうじん)化や拡幅等による高度化を通じて、農業の生産性向上や農村の生活環境の整備を図っていくこととしています。

データ(エクセル:27KB)
(3)地域コミュニティ機能の維持・強化
(集落機能を補完する農村RMOの形成を推進)
中山間地域を始めとした農村地域では、集落の小規模化により、農業生産活動のみならず、農地・農業用水路等の保全や買物・子育て等の生活支援等の取組を担ってきた地域コミュニティの弱体化が懸念されています。このため、複数の集落において地域コミュニティ機能を補完する農村RMOの形成を促進していくことが重要となっています(図表6-2-3)。
農林水産省では、農村RMOを目指す団体等が行う農用地の保全、地域資源の活用、生活支援に係る将来ビジョンの策定、これらに基づく調査、計画作成、実証事業等の取組に対して支援を行い、令和8(2026)年度までに100地区の農村RMOモデル形成支援地区を形成することを目指しています。また、地方公共団体や農協、中間支援組織等から構成される都道府県単位の支援チームや全国プラットフォームの構築を支援し、農村RMOの形成を後押ししています。

(事例)持続可能な地域づくりに向け、農村RMOの活動を展開(愛知県)
(1)地域コミュニティ機能の維持に向け、地域づくり協議会を設立

愛知県岡崎市(おかざきし)の下山学区(しもやまがっく)では、人口減少や高齢化が進行する中、地域の課題を「わがごと」として捉え、地域や住民が一体となり、生産、生活扶助、資源管理に取り組み、地域コミュニティ機能の維持・強化を図ることを目指し、同市や農協等が連携し、令和4(2022)年4月に「岡崎市下山学区地域(おかざきししもやまがっくちいき)づくり協議会(きょうぎかい)」を設立しました。
(2)農村RMOの設立を目指し、持続可能な地域づくりを推進

「地域支えあい車両」
による移動支援
資料:岡崎市下山学区地域づくり協議会

稲作体験プログラム
資料:岡崎市下山学区地域づくり協議会
同協議会の実行組織は、農用地保全部会、地域資源活用部会、生活支援部会、企画・施設運営部会から構成され、閉店した店舗を活動拠点としています。各部会では、遊休農地における稲作体験プログラムや自然環境資源を活用したウォーキング大会の開催、貸出車両による移動支援、地域農産物を活用した地域コミュニティ食堂の企画・開催等を行っており、これらのイベントへの同学区外からの参加者も増えています。
また、同協議会では、同学区の住民を対象に、地域の課題や魅力を把握するアンケート調査を行ったほか、幅広い世代が参加するワークショップを開催し、地域課題を「わがごと」として捉え、自主的に課題解決に取り組む機運の醸成が図られました。
同ワークショップ等の検討を踏まえ、同協議会は令和5(2023)年3月に下山学区地域将来(しもやまがっくちいきしょうらい)ビジョンを策定し、農用地保全、生活支援、関係人口の創出、地域プロモーションを軸に、持続可能な地域づくりに取り組んでいくこととしています。
今後も、住民の意見に寄り添いながら、直売所や体験農園等の農村RMO事業の本格運用を推進し、令和7(2025)年度以降の農村RMOの設立を目指すこととしています。
(デジタル技術を活用した地域との交流を深める取組が進展)
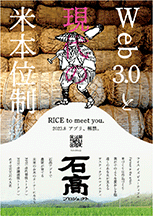
米の販路拡大に向け、
NFTを活用したプロジェクト
資料:福島県西会津町
近年、NFT(*1)(非代替性トークン)やDAO(*2)(分散型自律組織)等のWeb3に関連した技術や仕組みを駆使して社会課題を解決しようとする動きが活発化しています。人口減少下の社会における新たな価値創造として、コミュニティへの貢献をNFTの発行により還元し、いわゆる「デジタル村民」として継続的に地域への関わりを深める人材を増やす取組等がみられています。また、コミュニティで農業者を支え、販路拡大や地域の交流人口増加を図るため、NFT等の技術を活用する取組もみられています。
今後も、デジタル技術を活用した新たな関係人口の創出・拡大により、経済・社会・環境の相乗効果が発揮されるとともに、過疎地における新しい社会システムのモデルとなることが期待されています。
*1 Non-Fungible Tokenの略。ブロックチェーンを基盤にして作成された代替不可能なデジタルデータ
*2 Decentralized Autonomous Organizationの略。ブロックチェーンを基盤にした中央集権的な管理を必要としない組織
(農村部においても公共ライドシェアを推進)
人口減少及び高齢化が全国的に進む中、免許返納した高齢者を中心に移動手段の確保に対する不安が高まっています。
農村部の公共交通事業者だけでは移動手段を十分に提供することが困難な交通空白地では、農協や商工会、観光協会及びRMO等といった地域に根差した主体による公共ライドシェアの導入を推進する必要があります。
政府では、引き続き、全国各地での公共ライドシェアへの多様な関係者の参画を働き掛け、取組を推進することとしています。
(4)多様な人材の活躍による地域課題の解決
(「半農半X」の取組の広がり)
農業・農村への関わり方が多様化する中、都市から農村への移住に当たって、生活に必要な所得を確保する手段として、農業と別の仕事を組み合わせた「半農半X」の取組が広がりを見せています。
半農半Xの農は農業で、もう一方の「X」に当たる部分は会社員や農泊運営、レストラン経営等多種多様です。Uターンのような形で、本人又は配偶者の実家等で農地やノウハウを継承して半農に取り組む事例、また、食品加工業、観光業等の様々な仕事を組み合わせて通年勤務する事例も見られています。
農林水産省では、新規就農の促進等のほか、関係府省等と連携し、半農半X等の多様なライフスタイルの実現に資する「人口急減地域特定地域づくり推進法(*1)」の仕組みの活用を推進しています。
*1 正式名称は「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」
(事例)農業の維持・発展に向け、半農半Xを応援する取組を推進(山梨県)
(1)新たな人材の確保を目的に、半農半Xの取組を推進

山梨県甲府市(こうふし)では、田園回帰の意識の高まり等を背景に、都心からアクセスの良い同市に移住する都市住民が増加していることから、農業の多様な担い手の確保や農地保全を図るため、半農半Xを推進しています。
(2)新たな担い手となり得る相談者を支援

貸出用の農業機械で
作業する半農半X実践者
資料:山梨県甲府市
同市では、高齢化や担い手不足が課題となる中、新たな担い手となり得る人たちを呼び込むため、「農あるくらし」を希望する住民や憧れを持つ移住者等を対象に、ほかに仕事を持ちながら農業に挑戦するライフスタイルの実践を支援しています。
令和5(2023)年7月に設置した半農半X応援相談窓口では、小型の農業用機械の貸出しや栽培指導等を実施しています。また、農業未経験の相談者が安心して農業に挑戦できるよう、同市の農業センター内に「チャレンジ農園」を開設し、栽培指導等の支援を実施しています。
さらに、市の広報やSNS、移住相談会等でPRを行い、窓口を設置した令和5(2023)年度には34件、令和6(2024)年度には35件の相談が寄せられています。また、窓口を開設後、令和7(2025)年3月末時点で6人が半農半Xを実践し、3人がチャレンジ農園で研修を受けました。
今後も、半農半Xによる多様な働き方の支援に取り組み、農業に携わる人たちを増やし、幅広い担い手の確保や農地の保全を図ることとしています。
(特定地域づくり事業協同組合の認定数は着実に増加)
特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域特定地域づくり推進法に基づき、人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して、財政的、制度的な支援を行うものです。令和7(2025)年3月末時点の特定地域づくり事業協同組合数は、前年同月末時点に比べ13件増加し108組合(*1)となっています。
本制度の活用により、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を図ることが期待されています。
*1 人口急減地域特定地域づくり推進法に基づく認定を受け、特定地域づくり事業推進交付金の交付が決定されている組合の数値
(地域おこし協力隊の隊員数は前年度に比べ増加)
地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等に生活の拠点を移し、全国の様々な場所で地場産品の開発、販売、PR等の地域おこしの支援、農林水産業への従事、住民の生活支援等の地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。令和6(2024)年度の隊員数は前年度に比べ710人増加し7,910人となっています(図表6-2-4)。また、総務省が令和6(2024)年度に実施した調査によると、直近5年に任期を終了した隊員のうち、69%が活動地と同じ地域に定住しています(図表6-2-5)。
総務省は、地域おこし協力隊の推進に取り組む地方公共団体に対して、必要な財政上の措置を行うほか、都市住民の受入れの先進事例等といった調査等を行っています。
(5)地域を支える体制・人材づくり
(地方公共団体における農林水産部門の職員数は減少傾向で推移)
近年、地方公共団体の職員、特に農林水産部門の職員が減少しています。同部門の職員数については、令和6(2024)年は7万8,724人となっており、平成17(2005)年の10万2,887人から2割以上減少しました(*1)(図表6-2-6)。
また、地方公共団体の財政についても、生産基盤の整備や農林水産業経費である農林水産業費の純計決算額は、令和5(2023)年度においては3兆3,687億円と、平成17(2005)年度の約8割の水準となっています(図表6-2-7)。
農村地域においては、各般の地域振興施策を活用し、新しい動きを生み出すことができる地域とそうでない地域との差が広がり、いわゆる「むら・むら格差」の課題も顕在化しています。このような中、地方における農政の現場では、地域農業の持続的な発展に向け、地方公共団体等の職員がデジタル技術を活用して現地確認事務の効率化を図る取組、農業経営の改善をサポートする取組等が見られており、地域における農政課題の解決を図る動きが見られています。
農業現場の多様なニーズに対応するため、地方公共団体においては、今後とも限られた行政資源を有効に活用しながら、それぞれの地域の特性に即した施策を講じていくことが重要となっています。
農林水産省では、現場と農政を結ぶため、全国の地域拠点に地方参事官室を配置し、地方公共団体と連携しつつ、農政の情報を伝えるとともに、現場の声を汲(く)み上げ、地域と共に課題を解決することにより、農業者等の取組を後押ししています。
*1 総務省「地方公共団体定員管理調査結果」によると、令和6(2024)年の地方公共団体の職員数(281万1,749人)は、平成17(2005)年の職員数(304万2,122人)と比較して、約1割減少している。
(「農村プロデューサー」を養成)
農山漁村の自立及び維持発展に向け、地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いをくみ取りながら、地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサポートする人材を育成するため、農林水産省は、「農村プロデューサー」養成講座を開催しています。同講座の実践コースでは、地域づくりに造詣の深い講師による講義に加え、実例を基にした模擬演習や受講生自らの実践活動等が行われており、令和7(2025)年3月末時点で、地方公共団体の職員や地域おこし協力隊の隊員等369人が受講しました。
また、農林水産省では、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等を対象に相談を受け付け、取組を後押しするための窓口である「農山漁村地域づくりホットライン」を、本省を始め、全国の地方農政局、地域拠点等に開設しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883








