ご当地の郷土料理の魅力 ふるさと給食自慢
日本全国で提供されている学校給食のメニューの中から、その土地で親しまれている郷土料理や食材などを取り入れたものを紹介。その地域ならではの食の連載をお届けします。
第15回
山梨県山梨市の学校給食
ほうとう

山梨県の郷土料理であるほうとうがメインの献立。ほかに、きな粉揚げパン、れんこんとツナの和え物、旬のりんごは皮をむかずに、彩りを添えます。牛乳も山梨県産のものが提供されています。
体あたたまる冬の味覚
具がたっぷりで栄養満点「ほうとう」
(山梨市学校給食センター)
ほうとうは、一般的なうどんと違って幅広く切られた平打ち麺を使用し、そこに鶏肉、季節の野菜などを入れて味噌仕立ての汁で煮込んだ料理です。冬になると県内の各家庭などで作られてきた郷土料理ですが、時代が進むにつれて作られる機会が減少しました。そのため、子ども達が郷土の味に親しめるように学校給食として提供されています。

煮干しから取った出汁に合わせ味噌を溶き、根菜、はくさい、きのこ類、鶏肉、油揚げなどを火の通りづらい順に煮込みます。最後に、ほうとうに欠かせない食材のかぼちゃを入れて煮込めば完成です。

給食センターで調理して提供されるほうとうは、学校内で給食を調理していた時とは違った工夫が必要です。給食センターでは配送に時間がかかり、その間に汁が吸われて少なくなり、麺が伸びてしまいます。麺の長さは7センチメートル程度に抑え、打ち粉も少なめにすることで、給食センターでは少しサラサラした状態が、学校に届く時にはちょうど良いとろみ加減になります。

ほうとう麺と季節の野菜をかぼちゃと一緒に煮込むことで自然な甘味が出るため、低学年の子ども達も好き嫌いなく食べられる味になっています。山梨県には物事がうまく進んだときに「うまいもんだよ、かぼちゃのほうとう」という言い回しをする文化があるほど、定番の具材としてかぼちゃがよく使われます。ほうとうは、一番なじみ深いかぼちゃの食べ方として、子ども達が大好きな給食です。
山梨県の郷土料理「ほうとう」とは?
ほうとうの歴史
山梨県は県土の大部分が山地であり、稲作を行いづらい環境であったため、主食として米を用いるのが困難だったとされています。そのため、小麦粉を材料とするほうとうは食生活の中心として伝承されてきました。冬になると大鍋を用い、家の畑で採れた野菜を煮込んで、家族全員で朝晩ほうとうを食べるというのが山梨県の伝統的な光景でした。近年では家庭で作られる機会が減り、県外からの観光客に対するおもてなしとして、ほうとうをお店で食べてもらうということが増えています。

具だくさんで栄養たっぷり!
ほうとうの実力

ほうとうには、かぼちゃやだいこん、にんじん、はくさい、きのこ類、鶏肉、油揚げなどさまざまな具材が使用されています。たんぱく質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂ることができます。(監修:管理栄養士・国際中医薬膳師 清水 加奈子さん)

給食でほうとうを提供する際には、栄養士さんが教材を使ってほうとうの歴史や栄養について説明し、子ども達の郷土料理についての理解が深まるように工夫しています。給食として提供していくことで、子ども達の心に深く残っていきます。
全国給食牛乳コレクション
全国のほとんどの学校給食で毎日提供されている牛乳にも、地域によって違いがあります。子ども達に新鮮な牛乳を楽しんで飲んでもらえるように、どんな工夫があるのでしょうか。各地域で提供されているご当地牛乳を紹介します!
中部編

地産地消をモットーとし、創業80年以上の歴史を有する乳業メーカーである中央製乳(株)。牛乳のおいしさを決めるのは「生乳の鮮度」と「関わる人たちの愛情」という想いのもと、酪農家と従業員が一丸となって「中央牛乳」を生産しています。成分無調整の牛乳は乳牛に与えるエサや季節などにより風味が変わるそうですが、子ども達からは「とてもおいしい牛乳」と評判です。牛乳1本(200ミリリットル)あたり、約200ミリグラムのカルシウムが含まれていて、栄養はバッチリ。この中央牛乳は三河地域、知多地域、尾張地域の31市町村に届けられ、県内の約半数の子ども達が毎日飲んでいます。

高山市と下呂市の酪農家によって組織された、酪農の専門農協である飛騨酪農農業協同組合は、1929年に牛乳販売購買利用組合として創業し、約100年の歴史を有しています。給食用牛乳はビンまたは紙パックで供給しており、ビンに描かれた牛のイラストは、市内の小学生から募集した絵を採用しています。飛騨地方の清涼な空気や水、良質の飼料によって飼われた乳牛から搾られた牛乳は、「あっさりとしたさわやかな味」が楽しめます。また、組合の専門指導員(獣医師)が毎月農家を巡回し、牛の健康状態の確認や助言を行っています。品質管理が徹底された牛乳は、高山市、飛騨市、下呂市、白川村と飛騨地域全域に届けられています。
こちらの記事もおすすめ
記事の感想をぜひお聞かせください!
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449
FAX番号:03-3502-8766








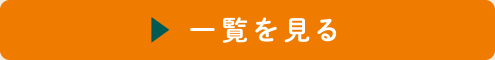
 感想を送る
感想を送る