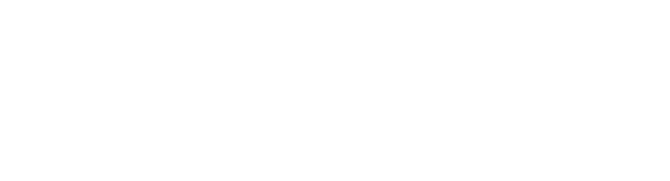大学の農系学部が研究・開発した製品と、その製品化までの道のりを紹介します。
第18回
木材の新たな可能性を目指して
三重大学の
「ウッドストロー」

私たちの日常生活のさまざまな場面で活用されるプラスチック。しかし近年、プラスチックごみによる海洋汚染や、「マイクロプラスチック」と呼ばれる微細なプラスチックによる生態系への影響が国際的な問題として関心が高まっています。そうした中で、三重大学大学院生物資源学研究科の野中寛教授は、プラスチックを一切使用せず、木材のみを使用した「ウッドストロー」を開発しました。時代のニーズに応える同大学の「ウッドストロー」は、木の良さや価値を再発見させる製品として2018年に「ウッドデザイン賞」も受賞。その開発までの道のりに迫りました。
プラスチックの
代替素材としての木材の可能性
現在、プラスチック代替素材の開発に向けた研究が各地で行われています。三重大学大学院生物資源学研究科の野中寛教授は、「木材を使って自由な形を作りたい」という発想を原点に、木材成分のみを活用したストローの開発に向けた研究に着手。試行錯誤を重ね、100パーセント天然素材の「ウッドストロー」の開発に成功しました。しかし、その研究に取り組むきっかけは、まったく異なる製品素材の開発だったそうです。
「木材の約50パーセントはセルロースという成分です。そのセルロース由来の増粘剤を、メーカーより紹介いただきました。ちょうどその頃、百貨店などの紙袋を製作している企業から、プラスチック製の取っ手を、環境への配慮と高級感を兼ね備えた素材に代えたいという相談を受けていました。そこで、セルロース由来(=木材由来)の増粘剤を使い、新しい取っ手作りの共同研究が始まりました」と野中教授は語ります。
いろいろな形に変身!
木粉粘土の可能性


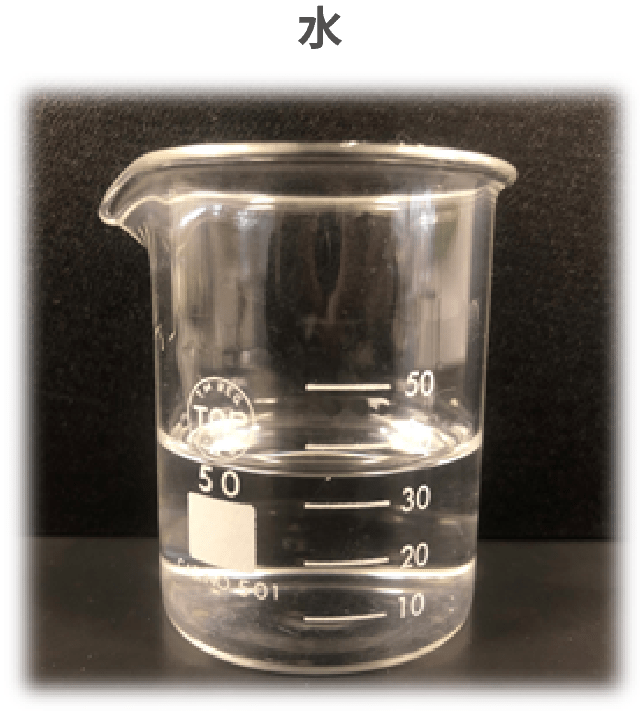
木粉粘土の材料
「新しい取っ手の開発では、当初、紙の原料であるパルプとセルロース系増粘剤をこねて粘土にして、型押ししたり、手回し式でところてんのように押し出したりして、ひも状の材料を作っていました。そのうちパルプのような繊維状の素材より、紙粉・木粉・竹粉・コーヒー粕など、粉末状の植物素材を使う方がきれいな粘土になることに気づきました。簡易的なシリコン型を使って、ひもに限らずいろいろな形に成形できることもわかってきて、この素材には大きな可能性があると確信したのです」。新しい取っ手の開発は、転換点を迎えました。

手回し式の押し出しの様子。


左:木粉シート、右:木粉ハニカム
上:木粉シート、下:木粉ハニカム
「木材は切る・貼る、紙であれば折る・切る・貼る・巻くなど、作れる形に限界があります。これを打破したいというのが本研究です」と教授が語るように、成形機の口金を替えることで、木粉粘土をシート状にしたり蜂の巣(ハニカム)状にしたり、多様な形へとアレンジできます。また、成形に失敗したら何度でも作り直せるところは陶芸と同じで、廃棄物の少ない環境にやさしい素材といえるでしょう。木粉は、木材の製造工程の中で必ず発生するものですが、通常あまり価値がありません。こうした木粉を活用し、付加価値をつけることができれば、国内の林業の発展にもつなげることができると考えています。
ウッドストローの特徴
プラスチック代替ストローとしては、生分解性プラスチックのストローや紙ストローが市販されています。しかし、生分解性プラスチックは土壌中での分解を想定しているため、海洋ではなかなか分解しません。また、紙ストローは、時間が経つと柔らかくなるなどの問題点があります。三重大学の「ウッドストロー」は、100パーセント天然、かつプラスチックを使用していない環境に配慮した素材であるのみならず、切削加工によるくずも発生せず、原料すべてが使えるので無駄がありません。また、食品成分を使用しておらず、世界規模での食糧不足にも配慮した素材として、今後の製品化が期待されています。



ウッドストローの製作過程の様子。左上から、木粉・増粘剤混練(こんれん)前、木粉・増粘剤混練後、成形。
「実は、ウッドデザイン賞を受賞した2018年時点では、ウッドストローを1時間ほど水に浸けておくと、ふにゃふにゃになっていました。そこで、さまざまな素材で実験を重ねた結果、柑橘類などに含まれるクエン酸を加えて加熱すると、成形品が耐水性をもつことがわかりました」。現在のウッドストローは耐水性をもち、ストローとしての機能を備えています。また、しなやかさを要する製品には柔軟剤を加えるなど、日々の研究によって、その可能性はますます広がっています。

これまでのウッドストロー(左)と現在のウッドストロー(右)
植物素材から生まれた
環境負荷の少ない製品の数々

エコプロ出展の様子
2018年から毎年連続して出展している展示会「エコプロ2021(日本最大級の環境展示会)」の会場には、木粉から作った「ウッドストロー」、竹粉やコーヒー粕から作ったストローをはじめ、コンセントタップやトレーなど植物素材の試作品が並び、多くの研究者や企業の関心を集めました。なかでも見た目のカッコよさで注目を集めたのが、コーヒー粕の黒いストロー。「コーヒーのチェーン店の関係者と話したところ、店で出たコーヒー粕で、ストローやマドラーはもちろん、配膳トレーやカップなど、将来的には多くの備品に再利用したいという考えをお持ちでした」。それが実現すれば、飲食業において、循環型のビジネスモデルを構築することが可能になります。

コーヒー粕を使用して作られたストロー
\学生の声/

三重大学
大学院生物資源学研究科
木質分子素材制御学研究室
熊谷 菊那 さん
再生可能資源である木材の利用拡大に向けて研究を行っています。木材は熱可塑性(高温で軟化して成形しやすくなり、冷却すると再び固まる性質)が乏しいため,プラスチックのような自由な成形が困難です。そのため加工性向上の研究を行っており、現在は木粉を用いてボトルの成形を試みています。
卒業後は、社会人として環境問題やその対策について向き合う際に、森林活用という視点でアプローチすることで研究で学んだことを役立てたいと思います。
今後の研究について

実験室での研究の様子
「プラスチックは非常に便利で、私たちの生活のさまざまな場面で欠かせない素材なので、そのリサイクル技術を向上させることも重要であると考えています。そのうえで、紙製品や木材製品などとともに、このウッドストローを作る技術も一つのオプションとして発展させていきたいと考えています。再生可能な植物素材の中でも特に木の端材や稲わら、籾殻、竹、コーヒー粕など、これまで廃棄されてきた素材や、余っている素材を使って製品化し、廃棄物を有価物へと転換させて循環型社会を創っていくことで、環境への負荷を減らすことができるのはもちろん、農業や林業にも貢献できるでしょう」と野中教授は語ります。

|今回 教えてくれたのは・・・|

三重大学大学院生物資源学研究科
資源循環学専攻
森林資源環境学講座
木質分子素材制御学研究室
野中 寛 教授
博士(工学)。専門はバイオマス科学。卒業研究でバイオマスに出会って以来、化学工学、農芸化学、木材科学分野で、バイオマス利用の研究を続けている。2005年に三重大学に着任後、木材などリグノセルロース系バイオマスの成分分離、セルロースやリグニンの利活用に関する研究に本格的に従事。並行して2016年より成分を分離せずに成形する研究を開始。俯瞰的な視点でバイオマスの社会実装、脱炭素化への貢献を目指す。

この記事のPDF版はこちら
(PDF : 1,132KB)
お問合せ先
大臣官房広報評価課広報室
代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449